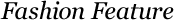World Street Classic Vol.4
2012.09.03
小野田:続いては、ラポ・エルカーン。この人は凄まじいことをサラっとやってのける。2006年に矢部(克己)さんが『GQ』で書いた、彼の無頼漢についての話は面白いんですよ、イリーガルな売春宿かなんかでオーバードーズで倒れてたっていうエピソードとか。ファッションとゴシップにまみれてる。 片や、『ルウォモ・ヴォーグ』ではセントラルパークで〈アディダス〉のジェレミー・スコットのキース・ヘリングを着てたり、タイトシルエットに直した祖父(ジャンニ・アニェッリ)の形見の〈カラチェニ〉のスーツに〈カルペディム〉合わせてスケーターと一緒に撮ってたり、結構ファッションとしてアンテナ高くやりこんでる感じなども。
小野田:じつは昔、アルファロメオのイベントで来日した際に小木ちゃんと一緒に見に行ったことがあるんですよ。
Poggy:行ったね。あれも凄かった、ホテルの目の前にフェラーリが何台も止まって。かなり前だけど、コレットで〈イタリアンインディペンデント〉のイベントやったとき、初めて彼を見たのかな。あと、彼のお爺ちゃんのスーツをセントアンドリュースに持って行って、自分のサイズに直してもらったっていう話は凄いですよね。
―完全なるサラブレットですね(笑)。
Poggy:余談ですが、今日自分が着てるスーツはジャンニ・カンパーニャの息子のアンドレア・カンパーニャのもので、ジャンニ・アニェッリがジャンニ カンパーニャで仕立てていた当時の襟型をもとに、今っぽくアレンジしてます。裏地もカモフラ柄にしていたり。
―おぉ(笑)。
小野田:2、3年前にラボラトリー/ベルベルジン®に来たらしく、オールドのクラブジャケットを買って行ったらしいんだけど、袋に入れようとしたら「着ていくからイイ」と、レジ前で裸の上にジャケット着て帰って行ったらしく(笑)。
Poggy:(笑)。同タイミングでUAの原宿本店でミーティングをしたんですが、そのときカッコ良い眼鏡をかけてたから「カッコ良いね、見せて」って言ったら、「あげるよ」ってくれました(笑)。「えー、くれるの」って驚きましたよ。
小野田:ホントは(今回のウェルドレスで)ラポ・エルカーンは違うかなって思ったんですが、僕にとってクロージングでの"珍プレー"がアリと自信になったのは、この人の影響が大きかったんで。
―最初は、ボタンたくさん開けて、イイ車乗り回してっていう、水っぽいイメージが強かったんですけど、いろいろ読むと本物感はありますよね。
小野田:メディアにはあまり姿を現さないお兄さんがいて、そっちは正統派のウェルドレッサーなんですが...。
―完全に次男坊って感じですね(笑)。
Poggy:イタリアの展示会で会ったときも「オーダー頼むぞ」って肩をバーンと叩かれて、年下にやられてたんだ...(笑)。
小野田:さっき話していた形見分けのスーツの話がとにかくすごくて。もともと完成されたスーツながらも祖父サイズの、自分の身体にとってはアンバランスなスーツに手を加えて、さらにアンバランスながらも自分流のシルエットに持っていってしまう。しかもそれを約80着すべて、そう直したらしく...。そういうことにチャレンジしてくれたお陰で、相当スーツが面白くなった。それまでは神経質にスーツを見てたけど、多少袖が短くても「買っちゃえ」って気を起こさせてくれるようになったし。
Poggy:本当のミックスカルチャーだから、説得力が違うんですよね。
小野田:次ですが、僕は最近アーティストが好きで、すっとんきょうなクロージングの扱い方をしてますがハーランド・ミラー(Harland Miller)が気になってます。ちょっと前の〈ダンヒル〉のキャンペーンに出ているんですが、最初は西洋人なのか東洋人なのか不明でした。イギリス人の絵描きなんですが、フランス人っぽいっていうか。前回話に出たシンガポールの『THE RAKE』でも表紙を飾っていますし、恐らくクロージング界の、次のマーク・ニューソン的な存在になる気がします。
小野田:それから、外せないのがユナイテッドアローズの鴨志田さん。2007年の『MEN'S EX』なんですが、シモーネ(元タイ・ユア・タイ/現フラージ)と鴨志田さんだけがダブルブレストを着ていて。「ダブルなんて終わった」と言われていたこの時期に、このタイミングでダブルをいち早く先取っていたのがすごく印象的でした。
Poggy:スコット・シューマンの登場以前は、日本の業界を中心とした知名度だったと思いますが、最近はイタリアだけでなくアメリカでも有名になっているんです。クラシックなスタイルって年を重ねてからでも花開くっていうのは鴨志田を見て教わりました。あと、ロンドンとかパリ行っても必ず蚤の市とか古着屋に連れて行ってくれたり、美術館に行って良い物を見るとか、あんまり口から直接ではないけど色々なことを教わっています。女性がいれば話しかけるし、ドアを開けてあげるし、上着も受け取って掛けてあげる。音楽が掛かれば踊るし、そういう自然な姿勢がカッコ良いんです。
―鴨志田さんの粋な感じは、話すほどに伝わってきますよね。
Poggy:それと信濃屋の白井さんですね。自分がピッティに初めて行った2006年に、偶然飛行機が一緒になって。ネイビーのジャケットを着てグレーのパンツだったんですけど、靴下とチーフが赤で、自分のお爺ちゃんと同じくらいの方がそんな格好してて、凄いカッコ良いなと思ったんです。もちろん、そのときは存在自体も知らなかったんですけど。後々聞くと、老舗信濃屋の白井さんだった。ハズしてる方は多いけど、イイ物をちゃんと着てる老齢の方ってなかなかいないので。そういう視線で見ると、とにかく勉強になる。イタリアでそういった方々の着こなしを見て、素敵な話をたくさん聞かせていただいて、自分は色々なことを学んでいます。 今って、クラシックな物がシーズンごとにアップデイトされているけれども、ただ本来は変わらないのがクラシックの良さだと白井さんに教わったかもしれないですね。
―今まで数名の方のお名前が挙がりましたが、ウェルドレスドマンに選ぶ基準のようなものはあるのですか?
Poggy:グッとくるかどうかなんだよね(笑)。
―あら、感覚的な話(笑)。
小野田:スティーブ・マックイーンだとかフレッド・アステアだとか、マルチェロ・マストロヤンニの名前が挙がったりするんだろうけど、「自分たちの世代では」というと、また挙がる名前も変わってきたり。
Poggy:なんだろうね、知らない人が見たら"ただスーツを着ている人"なんだろうけど、その人の話を聞いたりすると、人生すべてがスーツににじみ出ている気がして。スーツって同じ生地が全身の割合のほとんどを占めるから単調になる分、その人のスタイルがすごく大切になってくると思うんですよね。いま、こういった体験をして勉強しておけば、50代60代になったときにきっとカッコ良くなれると思うし。
Poggy:あと、思い出したけどホンズワース・ベントレー(Fonzworth Bentley)っていうディディ(P. Diddy)のお付きをずっとやってた人のモード感のあるクラシックスタイルにも惹かれていまして。3年くらい前カニエやタズがパリコレに行ってたときに、1人だけクラシックな格好してたのが彼だったんです。日本の演歌をサンプリングした曲をリリースしたかと思えば、別のPVではきちんとタキシードを着こなしているし。何を着て何をするかっていうのが映像を通して伝わってくる。 クラシックって突き詰めていくとスタイルが重要になっていくから、自分たちが90年代に影響を受けたストリートってTシャツ自体がカッコ良かったっていうより、"その人が着るTシャツ"がカッコ良かった。今は逆に"カッコ良いTシャツを着たあの人"って、ロゴとかデザインだけが先行しがちだから、もう一度自分たちの世代が伝えて行ければ、とは思っていますね。
小野田:自分たちの方に引き寄せるというか、こういう風にしたら面白いよとか。(スーツは)基本が決まってる世界ではありますが、逆に基本さえ押さえていれば亜流も楽しめますからね。そういうのが、今回挙げた人たちのスタイルからは伝わってきます。
Poggy:あとは、同じカルチャーを感じるかっていうのもあるのかな。
小野田:瞬発力だけのカッコ良さじゃなくて、持久力のあるカッコ良さがある。そういうのを築きあげていけるかが重要だし、面白いんだと思うんですよね。
Poggy:なんだか凄い方向に流れて行ってる気がするけど...大丈夫ですかね。
―はい。やってる側が面白いと感じているなら大丈夫ですよ。だって、こんなに幅の広いトークってフイナムくらいでしか出来ないでしょうし。
Poggy:そうですね。じゃあ引き続き、全力でいきましょう!
―お願いします!
さて、今回はPoggy、小野田両氏が考えるウェルドレスドマン。選び方は感覚に寄るところが多いそうですが、なんとなく一貫性があって、彼らの動向をチェックしておけば、参考になるポイントも学べるのではないでしょうか。Vol.5では、このウェルドレスドマンの続きとして、初のゲストを招いて、これからについて話していきます。そちらもお楽しみに。