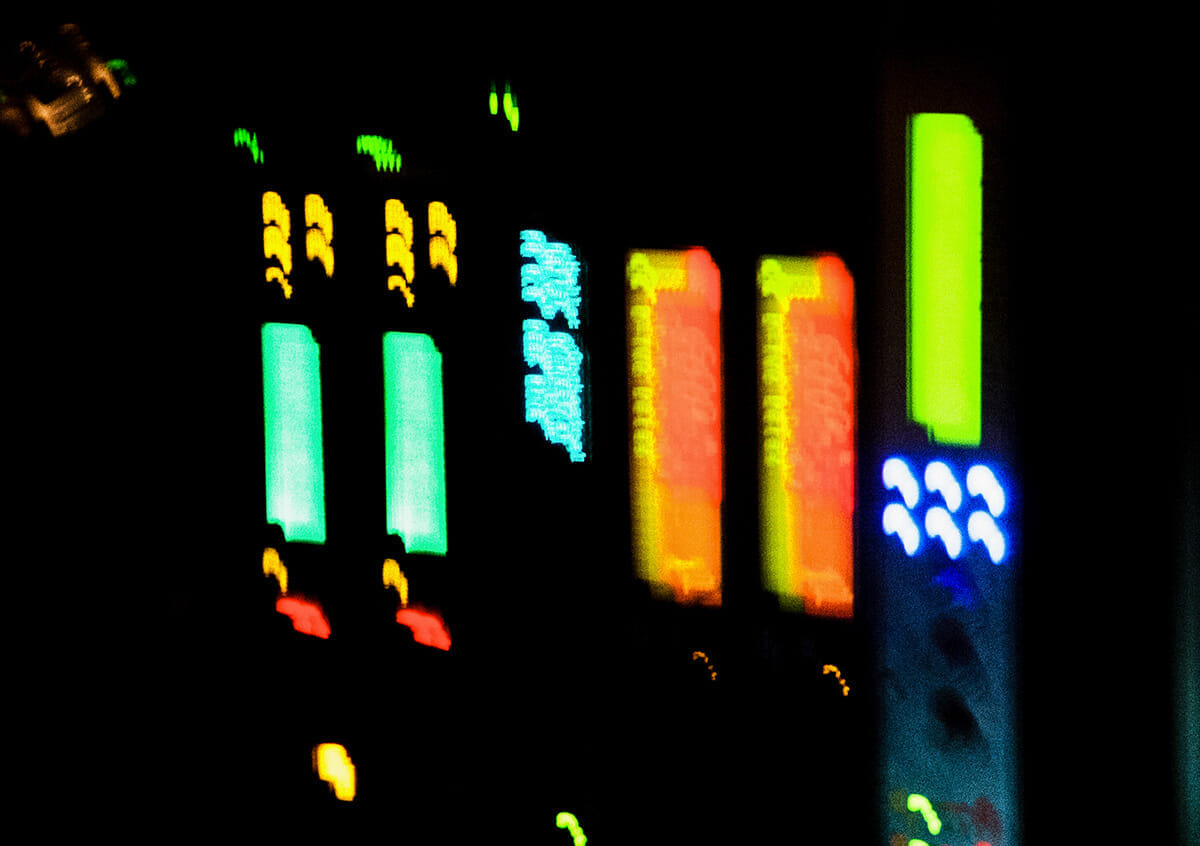Interview with yahyel.
「すべての垣根を越えた音楽を」
“yahyel”というプロジェクトを通して若者が描こうとしているもの。
デビューアルバム『FLESH AND BLOOD』のリリースとともに、ミュージックシーンを躍進するyahyel。深淵な場所で響くビートの上で揺れる艶めかしいジェンダーレスな声。静寂と喧騒を行き交うような音楽はあらゆるジャンルを自在に飛び越え、エレクトロミュージックの最先端で鳴っている。エコーとリバーブを使ったチル感溢れるシティ・ポップと、そのブームに抗うように現れた彼らが音楽に込める思いとは。バンドの核である池貝峻(Vo)・篠田ミル(Sampler)・杉本亘(Syn)の3 名に話を聞いた。
- Photo_Kisshomaru Shimamura
- Interview & Text_Naoko Okada
- Edit_Kenichiro Tatewaki