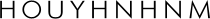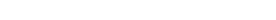FEATURE |
フイナムテレビ ドラマのものさし SEASON6 『心がポキッとね』~脚本家・岡田惠和

『心がポキッとね』 フジテレビ 水曜放送
「ここに来た時、人生もう終わってた。だから、ほっといてくれって思った。静かーに誰とも関わらず生きていこうって思ってたわけですよ。でもさ、あんたたちはさ、次から次へと俺を巻き込みやがってさあ。ぜんっぜん1人にしてくんねえんだもんなあ。ほんと勘弁してくれって思ったわけですよ。俺と関わらないでくれ、お願いしますってね。そう、だったんですよ。でも…ほんとはうれしかった。だってそうでしょ? そうやって悩んでるってことは生きてるってことだし、この先も生きていたいってことなわけで。だって、なんにも感じなくなっちゃったら、その時は心が死んじゃってるわけで。つまり、だから、人生終わったと思ってた私の壊れた時計を動かしてくれたのは、みなさんなんです。」
最終回のクライマックスで、春太(阿部サダヲ)は元妻の静(山口智子)の結婚式の席で酒に酔っぱらい泣きながら心情をぶちまけた。すべてを失い心を閉ざした男は、巻き込まれるようにして自分に輪をかけて壊れかけた人々に翻弄されることで、むしろ人としての感情を取り戻していったのだった。
脚本家・岡田惠和が好んで描くのは、「血縁関係に依らないコミュニティ」だ。それは『ビーチボーイズ』の頃から一貫して変わらないのだが、これが『最後から二番目の恋』や『さよなら私』になると、老後や死を見据えた上でのあたらしいコミュニティのあり方へと変化している辺りが興味深い。では、『心がポキッとね』通称『心ポキ』(この略称はほとんど浸透しなかったが)はどうだったのか。とにかく、めんどくさい、うっとおしいイカれた登場人物たちが次々と現れ、全員が自分勝手に振る舞うだけで他人のことを一切考えない、見ているこっちの心がポキッとなりそうだというような感想を抱くひとも多かったらしい。『最後から二番目の恋』を演出した宮本理江子がメイン演出ということもあり、「あんな感じの雑居物ラブコメなんでしょ」と思って見始めたひとたちが、「想像してたのと違う!」と思ったとしても無理はないかもしれない。
なんなら安部サダヲ演じる春太が一番まともにすら見えるわけだが、そもそも部下に暴言を吐き、妻に暴力をふるった過去を持つ男なので、易々とは感情移入できない。街中からいろんなものを「直せばまだ使えるから」と拾ってきてしまう(ついでに春太も拾ってしまう)アンティーク家具店のオーナー・心がまともかといえば決してそんなことはなく、誰をも受け入れるキャパシティを持っているということは、実は何も深く考えていないからっぽの人間に他ならないということもこのドラマは描いている。屈託のない明るさは、誰かにとって太陽のような存在となる一方で、誰かをイラつかせることもある。というように、登場人物に誰一人共感できないまま、スラップスティックに物語が進行していくため、見ている側はなかなかその世界に没入できない。「困ったひとたち」が駆け込むメンタルクリニックの院長(山西惇)は、ただ彼らの堂々巡りの自問自答を無言で聞くのみ。とうとう最後までひと言も発することはなく、癒しや慰めの言葉を口にすることもなかった。
これを、裏番組で堺雅人が精神科医を演じた『Dr.倫太郎』と比較すると面白い。倫太郎は、心を病んだ患者に対して、「もうそんなに頑張らないでください」「あなたは大丈夫です」と言いながらやさしく微笑む。堺の風貌と相まって、「癒されるわあ」という女性視聴者が多数いたのもよく分かる。確かにこちらのほうが分かりやすいし、当然、視聴率もいい(常に10%超えをキープ)。しかし、本当にそうだろうか。そんなに簡単に口当たりのいい言葉に癒されていいのだろうか。というのが、『心ポキ』の世界なのだ。だから、メンタルクリニックの院長は困った顔で話に頷くだけで、癒しの言葉は一切口にしない。訪れたひとたちは自分のことを一方的に話すだけ話して、あたかも答えを見出したかのようにすっきりして帰っていく。つまり、答えは常に自分の中にあるのだ。
こうした「分かりにくさ」によって視聴者が離れたことは想像がつくのだが、6話辺りから、不思議なことにうっとおしかったはずの登場人物たちが、なぜか可愛げのあるひとたちに思えてくる辺りから俄然面白くなってきた。春太の元妻で空間コーディネーターの静を演じる山口智子は、『ロンバケ』の頃の「ナチュラル芝居」をまんま引きずっていて実にイタいのだが(もちろんこれはわざとやっていたはずだ)、6話で静と同級生だった売れっ子空間デザイナーの栞(渡辺美奈代)にこんなことを言われる。
「どうして私が成功してると思う? 適度にダサいのよ、私は。自分のことセンスいいなんて思ってないし。ほら、あのダサダサの栞よ。でもね、世の中のほとんどの人はダサいわけ。私が考えることは居心地がいいの。」「一応先輩として圭子(※静の本名)の仕事に意見していい? ちょっとうっとおしい、圭子のは。どう?私すごいでしょって言われてるみたいで、何様だよって思う。私を認めろっていう押し付けがましさがあるし、おしゃれってこうでしょっていう感じがあって、そういうのが伝わってくるとイラっとするし、自分自分自分って感じ。それってイタい。なんか楽しそうじゃないんだよね、全然。」
あるいは8話で、心の母親・マリ(烏丸せつこ)からは、「なんかめんどくさいものいっぱい抱えてる顔してるね。脳の中に余分なものいっぱい入ってるよ。でも意外と根っ子は保守的だし常識人。決して大きくは冒険できないって、そういうタイプでしょ」と見透かされる。
これらの描写によって、なんだか静というひとが可愛そうに(それは同時に可愛くも)思えてくるのである。このひとも、いろいろ大変だったんだなあ、と。がさつで直情的で自分勝手なみやこ(水原希子)についても同様だ。亡き祖父の形見の壊れたオルゴールを春太に直してもらい、かつて祖父と2人で暮らしていた取り壊し寸前の家の庭に埋めるシーンで、「いつも私が好きになる人はある日突然目の前からいなくなる」と吐露する。つまり、大好きだった祖父が突然亡くなってしまったように、好きな人がいきなりいなくなってしまうかもしれない恐怖心からストーカー体質になったのだということが分かる。止まっていたオルゴールは春太の手で再び動き出し、それを祖父との思い出の家の庭に埋めることで、みやこもまた少しだけ変わることができたのだ。この人間を見つめるまなざしが、岡田惠和脚本の真骨頂だろう。そして、ここで春太がみやこに言うセリフが、『心ポキ』の世界観を象徴していた。
「私がおじいちゃんの代わりになりますよ。私じゃダメですか? 1人にしないって約束したし。いいじゃないですか。私たちは恋人でもないし夫婦でもないけど、いいじゃないですか、一緒にいたって。壊れた者同士、一緒にいましょうよ。」
こうなると、最初から安易に感情移入できる等身大の登場人物を設定せずにどこまでドラマを動かしていけるのか挑戦していのたのではないか、とすら思えてくる。ネタバレでも何でもないと思うので書くが、最終話は一応ハッピーエンドだった。とはいえ、ここまで困ったひとたちがすったもんだした末のハッピーエンドなので、それがいつまで持続するのか何の保証もない、極めて危ういハッピーエンドだ。現実の世の中が混沌とし、不可解な出来事が頻発すればするほど、フィクションがハッピーエンドを描くことは困難になる。安易なハッピーエンドは単なる絵空事にしか見えないからだ。おそらく、岡田惠和もその問題に直面しているのではないだろうか。
ハッピーエンドを描くのが困難な時代においてハッピーエンドをどう描くのか。この問題は、『さよなら私』(NHK)や『心ポキ』と放送時期が重なった『ボクの妻と結婚してください。』(NHK-BS)でも顕著だった。『さよなら私』も『ボク妻』も、死んでいく者が残された者に(妻が夫と子どもに、夫が妻と子どもに)何を遺すのかという意味で対になる物語だ。『ボク妻』は、樋口卓治の小説を原作とした舞台が先にあるので(主演はドラマと同じ内村光良と木村多江)岡田惠和のオリジナルではないが、両者は見事に同じ主題の変奏になっている。単に妻目線、夫目線の差というだけでなく、結果的に両者の味わいはまったく異なる。もし「同じような話ばかり書いて」と思うひとがいるとすれば、それは本編を見ていない証拠だろう。ちなみに『ボク妻』最終話のタイトルは「ハッピーエンド」だった。ここでも「血縁関係に依らないコミュニティ」としてのあたらしい家族像が描かれた。そして、死は決してバッドエンドではない、ということも。
あらためて『心ポキ』について考えてみると、確かに岡田惠和脚本としては決して完成度が高いとはいえないのかもしれない。ストーカー体質のみやこをストーカーする(ああややこしい)女・江里子(山下リオ)がメンタルクリニックの院長に問いかける、「私はどこに向かって何をすればいいんでしょうか? これから先どうすればいいんでしょうか?」というセリフは、ひょっとすると脚本家の心の声だったのではないか。そうした混沌の中に表出されたと思しき「愛すべき困ったひとたち」の姿は、滑稽でせつない。壊れた時計は直せばまた使えるように、人の心も壊れたら直せばいい。ただし、それは安易な癒しや励ましの言葉ではなく、面倒でうっとおしい人間関係の中でしか修理できないのものなのかもしれない。だから、耳触りのいい癒しの言葉(あえて言えばJ-POP的な)になびくようなひとたちは、このドラマから離れていったのではないか。そういう意味では、かなりきわどいラインを進んだ話だったといえるだろう。
最終回のクライマックスで、春太(阿部サダヲ)は元妻の静(山口智子)の結婚式の席で酒に酔っぱらい泣きながら心情をぶちまけた。すべてを失い心を閉ざした男は、巻き込まれるようにして自分に輪をかけて壊れかけた人々に翻弄されることで、むしろ人としての感情を取り戻していったのだった。
脚本家・岡田惠和が好んで描くのは、「血縁関係に依らないコミュニティ」だ。それは『ビーチボーイズ』の頃から一貫して変わらないのだが、これが『最後から二番目の恋』や『さよなら私』になると、老後や死を見据えた上でのあたらしいコミュニティのあり方へと変化している辺りが興味深い。では、『心がポキッとね』通称『心ポキ』(この略称はほとんど浸透しなかったが)はどうだったのか。とにかく、めんどくさい、うっとおしいイカれた登場人物たちが次々と現れ、全員が自分勝手に振る舞うだけで他人のことを一切考えない、見ているこっちの心がポキッとなりそうだというような感想を抱くひとも多かったらしい。『最後から二番目の恋』を演出した宮本理江子がメイン演出ということもあり、「あんな感じの雑居物ラブコメなんでしょ」と思って見始めたひとたちが、「想像してたのと違う!」と思ったとしても無理はないかもしれない。
なんなら安部サダヲ演じる春太が一番まともにすら見えるわけだが、そもそも部下に暴言を吐き、妻に暴力をふるった過去を持つ男なので、易々とは感情移入できない。街中からいろんなものを「直せばまだ使えるから」と拾ってきてしまう(ついでに春太も拾ってしまう)アンティーク家具店のオーナー・心がまともかといえば決してそんなことはなく、誰をも受け入れるキャパシティを持っているということは、実は何も深く考えていないからっぽの人間に他ならないということもこのドラマは描いている。屈託のない明るさは、誰かにとって太陽のような存在となる一方で、誰かをイラつかせることもある。というように、登場人物に誰一人共感できないまま、スラップスティックに物語が進行していくため、見ている側はなかなかその世界に没入できない。「困ったひとたち」が駆け込むメンタルクリニックの院長(山西惇)は、ただ彼らの堂々巡りの自問自答を無言で聞くのみ。とうとう最後までひと言も発することはなく、癒しや慰めの言葉を口にすることもなかった。
これを、裏番組で堺雅人が精神科医を演じた『Dr.倫太郎』と比較すると面白い。倫太郎は、心を病んだ患者に対して、「もうそんなに頑張らないでください」「あなたは大丈夫です」と言いながらやさしく微笑む。堺の風貌と相まって、「癒されるわあ」という女性視聴者が多数いたのもよく分かる。確かにこちらのほうが分かりやすいし、当然、視聴率もいい(常に10%超えをキープ)。しかし、本当にそうだろうか。そんなに簡単に口当たりのいい言葉に癒されていいのだろうか。というのが、『心ポキ』の世界なのだ。だから、メンタルクリニックの院長は困った顔で話に頷くだけで、癒しの言葉は一切口にしない。訪れたひとたちは自分のことを一方的に話すだけ話して、あたかも答えを見出したかのようにすっきりして帰っていく。つまり、答えは常に自分の中にあるのだ。
こうした「分かりにくさ」によって視聴者が離れたことは想像がつくのだが、6話辺りから、不思議なことにうっとおしかったはずの登場人物たちが、なぜか可愛げのあるひとたちに思えてくる辺りから俄然面白くなってきた。春太の元妻で空間コーディネーターの静を演じる山口智子は、『ロンバケ』の頃の「ナチュラル芝居」をまんま引きずっていて実にイタいのだが(もちろんこれはわざとやっていたはずだ)、6話で静と同級生だった売れっ子空間デザイナーの栞(渡辺美奈代)にこんなことを言われる。
「どうして私が成功してると思う? 適度にダサいのよ、私は。自分のことセンスいいなんて思ってないし。ほら、あのダサダサの栞よ。でもね、世の中のほとんどの人はダサいわけ。私が考えることは居心地がいいの。」「一応先輩として圭子(※静の本名)の仕事に意見していい? ちょっとうっとおしい、圭子のは。どう?私すごいでしょって言われてるみたいで、何様だよって思う。私を認めろっていう押し付けがましさがあるし、おしゃれってこうでしょっていう感じがあって、そういうのが伝わってくるとイラっとするし、自分自分自分って感じ。それってイタい。なんか楽しそうじゃないんだよね、全然。」
あるいは8話で、心の母親・マリ(烏丸せつこ)からは、「なんかめんどくさいものいっぱい抱えてる顔してるね。脳の中に余分なものいっぱい入ってるよ。でも意外と根っ子は保守的だし常識人。決して大きくは冒険できないって、そういうタイプでしょ」と見透かされる。
これらの描写によって、なんだか静というひとが可愛そうに(それは同時に可愛くも)思えてくるのである。このひとも、いろいろ大変だったんだなあ、と。がさつで直情的で自分勝手なみやこ(水原希子)についても同様だ。亡き祖父の形見の壊れたオルゴールを春太に直してもらい、かつて祖父と2人で暮らしていた取り壊し寸前の家の庭に埋めるシーンで、「いつも私が好きになる人はある日突然目の前からいなくなる」と吐露する。つまり、大好きだった祖父が突然亡くなってしまったように、好きな人がいきなりいなくなってしまうかもしれない恐怖心からストーカー体質になったのだということが分かる。止まっていたオルゴールは春太の手で再び動き出し、それを祖父との思い出の家の庭に埋めることで、みやこもまた少しだけ変わることができたのだ。この人間を見つめるまなざしが、岡田惠和脚本の真骨頂だろう。そして、ここで春太がみやこに言うセリフが、『心ポキ』の世界観を象徴していた。
「私がおじいちゃんの代わりになりますよ。私じゃダメですか? 1人にしないって約束したし。いいじゃないですか。私たちは恋人でもないし夫婦でもないけど、いいじゃないですか、一緒にいたって。壊れた者同士、一緒にいましょうよ。」
こうなると、最初から安易に感情移入できる等身大の登場人物を設定せずにどこまでドラマを動かしていけるのか挑戦していのたのではないか、とすら思えてくる。ネタバレでも何でもないと思うので書くが、最終話は一応ハッピーエンドだった。とはいえ、ここまで困ったひとたちがすったもんだした末のハッピーエンドなので、それがいつまで持続するのか何の保証もない、極めて危ういハッピーエンドだ。現実の世の中が混沌とし、不可解な出来事が頻発すればするほど、フィクションがハッピーエンドを描くことは困難になる。安易なハッピーエンドは単なる絵空事にしか見えないからだ。おそらく、岡田惠和もその問題に直面しているのではないだろうか。
ハッピーエンドを描くのが困難な時代においてハッピーエンドをどう描くのか。この問題は、『さよなら私』(NHK)や『心ポキ』と放送時期が重なった『ボクの妻と結婚してください。』(NHK-BS)でも顕著だった。『さよなら私』も『ボク妻』も、死んでいく者が残された者に(妻が夫と子どもに、夫が妻と子どもに)何を遺すのかという意味で対になる物語だ。『ボク妻』は、樋口卓治の小説を原作とした舞台が先にあるので(主演はドラマと同じ内村光良と木村多江)岡田惠和のオリジナルではないが、両者は見事に同じ主題の変奏になっている。単に妻目線、夫目線の差というだけでなく、結果的に両者の味わいはまったく異なる。もし「同じような話ばかり書いて」と思うひとがいるとすれば、それは本編を見ていない証拠だろう。ちなみに『ボク妻』最終話のタイトルは「ハッピーエンド」だった。ここでも「血縁関係に依らないコミュニティ」としてのあたらしい家族像が描かれた。そして、死は決してバッドエンドではない、ということも。
あらためて『心ポキ』について考えてみると、確かに岡田惠和脚本としては決して完成度が高いとはいえないのかもしれない。ストーカー体質のみやこをストーカーする(ああややこしい)女・江里子(山下リオ)がメンタルクリニックの院長に問いかける、「私はどこに向かって何をすればいいんでしょうか? これから先どうすればいいんでしょうか?」というセリフは、ひょっとすると脚本家の心の声だったのではないか。そうした混沌の中に表出されたと思しき「愛すべき困ったひとたち」の姿は、滑稽でせつない。壊れた時計は直せばまた使えるように、人の心も壊れたら直せばいい。ただし、それは安易な癒しや励ましの言葉ではなく、面倒でうっとおしい人間関係の中でしか修理できないのものなのかもしれない。だから、耳触りのいい癒しの言葉(あえて言えばJ-POP的な)になびくようなひとたちは、このドラマから離れていったのではないか。そういう意味では、かなりきわどいラインを進んだ話だったといえるだろう。
『ど根性ガエル』 日本テレビ 土曜21時~ 7月11日スタート
さて、次々と連ドラを手掛ける岡田惠和の次回作は、すでに話題となっている実写版『ど根性ガエル』(日本テレビ・7月11日スタート)だ。30歳になったひろしを松山ケンイチ(岡田とは『銭ゲバ』以来)、Tシャツに張り付いたピョン吉の声を満島ひかりが演じるという、これまた一筋縄ではいかなそうな題材である。かつて同じ土曜22時枠で岡田が手掛けた『泣くな、はらちゃん』辺りに通じる日常とファンタジーを行き来するようなメタ構造の物語になるのだろうか。「脚本家とは常に書き続けなければならない仕事。僕もいまだに悩んで、心がポキッと折れそうな時もある。」とは、先日発表された21世紀新人シナリオ大賞授賞式での岡田のコメントだ。書き続けていれば、数字や評価が今一つのことだってあるだろう。一喜一憂しながら、それでも書き続けるのが脚本家だ。「脚本 岡田惠和」のクレジットが付いたドラマにこれからも注目し続けたい。