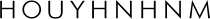FEATURE |
『深夜食堂』が恋しくて。 ドラマと映画と、時々、ごはん。Special Interview 小林薫

-原作が掲載されている『ビッグコミックオリジナル』は、年齢層がやや高めの読者層ですが、ドラマ化によって幅広い年齢層にも届くようになりました。見た人のリアクションは小林さんの耳に入ってくるものなのでしょうか?
小林: 僕は日ごろから、リアクションというのは良いものも悪いものもあまり気にしないようにしているんです。ただ、大阪で撮影をしていた時に飲食店の人に聞いたのは、午前0時に店を閉めて、ちょうど家に帰ると『深夜食堂』をやっていたからよく見ていた、と。帰宅が遅い飲食業の人たちがけっこう見ていたらしいんですけど、その人たちにしたら、時間帯的にも内容的にも、「自分たち向けのドラマが始まった」という感じだったのかな、と思ったりはしました。 いろんな層の人が見ているということで言うと、韓国や台湾、中国でも人気らしいんですよ。まあ、放送はしていないから、みんなネットで見ているらしいんですけど。以前、上海から取材を受けたことがあって、「なんで上海なの?」と聞いたら、「現地で『深夜食堂』が人気なんです」と。何が彼らを惹きつけているのか、本当のところは僕にも分からないんですけど、もはや「日本の深夜に放送しているテレビドラマ」という枠を超えつつあると思ってます。
-やはり人間ドラマとしての普遍性が受け入れられているということなのでしょうか。
小林:
よく「『深夜食堂』の魅力とは何ですか?」みたいなことを聞かれるんですけど、僕自身、それほど分析できていないんです。ただ、フードスタイリストの飯島奈美さんの料理にしても、熱いものは熱いまま出すし、ビールにしても、ノンアルコールだけど泡立ちにまでこだわって、しょっちょう取り替えている。お金のかかっている映画やドラマでもなかなかそこまではしないですよ。なにしろ撮影中に「料理待ち」がありますからね(笑)。
照明なんかも、本当はもう少し人数がいなきゃいけないところを半分の人数でやっていたりするんだけど、それでも「この辺で」という妥協はしない。それぞれのパートで各々が、なぜかそうやっている。変な話、こだわればこだわるほど、それぞれのパートの持ち出しになると思うんですよ。でも、はたから見たら、「何かマニアックにつくっているな」という雰囲気がまず伝わってきて、それで「ちょっと見てみよう」とか「試しに見たら引き込まれた」というように、見る人の何かをくすぐるのかもしれないですよね。

-今お聞きしたようなつくり手のこだわりを知ると、さらに見方が変わりますが、何も知らずにパッと見ただけでも画面からそれが滲み出ているような気もします。
小林:
今のテレビのつくり方からすると、マイナスの要素が多いんですよ。料理が出てくるといっても「タコさんウインナー」だったりして、全然グルメっぽくない。基本的には美男美女が出てくるような話ではないし、「あのファッションかっこいいね」という意味でのファッション性があるわけでもない(笑)。そういう意味では、「足らないもの」ばかりが画面の中に溢れているんです。不破万作さんが演じている「忠さん」という、ストリップ劇場に入り浸ってる酔っ払いのおっちゃんを今どき誰が見たいのか、という話だろうし、年とったゲイバーのママ・小寿々さんにしても、世間一般からすればちょっと外れた人。でも、そういう人たちが、あのドラマの魅力になっているんじゃないですか。
分かりやすい成功者だとか、より優れた才能をもった人たちに対して憧れをもって見るという構図じゃなくて、もしかしたら、ドラマを見ている人たちよりも何割か不足している人たちが出ている。それが一つの場所に寄り集まってくることで、何かを形づくっているんじゃないか。そういう意味での居心地の良さみたいなものがあるのかもしれないですけど、考えてみたら、それは時代や世間に逆行しているんですよね。
-第1弾が放送された2009年は、まだテレビはアナログ放送でしたが、第2弾がスタートした2011年に地デジに切り替わったんですね。そして、今は東京オリンピックに向けてふたたび都心の再開発が進んでいます。世の中が急激にデジタル化し、街の風景も変わっていく中で、『深夜食堂』の世界だけが時代に取り残されたように超アナログな手触りを保っている。こじつけかもしれませんが、そこにホッとする何かを見出す人たちも多いのかもしれません。ここ数年、一時期の「昭和レトロブーム」とは違う意味で、日常的に横丁や下町で飲み食いする若者も増えていますし、主流ではないかもしれませんが、そういうものに引き寄せられる人たちが確実に増えているような気もします。

小林: ああ、なるほど。中国や韓国で人気があるのも、ひょっとするとその辺りなのかもしれないですね。急激な経済発展の影で、取り残されたような気持ちになっている人たちも多いだろうし、振り返ってみると、何か自分たちは大事なものを忘れてきたような気分になる。その失われつつあるものを『深夜食堂』の中に見出すというか。
-先ほど、パート3のドラマと映画のセットの話を伺いましたが、映画でマスターを演じるうえでドラマ版との違いはあったのでしょうか。
小林:
ドラマでは、マスターは基本的に外でロケ撮影することはなかったんですけど、今回映画ではじめてロケに出たんです。マスターの部屋もチラッと出てくるんですけど、そこで落語を聴きながら洗濯物を干すシーンがありました。そのシーンで天気待ちを二度しているんですけど、「そんなに待たなくても、そこそこ晴れていればいいだろう。黒澤明じゃないんだから」と思ったんだけど(笑)、ところが、ただベランダを撮っているだけじゃなくて、カメラが引いたら、その後ろに新宿の高層ビルがそびえ立っているという構図だったんです。まさに大都会の中に取り残されたような場所があり、その一角にマスターの住まいがあって、そこから店に通っているんだということが分かる。そうすると、僕がそこで「こういう感情で、こういう芝居を」と思うことよりも、マスターの部屋と高層ビルの対比のほうが映像としては主眼になる。そのためにはくっきりとした青空の中にビルが連なっている様子が映っていないといけない。それを撮るために随分待ちましたけど、いまさらながら、「映画ってこうやって撮っていくんだよな」と実感しました。
そういうものを目の当たりにした時に、役者がどういう感情で動いたかなんていうのは小さなことで、言ってみればどうでもいいようなものなんじゃないか、監督の目線ってそういうものだよなと思いましたね。もちろん、役者は役者として、「ここはこういう感情で演じよう」という思いみたいなものはあるんですけど、映画の場合、それよりも何よりも「何がどう画面に映っているのか」が命なんですよ。「役者の気持ち」って、監督からすればずいぶん空回りしていることもあるんだろうなと、今回あらためて思いましたね。
-監督やカメラマンは全体を俯瞰して見ているけれど、俳優は自分の役や自分が出ているシーンしか見ていないということですか。
小林: そう。役者は自分のいる窓から作品を見るしかないんです。