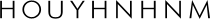FEATURE |
PLUS L by XLARGE® 江川芳文、43歳。いまさらだけど「服づくり」を語る。

かつての裏原宿。隆盛を極めたシーンの中心で、自身のバックボーンであるスケートボードに実直に向き合い、自らの表現を貫き続けてきた"YOPPI"こと江川芳文さん。90年代から00年代にかけて、多くの男子が恋い焦がれた〈ヘクティク〉創設メンバーの1人であり、ピストのカルチャーをも日本で広めた先駆者は、いまの時代に何を感じているのか。家族をテーマにしたブランド〈オンブレ・ニーニョ〉のデザイナーとして活動する一方で、来年に25周年を迎える〈XLARGE®〉と組んで〈PLUS L by XLARGE®〉を発足したばかりの彼に、改めて自身の「服づくり」にかける想いついて聞いてみた。
Photo_Hidemasa Miyake
Text_Hiroaki Nagahata
Edit_Hiroshi Yamamoto
隆盛を極めた「裏原宿」時代。江川芳文が服づくりを始めたきっかけ。

江川芳文
東京都世田谷区出身。東京のストリートシーンを牽引し続ける中心人物。1994 年から〈ヘクティク〉のディレクターとして活躍。現在も T-19 所属のスケーターとして活躍する等、 趣味と仕事を共存している希有な存在。2012年からは〈オンブレ ニーニョ〉を発足。
―まず、江川さんがスケートカルチャーにのめり込むようになったきっかけを教えてください。
江川:もともと周囲の影響で始めたのが最初ですね。そこからどんどんのめり込んでいって、決定打となったのが海外のスケートシーンを目の当たりにしたこと。俳優業(当時は事務所に所属して「金八先生」やポカリスエットのCMに出演)で稼いだお金を握りしめて、アメリカまで行って、大会に出て。日本とはまったく異なる環境を実際に味わったことで、こういったカルチャーを日本で表現してみたいと、漠然とした目標として持つようになったんです。
―当時、憧れていたライダーはいらっしゃいましたか?
江川:ドッグタウンのライダーはもちろん、クリスチャン・ホソイやジョバンテ・ターナー、マイク・キャロルにも憧れていましたね。なかでもクリスチャン・ホソイは好きすぎて、彼の自宅まで押しかけたこともあるんですよ(笑)。当時雑誌『ファイン』の編集長だった大野さんの取材に同行して、一緒にビリヤードをやったりして(笑)
―彼が2000年にドラッグで逮捕されたときはどんな気持ちでしたか?
江川:悲しいというよりも「これもまた人生だな」とは思いましたね。かつてはロックスターのような扱いだったのに、90年代を迎えると状況が一変。流行となってしまった反動とともに、スケート業界全体が急速に落ちぶれてしまいましたからね。急激な環境の変化の結果なのかなと。ただ全盛期を目にしている僕にとっては、彼は未だにヒーローではありますよ。
―〈ヘクティク〉は当初、セレクトショップからスタートしました。ショップを始めるうえでロールモデルにしたお店はありましたか?
江川:ロスにあった〈XLARGE®〉の1号店ですね。当時の〈XLARGE®〉には、毛足の長い絨毯が敷いてあって、入口のすぐ横になぜかバーバーチェアがドンと置いてあって。いわゆる洋服屋さんとは一線を画した雰囲気だったんですよ。実際に〈ヘクティク〉のオープン当初の床も絨毯にしましたし、肉屋さんで使うようなアルミの什器を使ったのも、〈XLARGE®〉のような洋服屋さんらしからぬ演出を意識してのセレクトでしたからね。
―その後、オリジナルブランドとして〈ヘクティク〉の前身となる〈PKG〉を始めたわけですね。
江川:〈スピード〉とか〈ヘリーハンセン〉とか、日本で未展開のブランド、アイテムを仕入れては売って、また仕入れにアメリカに行って。アメリカに行くのは楽しかったんですけど、繰り返しているうちに段々欲しいものが無くなってきて。だったら自分で作ってみようということで始まったのが〈PKG〉だったんです。最初は古着っぽいシャンブレーシャツやシャカシャカのナイロンパンツを作って。そこからですね服づくりを始めたのは。
―当時、服をデザインするプロセスはどういうものでしたか?
江川:世に出回っている既成品に対する小さな不満がデザインの発端ですね。「この要素があれば最高なのに」とか、そういう些細な部分。些細な部分を突き詰めていくうちに、ベースにしていたアイテムを分解しちゃって、元に戻せなくなってしまったり(笑)。ただ、そういった試行錯誤を繰り返していくなかで、服づくりの基礎を学んでいきました。専門的な勉強をしているわけではないからこそ、現場で培ってきたんです。

ーブランドは瞬く間に人気ブランドの仲間入りを果たし、ショップには行列ができることもあったと思います。その頃、当事者である江川さんは、どんな気分だったのでしょうか?
江川:少しは天狗になりますよね(笑)。「自分が着るか着ないか」を基準に作った服が、あっという間にたくさんの人々に受け入れられたわけですから。「僕が好きなものはみんな好きだよね」という変な自信を持っていた時期もありましたよ(笑)。もちろん服づくりをする以上、そういった意固地な部分は必要ではありますけど、かなり視野は狭かったんじゃないかな。ただ、そういった時代を当事者の1人として過ごすことができたのは、大きな財産だとは思っています。
―同年代の裏原宿界隈のブランドのデザイナーたちと、服づくりについて話すことはありましたか?
江川:当時は〈ヘクティク〉の下に〈ネイバーフッド〉の事務所があって。テツ君(〈WTAPS〉の西山徹)と情報交換することはあっても、服に関する話はしていなかったなあ。スケシンさん(現C.E)に会いに行って、音楽やアートの話をしたり、ときにはMACの使い方まで教えてもらったり、そんな感じですよ。
―となると、本当に服づくりに関しては素人だったわけですね。
江川:生産を請け負ってくれていた方が師匠ですね(笑)。僕みたいな素人が無理を言っては、できる・できないをはっきりと示してくれて、できない理由もきちんと教えてくれる。作れる可能性があるものに対しては、全力を尽くしてくれましたし。
―裏原宿と呼ばれた世代が出てきたことによって、服作りの多様化が進んだようなイメージがあります。
江川:当時、僕みたいなアイディアで服をつくっている人がいなかったですからね。だからこそ僕も手探りだったし、生産の方も手探りだったんじゃないかな。それでも、服づくりに対する経験値は師匠の方が高いから、僕らも素直に従ったりして。ただ、当時の僕は我が強すぎたからなあ…(笑)。内心「鬱陶しい」と思っていたんじゃないですかね(笑)
―〈ヘクティク〉はルーツにスケートボードがあったとは思うのですが、ファッションとして多くの人に受け入れられました。江川さん自身は、スケートとファッション、どちらを意識していたのでしょうか?
江川:あくまでもファッションですね。実際に〈ヘクティク〉のショップには、スケート用のギアは置かなかったですから。スケートカルチャーにハイファッション的な目線を取り入れたり、その逆をやったり。今となってはそこまで新鮮味はありませんが、その頃はそういうゾーンが無かったんですよ。ただ、やっぱりスケーターである僕がやっていたので、始めの頃はスケートショップとして扱われることが多くて…、正直葛藤はありました。