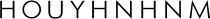FEATURE |
『リップヴァンウィンクルの花嫁』岩井俊二監督インタビュー 残酷で美しい現代のフェアリーテイルはいかにして生まれたのか。

黒木華演じる「皆川七海」は、1992年生まれの23歳、東京で派遣の教員をしているという設定だ(ちょうどバブル経済崩壊後の失われた20年と呼ばれた時代を七海は生きてきたことになる)。出身は岩手県の花巻、宮沢賢治の故郷として知られた土地である。七海のSNSのアカウント名「クラムボン」は宮沢賢治の童話のタイトルに由来する。東京と東北。やはり、この設定には「3.11以降の物語」という意味合いを思わずにはいられないのだが。
—七海が岩手・花巻の出身だったり、SNSのアカウント名が宮沢賢治からの引用だったりするのも「3.11以降の物語」という意味合いからなのでしょうか?
岩井:そこは直接的には関係ないんですが、3.11というのは地震と津波と放射能だと思うんです。震災以降、その不安を我々は常に背負わされているわけです。市民レベルで見れば、一回は「きずな」とか言ってみんなでまとまってみたりはしたものの、その後は権力のある人たちが適当にやっている姿や長いものに巻かれていく様を見て、多くの人たちが残念な気持ちになっている。でも、それを声高に言うこともなかなかできないという状況で、サッカーの日本代表が次々に格下のチームに負け続ける試合を見せられているような残念な状態が続いている気がするんですね。「毎回こうだよな」というがっかりした気分が、日本全体の閉塞感につながっているんじゃないかと思う。ただでさえ放射能と、次いつくるかもしれない地震のプレッシャーを抱えているのに、さらに負け試合を延々と見せられ続けているという。いつまでも地震と放射能を意識して考えるのは難しいことでしょうけど、ふと振り返れば必ずそれがあるという、なかなか過去に体験したことのないストレスとプレッシャーのなかに今の我々はいるわけです。そのことをどう表現しようか、どこに逃げ道を見出したらいいんだという自分なりの葛藤が、こういう物語としてひとつの形を成したのかなという気がしています。

—閉塞感をどう乗り越えるか、どうやって自由になるか。
岩井:その感覚は『PiCNiC』(96年)や『スワロウテイル』(96年)の頃からありましたね。国や社会というものを国民なり市民が信じて日々暮らしていて、豊富なサービスが供給され、それで楽ができている部分もあるんだけど、そうしたサービスが次々に社会に乗っかることで結果的には全体が重くなっていく。何か見えないものを背負わされていくことで、どんどん疲弊していくという感覚がある。『PiCNiC』をつくった頃は、日本を病院のような国だなと思っていました。衣食住には困らないし、いろんなサービスが自動的についてきて、何も不自由なく生きていける感じなんだけど、何かが足りない。生きるうえで最も重要なものが足りていないような気がして、ああいう「病院から飛び出す話」を書いてみたり、日本にやってくる移民たちのワイルドな生活を描いたり(『スワロウテイル』)していたんですけど、その思想はずっと受け継がれていて、この『リップヴァンウィンクルの花嫁』にも流れていると思う。閉塞した社会のなかにいると非常に息苦しんだけど、そこからドロップアウトしたアウトローたちの何といきいきとしていることか。今回はそういうこともひとつの大きなテーマだったのかなという気がします。
前述の『泣いた赤鬼』について考えると、青鬼は友だちの赤鬼を助けた「やさしい鬼」のようで、実はそれによって赤鬼はずっと人間に嘘をつき続けなければならないカセをはめられる話とも読める。青鬼は善なのか悪なのか。『リップヴァンウィンクルの花嫁』の世界では、誰が赤鬼で誰が青鬼なのか。そのあたりのことを考えると、綾野剛演じる「安室」という男の存在がどうしても気になる。あからさまな悪人ではない分、屈託なく、より巧妙に人の心に入り込む。きわめて現代的な悪を綾野剛が絶妙な軽さで見事に演じている。

—『泣いた赤鬼』の話を踏まえると、綾野剛さん演じる「安室」の存在が引っかかります。岩井監督のなかで、この男はどのような人物として造形したのでしょうか。
岩井:安室は「なんでも屋」ですが、究極のサービス業というか、彼のなかでのサービス業の精神は一貫していてブレていないと思うんです。詐欺師のようでいて、騙して逃げ切るタイプではなく、いわば相手と共存する系の詐欺師。「共存する詐欺師だったら悪くないよね」と思ったら大間違いで、悪徳占い師に巧妙に洗脳されるみたいに、ずっとそばに居られて殺されない程度に飼い殺しにされていくということなので…。
—いちばんタチの悪い悪人というか。
岩井:そう。エサも持ってくるし、恩も売ってくる。安室という男は悪人像としてはしっかりあると思うし、そういうつもりで描いてもいるんですけど、ただ、その男が悪いことをして懲らしめられる話ではなくて、そんな彼ですら七海と呼応して人間らしさを見つけていくみたいなことにならないかなというのが、自分のなかの願いとしてはありましたね。
—安室と出会わなければ七海はもっと普通に暮らしていたかもしれない。安室と会ったことで客観的には堕ちていくように見えるけれど、実は安室と関わることで七海は生きる実感のようなものを得ていくともいえるわけですよね。
岩井:そうなんです。一見すると七海にとってはどんどん堕ちていく話なんですけど、堕ちているように見えて実は昇っているような、そういう話がつくれないかなと思っていました。社会のヒエラルキーを堕ちていく話というのは、往々にして非常に失礼なことになるんです。この前までお屋敷に住んでいた人が長屋住まいになるくらい落ちぶれてしまった、というような。堕ちた先にも人は住んでいるし、その人たちなりの生活があるわけじゃないですか。「長屋の人たちがそんなに悪いのかよ」っていうことにもなるし(笑)。この社会から堕ちることは、実は解放されることだったり、堕ちているように見えて逆に伸びあがっていくことなんじゃないか。そういうことを描けたら、とは思っていました。