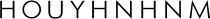FEATURE |
『リップヴァンウィンクルの花嫁』岩井俊二監督インタビュー 残酷で美しい現代のフェアリーテイルはいかにして生まれたのか。

—この映画ではSNSがとても重要なツールとして描かれています。2001年公開の 『リリイ・シュシュのすべて』ではネット掲示板(BBS)が重要なモチーフになっていました。今はあの頃よりもさらにネットがパーソナルなメディアになったわけですが、今回はそのあたりの変化も描きたかった部分だったのでしょうか?
岩井:ツールの変化というより、SNSが我々の社会にどんな影響を与えているのかが重要だと思います。新しいものなので、どうしてもみんな半信半疑で見ていると思いますが、実はそれまでの社会のあまり良くなかった部分を補完する役割を偶然担ってしまっているのかもしれないと思うことがある。他人同士が平気でしゃべる場所なんて現実にはまずありえない。現実社会では他人と壁をつくりまくって他人面しているけど、まるでその反動のようにSNSでは見知らぬ人と会話をしまくっている。あたかも他人との会話をこの場所に隔離してしまったかのように。そのことをみんなもうちょっと意識したほうがいいんじゃないかなという気はします。本当にそれで良かったのか、もっと現実の社会でお互いにコミュニケーションをとっても良かったんじゃないか、という反省として。海外で暮らしていると、知らない人と道ですれ違って目が合ったら「ハロー」なんて挨拶するのは日常茶飯事ですけど、日本ではまずないですよね。じゃあ日本人がそんなにシャイな人たちなのかといえば、フェイスブックやツイッターが入ってきたら、たちどころに他人と会話をしているわけです。そういう意味でも、そもそも自分たちがどんな姿をしていたのかをあらためて考えさせられるのがSNSなんじゃないでしょうか。
—考えてみると、いつの間にか他者との関わり方がずいぶんいびつな形になっているわけですよね。
岩井:現実社会ではなるべく他人と関わらないようにしながら、SNSのなかでは他人としゃべりまくり、「いいね」を押し合ってやさしさを確かめ合ったり(笑)、みんなが多重人格化しているような不思議なことになっていますよね。
—そういえば、予告編で黒木華さんがかぶっている「ねこかんむり」が印象的ですが、あれはやはりSNSのアイコンのイメージですか?
岩井:そうですね。誰もがキャラクターをかぶっている社会の象徴というか。LINEのスタンプなんかもそうですけど、本来だったら恋人にしか使わないようなエモーションをわりと平気で他人にぶつけてきたりして、「この人、俺に気があるんじゃないか」みたいな状態で送られてきますよね?(笑)。SNS上ではお互いやさしく、愛に満ちあふれた状態なんだけど、むしろそこに吸い取られてしまって現実社会はどんどん殺伐としているような気もします。それってどうなんだろう、と。でも、それはSNSが悪いわけじゃなくて、その手前の社会にあまりにも他人との関わりがなさ過ぎたので、みんなそこに殺到しているだけなのかもしれない。そうしたひとつのあだ花と見たほうがいいんじゃないかと僕は思いますけどね。

—SNS的なコミュニケーションが進むことで、ネットのなかでこれだけいろんな人と会話をしているんだから現実社会でももっと人と関わったほうがいいと思う人が増えるのか、あるいはネットで完結してしまって現実はますます殺伐としていくのか。今はそのどちらにでも転べる狭間にいるような気がします。
岩井:たとえば友だちに久しぶりに電話をする場合、「お元気?」みたいなあいさつや通り一遍の話をしてから本題に入って、電話を切る時もパッと切れないから何か言ってから切るわけですね。メールにしても枕詞みたいなことを最初に書かなければならないけど、LINEやツイッターのメッセージ系になると、久しぶりなのに前置きもなく、いきなり要件を突きつけられたりする。そういう簡単なコミュニケーションが主流になると、全体的にやや淡泊になるというか、それ以前にわずらわしいと思っていた部分が削がれてくるのかもしれない。そうすると、直接会って会話をしていても、SNSの癖みたいなものが影響したり、人のコミュニケーションのあり方が微妙に変更させられることはおそらくあるんでしょうね。
—コマ切れのコミュニケーションが主流になるなかで、今回の作品はそうした風潮に逆行するかのように上映時間が3時間という長尺ですね。
岩井:今、インターネットのおかげで映像もフッテージ(断片映像)のようになっていると思うんです。映画の黎明期を思い出すんですけど、あの時代は映画といっても数分間しかなくて、ただ駅に列車が入ってくるだけとか、飛行機が飛び上がって壊れて終わりとか、そういうものしかなかった。今YouTubeを見ているとそんな感じのものが多いじゃないですか。1周してまたそこに戻っているのかなという気がするんですけど、だからといって悪くなったとは全然思っていなくて、新しいツールが出てきたからそうなったんだろうし、映画の黎明期に起こったようなことが新しいフェーズに入ったんだなと思います。ただ、世の中の流れはそうなんだけど、僕の場合はそれと比べてどうこうではなくて、あいも変わらず好きでこういうことをやっているだけなんですよ。それ以上でもそれ以下でもない。そうしたら、とうとう3時間になってしまったという(笑)。
—撮影についても少しうかがいたいのですが、今回6Kのカメラを使って比較的少人数のスタッフで撮影された、と。
岩井:6Kというのは、今カメラのスペックがそこまで来てしまったので、それで撮るとそうなるという話なんですけど、便利といえば便利で、たとえばマイクが映り込んでしまってもトリミングできる。仕上がり自体は2Kになるので、画面の一部を切り取って引き延ばしても画質が落ちないんです。深夜ドラマの『なぞの転校生』(2014年。プロデュース&脚本)の時は時間がなかったので、引きの画で撮っておいて、アップが欲しかったらそこから切り取ったりしていました。それが可能な画質だからそれを使おうと。少人数のスタッフに関しては、自分がせっかちなので、待つのがダメなんですよね。ウチは照明部がいないんです。ということは自分でやっているということなんですが、照明は最初に現場に入ってセッティングにも時間がかかるので、自分でやったほうが早い。
—早いし、自分のイメージ通りにもなる、と。
岩井:そうですね。大概のことを自分でやってしまうので、そんなにスタッフの数がいらないということはあるかもしれない。今回、サウンドの最終ミックスまで自分でやっているんですけど、そういうクリエイターは増えているんじゃないですか。昔はそういうわけにはいかなかったですけど、今はツールがどんどん自分のパソコンに入ってくるようになっているし、若い人たちの中には自分で撮影して自分で編集して自分で仕上げるという人も多いですよね。
—今回の撮影は、このところ岩井監督と一緒に組むことの多い神戸千木さんですね。その師匠にあたる篠田昇カメラマン(岩井監督とのタッグで知られた名カメラマン。2004年死去)を失って以降、撮影をどうするのか、画づくりをどうするのかという問題があったのではないかと勝手に想像するのですが。
岩井:もともと自分で撮影もしていたので、それはなかったですね。篠田カメラマンとはいいコンビだと思っていたし、お互いのことをわかっているから楽ではありましたけど、僕の場合、あまり人の技術に依存しない方だと思います。お互いに依存しちゃダメだと思うんですよ。各々が技術をしっかり持ったうえで重なるからいいセッションが生まれるわけです。お互いが撮るべき画をわかっていれば、どちらがカメラを持とうが実はあまり関係がない。僕の場合、自分で触らないとわからないので自分で撮影をやったり照明をやったり美術をやったり編集をやったり音楽をつくったりするんです。そうすることでしか学習のしようがないので、大概自分でやってしまう。だからといって人に触らさせないということではなくて、自分でやることによって理解したうえで、予算がある時は人に頼んでやってもらいます。今回は予算がなかったので。大概のことを自分でやっている時は予算のない時です(笑)。
「やんちゃな作品をつくったな」。岩井監督は『リップヴァンウィンクルの花嫁』を撮り終えてそう実感したというが、それは簡単に「集大成」「最高傑作」とレッテルを貼られてしまうことを拒む作家としての姿勢の表れなのかもしれない。岩井俊二が作家性で観客を呼べる日本でも数少ない映画監督であることは疑う余地がない。だから、タイトルと予告編だけではどんな話なのか判然としない本作も、「岩井俊二待望の実写長編」とだけ謳えば本当はそれで済む。得体のしれない現代ニッポンのすがたを浮き彫りにし、そこに一筋の光を見ようする『リップヴァンウィンクルの花嫁』は、観る者にとてつもない「おみやげ」を手渡す。それは一見ずしりと重いようでいて、白くふわりと空に舞い上がるはかない美しさをたたえている。誰のものとも似ていない、唯一無二の岩井俊二作品である。
リップヴァンウィンクルの花嫁
監督・脚本:岩井俊二
出演:黒木華 綾野剛 Coccoほか
原作:岩井俊二『リップヴァンウィンクルの花嫁』(文藝春秋刊)
撮影:神戸千木
美術:部谷京子
音楽監督:桑原まこ
制作プロダクション:ロックウェルアイズ
配給:東映
©RVWフィルムパートナーズ
2016年3月26日(土)公開