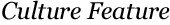話題のドキュメンタリー映画『エンディングノート』が語りかけるものとは。
2011.09.30

―そもそも、お父様の病気が発覚した段階で撮ろうと思ったのか。それとも、他に別の理由があって撮ろうと思ったのか。撮影を決意するタイミングやきっかけはあったのですか。
砂田:父親にカメラを向けるというのはもっと昔からやっていたことで、カメラ自体は小学生ぐらいからいじっていたし、家族を撮るということも割と早い段階からやっていました。でも、病気になった直後というのは、やはりそれまでと同じように撮るということはできなくて。そこで一回すべて止まってしまって、カメラを向ける気にもなりませんでした。先ほども言ったように、「撮りたい時にしか撮らない」という気持ちを強く持ってからは、比較的撮れるようになりましたね。
―撮られることにお父様は何か仰っていましたか。例えば、嫌悪感を示したりというようなことは?
砂田:それはなかったですね。そうなる前に、もうやめました。これはそういうような状況になるだろうなという風に予測してカメラを向けないようにしていたので。怒ったりというようなことはなかったです。
―作中に自分でナレーションをするというアイデアはいつ思い付いたのでしょうか。
砂田:それは完成する直前に決まったんですけど、決まる以前はずっと男性に読んでもらおうと考えていました。できるだけ、この作品を作っている人間との距離感というのを保ちたかったから、自分が読むことでセルフドキュメンタリーの色を強めるのが嫌だったんです。ただ、亡くなった人の言葉を生きている人間が勝手に語るということについての違和感やタブーというものに対する責任を、どこかで取らなければいけないとも思っていました。そうした時に、自分が読むことはある種責任の取り方の一つになるのではないかと思ったんです。この作品に90分お付き合いくださいという風呂敷を広げるやり方が一番良いのではないかと。

―ナレーションや構成、お父様のキャラクターという要素がとても印象的で、人の死を扱った映画なんだけど、その死に向かって行く姿というよりは、生きることそのものに強く焦点が向いている映画だと感じました。
砂田:例えば、映画内では「To Do」というような形で、あれやるこれやると演出していましたけど、あれはもちろん私が考えたチャプターだし、父親自身は死に向かっていったわけではなく、ただ毎日を一生懸命生きていただけだと思うんです。いつかは来るだろうけど、それまでは毎日頑張ろうという気持ちで、今やれることは今やっておこうという姿勢が、見方を変えれば段取りに見えたということだと思います。仰る通り、私が描きたかったのは、死を段取ることの大切さとかいうことではまったくなく、最後の日まで生きることそのものだったと思っています。
―お父様は自分にとってどういう存在だったのか。理想の父親だったのか。砂田さん自身から見たお父様というのを、映画を通してではなくダイレクトに聞かせてください。
砂田:やっぱり思い返してみて、最初に出て来るのは面白い人だったなということですね。それは色んな意味で。愛情の表現も、言葉の発し方も、段取りも、色んなこと含めてエンターテナーだったなと思います。
―自分の肉親に対してそこまで客観的な視点を持つというのはなかなか難しいことなのではないでしょうか。そのような砂田さんの視点というのは映画にも表れている気がします。
砂田:家族のなかで父親の話をする時なんかも、最初に面白い人だったよねという話になりますね。笑わせてもらった記憶しかないんですよ。
―映画を観ていると、他のご家族の方、例えばお兄様やお姉様にしても、ご家族との距離感というのが印象的でした。べったりでもなく、かといって疎遠な関係でもない。その辺りの家族関係というのは、他の家族には観られない良さがありますよね。
砂田:その離れすぎず付きすぎずという、微妙な行ったり来たりをしている感じですね。