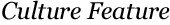廣山直人と倉石一樹。 新譜と新店舗、そしてバンド。
2011.10.31

―そういったスタンスは倉石さんらしいですよね。ちなみにお二人ともに確固たるステータスを築きながら、なぜ新しい環境でのクリエイションに挑戦するのでしょうか。
倉石:僕は洋服を作るのが好きなんですよね。最近では工場にも頻繁に顔を出すようになったし。やり出したら、糸から作りたくなってきたり。突き詰めていくと、どんどん物作りの面白さにハマっていってしまい。お店にも工業用のミシンを置こうと思っていましたし。
―代々木を拠点にするあたりからも、これまでとは違うアプローチを試みているように感じます。
倉石:異なるアプローチを強く意識することは無いんですけど、これまでとは違う客層に見てもらいたい気持ちはあったかもしれません。実際、自分自身も年齢を重ねて洋服の趣味も変わってきましたし。今作っている洋服は、かなりオッサン臭いですからね(笑)。
―直人さんもメジャーからインディーズへと立場を変えましたが、それはどういった気持ちからなんですか。
直人:もっとフレキシブルに動きたかったからですね。これだけ音楽の表現方法、表現場所が多様化しているなかで、作った曲を何ヶ月も暖めておくのはどうかなと。今日作った曲を、明日メンバーに聴かせて、一週間後にはライブで披露したいんです。
―改めてインディーズで活動してみて、いかがですか。
直人:楽しいですよ。思いついたアイディアをどんどん試せますし、自分たちの意志でいろんなことを決断できる。もちろん大変なこともありますけど、それ以上に楽しんでいます。
―そんななかソロとしての3作目『Spaces in Queue』では、どういったことを表現しようとされたのでしょうか。
直人:より人間味のある表現を心がけましたね。ここまでテクノロジーが進化していると、どんな曲も作れちゃうじゃないですか。そこをあえてデジタル技術に頼りすぎず、一発録音にしてライブ感を重視しています。ハードディスクに録音して、修正を重ねて、というのが当たり前だった僕にとっては、このアナログな曲作りが逆に新鮮なんです。
―時代に逆行しているんですね。倉石さんは聴かれましたか。
倉石:もちろんです。どの曲も良かったですね。僕の知っている直人の好きな音楽がボンヤリ見えるというか、洋楽のような感じ。

―倉石さんは先頃オープンしたショップ「Heather Grey Wall」は、コンセプトとかはあるんですか。
倉石:パタゴニアの日本1号店が目白にあるじゃないですか。あそこが"デスティネーション・ストア"と言われていて、つまり"目的地となるショップ"というコンセプトで始まったんですよ。「Heather Grey Wall」もそうなってくれたらと思っています。このお店のために足を運んでもらえるような。で、どうせ来てくれたならゆっくりしてもらいたいので、このテーブルも椅子もそのままにしようかなっと。
―さすがに一般のお客さんが座るのは、緊張しそうですけどね。
倉石:そんなことないですよ、気軽に座ってください。僕もコーヒー出す気まんまんですから(笑)。
―倉石さんも店頭に立つという話を伺ったのですが。
倉石:そのつもりです。全部、半額にしちゃったりして(笑)
直人:それは面白いですね(笑)
倉石:最終的にはあげちゃったりして(笑)
―さすがにそれは無理でしょうけど、倉石さんが立っているだけで、会いに、見に来る方も増えそうですよね。コミュニケーションという部分では、倉石さんは服作りにおいても絶妙な距離感で人と仕事をしている印象があるのですが。
倉石:誰かと一緒に物作りをするときは、僕自身がその人のことを尊敬しているのかが重要なんですよね。だからこそ僕はパートナーの意見を尊重するようにしています。
―そのサジ加減が絶妙なのかなと。
倉石:宮下君とやるときも、彼の服作りが好きだから、ですからね。お互いの意見をぶつけ合うと言うよりも、彼の個性をのなかに僕の感性を潜ませるようなイメージ。
―ファッションと音楽という意味で違いはありますけど、直人さんもバンドとソロでまったく違う作品を作っていて、個性を巧く使い分けている印象があります。
直人:そういった意味では倉石さんと近い部分はあるかもしれません。ボーカルをリエフゥにお願いしたり、ビジュアルのディレクションを倉石さんにお願いするのは、彼らの色が好きだし、取り入れたいからですからね。最初から信頼しているので、上がってきた作品に対して、文句の付け所がないんです。
―そのへんの感覚が、お二人は似ているというか。
倉石:そうかもしれませんね。今回のツアーTシャツのデザインも、いちよう要望は聞きますけど、ほとんど僕の独断で進めていますからね(笑)。感覚的な部分で理解しあえている、というのはあると思います。