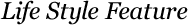HOME > LIFE STYLE > FEATURE
目利きが選んだ10のお気に入り。 No.2 小木"Poggy"基史さん
2011.08.30
No.7 エムシーエム バイ フェノメノンのショルダーバッグ
人気の移り変わりを実感した思い入れ深いブランド。
〈エムシーエム(MCM)〉は、LWTを始めるときに、スタイリストのMASAH君と「エムシーエムいいよね!」と話しをしていて取り扱いをスタートしたブランドです。ちょうどその頃、〈アディダス Y-3(adidas Y-3)〉をやっていたマイケル・ミハエルスキーが、〈エムシーエム〉のディレクターに就任して、イタリアの『ヴォーグ』などに、広告が出始めた頃でした。当時はヒップホップ好きな人たちからは、絶大な人気だったんです。アメリカに持っていくと「ワ~オ! エムスィーエームッ!」みたいな反応で。でも日本だと、年上の方たちに、汚い物を見るような怪訝な顔をされたりしました......。MCMの人気が絶頂期から下り坂になっていった90年代を知っている人たちには、受け入れてもらえませんでしたが、最近は若い子たちが持っていたりするんです。昔を知らない世代が、純粋にかっこいいと思って持ち始めているんだと思います。10月に発売する〈エムシーエム バイ フェノメノン(MCM by PHENOMENON)〉は、これで3シーズン目。次のはすごく良くてお薦めですよ。ブランドの人気が移り変わっていく様子を、初めて自分で目の当たりにしたのが、〈エムシーエム〉だったので、思い入れもすごくありますね。

〈エムシーエム〉人気の火付け役は、やっぱり〈フェノメノン(PHENOMENON)〉。新作はタイガーカモ柄がすごくかっこいいので期待してください。¥79,800(ユナイテッドアローズ 原宿本店 メンズ館 03-3479-8180)
No.8 リーガルとヴァンのコラボシューズ
ずっと復刻して欲しかった念願のシューズです。
〈リーガル(REGAL)〉のシューズも、LWTで取り扱ったときは、上の世代は面白がってくれたのですが、他の人たちからは、「え!? リーガル?」という感じで、良い反応をもらえなかったこともありました。この〈リーガル〉と〈ヴァン(VAN)〉のコラボシューズは、64年に発売されていたものの復刻版です。以前、〈リーガル〉本社にお邪魔したときに、大量のアーカイブの中からこれを見つけて、もう一度発売できませんか? と、ずっとお願いし続けていました。それが、ようやくOKをいただけて、昔のロゴ、昔の形そのままで、リリースすることができました。

よく学びよく遊べのアイビーの精神をリスペクトして、復刻させるだけでは面白くないので、よく見るとクレイジーカラーになっているものを14足だけ製作してもらいました。そちらはユナイテッドアローズ 仙台店のみの発売。でも、遊びすぎたかもしれません(笑)。¥50,400(ユナイテッドアローズ 仙台店 022-722-3862)
No.9 チョロQ zero for BEAUTY&YOUTH
角張っているクルマに思わず反応してしまう。
日本の旧車が好きで、特に70年代~80年代の角張ってる頃のクルマを見ると、思わず反応してしまいます。以前はこのチョロQと同じ、〈ホンダ(HONDA)〉のシティに乗っていて、シティにクロームメッキのホイールを履かせて、すごく気に入っていました。ヴィンテージデニムに新しい〈ナイキ(NIKE)〉のスニーカーを合わせるみたいな感覚ですよね。今は家族もできて、なかなか旧いクルマに乗るのは難しい環境ですが、例えば当時のデザインで、中身がハイブリッドになっているとか、そういうクルマが出て来たら、また絶対に乗りたいと思います。

先先日パリに行ったときに、ラルフローレンのカーコレクションの展示があったんです。1900年代初頭からのすごいクルマがいっぱいで、めちゃくちゃかっこいいんです。でも自分にリアルなのは、やっぱり80年代の日本のクルマなんですよね。 ¥1029(ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ 渋谷公園通り店 03-5428-1893)
No.10 ユナイテッドアローズ 原宿本店 メンズ館
UAの根底をリスペクトしながら、自分たちの世代感を大切に。
自分が新しいことをやらせてもらえている唯一の場所が、UAの原宿本店の地下のフロアですし、ここは間違いなく"お気に入り"です。UA創業メンバーの想いを大切にしながら、いろいろなことにチャレンジさせてもらっています。例えば店内にDJブースを設置したこともそうですし、洋服を着せたトルソーを、売り場の上の方にディスプレイしたのも、ヨーロッパの老舗のディスプレイの方法を、参考にしたりしています。今後は、歴史を感じられるものを混ぜていったり、ライフスタイルを感じられる売場にしていこうとメンバーと話しをしています。UAの不偏的な根底部分をリスペクトしながら、自分たちの世代感を大切にしていければ良いなと思っています。