RECORDING, SOUNDS and ENVIRONMENT
オノ セイゲン
空間デザイナー/ミュージシャン
録音エンジニアとして、82年の「坂本龍一/戦場のメリークリスマス」にはじまり、多数のアー ティストのプロジェクトに参加。87年に川久保玲から「洋服が奇麗に見えるような音楽を」という依頼により作曲、制作した『COMME des GARCONS / SEIGEN ONO』ほか多数のアルバムを発表。
Photo by Lieko Shiga
音楽評論とは何か
2011.04.16
2月にサイデラ・マスタリングのロビーで画家クラーク志織さんの個展「7人の音楽評論家の肖像展 / クラーク志織」があったことは前にも紹介した。編集者、ミュージシャン、レコード会社の制作宣伝担当者は必読の7人それぞれの「音楽評論とは何か 」の一言を紹介。
 音楽に評論は必要はないと思う。人それぞれが思うことを語ればいい。
音楽に評論は必要はないと思う。人それぞれが思うことを語ればいい。
ぼくが書くものもその程度のものだ。ただ、音楽は人の中から生まれ、言葉を介してつながりをもとうとするのも人間だ。ましな言葉が書けたらいいなと思う。

音に共鳴し、奏でる人の言葉を聴き、文字で応えること


反応
佐藤英輔
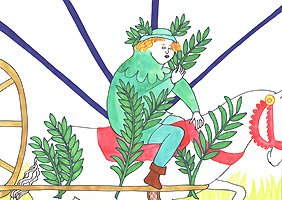
音楽というエンターテインメントの一部。と同時に、最良のそれは音楽を通じて世界を見るための道しるべとなる。
高橋健太郎
私にとっての音楽評論とは、その音が、言葉がどういう時代に、どういう状況下で、どういう人間からどこに向かって発せられたものなのかを考えることです。
それはつまり、音楽を成り立たせている環境/世界と私自身の関係性、私自身の受け止め方、私自身の生き方を考えることでもあります。結局、自己との対話、ということでしょうね。
よろしく哀愁。
松山晋也

ぼくが書くものもその程度のものだ。ただ、音楽は人の中から生まれ、言葉を介してつながりをもとうとするのも人間だ。ましな言葉が書けたらいいなと思う。
青木和富

音に共鳴し、奏でる人の言葉を聴き、文字で応えること
今井智子
→ twitter

ことばでひとを音楽に惹きよせること、誘惑すること。
音楽の聴き方をどうひろげるか、聴き方の多様性を示唆すること。
音楽をめぐって書いていても、
それだけでもひとつの文学であるかのようにふるまうこと。
ことばによって、音楽/音楽家に、(可能なかぎり)寄り添おうと、共感しようとすること。
小沼純一
音楽の聴き方をどうひろげるか、聴き方の多様性を示唆すること。
音楽をめぐって書いていても、
それだけでもひとつの文学であるかのようにふるまうこと。
ことばによって、音楽/音楽家に、(可能なかぎり)寄り添おうと、共感しようとすること。
小沼純一
→Blog

反応
佐藤英輔
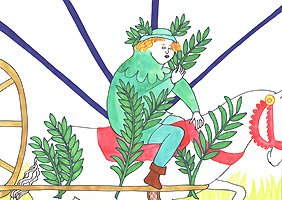
音楽というエンターテインメントの一部。と同時に、最良のそれは音楽を通じて世界を見るための道しるべとなる。
高橋健太郎

私にとっての音楽評論とは、その音が、言葉がどういう時代に、どういう状況下で、どういう人間からどこに向かって発せられたものなのかを考えることです。
それはつまり、音楽を成り立たせている環境/世界と私自身の関係性、私自身の受け止め方、私自身の生き方を考えることでもあります。結局、自己との対話、ということでしょうね。
よろしく哀愁。
松山晋也
「音楽評論とは何か 」どこかでアンコール展示してくれると思うので覚えておこう。








