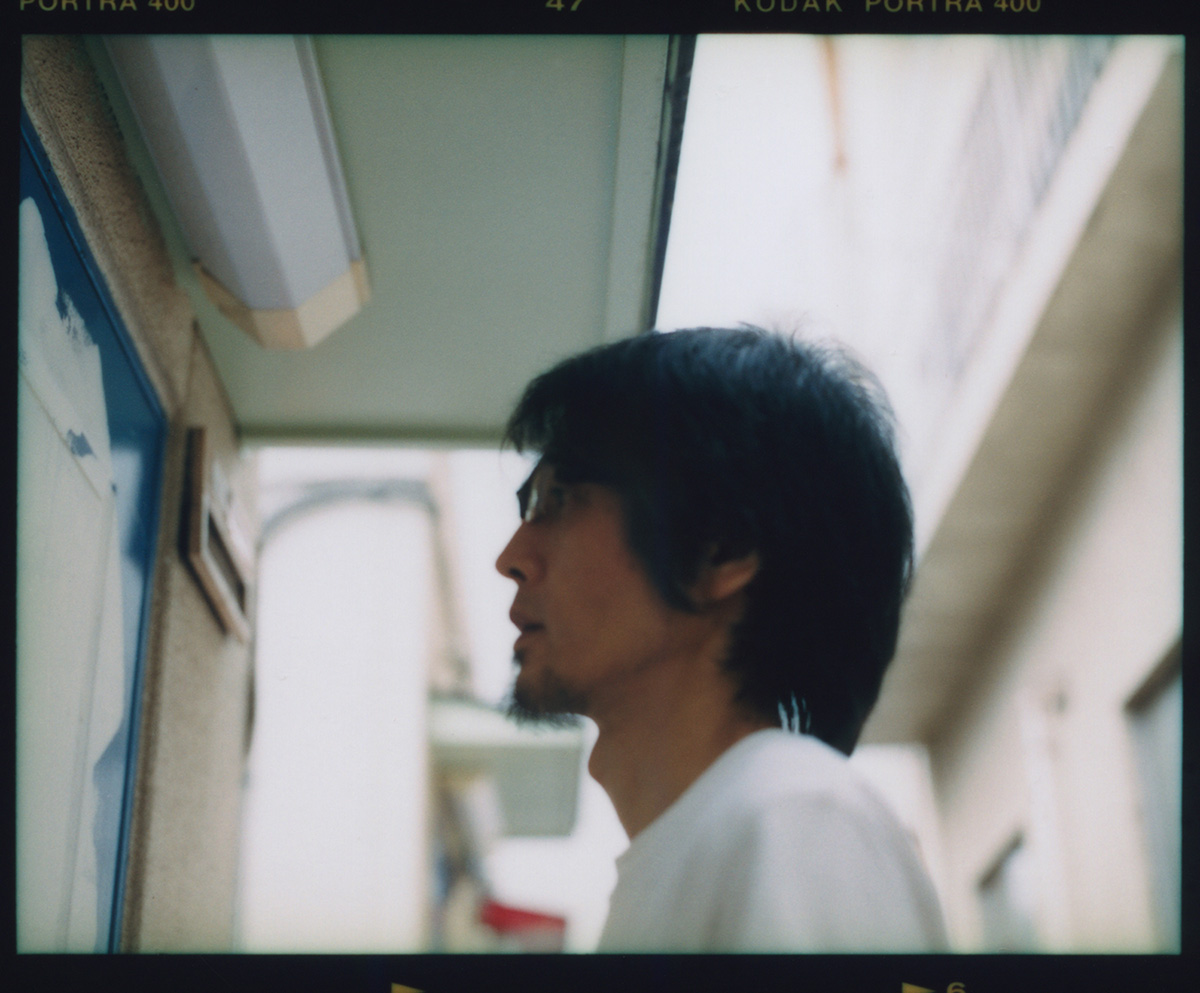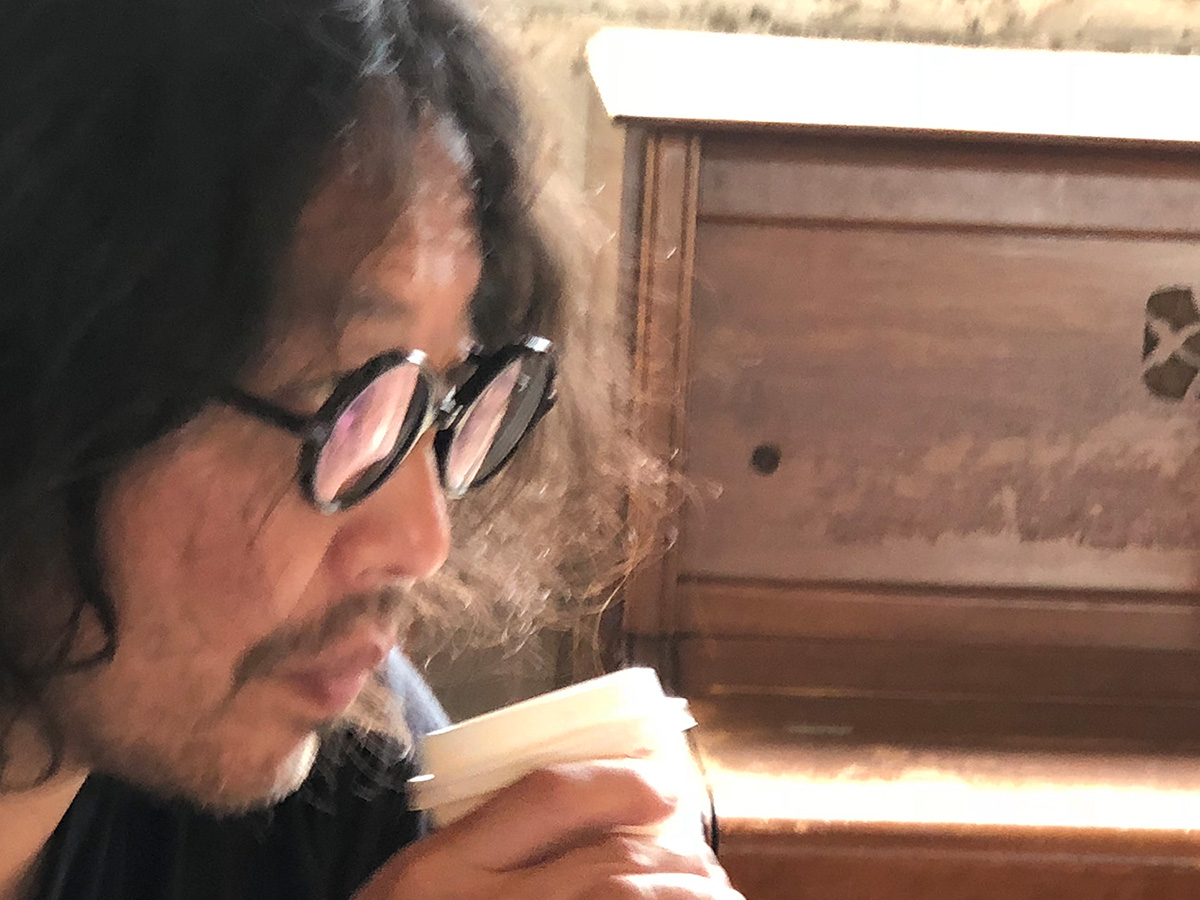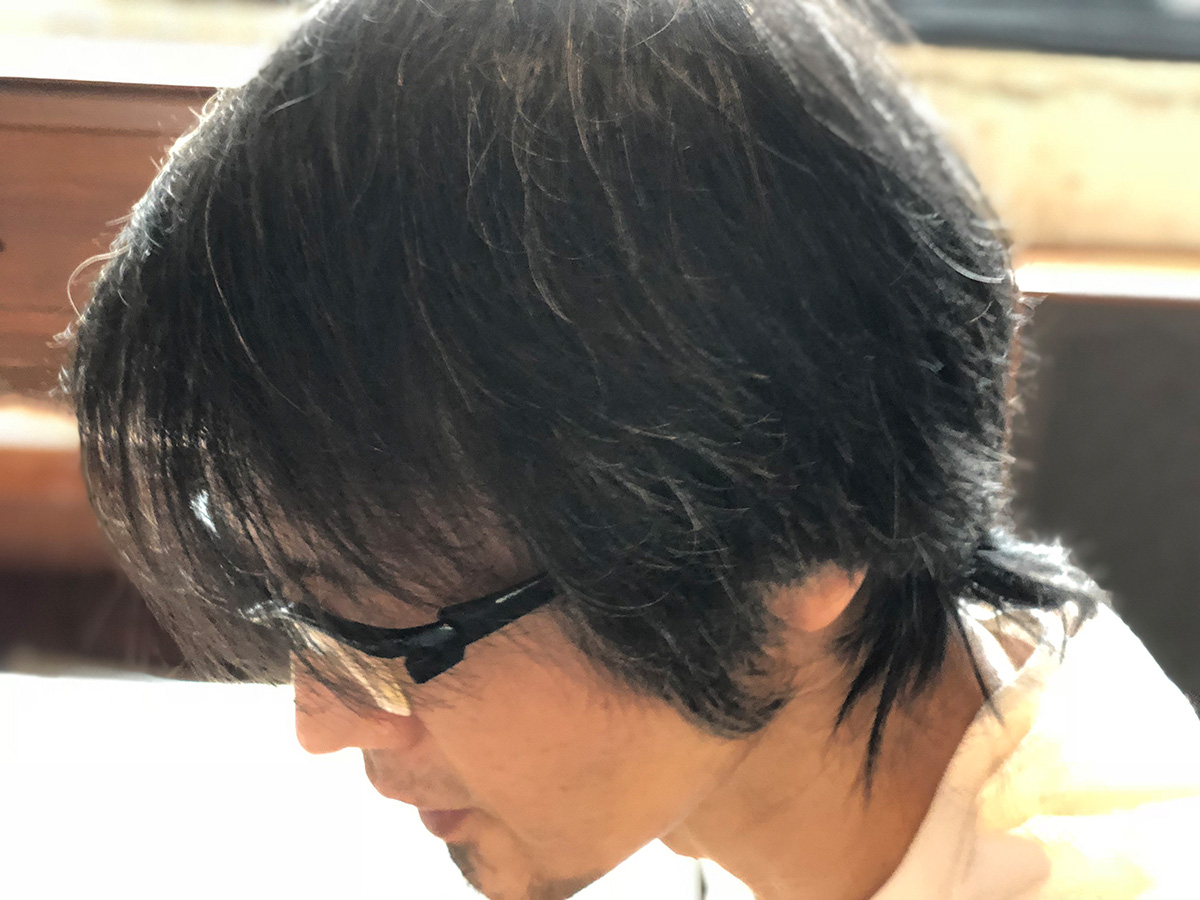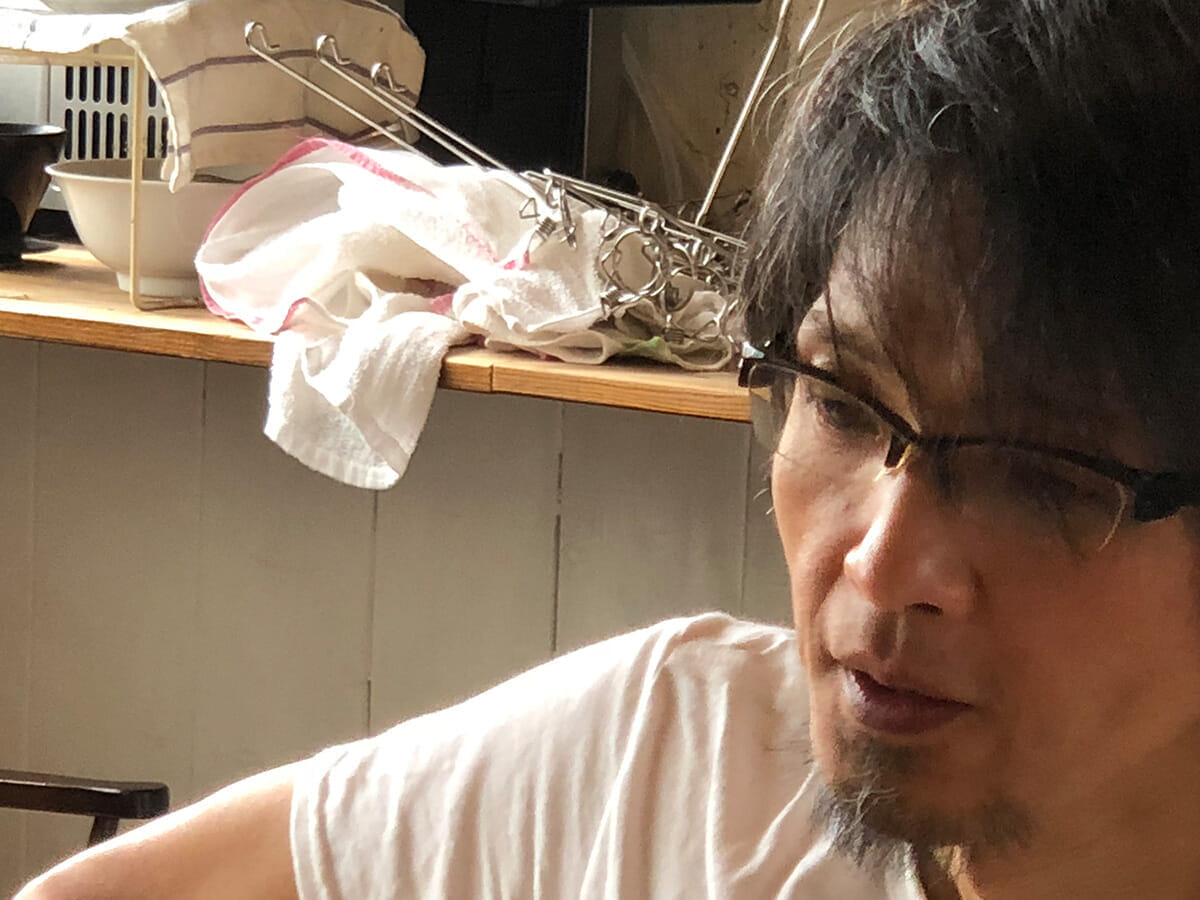曽我部恵一
1971年生まれ。1990年代からサニーデイ・サービスの中心人物として活躍し、バンド解散後の2001年からはソロアーティストとして活動を開始。現在はソロのほか、再結成したサニーデイ・サービスなどで活動を展開。2004年に自主レーベル「ROSE RECORDS」を設立し、自身の作品を含むさまざまなアイテムをリリースしている。
よしもとよしとも
1964年生まれ。85年、四コマ漫画『日刊吉本良明』で第1回あすかまんがスクールに入選してデビュー。86年、岡崎京子の『セカンドバージン』のアシスタントを務める。長編『レッツゴー武芸帖』『東京防衛軍』発表以降、『青い車』など完成度の高い短編を多数発表。『青い車』は2005年に奥原浩志監督によって映画化された。2010年、長嶋有の小説『噛みながら』を漫画化(『長嶋有漫画化計画』収録)。現在、noteにて、新作小説『イケメン漁師』を公開中。note.mu/yoshitomo2018
『the CITY』から『オーディナリーミュージック』へ。
2016年、サニーデイ・サービスは、珠玉のポップソング集『DANCE TO YOU』をリリースし、2017年の『Popcorn Ballads』、2018年の『the CITY』では、混沌を抱え込みながらもたまらなくロマンティックな楽曲群の魅力もさることながら、突如ストリーミング配信のみという最先端の手法でリリースして我々の度肝を抜いた(のちにアナログも発売)。さらに、『the CITY』のジャケットに、よしもとよしともさんが写っていたことにも驚かされた。90年代からお互いの創作にシンパシーを抱いてきた2人。2009年に曽我部恵一BAND『ビレバンのソカバン』のジャケットをよしもとさんが描き下ろしている関係性ではあるが、ここにきて2人は急接近している印象もある。
まず、お2人を結ぶ最近のトピックとしては、サニーデイ・サービス『the CITY』のジャケットによしもとさんとそのご家族が写っていることだと思いますが、あれはどういう経緯だったのですか?
曽我部 よしともさんの娘さんがこの店(曽我部さんが経営する下北沢のカフェ『CITY COUNTRY CITY』)でバイトしているので時々顔を合わせることもあって、よしともさんも佳代さん(よしもとさんの妻で映像作家の中村佳代さん)も以前から知っているから、一緒に写りたいなと思ったんです。他にもエンジニアさんのご家族やベースの田中(貴)君がよく行くラーメン屋のおやじさんなんかも入ってます(笑)。自分の友だちだけだと年齢とか雰囲気が近い感じになってしまうので、なるべくいろんな人たちが写っている集合写真にしたかったんです。
サニーデイ・サービス『the CITY』ジャケット
ゆるく知り合いだけど、そんなによく知っているわけでもない人たちの集合写真。
曽我部 そう。だから、各々会ったことはなくても、どこかでつながっていたりする関係性ですね。
まさにザ・シティというか、街をそのまま切り取ったような写真なのかな、と。
よしもと うちの家族はなんか妖怪っぽいというか、魑魅魍魎感が出てる(笑)。
バックグラウンドを知らずにこの写真を見ると、「ここに写っているのは一体どういう人たちなんだろう」という、ある種ザワザワする感覚になるというか、普通に「親戚一同集まりました」みたいにも見えるし、結婚式のサクラで集められたニセの親戚みたいな不穏さもあります(笑)。
曽我部 どう見えているのか今ひとつよくわからないんですけど、自分から見ると、知り合いの集合写真以上でも以下でもないんですけどね。誰かが死んだ時に集まってくれた人たち、たとえば、「僕が死んだ時に集まってくれるかもしれない人たち」みたいな。
ああ、そう言われると確かにそういう写真にも見えてきますね。ちなみに、よしもとさんはどういう感じでオファーされたんですか?「こういうコンセプトでこういうビジュアルで」という説明はあったのでしょうか。
よしもと 確かザ・バンドのジャケットを見せられたんですよね。
曽我部 ええ。集合写真のジャケットってそれほど多くないので、ザ・バンドのジャケットを見てもらって、「雰囲気的には多分こういうようなことだと思うんですけど」みたいな。
なるほど。ジャケットによしもとさんが登場された流れから、曽我部さんのTBSラジオの番組『オーディナリーミュージック』に出演されることになるわけですが、出演といってもトークゲストではなく、選曲を担当するゲストという形なんですよね。
※『オーディナリーミュージック』2018年4月30日・よしもとよしとも選曲 www.tbsradio.jp/247696
曽我部 そうなんですよ。普段は知り合いのミュージシャンに選曲をお願いすることが多いんですけど、ジャケットに出ていただいたつながりで、「よしともさんに頼むんだったら、今かな」と思ってお願いしました。
よしもと いやー、あれはやっていてすごく楽しかったです。
曽我部 あれって選曲するだけじゃなくて、音も完全に作り込んでましたよね?
よしもと 一応、完パケでお渡ししてます(笑)。番組は前半後半にわかれているんですけど、前半部分は20年前に作ったミックスです。
その前半部分の選曲は、1997年発表の短編『ライディーン』を描く時のB.G.Mというかサウンドトラックとして作られたということですが。
よしもと 本当は45分あるんですけど、真ん中で切ったらちょうどラジオの尺に収まるなと。90分テープにDJミックスみたいな感じで録っていて、その片面のちょうど半分くらいまでですね。
曽我部 番組で流れたのは、その時作ったもののままですか?
よしもと 基本はそうです。それをパソコンに落としたら曲ごとに音のレベルが違っていたので調整してお渡ししたという感じですね。
曲のつなぎもすごくスムーズでしたけど、じゃあ、当時からミキサーを使って作ってたんですね。
よしもと やってました。そうそう、確か『ライディーン』を描いている時だったと思うんですけど、妻が曽我部さんと仕事をしていて、CMのために『NOW』という曲を書いてもらったんです。
よしもと カセットに入った15秒くらいのデモだったんだけど、『ライディーン』を描きながらその曲を聴いた記憶がある。「ああ、いい曲だなあ」と。多分、時期的にも合ってると思うんだけど。
曽我部 97年か、そうですね。ちなみに毎回ああいうミックステープを作るんですか、漫画を描く時に。
よしもと 最近はiTunesでプレイリストを作って、という感じですけどね。ただ、iTunesってテープと違って終わりがないから、キリがないじゃないですか。
テープだと、45分とか90分とか物理的な制約がありますからね。
曽我部 ああ、やっぱそうか。僕、Spotifyのプレイリスト作っているんですけど、たぶん今20時間くらいありますよ(笑)。今は逆に制限がないのが面白いと思っているので、いっそのこと24時間分くらい選曲したいと思ってるんですけど。
朝から夜まで1日分のプレイリストをつくることも可能ですしね。
曽我部 そういうこともできるから、それはそれで面白いんですけど、ただ、この前よしともさんの選曲を聴いて、こういうコンパクトな選曲って大事だなとも思ったんですけどね。
よしとも 実は別のプレイリストも作ったんですけど、古いものを引っ張り出して聴いてみたら、結構いいんじゃないか、これ、と。
曽我部 うん、良かった。意外とロックンロール。ロックンロールでしたね。
よしもと 根っこにパンク/ニューウェーブがあるんだけど、パワーポップとかも結構好きなんです。そういえば、昨日はじめてテンプテーションズの60年代のライブを聴いたんですけど、めちゃくちゃカッコよくて。エンターテインメントって感じで。
曽我部 昔のカセットテープって全部とってあるんですか?
よしもと とってあります。高校時代に聴いていた80年代のものもほとんどありますね。結構いい加減に保管していて、聴き返すことはほとんどないんですけど。
『ライディーン』と『江ノ島』、漫画と音楽。
で、曽我部さんは、よしもとさんの『ライディーン』にインスパイアされて『江ノ島』(99年のアルバム『MUGEN』収録)という曲を作られたわけですよね。
よしもと ああ、俺の漫画を元にして曲を作られたことをご本人から直接聞いたことがなかったので…
ホントだったんだ、と(笑)。ところで、曽我部さんは漫画との親和性が高い方だと思いますが、漫画からインスパイアされて曲を作ることも多いんですか?
曽我部 もちろん漫画は好きなんですけど、「この曲はこの漫画から影響を受けた」というものは実はそんなにないんです。
直接的な影響ではなく、断片的にインプットされたものがどこかに影響しているというような。
曽我部 うん、そうですね。『ライディーン』くらいです。直接、この漫画からこの曲、というのは。
そうなんですね。ということを聞いて、よしもとさんはどう感じますか?
よしもと いやー、『江ノ島』を聴くと、「しっかりしなきゃな。こんな曲を書いてくれたんだから」と、いつも背筋が伸びる思いですよ(笑)。
曽我部 あの曲は、ライブで演ると風景がスパンッと見えるんですよ。本当にシンプルな、音数も言葉数も少ない曲なんですけど、風景があるのは、多分よしともさんの漫画の景色なんだと思う。そこの影響が強いから、スパンッと絵が見えるのかなと思いますけど。
もともとサニーデイのファン層とよしもとさんのファン層はかなりカブる印象がありますが。
よしとも まあ、俺は最近、全然漫画を描いてないから、知っているのも一部の人たちって感じだけど、サニーデイはどんどん新しいファン層が生まれているので…。
97年の『ライディーン』から『江ノ島』が生まれ、それから20年が経った2018年、サニーデイのアルバムジャケットによしもとさんが登場し、曽我部さんのラジオ番組の選曲を担当するというのは、90年代以降のカルチャー史的にも大きなトピックのような気がするんですけど、放送後のリアクションは結構ありましたか?
よしもと 放送は早朝の4時からだったんですけど、がんばって起きて、リアルタイムでTwitterをチェックしてました(笑)。結構、評判が良かったみたいで安心しましたけど。
後日談として、よしもとさんが選曲でピックアップしたことが縁となり、Hi, how are you?と横沢俊一郎がココナッツディスク吉祥寺店でインストアライブを行うことになった。よしもとさんが選曲した『オーディナリーミュージック』の余波が確実に何かを生み出していることは特筆しておくべきだろう。その辺りの経緯はココナッツディスク吉祥寺店のブログ に記されている。
よしもとさんは、漫画を描く時にご自分でサウンドトラックを作るくらいですから、音楽からインスパイアされて漫画を描くことも多いわけでよすね?
よしもと うん。なんか、最初に頭の中にモヤモヤしたものがあって、何かあるんだけど、形がはっきりしない。「こういう感じのもの」というのがまずあるんですけど、それを定めるためにいろんな音楽を引っ張り出してきて、「これがハマるかな」という感じで試してみたりします。あとは新しい音楽、今まで聴いたことのないような音楽を聴いた時に、それが後から何かの形になって出てきたりとか。両方ありますね。
曽我部 その最初のモヤモヤしたものを、音に置き換える、ということなんですか?
よしもと 理屈で考えていくと変な方向に行っちゃったりするので、もっと直感的というか、肌で感じる何かが大事で。それにはやっぱり音楽で形容するというか定めていくのがいいんですよね。
曽我部 それが、あの『ライディーン』のプレイリストになっているわけですね。
よしもと そうです。テープの後半にはスティーリー・ダンとかグローバー・ワシントンJr.とかも入っているんですけど。
曽我部 メロウな感じ。漫画の『ライディーン』のイメージに直結する感じでもないですよね?
よしもと あの漫画の中でおやじになった登場人物たちの現在が出てくるじゃないですか。そっちのイメージとして欲しかったんですね。
曽我部 ああ、なるほど。そうやって描かれたんですね、あの漫画は。
待望の新作プロット。
よしもとさんにとって、漠然とした自分の中のイメージに何か方向性をつけてくれるものとして音楽が必要な場合がある、ということですかね。
よしもと そう、そうなんです。それはサニーデイの新作『the CITY』を聴いても、やっぱりあるんです。
よしもと えーと、実は2年前に考えた話というのがあって、実はそれ、今日持ってきたんですよ(と言いながらトートバッグからプロットが書かれた紙を取り出す)。2016年の6月に書いたものなんですけど、ちょっと曽我部さんに読んでもらおうかな。
(曽我部さん、しばし黙読)
よしもと こういう話がボンッと出てきて。ちょうどサニーデイの『DANCE TO YOU』が出た時くらいなんですけど、そこに収録されている『パンチドランク・ラブソング』のMVを妻が撮ることになって、このプロットのタイトルだけ持って行かれちゃったんです。だから、あのMV(若い漁師を村上虹郎が演じている)のモトネタは実はこれなんです(笑)。で、この話を描こうと思って、某編集部に掛け合ってみたんですけど、「意味わかんないよ、これ」と言われて没になっちゃったんです。
VIDEO
よしもと あるんですよ。なんでわかんないのかなあと思って、こっちもがっくりくるじゃないですか。それでモチベーションがすごく下がっちゃって。
曽我部 …これ、面白いですよ。すごく今な感じがする。描いてください。
よしもと 時間が経って読み返すと「やっぱダメだ、これ」っていうのもあるんですけど、一応これはまだ生きていて。で、『the CITY』を聴いた時に、このプロットとすごくハマったんです。「あ、これは何か同じものなんじゃないか」みたいな。それで、「やっぱいけるんじゃないの、これ」っていうね。
『the CITY』を聴いて、あらためて背中を押される感じが。
『the CITY』と同じもの、というのはもう少し具体的に言うとどういうことですか?
曽我部 なんかわかる。断片がいっぱい散りばめられてある、というか、SNSで知った、日々埋もれていくニュースの断片みたいなものがいっぱいあるような気がしますね、この話の中に。そういうもので自分の住んでいる世界ができてしまっている感じというか。本当はそれだけじゃないんだけど、そういうもので頭の中が構築されている気分になるような、今の空気感がありますよね。
よしもと ただ、こういうものを出すと編集さんに嫌がられるのかなと勘ぐってしまうんですけどね。
曽我部 すごく現実にありそうな話。でも、そこに重力というか重さがない感じ。そこがいいなと思います。
否定も肯定もせず、現実にありそうなことを描いているんだけど、特定のモチーフに対して編集者が過剰反応しちゃうんでしょうかね。
曽我部 多分、物語としてわかりやすい感動がない、「泣ける」とかがないと思うんじゃないですか、よくわからないですけど。
なるほど。単純に「泣ける」とか「笑える」という感情に落とし込めない、と。
よしもと そうそう。『the CITY』も、まさにそういう感じがありますよね。
曽我部 確かに。でも、音楽はそれで成立するんですけど、物語って、今は純文学みたいなものも成立しづらいから、なかなか難しいですよね。漫画にしても。
映画でも小説でも、泣ける、笑えるというものがヒットしますし。
よしもと わかりやすいものが求められていることはあると思います。
「よくわからないもの」をわからないものとして世に出す、ということには出版社側はならないわけですよね。
よしもと そうですね。だったら、DIYで、自分で勝手に描いちゃって世の中に出す。…というエネルギーがないんですよ、俺。
よしもと ほんとに、その辺りは曽我部さんを見習わなきゃならないんですけど(笑)。
ストリーミング、SNSを駆使した手法。
曽我部さんは、自身のレーベルを起ち上げて以降、音楽の作り手でありディストリビューターでもあり続けているわけですが、『Popcorn Ballads』『the CITY』では全曲ストリーミング配信という最先端のリリース方法を試みています。さらに『the CITY』の音源を他のアーティストが解体・再構築するリミックス『the SEA』がSpotify上のプレイリストとして現在進行形で発表されています。『the CITY』の中の一曲『ラブソング2』のリミックスというかカバーである痛快な『FUCK YOU音頭』をはじめ、すさまじいリミックス群をリアルタイムで更新・シェアするという形で順次アップしていくという手法も画期的です。今、曽我部さんがやられていることは、言ってみれば、勝手に作って勝手に出す、未完であっても、そのプロセスをも公開していくというスタイルですよね。
曽我部 そうですね。自分のレーベルを作ってから、やり方としては勝手に作って勝手に出すようにはなったんですけど、それが「CDというパッケージすらなくていい」ということになったのは『Popcorn Ballads』からです。
それは海外の、たとえばフランク・オーシャンとかチャンス・ザ・ラッパーなんかの手法に触発された部分も大きいわけですよね。
曽我部 まあ、そういうメディアができて、みんな利用しているし、これは手法としていいな、面白いな、と。
日本だとまだ曽我部さんのような手法でリリースしているアーティストは少ないですよね。
大手レコード会社だと、いついつアルバムを作って、こういうプロモーション展開して、ツアーをやって、という大きな計画の中で物事が進んでいくことが相変わらず多いと思うんですが。
その辺りは大手出版社の漫画の世界ともおそらく近いものがあって、両者同じような問題にぶつかっているアーティストや作家は多いと思うんです。その根本には「売れるもの」「売れそうなもの」「過去に売れた前例があるもの」ばかり志向することにもあると思うのですが、曽我部さんはそうしたシステムからかなり自由に、自分の出したいものを出したいタイミングで出されているという印象があります。
曽我部 音楽は、形がいらないといえばいらないんです、聴くだけなので。本とか絵は、どうしてもモノだから、そう自由にもできないのかもしれないですよね。
よしもとさんは、編集者に「わかんないよ、これ」と言われたプロットを、何らかの形で世の中に出そうと思っているわけですよね。
よしもと 今いろいろ考えているところなんですけど、これを漫画として描こうとすると、多分半年くらい時間がかかる。怖いのは、その半年の間に状況がガラッと変わっちゃうんじゃないかということ。
となると、あまり時間を置かずに世の中に出したほうがいいわけですね。
曽我部 でも、この話は大丈夫なんじゃないですか。社会状況的に1年や2年で、ここにあるリアリティみたいなものは損なわれないんじゃないですかね。
よしもと そうですね。この前にも、ネームの段階まで描いていたものがあるんですけど、自主的にそれは没にしちゃったんです。時間が経って読み返したら、「これは違うぞ」という感じになって。
よしもと 表面的なことを最初は考えちゃって、現実に起きている事象みたいなものを取り上げていたんですけど、これは時間が経つと古くなるな、時間とともにコロコロ立場が変わっていくなと思って。
曽我部 いましろたかしさんなんかは、そういう社会状況みたいものをガッツリ扱っていますよね。
よしもと そういう直接的なことをやろうと思ったこともあるんですけど。
よしもと でも、それだと時間が経つと効果がなくなるな、と。
曽我部 なるほど。今読ませてもらったプロットは、不安と恐怖、ある種のホラーのようなものと、安堵感ややすらぎのようなものが同時にあるような話ですよね。
よしもと ああ、そうです。孤独っていうのが基本にあるんですけど、『the CITY』を聴いた時も、いろんな孤独がごちゃまぜにある感じがしたんです、最初。
曽我部 いろんな時期の曲を寄せ集めたようなところがあるので、それでそういう感じになっているのかもしれないですね。
曽我部 結果的にそうなりました。半分くらいは、各アルバムからこぼれた曲、入らなかった曲を寄せ集めた感じなんです。だから、頭から最後まで自分でストーリーを組み立てて作ったという感じになっていないので、そこがむしろ新鮮ですね。
よしもと アナログでいうとA、B、C面は、レイモンド・カーヴァーの短編を初めて読んだ時のような感じを受けました。投げ出されてそのまま、みたいな。
なるほど。バラバラの話を集めた短編集なんだけど、何か底に一貫して流れているものがある。
よしもと そうですね。それがサニーデイというものなのかな、と。コアにあるものが。
よしもとさんが作られたプロットを漫画で描くのに半年かかるとして、半年費やして漫画として描くのか、誰かに託して描いてもらうのか、あるいは別の形か、ということになりますよね。
よしもと そうなんですよ。実は2000年代に入ってから、いろんな人との合作というのをやっているんです。長嶋有さんの小説を俺が漫画にしたり、俺の原作を衿沢世衣子さんや黒田硫黄さんが漫画にしたり。それを一つの本のような形にまとめてみようかという話が前からあったんだけど、どういう切り口でまとめるのがいいんだろうというところで話がなかなか進まなくて。じゃあ、そういう合作であるとか、漫画ではないもの、たとえば俺の場合、小説や脚本もちょこちょこ書いていたりするので、この話も小説の形であれば早く形にできるなとか、いろいろ考えているところなんです。まずボンッと小説のような形で出してみて、「誰かこれを絵にして」みたいにして人に投げてみようかな、とかね(笑)。
よしもと サニーデイの『the CITY』の後に作られたリミックス『the SEA』みたいな感じですかね。その辺、いま曽我部さんがやっていることが参考になるのかなと思っているんです。なんていうか、しっかりした形で出しちゃうと、埋もれちゃうような気がしていて。漫画として描いて、出しました、というと、一時的には話題になるかもしれないけど、すぐに掻き消えちゃうような気がする。
たとえば深夜ドラマとかネットドラマとして1話30分の連続物で数本、というのは可能性があるかもしれないですね。
よしもと 少し前に漫画家のやまだないとさんの個展に行った時、やっぱり漫画の話になって、やまださんも、漫画ではなくてネタみたいなものを脚本なりの形で出して、あとは煮て食うなり焼いて食うなり誰か好きにして、みたいなことをみんなでやったら面白いんじゃないか、と言ってましたね。
完成度とスピード。
お話は次々に浮かぶんだけど、それを漫画にするのが物理的に困難ということなんでしょうか。
曽我部 漫画というものに落とし込む意味を探っているということですか?
よしもと 単純に自分の場合だと、体力的にしんどいなというのが、まずあるんだけど。
曽我部 わかります、それ。このアイデアを誰かがやってくれたらいいのに、という(笑)。
よしもと だから、漫画という形に落とし込むことと、スピードを重視してすぐに出すことと、どっちが重要だ、みたいなことはちょっと考えちゃいますね。
曽我部 ひょっとしたらスピードのほうが重要な時代かもしれないですね。
よしもと そうなんですよ。だから、思いついたらどんどん出していったほうがいいんじゃないか、という。
曽我部 今は「十年ぶりの新作です」みたいなアーティストがだんだん減ってきているというか、そんなに目立たなくなっている。昔だったらレディオヘッドが何年ぶりに出したというのが話題になったんですけど、今やそもそもアルバムというフォーマット自体を誰も気にしていないというか、誰々がこういう新曲を出してこういうMVがYouTubeに上がっているというほうが即時性があるというか即効性があるんでしょうね。丁寧に時間をかけて傑作を作ったというのがあんまり効いてこない。
完成度よりもスピードが重視されるということなんでしょうか。
曽我部 たとえば、完成度を上げるために、人海戦術じゃないけど、分業して、「はい、ドラムのトラックは誰々が作ってください」「エンジニアは誰々で」という形で、すごく優秀なスタッフで一曲作るみたいなことでスピードを上げていくのが今は主流になりつつありますね。
あくまでも一曲一曲に才能もコストも集中されているということですか。
曽我部 そう。あくまでも一曲一曲が勝負という50年代とか60年代のロックンロールのつくり方みたいな感じにまた戻っている。裏方がビシッといて、でも裏方と表のアーティストとの差はすごくある。今はジャケットとかもないので、エンジニアが誰かとかプロデューサーが誰かもわからないし、多分あまり関係がなくて、誰それの新曲ということでみんな聴いている。ふたたびシングル主流の時代になっているんです。
それこそ、テンプテーションズとかが次々にシングルを出していた時代のような。
曽我部 そうそう。曲もどんどん短くなっていて。僕は好きなんですけどね、そういうの(笑)。ただ、それを漫画の世界に置き換えるとどうなるんだろう。まあ分業はできなくはないか。
話を作る人、絵を描く人、背景を描く人という分業は昔からありますよね。
よしもと 何て言うんだろう。漫画っていうことで全部ひっくるめられちゃうわけですよね。たとえばジャンプに載っているものも漫画だし、自分の描いているようなものも漫画で。決して自分の漫画が特別だとは思っていないんだけど、主流とは違うところにいざるを得ないというか。そもそも俺自身、漫画を読まないんですよ。現在形の人は、ごく限られた人しか読まない。あとは昔の漫画を古本屋で買って読む感じで。
よしもと 松本零士の四畳半物とか、すごくいいですよね。
曽我部 ああ、ちょっとエロいやつ(笑)。新しい漫画については、「今こういうのが流行ってるのか」というリサーチの意味でも読まないんですか?
よしもと ヒットしているものとか、一応気になるんだけど、絵を見た段階で「あ、いいや」ってなっちゃう(笑)。コマの切り方とか構図が、全然自分にしっくりこない。
よしもと 送られてきた雑誌なんかには目を通すんですけど、見ているだけですごく疲れるんですよ。たとえば昔の『カムイ伝』とかだったら、飛んできた手裏剣をカムイがバク転しながら避けていって、タタタタタッて手裏剣が木に刺さっていくのが全部一コマで表現されていたりする。一コマでアニメーションみたいに見えるんです。今の漫画だと、一つ一つの動きを一コマずつ表現したりするから、見ていて疲れるんです。
曽我部 白土三平さんのは確かにそうですよね。すごいですよね。
過去の漫画を掘り起こしながら、自分にとってしっくりくる絵を探しているという感じですか。
よしもと そっちのほうが発見があったりしますからね。音楽でも、昔のものを聴いたりすると、なんか新鮮だなということも多いんです。じゃあ、新しい漫画がすべてダメなのかというとそんなことはなくて、面白い漫画を描いている人も、もちろんいますけどね。
曽我部さんは新しい音楽もかなりお聴きになっていると思いますが、それは何かそこにヒントがあるかもしれないというような聴き方なのでしょうか。
曽我部 ヒントとまではいかないかな。でも、新しいものはすごく聴きますね。音楽はやっぱり新しいもののほうがいいんですよ。漫画に関しては確かに新しいものイコールいいものにはならないと思いますけど、音楽に関しては、新しいものはとりあえず「新しいものとしての意味」がある気がするんですね。
どう作り、どう届けるか。
たとえば、漫画でいうと、雑誌連載からコミックス発刊、シリーズ化で収益を上げるという旧来の出版システムが壊れつつあって、あらかじめ映像化を前提とした設定や売れそうなネタに固執するあまり、作家性や独創性がないがしろにされる状態が続いています。それに対して一個人の作家がTwitterなどで作品を発表し、それがインフルエンサーにフックアップされて書籍化、ヒットにつながるケースも出ています。深谷かほるさんの『夜廻り猫』はその成功例だと思いますが、勝手に描いて勝手に出すとなると編集者がいなくても作れるんじゃないかということにもなるんですが、その辺はどうなんでしょうか。やっぱり編集者はいたほうがいいんですか?
よしもと 1人でやっている人はいると思うんだけど、大変だと思いますよ。ジャッジする人がいるかどうかは大事ですよ。
音楽の場合、特に曽我部さんのやり方だと編集者にあたる人はいないわけですよね。
曽我部 いないんですよ。マネージャーに「これ、どうかな」と聞くくらいで。漫画家さんは基本的には編集の方とセットという感じが僕はしていて、それはすごく羨ましいなと。漫画の場合、編集の方が若い漫画家さんを育てるみたいなイメージがあるじゃないですか。音楽の場合、プロデューサー的な意味で「いかに売れるようにするか」ということをやるディレクターさんはいるんですけど、作品そのものにはそこまで関与できないんじゃないかな。もう曲としてできちゃってるものは、そんなに変えようがない。
ちょっとアレンジを変えるとか、そのくらいですよね。
曽我部 そうそう。僕の場合は、自分がいいなと思ったものをそのまま出しているだけなんですけど、そういう編集者的な人がいるといいなとは思いますね。ジャッジしてくれる第三者が。
逆にそういう人がいると、いろいろ意見を言われるから嫌だ、ということにはならないんですか?
曽我部 その人のジャッジの精度がどのくらいかにもよるんでしょうけど、好みみたいな話になってくると、ちょっと嫌だなと思っちゃうかもしれないですね。漫画の編集の方は、的確にジャッジするプロっていう気がするけど。ちなみに、漫画の場合、まずプロット段階のものを編集の方に見せるんですか?
よしもと そうですね。ちょっとこういうことをやろうと思っているんだけど、というところからまずはじまるので。
曽我部 物語ですからね、漫画は。音楽の場合、最初に曲の断片だけ聴かせたところで、「は?」っていう感じだと思うんですよ。たとえばスネアの音だけとか(笑)。漫画だったら、プロットを前にして「この物語についてどう思うか」という具体的な話がしやすいんでしょうけど、音楽だと、断片だけ渡しても「それじゃわかんねえよ」と言われるだけだと思う。
曲として、頭から最後までできていないとその曲の良さもわかりにくいですからね。
曽我部 そう。曲としてできちゃえばね、人に聴かせて反応をうかがったりはしますけど。でも、面白い漫画っていうのは、プロットの時点で面白いんですよね、きっと。
曽我部 そういうことですよね。僕もMVを作る時に、監督さんが何行かのプロットのようなものを出してくれたりするんですけど、面白いものは、もうその5行くらいのストーリーの時点で面白いですもんね。何か迫力があるというか。
曽我部 その時点で映像は見えなくても、何か迫力があるというか。僕は、このよしともさんのプロットにも、そういうものを感じましたけどね。
よしもと なんとか世に出したいなとは思っているんですけどね。具体的には、とりあえずこれを小説の形で出そうと思っているんですよ、今。
曽我部 小説のほうがエネルギーはかからないんですか?
よしもと なんていうか、勢いでできちゃうところはあるんです。ラップのフリースタイルみたいなもので(笑)。
よしもと とりあえずそれをボンッと投げちゃって、絵にするかどうかはそれから考えるわっていうくらいのスピードでやっちゃったほうがいいのかなと。
よしもと だけど、やっぱり漫画というものも一方ではきちんと出したいという思いはあるので、それはそれで進めて、しかるべきタイミングでちゃんと出さなきゃなっていう気持ちはもちろんあるんですけど。
曽我部 でも、年とると、確かに落とし込むのが億劫にはなりますよね。僕、いろんなアイデアを毎晩何十個も思いつくんですけど、でも、全部面倒くさいですもんね、それを実現させることを考えると(笑)。ただ、お金と人手があったらやりたいなと思うことはすごくたくさんあるんです。村上隆さんなんかを見ていると、それをちゃんとやっているから偉いなって思いますね。そのエネルギーって大事だなと。
そのエネルギーはどこからやってくるものなんでしょう。年齢とともに体力や集中力は低下していくものだとして。
曽我部 うーん、僕もよしともさんも、基本的には個人でやっていることだから、これでスタッフを百人くらい集めてということになると気が遠くなるような話で。じゃあパーソナルに、1人でできることをやっていこうってことにすぐになっちゃうんですけど、でも、「これくらいの人とスタジオの設備とお金があったら、これくらいのことができるのになあ」とは思っちゃうんですよ。ハリウッド映画、たとえばマーベルとかを観ていると、いいなあと思うんですよね。巨大なシステムの中からアイデアが生まれてきて、それは僕たちみたいな日々の生活の中で個人の気持ちを形にしていくようなこととは違うわけですよ。もっとアノニマスなものだと思うんです。
コラボレーションの可能性。
そのアノニマスに関連して、ちょっと『the CITY』と『the SEA』の話に戻っちゃうんですけど、一度自分が作ったものを他の人に託して解体、再構築してもらおうというのは、どういった心境からはじまったんですか?
曽我部 そもそも、自分たちの作ったものを誰かにめちゃくちゃにしてもらって、それを出そうと思っていたんですよ。でも、それなりに時間がかかっちゃうので、自分たちで完璧に作ったものがあるんだから、まずそれを先に出して、追って作業をしようかなと思って今やっているんですけどね。
『the CITY』の先に『the SEA』、つまり街の先に海があって、『the CITY』のジャケットではたくさんの人たちがいたのに、『the SEA』になると子どもたちだけになっているというのも不穏さが漂っています。まるで楳図かずおの『漂流教室』のような。それと同時に、この子どもたちが未来を作っていくのか、というわずかな希望のようなものも感じます。
曽我部 大人は全員死んで子どもたちだけが曇り空の海辺にたどり着いて…っていうSFのイメージで作ったんですけどね。
『the SEA』では、この人にはこの曲、という感じで、ある種、編集者的な采配でそれぞれの方にリミックスをオファーしていくわけですか。
いったん自分の作ったものを他の人に託していじってもらう、再構築してもらうということは、それまで作り上げてきた歴史とか時間をもう一度ゼロにすることで、次のステップに行こうということだったんでしょうか。
曽我部 次のステップということは考えてないんですけど、なんか自分の作ったものに満足がいかないというか、「こういうものができました」というものを作っても、それだけなんです、結局は。それだけだとつまんないなあと思って。
自分ですべて作っていると、一から十まで自分が「わかるもの」になるわけですが、それをもう一回「わからないもの」にしてほしいという感じですか?
曽我部 それもあるし、自分の個性みたいなものが曲に出たからといって、それにどういう意味があるのか、と。これはいいとか、これは良くないとか、これは普通だとか言うんだけど、それは何を基準に言っているのか、ということがいまいち良くわからなくなっちゃって。それで一回実験してみたかったというか、むしろ自分じゃない人がやったほうがいいんじゃないか、とか。なんか、自分のやっていることがつまんなく感じちゃったのかな。
そうだったんですか。よしもとさんは以前、自分の絵に飽きているとおっしゃっていましたが、近いものがあるのかもしれないですね。
曽我部 よしともさんが誰か他の人とコラボをするのもそういうことですよね。
よしもと うん。一回、何か異物が介在したほうがいいというか、人に預けて予想もつかない返され方をされたほうが、なんか面白いんですよ。スリルがあるっていうか。
ある程度キャリアを積んでくると、どこかでそういうモードになるっていうことなんですか?
よしもと 2000年代に入る頃から、漫画の形で描くのがちょっと面白くないなという気分になったんですね。で、全く別の形式でやってみようとか、絵を他の人に任せるとか、そういうことをやり出した。自分の範囲内でできちゃうもの、予想ができちゃうものだと面白くないってことなんだろうと思います。
曽我部 そうなんでしょうね。僕の場合も、人に任せる部分は今までもあったんです。おそらく、ここまでだったら自分のオリジナリティみたいなものが守れるという範囲の中で任せていたんだと思うんですけど、今は、それをどこまで逸脱できるのかってことを考えていて。「オリジナリティってそもそも何?」ってところがあるから、全部人に任せて名前だけ曽我部恵一で出してもいいじゃん、みたいなことをちょっと思うんですよ。そのほうが広がりがあるのかもしれないな、とか。結局、できたものが楽しくって、良ければいいだけなので。どういうものがワクワクしたりドキドキしたりするかなっていうことが大事なんです。「こんなにがんばって、こんな作品を作りました」っていうだけだと…。
まあ、それを求める人たちもたくさんいるとは思いますが。
曽我部 でも、お客さんとして見たら、「あ、そうなんだ」っていうだけの話で(笑)。僕が聴き手だったらそう思っちゃうから。「もうちょっと何か楽しませてよ」って。それで今はいろいろやっているんだと思うんですけどね、僕としては。
よしもと 俺は『DANCE TO YOU』を最初に聴いた時に、「でかいな」と思ったんですよ。
「でかい」というのはスケールが大きいっていうことですか?
よしもと いや、とにかくでかいな、と。音楽として。それで『Popcorn Ballads』を聴いたら、ますますでかくなっていた、と。
曽我部 僕の中では、何か大きいもののある一部だけなんですよね、『DANCE TO YOU』は。だから、大きく感じられるのかもしれない。曲数も少ないんですけど、膨大なものの中の氷山の一角という感じがあって。この「何か大きいもの」という感じは、まだしばらく続くのかもしれないですけど。
よしもと 何か、サニーデイ・サービスのイメージをなぞっているものとは違う、もっと広がっている感じがしました。ちょっとこれは今までとは違うぞ、と。
曽我部 そうですね。違うところには行けた気がしています。そのせいなのか、今は昔の曲をライブとかでやる時に、すごく変な感じがするんですよ。
よしもと 3月に行われたサニーデイのライブに行ったんですけど、新しい曲がすごく良くて。
曽我部 基本的に『DANCE TO YOU』以降の、ここ2、3年くらいの曲ばかり演っていますからね。
『DANCE TO YOU』からはじまった何か新しく大きなうねりのようなものが今も続いているという感覚なのでしょうか。
曽我部 感覚がね、作り方がそれまでとは変わってきているから。
発表する手法が変わってくると、作る作品自体も変わってくるということはあるんですか?
曽我部 もちろん、そういうこともあるとは思うんですけど、90年代から『DANCE TO YOU』以前までは、わりと私小説というか、「わたくし的」なものを表現していたんですよ。でも、今は「エンターテインメントがやりたいだけ」っていう感じがあって。楽しんでくれたらそれでいいっていう感じに変わったところがある。だから、わたくし的な、日記のようなところに戻ると、何かこっばずかしいというか(笑)。パキッとした明確な境があるわけではないので、昔作った曲にスムーズに戻れることもあるんですけど、今は「エンタメだったらなんでもいいんじゃない?」ってところがある。今のほうが自由に「個」としてやっていると見られることもあるんですけど、基本的には、わたくし的なことを表現していくことに今は全然興味がないんです。
曽我部 はい。エンタメであればいい。「いい脚本」であれば、なんでもいいかなと思っているんですけどね。
ところで、よしもとさんは小説を書き上げて、それを元に他の漫画家が描いたとしても受け止められるんでしょうか。「やっぱり自分で描きゃよかった」みたいなことにはならないですか?
よしもと いやあ、わかんない。でも、そこまで考えずに、まず出していこうと。
曽我部 うん。すごく今っていう感じがしましたけどね、この話。
よしもと なんか、これを書いた2016年と根っこの部分は全然変わってないなと思う。表面的なところをすくうとズレが生じるんだけど、根底にあるものは全然変わってないから。
曽我部 現代の政治状況や社会状況に対して警鐘を鳴らすみたいな意識はあるんですか?
よしもと あ、そういうのはなくて、「世の中の正体をつかみたい」っていう気持ちが強いんだと思う。「なんなんだ、この状況は」「なんでこんなことになってるんだ?」っていうことが今現在もずっと続いているので。今の政治の状況を見ると「政府は嘘ついとる!」って話になるんだけど、もっと根本に何かあるんじゃないか、普通の人々の中に潜んでいるものがあるんじゃないか、というところまで降りていかないとなかなか本質が見えてこない。で、本質の部分まで降りていけば、時間が経っても効力は弱まらないんじゃないか、と。得体の知れないものの正体を突き止めるという意味では、それが一番的確なことなんじゃないかと思っているんです。
曽我部 僕はそれをよしともさんの漫画で読みたいけどなあ(笑)。
よしもと うん。漫画にしたら、また変わりますからね。自分が描くとしたら、もっとコメディっぽくなるかもしれないし。
曽我部 確かに。他の人が描いたら、そういう部分がどうなるのかなとは思いますね。
VIDEO
サニーデイ・サービス『卒業』