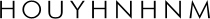FEATURE |
ceroとその周辺。『Obscure Ride』と共鳴するもの。聞き手:九龍ジョー

ー最初に「語られやすさ」って話がありましたけど、いまって一つのメディアで語りつくさないことで、断片化した物語を受け手のほうで組み合せるっていう作品が増えていますよね。
荒内:それ、ちょっと意識しましたよ。例えば「Yellow Magus」の歌詞を書くときとかも、説明もなしに進めておいて、あとでアルバムの中に収まるときに、なにか物語が見えてくるかもしれないなって。
髙城:そういう物語的な解釈って、いわゆる音楽ライターさんたちよりも、ブロガーの人だったり、いわゆるリスナーの人たちのほうが、いろいろ深読みをしてくれてる感じがありますね。
ーたぶんライターはリスナーの解釈を狭めないように、そこにはあまり深入りしないようにしてるのかもしれないですね。ただ、純粋なリスナーにとっては、断片の中から物語がどんどん駆動するようなアルバムだと思います。一曲目の「C.E.R.O」のあとのSEや、「Summer Soul」のノイズ、あとインタールード(「Rewind Interlude」)だったりっていうのも、そういうのを誘発する仕掛けになっていますよね。
荒内:もともと髙城くんがああいうスキットを入れたいっていうのは言ってたんですよ。
髙城:例えば「Rewind Interlude」を作ったときは、ホント単純に岩見(継吾)※6さんにウッドベースで入ってもらったから、使うかどうかわからないけどインタルード的なものを録っておきましょうよ、みたいな軽い思いつきだったんです。でも、並べてみるとそこに意味合いが発生するっていうのはありますよね。
※6 コントラバス奏者。exミドリのメンバーとして活躍し、現在はOncenth Trio 、AlfredBeachSandalなどで活動中。

荒内:ぼく、ケンドリック・ラマーの『Good Kid M.A.A.D City』って、初めてヒップホップのアルバムで内容がすごく知りたくなったアルバムなんですね。それでちゃんと歌詞を調べてみて、内容を理解しつつ、もちろんぼく自身はコンプトンのギャングとかと関係があるわけではないですけど、ああいうスキットが入ることで、一つの物語としても受け取れるなってことがわかって。
髙城:スキットが入ることで、物語が駆動させられるわけだ。うん、それはすごいあるね。そういう音楽はこれまでもあっただろうけど、まだまだ有効なやり方だと思いますね。
ーまた、物語が物語を引き寄せるというか、例えば「Elephant Ghost」の歌詞が、漫画家の座二郎さんの『RAPID COMMUTER UNDERGROUND』(小学館)のある回とシンクロしましたよね。偶然とはいえ、そういうリンクは面白いなと。
髙城:そうですね、そういうことはいっぱいありますね。あと、『Obscure Ride』を聴くたびに異なる物語を生きられるみたいなことを言ってる人もいて。聴くたびにこれは新たに自分が体験したことのような気がしちゃうんだけど、自分が忘れてるだけのことなのかもしれない、みたいな。なるほどなぁ、と。そういう「記憶喪失」みたいなことは、テーマだけじゃなくて、実際に容れ物としても機能しているのかもしれないなって。
ーそういう解釈って、精神分析的になってしまうと答え合わせみたいで面白くないんだけど、ceroの場合、集団制作っていうのが上手く機能して、そうならないのがいいなと。
橋本:例えば、髙城くんとかあらぴー(荒内)が曲をつくってきたときに、ぼくに対してギターの領域を指定するようなことがあまりないんですよ。それってつまり、ぼくが物語を間違って捉えて音にしている可能性だってあるわけで。ワンマンなリーダーがいるバンドだと、ここは絶対こうしろとかあるんだろうけど、それはないから。
髙城:むしろそこに関してはバンド内ディスコミュニケーションな感じすらあるからね(笑)。軽くそういう話をしたりはするんですけど、こうしようみたいなヴィジョンは、そもそも自分自身だってはっきり掴めているわけじゃないですからね。
ーアルバムが出てから知ることだってあるわけですもんね。
髙城:1曲目「C.E.R.O」で電話が鳴っているんですが、8曲目の「Roji」の「(ここでPhone call)」っていう歌詞のところで電話の受話器を取るみたいなことも、取材を受けるようになってから気づいたことだし。
荒内:そうだったっけ?(笑)
髙城:ただ、なにも言わずとも、そういう歌をつくってきて、練習を重ねていくうちに、なにかある物語を生きるようにはなってきますよね。
ーそう考えると、「Obscure Ride」(曖昧な乗り物)って、そのまま、現時点での「cero」というバンドのことを指している気もしますね。
髙城:まあ、いまのceroはソフトっていうよりはハードっていうか、容れ物みたいなものですからね。そこにいろんな人が持ち寄ってきてくれる。だからリスナーや観客の存在も大きいですよ。