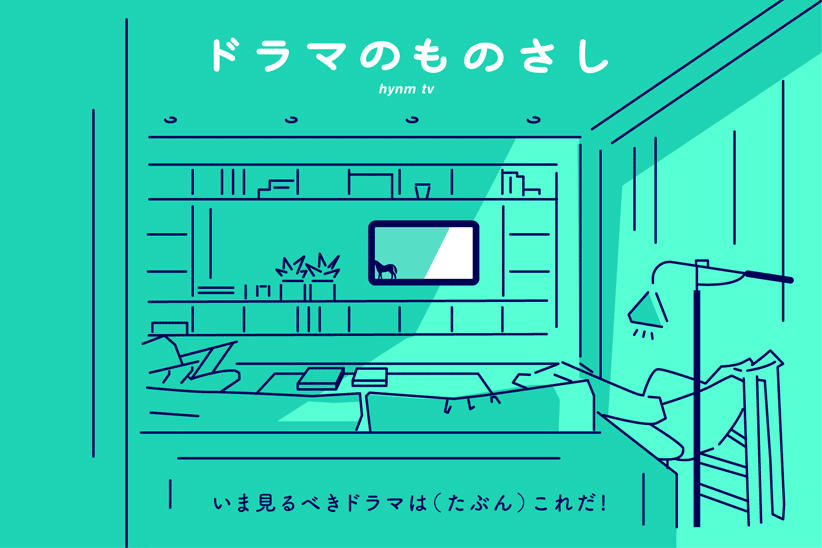2015.6.19 FRI
フイナムテレビ ドラマのものさし
『若者たち 2014』
ドラマから流行語が生まれたり、なにやらテレビドラマの周辺が騒がしい。実際見応えのあるものも多く、「映画は観るけどドラマはちょっと...」なんて言って食わず嫌いしているのはもったいない。でも、すべての連ドラをチェックするのは物理的に無理。しかも、高視聴率だから面白いかといえば、実はそうでもなかったりするから話はややこしい。そこで、ほんとうに面白い、いま見ておくべきドラマを独自の視点で採り上げていくのがこのコーナー。ブッタ斬りでもメッタ斬りでも重箱の隅つつき系のツッコミ芸でもなく。そのドラマの「何がどう面白いのか」「どこをどう面白がるべきか」をふんわり提示する、普段ドラマを見ないひとにこそ読んで欲しいドラマ・ウォッチ・ナビ!
Text_Shin Sakurai
Design_Shogo Kosakai[siun]
Edit_Ryo Komuta
『若者たち 2014』フジテレビ 水曜22時 7月9日スタート
「君の行く道は 果てしなく遠い」......。 2014年7月30日公開
1966年に放送されたドラマ『若者たち』の主題歌は、ドラマを見ていない世代でも聴き覚えがあるほどよく知られた歌だ。その名曲が、リメイクドラマの挿入歌として48年ぶりに森山直太郎の歌唱で甦った。
妻夫木聡、瑛太、満島ひかり、蒼井優、長澤まさみ、橋本愛など、今をときめく若手俳優が結集し、『北の国から』の杉田成道が20年ぶりに連続ドラマのメイン演出を手掛ける『若者たち2014』が、7月9日からスタートしている。
ところが、フタを開けてみると、初回放送時から賛否両論が巻き起こった。賛否というか、ネットの感想などを見ると圧倒的に「否」が多く、視聴率も初回こそ12.7%だったが、2話、3話は7.8%とひとケタ台に。これだけのメンツを揃えて、なぜこんなことになってしまったのだろうか。
1966年の『若者たち』は、当初数字は低かったものの、若者が抱えるさまざまな社会的な問題を描き、じわじわと人気が上がっていったことで伝説化したドラマだ。テレビ局の上層部は「予算がかかり過ぎるわりに数字が良くない」との理由から打ち切りを検討(実際には内容が局の意向に沿わなかったらしい)、予定よりも短い本数で放送は終了し、かつ第33話が朝鮮人差別を促すとのことで放送中止になるなど、さまざまな逸話があることも伝説化に一役かっているのだろう。当時、放送継続を願う視聴者からの署名が局に殺到したというから、その人気のほどがうかがえる。ちなみに、江口洋介が「あんちゃん」を演じたドラマ『ひとつ屋根の下』(93年)は、この『若者たち』が元ネタだ。
まさに66年の放送当時「若者たち」だった杉田成道は、今回のリメイクを熱望し、自ら企画したというが、豪華俳優陣とベテラン演出家による珠玉のドラマを期待して見始めた2014年の視聴者は、初回の冒頭でいきなり面食らうことになる。
物語の中心である佐藤家の朝食の風景を捉えたシーンでは、長男・旭(妻夫木聡)の大仰なセリフ回し(『するってぇと何かい』『てやんでぃ』的なべらんめえ調)と、それを受ける三男・陽(柄本祐)の妙に芝居がかった説明口調の応酬に、「なんだ、この時代錯誤感は」と開始5分にして頭を抱えてしまったひとも多かったようだ。
しかし、録画したこのシーンを見返すと、これは意図的に芝居がかっているのだ、ということがわかる。妙齢にも関わらず独身の長女・ひかり(満島ひかり)を心配した兄たちが見合い話を切り出すために小芝居をしているという設定なので、長男も三男もいつも以上に大仰で芝居がかった物言いになっているのだろうし、三男は演劇をやっているという設定から、より芝居口調が強調されている、という演出上の意図が(おそらく)あったに違いない。違いないのだが、演出や芝居のトーンが、あまりにも現在放送されている他のドラマと違いすぎるため、おそらく皆ギョッとしたのではないか。それくらい、冒頭の食卓のシーンの異物感は強烈だった。
が、こういうシーンを冒頭に置くことによって、「これはこういう世界観の話です」ということを明確に打ち出したのは案外良かったのかもしれないな、とも思う。コンサート会場の入口に「森進一ショー」という看板が出ていれば、「なんでこの歌手の声はこんなにしゃがれているの?」「ビブラートをきかせすぎているのはなぜ?」とは誰も思わないだろう。なぜなら、それが「森進一の歌」だからだ。『若者たち2014』は、しょっぱなから「これは2014年の社会をリアルに描くような話ではありません。自分の歌を歌いたいように歌います」と作り手が宣言しているようなものだ。
もっとも、それはあくまでも演出のトーンの話であって、「童貞は黙ってろ」とか「軽部さん、何気にディスられてるしね」などというセリフがあったり、言葉だけを抽出すると、実は意外と今っぽさが採り入れられていることがわかる。あまりにも演出と芝居が時代がかっていたせいで、セリフが耳に入ってこなかったという問題はあったにせよ。
そうしたマイナス点があったとはいえ、簡単に全否定してしまうにはあまりにももったいないというほど、このドラマには「ドラマ的な幸福感」というべき時間が流れている。ドラマ的な幸福感というのは説明が難しいのだが、「ああ、今ドラマを見ているなぁ」としみじみと思える瞬間とでも言えばいいのか。
たとえば山田太一脚本の『ふぞろいの林檎たち』や倉本總脚本の『前略おふくろ様』『北の国から』でも何でもいいのだが、ある期間、ひとつのドラマに寄り添うようにして見続けた体験が見る者のベースにあるかどうかが問われるような気もする。「ドラマ的な幸福感」を体験したことのないひとに濃密なドラマ的な時間が流れるドラマを見せるのは、ふだんジャーマンテクノしか聴かないひとを森進一のコンサート会場にいきなりぶち込むようなものだろう(森進一に深い意味はありません)。
1話で、何かやらかして刑務所に入っていた瑛太演じる次男の暁が出所するシーンが描かれ、2話では、暁が「何をやらかしたのか」を中心に描くのだが、高齢者相手の詐欺という現代的な犯罪をモチーフに、被害者家族の希薄になった親子関係が描かれる。3話は、瑛太が主演したドラマ『それでも、生きてゆく』『最高の離婚』を手掛けた並木道子が演出したこともあって、1、2話と比べてかなり抑制の効いた画面づくりで瑛太の持ち味を引き出していた。
考えてみれば、暑苦しい演出と芝居は長男・旭というキャラクターの前時代的な暑苦しさとリンクしていたともいえる。そこに、ある一件で旭と対立して家を飛び出した次男の暁が佐藤家に戻ってくることでトーンが一変し、暑苦しさが緩和されていく。さながら旭が熱を帯びた泥臭い昭和を体現し、暁が体温の低い醒めた平成を体現するかのように。これが狙いだとしたら、それはそれで巧妙な演出プランではないだろうか。
三男の陽は学生演劇の劇団を運営していて、つかこうへいの戯曲『飛龍伝』を稽古をしていたりするのだが、『飛龍伝』といえば、全共闘の女リーダー・神林美智子を富田靖子、牧瀬里穂、石田ひかり、内田有紀、広末涼子、黒木メイサが歴代演じ、今年10年ぶりの復活作では桐谷美玲がそのバトンを受け取る。いわば若手女優が実力派へと成長するための登竜門的役柄なのだが、ドラマ内ではその役を橋本愛が演じることになるらしい。1960年代と2014年を接続するために間に『飛龍伝』を置く、というのはある意味で正解なのだろう。芝居がかった演出は、芝居というジャンル自体がもつ熱を描くためにも必要だったのかもしれない。ダサい、暑苦しいと忌み嫌われ、今や失われつつある「かつての若者たち」の熱を受け継ぐものとして。
しかし、連続ドラマは1話の評価が肝心なので、そこでつまづいた視聴者はなかなか戻ってきてはくれないのがイタいところだ。実力派若手俳優たちのもつ画力(えぢから)だけでも十分に見る価値があるのだから、何とかして戻ってきてほしいと思う。おそらく「果てしなく遠い」とこへ行ってしまった若者たちにも。