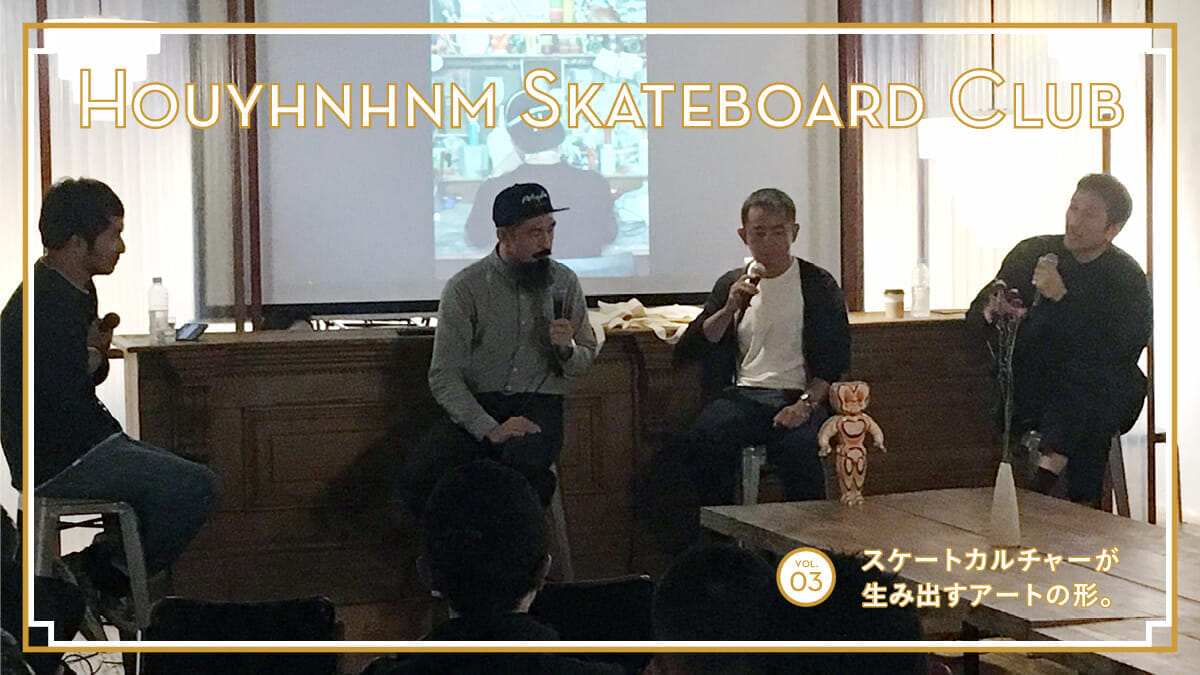HAROSHI氏 / 現代アーティスト
世界中のスケーターに広く知られる、スケートカルチャーを背景に持った現代アーティスト。乗り古したスケートボードを用いて、様々なスカルプチャを製作。これまでに数々の個展、グループ展を開催し、また様々なブランドや企業ともコラボレーションを発表。現在はスケートブランド〈HUF〉所属のアーティストとしても活躍。また昨年には盟友であるUSUGROW氏と共同運営で葛飾区にギャラリースペース「HHH Gallery」をオープン。haroshi.com
竹村卓氏 / 編集者、ライター
幼い頃からBMXやスケートボードなどのカルチャーに慣れ親しみ、21歳で単身渡米。カリフォルニアを拠点にその活動をスタートさせ、帰国後は編集者・ライターとして様々な媒体やメディア、広告案件で執筆活動を行う。シルクスクリーンでTシャツなどを製作するプライベートブランド〈RESTAURANT〉の活動も行い、主な著書には今回のテーマに最適なアーロン・ローズやエド・テンプルトンらアーティストを訪ねて回ったインタビュー集「ア・ウェイ・オ ブ・ライフ 28人のクリエイタージャーナル」などがある。
平野太呂(以下、平野) いよいよHSCも3回目ですね。ショップ、チームと来て、今回はアートがテーマ。個人的には本命ともいえる回かなと思っていますが、千ちゃんはどうですか?
小澤千一朗(以下、小澤) 前回の打ち合わせの時に太呂からいろいろなアイデアが出てきていたから、「あ、これは太呂の本命なんだな!」って感じてましたよ(笑)。スケートとアート、僕も楽しみですね。
平野 まずスケートボードとアートと聞いて、何が思い浮かびますか?
小澤 やっぱりマーク・ゴンザレスは欠かせない存在というか、象徴ですよね。あとは僕ら的にはニール・ブレンダー ※1 とかね。
※1 1980年代を代表するスケートチームの「G&S Skateboards」でライダーとして活躍し、自身のシグネチャーデッキにシュールでローブローなドローイングを施すなど、創造性とDIY精神に溢れたスケートアートの第一人者。近年はまったく新しいスケートボードである“Polarizer”なるデッキを開発中。
平野 そうなんだよね。それが正しい真実かどうかというのは定かではないんですが、あくまでも僕らの見解としてスケートカルチャーとアートの始まりから話していこうかなと思います。
まずスケートボードのデッキって、足と接地する面には、必ず滑り止めとしてグリップテープが貼られていますよね? その部分にスケーターたちが落書きを始めたのがそもそもの最初なんじゃないかなって僕は思っていて。
そのグリップテープと反対側の地面と接地する面には、各ブランドがオリジナルでグラフィックをプリントしていて、一般的にはそのデザインの方に注目するんですけど、それはあくまでもスケートデッキのプロダクトデザインであって、特に70年代や80年代前半というのは、デッキブランドやカンパニーの名前がドーンって入ってるものが多かったんですよね。
だから今でこそアートと呼べるようなスケートデッキも多いですが、当時はブランドロゴやカンパニーのシンボル的なデザインくらいにしか認識できなかったんです。そうした当時の主流だったスケートデッキにアートとしての側面を持たせたきっかけとなったのが、グリップテープに描かれた落書きだったわけです。
僕ら自身、80年代の中頃にゴンズがグリップテープに落書きしているのを見て、まだその当時はアートとしては見ていなかった。アーティストではなかった変わり者のゴンズがただ落書きをしているだけ。それが今となってはアーティストとしても大成したゴンズによる行為だったということを思うと、「やっぱりあれがアートの始まりだったのかな」と改めて思ってしまうんですよね。
小澤 ナタス・カウパス ※2 なんかもそうだったよね。
※2 ゴンズと並び、ストリートスケートの礎を築いたとされる、スケート界のゴッドファザー。その個性的な着こなしやスケートスタイルは当時から時代を先取り、1989年にリリースされた『Streets on Fire』での彼のフッテージは、スケーター間では伝説に。
平野 そうでしたね。彼もまたスケートデッキのグリップテープに落書きをしていたスケーターのひとり。後にデザイナーとしても活躍することから、やはりそうしたアート分野への才能もあったんだなって思いますよね。
小澤 〈QUIKSILVER〉※3 とか〈ELEMENT〉※4 のブランドサインを手掛けたのは、彼だからね。太呂にとっては、スケートボーダーのアーティストって言うと今挙がったような人たちで、スケートデッキのグリップテープアートから始まったということなんだね。
※3 カリフォルニア州のハンティントンビーチを拠点とするサーフブランド。80年代のスケートカルチャーに傾倒した人たちにとっては、リース・フォーブスらスタースケーターをサポートしていたことはもちろん、当時のスケーターがこぞって愛用していたことから、スケートカルチャーと所縁のあるブランドという認識を持っている人も少なくはない。
※4 1992年にプロスケーターのジョニー・シラレフが設立したスケートブランド。現在、チャド・マスカや新世代のスターであるナイジャ・ヒューストンをはじめ、世界中を魅了するトップアスリート・スケーターたちが所属する人気ブランドへと成長。青少年を育成する非営利団体「ELEMENTAL AWARENESS」の設立など、社会意識の高い活動を行う一面も。
平野 じゃないかなと思っているんだけどね。そして、そこからいよいよグリップテープ側の落書きではなく、デザイン的にはメインとなる裏面にもスケーター自身が手掛けたグラフィックが出てくるんですよね。僕の知っている限りでは、ニール・ブレンダーというスケーターが最初だったと思います。
彼については、映像なども交えつつご紹介していきたいんですが、ここでニール・ブレンダーと友人としての親交もある竹村卓をゲストとして呼びたいと思います。ちょっと早いですが、どうぞ前の方まで!
おそらく80年代の中頃に撮影されたであろう5枚のオールドスクールなスケートデッキ。スケートアートの始まりともいえるグリップテープのアートワークは、よく見ればゴンズらしい絵のタッチと自身の名をパロディさせたデザインが印象的。
ゴンズ同様、スケートデッキの表面に自信によるアートを施していたナタス・カウパス。彼のトレードマークとも言えたボンレスのトリックを収めた一枚の写真からもスケートデッキのグリップテープアートが確認できる。
ただ滑ってトリックを決めるだけがスケートではない。(平野)
竹村卓(以下、竹村) 竹村卓です。よろしくお願いします。
平野 卓は80年代から一緒にスケートしていた友達なんですけど、カリフォルニアに住んでいた時期もあって、その当時から現地のスケーターやアーティストなんかと親交を深めていたんですよね。
竹村 1995年から2000年までの時期ですね。初めはちょこっとアリゾナにいて、それからずっとロサンゼルスにいたんですよね。
平野 そのロサンゼルスで、たまたま〈HUF〉のキース・ハフナゲル ※5 やマイク・キャロル ※6 とかが住んでいるエリアに卓も住んでいたんだよね。
※5 90年代に〈REAL〉の看板ライダーとして活躍した元祖オーリーマスターの異名で知られるレジェンド・スケーター。2002年にスタートした自身のブランド〈HUF〉は、日本だけでも7店舗展開するなど、世界的に人気なスケートショップとして成長。
※6 80年代からスケートシーンを牽引してきた、フリップトリックが代名詞でもあるトップスケーター。「H-Street」、「PLAN B」を経て、1994年にリック・ハワードやスパイク・ジョーンズらと共に〈GIRL SKATEBOARDS〉の立ち上げに参画。現在はスケートシューズブランドの〈LAKAI〉のオーナーとしても成功するなど、実業家としても活躍。
竹村 僕が住んでいる家の数件隣がマイク・キャロルの家で、行きつけのスーパーも一緒だったんですよね(笑)
平野 それから僕らは『Relax』※7 という雑誌の当時巻末にあったボードカルチャーの連載企画で一緒に仕事をするようになるんですよね。
※7 マガジンハウスより1996年に創刊され、若い男性を中心に人気を博したカルチャー雑誌。若かりし頃の竹村氏と平野氏は、岡本仁編集長時代に同誌の海外企画やスケートボードの企画をよく担当していた。2006年9月号をもって休刊。
平野 うん。それと当時僕らが憧れた沢山のスケートボーダーがいたわけだけど、その中でも特別な存在でもあったニール・ブレンダーの話をすると、映像でも流している80年代後半に行われたであろうローカルのスケートコンテストで、彼は限られた自分の持ち時間の中で得意なトリックを決めながら、突然セクションだったウォールに絵を描き出すんです。
この映像がスケートカルチャー的には衝撃映像で、ただ滑ってトリックを決めるだけがスケートではないというね。彼が実際にそうしたメッセージを持っていたかというのは定かではないですが、当時この映像を観ていた僕らからすると、そんなアティテュードを感じたんですよね。
竹村 彼のこの伝説的なアクションを機に、コンテストや映像作品でもニール・ブレンダーに影響を受けたであろうスケーターというのが続出するんですよね。トーマス・キャンベル ※8 やゴンズも実際に、スケーターがアートを発表できる土壌を作ったのは、ニール・ブレンダーだと言っていたしね。
※8 スケーターとしての活動以外に、映像作家、ぺインター、フォトグラファー、サーファー、レコードレーベル「Galaxia」のオーナーなど多様な顔を持つことでも知られる、西海岸カルチャーを語る上で欠かせないマルチアーティスト。また自身が監督を務めた映画作品「SPROUT」や「The Present」は、サーフカルチャーにおける不朽の名作として多くのファンから今なお愛される。
小澤 太呂はそうしたアーティスト性の高いスケーターから影響を受けながらも、絵を描きたいとは思わなかったの?
平野 あ、僕? 僕は絵が描けないから、写真を撮っているんでしょうね(笑)。
80年代後半に開催されたローカルのスケートコンテストにて、若き日のニール・ブレンダーが残した伝説的なパフォーマンス。それは競技中にポケットに忍ばせたスプレー缶を使い、セクションの至る所に即興のドローイングを残したこと。スケートデッキに乗ってトリックをすることだけがスケートの表現ではないことを証明した衝撃的な映像だ。
こうしたスラムした写真もスケートなんだ。(小澤)
小澤 なるほどね。あと、この時代でいうとマイク・バレリー ※9 も変わった存在だったよね。
※9 男臭く、無骨なスタイルが持ち味の元祖ハードコアスケーター。様々なスケートブランドに所属しながら、90年代には「BALCK LABEL」で一時代を築く立役者に。その後プロレスラーやハードコアバンドのボーカル、アイスホッケーのプレイヤーに転身するなどスケートボード以外の分野にも挑戦し、話題に。またスケートボードのドキュメンタリーフィルム『DRIVE』シリーズを手掛けた人物としても知られる。
平野 そうだね。彼は元々は爽やかなイケメンスケーターとして女性からも人気を得るような存在だったんだけど、いつからかプロレスラーに転向したり、バンドのボーカルを務めたり。少し前には『DRIVE』というタイトルの旅をテーマにしたスケートドキュメンタリーのムービーも作っていた人物ですね。アーティストでこそなかったですが、変わり者が多いスケーターを象徴するような人物でしたね。
小澤 アートのみならず、スケートカルチャーのフィルターを通して、それに付随する様々なカルチャーに傾倒するスケーターが増えたと言うのも、もしかしたらニール・ブレンダーというひとりのスケーターによる影響が大きいのかもしれないね。
平野 そしてその後、ニール・ブレンダーだけではなく、マーク。ゴンザレスも自身の二枚目となるシグネチャーデッキからはアートワークを描くようになるんですよね。それがおそらく80年代の後半くらいだったと記憶しているんですが、この頃からスケーターが自分のデッキに絵を描くという行為が普通になっていくんですよね。ちなみにスケートボードとアート、そして写真を振り返る際に、重要な文献として資料的な価値も持つ『Dysfunctional』※10 という写真集があるんですが、皆さんご存知ですかね?
※10 1999年にアーロン・ローズによって発行され、70年代から90年代のスケートカルチャーを独自の編集視点で構成した資料としての価値も持つ作品集。今回登壇した面々にとって思い入れの深い一冊であり、スケートとアートの歴史を知る上で必読。表紙のスラムしたエド・テンプルトンを撮影したのは、日本が誇る写真家のホンマタカシ氏。
小澤 僕らの大好きな一冊ですよね。この本にはいろんな魅力があるんですけど、ニール・ブレンダーがアートワークを提供したデッキも含め当時のアートとして評価され始めたスケートデッキのカタログページも載っていたりして、とても貴重な内容なんだよね。
竹村 そうだ、懐かしいね。あと表紙は写真家のホンマタカシ ※11 さんが撮影していて、被写体となったのがエド・テンプルトン ※12 というね。
※11 異例とも言える大学在学中に広告制作会社の「ライト・パブリシティ」に入社し、カメラマンとしてのキャリアをスタート。その後、90年代にはロンドンへと渡り、現地で熱狂的な人気を誇ったファッション&カルチャー雑誌『i-D』などの雑誌にメインフォトグラファーとして携わったことで、国内外でその名を知られる存在に。1998年には第24回木村伊兵衛写真賞を受賞し、写真家としての地位を確立。数多くの雑誌や写真集に携わり、近年は美術館での巡回展も行うなど、その活躍は多岐に渡る。
※12 プロスケーターとしてシーンに輝かしい功績を残しながら、自身が手掛けるブランド〈TOY MACHINE〉では、お馴染みのキャラクターである“トランジスターセクト”の生みの親としても知られる。また近年はフォトグラファーとしての活動も目覚ましく、『Teenage Smokers』シリーズを始め、これまでに数冊の写真集を発表し、世界各国で定期的に写真展やアートショーも開催。妻のディアナ・テンプルトンも写真家。
平野 撮影したのが、スケートフォトグラファーではなく、ホンマタカシさんだったかというのは、この本を編集したのが「Alleged Gallery」というギャラリーをキュレーションしているアーロン・ローズ ※13だったんですが、写真やアートにも精通していた彼だからこそ、スケートフォトグラファーだけではなく、幅広いジャンルから彼の食指を動かした写真家に指名があったのかなと、勝手に推測しています。
※13 1992年から2002年の間、ニューヨークの伝説的なギャラリー「ALLEGED GALLERY」のオーナー兼キュレーターとして数多くのアーティストたちを世に送り出した、ストリートアートの仕掛人的存在。2004年には、コンテンポラリー・アート・センターで開かれたクループ展『BEAUTIFUL LOSERS』を企画し、映画化やドキュメンタリーブックも出版されるなど一斉を風靡。現在は、アート本の出版社である「ALLEGED PRESS」で出版物を手掛けており、フリーランスの編集者として活躍している。
竹村 これまではスケートカルチャーを伝える本で言うと、『THRASHER』のような専門誌の雑誌しかなかった中で、この書籍が出てきたのはかなり革新的だったよね。スケーターではなかったアーロン・ローズが作ったことにも意味があったし、今改めて編集者としての目線で見ても、為になる一冊だよね。 時系列ごとに構成されていたり、写真集なようで資料的な要素もあったり。
小澤 背表紙にまたがって、転んでいるエド・テンプルトンの姿がまたなんとも最高なんですよね。この写真があったから、そうしたスラム ※14 した写真もスケートなんだって改めて認識させられて、僕が作っている「Sb」の創刊号の表紙でもメイク以外の写真も使うようになったんだよね。
※14 スケートカルチャーのいうスラムとは、トリックを失敗して地面に叩きつけられることを指す。難易度の高い技や未開のスポットを攻めるスケーターにとってはつきもの。
竹村 だからタイトルも『Dysfunctional』なんだよね。
竹村 機能していない、つまりはメイクしていないみたいな。そこにどんな意味が込められているのかっていうのは、本を作った本人に聞くしかないけどね。
小澤 とはいえ、アーロン・ローズは「Alleged Gallery」というギャラリーを通してスケーターに対しても変わらずサポートは行なっていたわけだから、間違いなくスケートとアートの関係性というのは、彼の中でテーマになっていただろうね。
平野 それまではさっきも言った通り、スケートボードへのアートなんて落書きとしか認識されていなかったし、二束三文の価値もないものだったんですよね。それを変えた存在がアーロン・ローズと、彼がニューヨークで運営していた小さな「Alleged Gallery」というギャラリーだったんですよね。
この「Alleged Gallery」を通じて、様々な無名アーティストやスケーターたちがアートの分野で活躍の場を得ていったし、有名になっていった。僕は改めて編集者やキュレーターの仕事ってすごいなって思いましたね。
平野 色々やっているみたいだけどね。「Alleged Gallery」はクローズしてしまったけど、周年に合わせて期間限定のポップアップ形式でギャラリーを開催したりしているし、フリーランスのキュレーターとしても相変わらず活動している。あとはフィルムを撮ったり、バンドを組んだりしているよね。
竹村 あと最近は絵も描いたりしているんじゃないかな。
その時に初めてスケートカルチャーのデッキや写真、絵を集めて展示したりしている人が、この世界にはいるんだということを知った。(平野)
竹村 ちなみに太呂がアーロン・ローズに興味を持ったきっかけってなんだったのかな?
平野 1995年にニューヨークへ遊びに行った時に、友人から「マーク・ゴンザレスの絵が飾ってあるギャラリーがあるよ!」って教えてもらって、当時はゴンズの描いた絵なんか飾ってどうるのかななんて思いながらも、案内してもらった場所に行ったら、そこが「Alleged Gallery」だったんですよね。
ただ、ちょうど展示の準備をしている段階だったのか、搬入の途中で床にマーク・ゴンザレスやエド・テンプルトンの絵やら写真が無造作に転がっていて、ギャラリーの中にはアーロンどころか誰もいないんですよね。それで僕は未完成なそのギャラリーの空間をしばらく眺めてから、その場所を後にするんだけど、その時に初めてスケートカルチャーのデッキや写真、絵を集めて展示したりしている人が、この世界にはいるんだということを知ったんですよね。
竹村 「PRINTED MATTER」※15 も行ってたよね?
※15 1970年代からアーティストたちの自費出版本を世に送り出す書店として知られるアートブック専門店。アーティストのソル・レウィットとルーシー・リパードのふたりが中心となって設立し、非営利目的での運営していることでも話題に。2016年に創立40周年を記念し、拡張を兼ねた移転オープンした。一流のアーティストや写真家に混じり、有名無名問わないスケーターたちの作るZINEも置かれる。
平野 そうそう。今ほど賑やかではなかったソーホー地区に「PRINTED MATTER」っていうリトルプレスのZINEや写真集なんかを置いている、小さな街の本屋さんがあって。たまたまふらっとそこに寄ったら、やっぱりそこにもマーク・ゴンザレスが作ったZINEがいくつか置いてあって、試しに2冊くらい買って帰ったんですよね。
平野 その二つの出来事があって、少しづつ僕の中でスケートカルチャーとアートの関係性というのが浮き彫りになっていくんですよね。
小澤 1995年だと、ちょうどゴンズがスケートとは少し距離を置いて、パリにいた時期かな?
竹村 そうだね。当時めちゃくちゃ人気だった「BLIND」※16 というスケートチームから脱退して、いくつかのスケートチームを転々とした先に、急にパリへ移住したらしいなんてニュースが知り合いづてに届いてね。
※16 1989年にマーク・ゴンザレスが設立したスケートブランド。90年代に突入すると、「POWELL PERALTA」とは犬猿の中と揶揄されながら、1991年にスパイク・ジョーンズ監督がディレクションを務めた名作『VIDEO DAYS』をリリースし、一躍人気ブランドの仲間入りを果たす。
平野 ゴンズの沈黙時代ですよね。それと今思えば、スケートシーンもスケートデッキのウィールの大きさがどんどん小さくなっていって、スケーターは皆トリックの難易度を競うようになっていった変革期でもあったんですよね。実はその頃僕も少しスケートから距離を置いていたんですよね。ただ卓はひとりで滑っていたよね(笑)。
竹村 そうだったね(笑)。あの頃は高井戸の高速道路の下がスケートボードのできる場所になっていて、よくコソ練していましたね。
平野 卓にはゴンズのようなスランプがなかったんだね。
小澤 世界的にはニール・ブレンダーやゴンズが出てきたけど、まだまだ日本ではスケートアートは夜明け前の時代だよね? そこからアメリカではさらに専心して、スケートシーンにも大きな影響を与えた『ビューティフル・ルーザーズ』 ※17 が登場してくると。
※17 2004年に「アレッジドギャラリー」のキュレーターだったアーロン・ローズが主宰した、落ちこぼれなアーティストたちを招聘したクループ展。ニューヨーク、ロサンゼルス、パリ、ミラノなどを巡回し、後にアートの常識を覆したムーヴメントとして、ドキュメンタリー映画や書籍として発展。
平野 そうなんですよね。「Alleged Gallery」を主宰していたアーロンは、その後も精力的にインディペンデントなアートの布教活動を続けていき、2004年にアートの巡回展として『ビューティフル・ルーザーズ』が生まれたんですよね。
その詳細についてはここでは割愛しますが、小さなギャラリーから始まった小さなムーブメントが、いつしか世界各国の大規模なミュージアムで開催するようになり、それが映画や本となり、現在まで語り継がれる歴史の1ページとなったわけですね。
ニール・ブレンダーは、志を持つ人たちにとって背中を押してくれるような存在。(竹村)
竹村 ここで今回のテーマを考えると難しいのが、『ビューティフル・ルーザーズ』に参加していたアーティスト全てが、スケーターというわけではなかったということだよね。レイモンド・ペティボン ※18 とかバリー・マッギー ※19 とかね。
※18 ポール・マッカーシーやマイク・ケリーと並んで、アメリカ西海岸を代表する現代アーティストのひとり。1978年に、実兄のグレッグ・ギンとチャック・ドゥコウスキーによるパンクバンド「BALCK FLAG」のレコードジャケットやクレッグのインディーズレーベルであった「SST」のための作品を描き始めたことで、自身のアートワークが「SONIC YOUTH」のカヴァーに起用されるなど、徐々にパンクシーンへと浸透していく。その後は、稀代のドローイングアーティストとして大規模なミュージアムなどで展覧会などを開催するまでに。
※19 コンテンポラリーアートの世界で活躍する、サンフランシスコを代表する現代アーティスト。またTWISTという名でストリートアートも手掛けることでも知られる。1998年にサンフランシスコ近代美術館で巨大な壁画を制作し、同館のパーマネントコレクションに選定され、同年にミネアポリス、ウォーカー・アート・センターで初の個展を開催し、全米のアートシーンを震撼させた。さらに2001年にはベニス・ビエンナーレに史上最大のインスタレーション作品を出品し、近年では2012年にユーシーバークレー・アートミュージアムにて90年代からのキャリアの集大成とも言える大展示を行なった。
平野 確かにライアン・マッギンレー ※20 とかアリ・マルコポロス ※21 とかもそうだしね。
※20 ニューヨークを代表する写真家。2002年に無名だった彼がインクジェットで自作したという初期写真集「The Kids Are Alright」が話題となり、翌年25歳の若さながら、ホイットニー美術館で個展を開催。彼の作品を象徴するヌードやロードトリップ作品、その多くが世界中で人気を呼ぶ。
※21 オランダはアムステルダム出身で、現在はニューヨークを拠点に活動する写真家。かつてアンディ・ウォーホールのアシスタントを務め、写真家という立場から激動の90年代の過ごしたスケーターやラッパーなどのユース世代を追いかけた写真集を数多くリリース。中でもアリの名を広く世に知らしめたのは、「Not Yet」や「Out & About」などの代表作。
竹村 アーロン自身は先ほども話したように生粋のスケーターでなくて、あくまでもギャラリーのキュレーターであり、本にまつわる編集者。そんな彼がスケートアートにとって重要な時代に、才能あるスケーターをサポートし、チャンスを与えたという事は、間違いなくスケートシーンに大きな貢献をもたらしたと思う。
どの分野でもそうだけど、プレイヤーだけではシーンは大きくならないんですよね、きっと。そういえば僕が気になったのは、『ビューティフル・ルーザーズ』には、あまりゴンズが関わっていなかったということ。個人的には結構意外だなって。
平野 ゴンズ、二度目のスランプの頃ですよね。おそらくメンタルがダウンしていた時期なんだろうね。改めてゴンズはアーティスト的というか感性そのものが繊細だったんだなって思いますね。
竹村 昔からスケートも調子が良い時と悪い時のムラが激しくてね。
平野 少し前はインタビューやスケートセッションの撮影とかでも、カメラマンのカメラを叩き落とす遊びが彼の中で流行っていたりしてね。ちょっと嫌な感じだった。それが彼の童心からくる純粋無垢な遊び心からくるものなのか、アーティストが故の不安定なメンタルからくるものなのか。
竹村 そういえば『ビューティフル・ルーザーズ』にはニール・ブレンダーも入っていないよね。まぁ彼の場合、昔からこうしたグループ展やイベントごとにはあまり積極的じゃないイメージもあるけどね。
平野 うんうん、そうですよね。それはきっと彼のアンタッチャブルな性格もあってなんでしょうかね。
小澤 ニールの今の作品って言うのはどこで見られるんだろうね。
平野 ギャラリーがついているわけでもないし、デッキをリリースしているわけでもないからね。どこで見られるんだろう? ただ今でもダイナソーJr .のアートワークは手がけているので、そこでは見られますけどね。
竹村 あとは僕が今年の夏にキュレーションした『LOVE + GUTS』※22 というアートショーで一点だけ日本に未発表作品を持ってきましたけどね。
※22 2005年にパット・ノーホー、スティーブ・オルソン、ランス・マウンテンが中心となりアメリカで始まったレジェンドスケーターたちによるアートショー。今年「HERSCHEL SUPPLY CO.」主催の下、今回ゲストとして参加している竹村氏がキューレーションを行い、日本にも初上陸。ホストの平野氏もアーティストとして参加。渋谷のスケートショップ兼ギャラリーの「16(Sixteen)」でプレビュー展を行い、静岡の静波にある「bnb GALLERY」でメインイベントが開催された。
平野 あと意外にInstagramはやっているんですよね。そのアカウントを見る限りは、〈HEATED WHEEL〉※23 という気の合うおじさんたちでやっている細いシェイプのデッキブランドをやっているみたいなんだよね。
※23 近年ニール・ブレンダーが「Alien Workshop」時代の盟友でもあるスティーブ・クラーと共に細々と活動するデッキブランド。表裏を逆にしたクルーザーようなフォルムが特徴的で、彼らがハンドメイドでカスタムするそれらのデッキには、ニールの代名詞でもあるアートワークが描かれている。別名“Polarizer”とも呼ばれる。
小澤 昔からニールはスキムボード ※24 に手を出すのも早かったし、そうした先見の明があったのかな。
※24 1920年代にアメリカ西海岸の人気ビーチであったラグナから発祥したマリンスポーツ。サーフィンとは異なり、足に固定する紐がついていないため、様々なトリックができることからスケートボードに限りなく近いサーフィンスポーツとしても人気。
平野 今でもスキームボードには興味を持っているみたいで、たまに関連画像をInstagramでポストしているけどね。
竹村 僕が思う、彼の魅力って、不思議な部分でもあるんだけど、お世辞にも絵の上手いアーティストではなく、スケートの実力もトップクラスの腕前とは言い難い。確かオーリーができなかったくらいだから。それでいてスケートアートの先駆者であり、なぜか惹かれるものがあるというね。
竹村 でもそんなニール・ブレンダーっていうアーティストがいたからこそ、スケート下手でも滑ってていいんだとか、絵が下手でも好きなら描いていいんだっていう。だから彼は志を持つ人たちにとって背中を押してくれるような存在でもあったのかなって。
何千枚もあるデッキからそのパーツに相応しいものを選ぶのが最も骨を折る作業ですね。(HAROSHI)
平野 まさにそうですね。となると、そんな多くのスケーターに夢を与えたニール・ブレンダーから影響を受けたかどうかは定かではないですが、日本が誇る、今を時めく現代アーティストのHAROSHIくんにそろそろ登壇してもらいましょうか。
HAROSHI 待ちくたびれちゃいましたよ(笑)。というのは冗談ですが、こうした講義を模したイベントというのはあまり慣れていないので、お手柔らかにお願いします。
小澤 HAROSHIは、この中だと太呂と一番付き合いが長いのかな?
平野 僕の記憶では、HAROSHIくんとの一番最初の出会いは、僕がやっている代々木上原の小さなギャラリーでアクセサリーの展示をしてもらったのが初めてだったと思っているのですが、いかがでしょうか?
HAROSHI その展示ももちろん覚えているんですけど、一番初めは確か2000年くらいにジョン・カーディエル ※25 が駒沢公園に来た時に僕らでアテンドをしたのが最初じゃないですかね。
※25 「ANTIHERO」のファウンダーとして多くのスケーターから愛されるレジェンドスケーター。キャリア全盛であった2003年に一時的に半身不随になるほどの大怪我に見舞われながらも、見事復活を果たした不屈の精神を持った存在としても知られる。現在はピストバイクのライダーやレゲエのセレクターとしても活躍する。
平野 あー、そんなのあったね。HAROSHIは駒沢のローカルスケーターでもあるんです。
HAROSHI 孝雄さん ※26 のカフェでお話したこともありますよね。それは確か太呂さんたちとスケートデッキのリシェイプ展をやった時だと思います。
※26 本名、新倉孝雄(にいくら たかお)。80年代から駒沢ローカルのスケーターとして活動し、その後カリフォルニアやインドネシア、中南米などを旅しながら絵を描き始める。1995年にはサンディエゴで開催されたアートショー「WALK」に出展し、その後も国内外の様々なギャラリーで精力的に展示を行う。現在は〈RVCA〉や〈NIXON〉などからサポートを受けるアーティストとして活躍。さらに駒沢公園近くの人気カフェ「nico」のオーナーでもある。
平野 そっちの方が先だったのか。まぁ、というような今から20年近く前に出会ったHAROSHIという人物は、皆さんもご存知だと思いますが、使い古されたスケートデッキの廃材や古材を使ってリサイクルして物作りをしているアーティストなんですね。
竹村 その前はハーベストという名義で、さっき太呂の言っていたアクセサリーを作っていたんだよね。
HAROSHI そうですね。ちなみにそのハーベストという名前は、僕が昔からマーガレット・キルガレン ※27 が好きで、彼の最後の作品集の名前から採っているんですよね。
※27 アメリカの現代アートシーンに今なお影響を与え続ける、サンフランシスコ出身の女性アーティスト。自身もサーファーであり、サーフやスケートのコミュニティに深く精通しており、過去にはトミー・ゲレロのCDジャケットにもアートワークを提供。夫はバリー・マッギー。2001年に他界。
平野 それは知らなかったな。なるほどね。ちなみにHAROSHIの作品は、どういった工程で作られるのか知りたいね。
HAROSHI まぁ大まかに説明するともう使わなくなったスケートデッキを集めて、作る作品のモチーフに合わせてスケートデッキを重ねて切断して、剥がしたり、繋ぎあわせたりという作業の繰り返しですね。
竹村 スケートデッキってブランドや会社によって微妙にシェイプも変わってくると思うけど、その辺りはどうなの?
HAROSHI 同じ会社のデッキでまとめるともちろん相性も良いんですけど、違うコンケーブでも物によっては板と板の間に別の会社のものを挟むと調子が良かったりして、いろいろあるんですよね。
竹村 その視点でスケートデッキを見ているのは、おそらくHAROSHIくらいだろうね(笑)。
HAROSHI 色とかも仕上がりを左右する選定基準としては重要なんですけど、実はそれ以上にデッキのコンケーブやキックの形状が厄介だったりするんです。だから千枚以上もあるデッキから相応しいものを選ぶのが最も骨を折る作業ですね。
平野 適材適所でね。この日持って来てもらった作品は持ち運ぶのできるサイズ感だけど、過去にはとんでもなく大きい作品とかもあったよね。
大変だけどそこにこだわりを持っているのは、いちスケーターとしてのプライドですね。(HAROSHI)
HAROSHI そうですね。〈HUF〉のニューヨークとロサンゼルスのお店がオープンした時に作ったモニュメントはかなり大きいですね。あとは馬のモチーフの作品も一度作ったことがあるんですけど、それは実際に大人の人間が乗れる強度と大きさで作っています。
HAROSHI 昔薬局の前にあったムーバーをベースにしていて、実際にそのムーバーも解体して再構築しているので、本物同様に動くんですよね。ポイントは前足が折れているんですけど、それでも走るよっていう。
平野 こういう折れているところとかを残すのはHAROSHIらしいよね。
HAROSHI そういってもらえると嬉しいですね。あまり伝わらない部分かなと思っていたので。
竹村 むしろHAROSHIの作品の魅力はあそこでしょ。
平野 実際に誰かが乗っていたんだなっていう痕跡が分かるもんね。スケートデッキを使っているからこその特徴だよね。
竹村 あれは実際に折れてしまったスケートデッキを集めて作ってるの?
HAROSHI そうなんですよ。だから折れたスケートデッキから形や色をまた合わせて行く作業があるので、本当に大変なんです。大変だけどそこにこだわりを持っています。さっき太呂さんがおっしゃっていた通り、使用感をあえて残すことで説明的なディテールとしても機能させているんです。
平野 そうした作品は日本ではもちろんだけど、世界でも次第に評価されていくわけですが、これまでの活動を簡単に訊けたらと思うんだけど。
HAROSHI 2010年頃までの僕っていうのは、デッキを使ったアクセサリー作りから立体物までを手掛けていて、たまに個展を行う程度だったんですけど、2010年に青山で行なった個展が国外でも好評を得まして、それから〈NIKE〉との仕事が決まったりしたこともあり、少しづつアートに関心のある人たちから知られていくようになるんですね。
そしてここからさらに次のステップに行くには、ニューヨークの有名なギャラリーで作品を発表しないといけないなと思い、その後様々な偶然が重なって、晴れてニューヨークにある「Jonathan Le Vine」 ※28 というローブロウやストリートシーンから絶大な信頼を得ているギャラリーに籍を置くことになったんです。日本でも有名な、あのINVADER ※29 やWK ※30 なども所属する、ストリートシーンでは一流とされるギャラリーです。
※28 ニューヨーク出身のキュレーターであったジョナサン氏が手掛けていたストリートシーンで広く名の知れたギャラリー。INVADERやWKなども所属していたことでも知られ、2011年から2016年までHAROSHI氏も籍を置き、数々の作品を発表。今年閉業した。
※29 アーケードゲーム「スペース・インベーダー」のキャラクターをモチーフにした作品をパリをはじめ世界各地の都市に数多く残す、フランス人ストリートアーティスト。近年は地域や国にちなんだ建物や動物をモチーフにした作品も多い。
※30 ニューヨークを拠点に活動するフランス人グラフティアーティスト。人物の動きを写真に撮影し、それをモノクロのインクで着色して仕上げるという手法でストリートシーンで話題となる。今最も入手困難な作品を生み出すアーティストの一人としても知られる。
HAROSHI 実はそこが不払いなどの問題がありすぎて、結局5年くらいでそのギャラリーの所属を離れました。今もその当時のいろいろなお金の問題を解決しているところです(笑)。
竹村 でもギャラリーはまだ残っているよね? 僕もよくそこのギャラリーからメールをもらっていたからさ。
HAROSHI 嘘みたいな話ですけど、今日ちょうどなくなりますという内容のメールがありました(笑)。
HAROSHI そうなんですよね(笑)。お金の回収ももう出来ないだろうし、作品もまだ残っていて、しかもサイズがめちゃくちゃ大きいやつなので、どうしたものかと。けど、そうしたニューヨーク時代の問題はいまだに残ってはいるんですが、今は日本でも別のギャラリーに所属しながら気ままにやらせてもらっている感じです。なんとかなるもんですね。
竹村 それ以来、アメリカではアートショーとかはしていないの?
HAROSHI 昨年「KITH」というスニーカーブティックのお店で小さなショーはやりましたが、大きなショーはやっていないですね〜。
小澤 今はほとんどないということだけど、当時はどんなクライアントと仕事していたの?
HAROSHI 国外でした一番最初の大きな仕事と言えるのは、〈NIKE〉のCEOであるマークパーカーとのコミッションワークでしたね。確か2010年ごろだったと思います。写真にもあるダンクなどのモデルを僕の作風であるデッキのスカルプチャーで制作するというものなんですけど。
それで、作品を納品しにポートランドに行った際に〈NIKE〉の担当者に『「The Berrics」※31 というスケートパークに沢山スケートデッキの廃材が余ってるから自由に使っていいよ』と言われたので、それなら僕がBATB※32 のトロフィーをそのデッキから作るってスティーブ・ベラ ※33 やエリック・コストン ※34 に伝えて欲しいと言ったんです。
※31 トッププロスケーターのエリック・コストンとスティーブ・ベラが運営する、スケートメディア。またそのメディアによるプライベートなスケートパーク。スケート専門のウェブメディアとして様々な個性的なコンテンツを抱え、世界屈指の人気を誇る。またロサンゼルスに構えるスケートパークではハイレベルなコンテストを数多く開催しており、新世代のスケーターにとっては登竜門的な場所としても知られる。
※32 「The Berrics」が主催する世界最高峰のスケートゲームイベント、Battle at the berricsの略称。毎年4月〜6月ぐらいの時期に開催される。スケートゲームとは、ストリートでのスケートボードによる遊びから生まれたもので、ルールはいたって簡単。親になったスケーターがメイクしたトリックを子になったスケーターもチャレンジし、子になったスケーターが5回失敗したら負けというもの。親が失敗したら子のスケーターに親が回ってくる。
※33 「The Berrics」を共同運営するエリック・コストントは旧知の仲として知られ、前例のないスケートメディア兼スケートパークを成功に導いた立役者とも言われる。また〈ALIEN WORKSHOP〉や〈DC Shoes〉の看板ライダーとして様々な実績を残し、シグネチャーモデルも数多くリリース。「ギルバート・グレイプ」などで有名な女優のジュリエット・ルイスは元妻。
※34 天才スケーターの名を欲しいままにする、90年代を代表するプロスケーター。「H-STREET」、〈GIRL SKATEBOARDS〉での黄金期を経て、〈es〉、〈LAKAI〉、〈NIKE SB〉と名だたるスケートシューズブランドを渡り歩き、これまでに数々のフッテージを発表。現在はガイ・マリアーノと一緒に立ち上げたアパレルブランドの〈Fourstar〉や、スティーブ・ベラと共に設立したスケートパークとWebメディアの機能を盛り込んだ 「The Berrics」を運営。
平野 一応説明して置くと、「The Berrics」では定期的にスケートのコンテストを開催していて、その入賞者へのトロフィーをHAROSHIが手掛けることになったんだよね。このことをきっかけに、HAROSHIという存在が世界的なネームバリューを持ったアーティストであると、一気に加速していくんだよね。
HAROSHI そうですね。でもそれからしばらくは「The Berrics」からなんの連絡も無くて、僕も次の仕事の準備をしているうちに忘れていたんですが、その後にロサンゼルスの〈HUF〉でショーをやった時に、「The Berrics」の二人がやって来て、『お前トロフィー作るって言ったよな?』って急に言われて。その時に一ヶ月後に納品という無茶なスケジュールを振られて、しかも最初はタダで作ることになったんですよ。
平野 無茶苦茶だね(笑)。むしろ搬入とか搬出とかの移動を考えたらマイナスじゃない?
HAROSHI その時は流石にお金もなかったので作品を郵送で送りましたけどね。でも作品はどれも気に入ってもらえたので、それから6年間はトロフィー製作の担当アーティストとして「The Berrics」と良いお付き合いをすることができたので、結果的には良かったかなと。
竹村 良かったね。そこからキースとも仕事をするようになったのかな?
HAROSHI キースとは知人を介して出会ったのですが、その時はまだ日本でしかショーもしたことがない頃なのに僕の作品に興味を持っていてくれて、『ロサンゼルスの僕のお店でアートショーをやらないか?』って誘ってくれたんです。内容も好きなようにして良いよと言われて、その2年後に〈HUF〉と初めてのアートショーが実現したんですよね。
当時の〈HUF〉はブランドとしてまだ若くて、規模も今よりもずっと小さかくて。ロサンゼルスのダウンタウンに小さいウェアハウスがあったんですが、そこでアートショーを行なって、当日は1000人くらいのお客さんが来てものすごい盛り上がったんです。そこで彼らのクルーと仲良くなれて、以来ずっと手厚いサポートを受けています。
小澤 今となっては〈HUF〉もスケートブランドを代表するビッグブランドになったけど、今でも彼らと仕事をする時は自由にやらせてもらってるの?
HAROSHI 基本的にはそうですね。でも新たにショップをオープンする際には、これを作って欲しいというリクエストの依頼もあります。ロサンゼルスのお店の時に作った、あのバカでかいミドルフィンガーのスカルプチャもそれです。普段はああしたモチーフを作る事ってほとんどないので、僕自身かなり新鮮だったんですけど、いつの間にかアイコニックな作品になってしまって少し複雑なんですね(笑)。
竹村 キースといえばの代名詞な印象は、確かにあるね。
HAROSHI 僕はどちらかというと今日持って来たようなGUZOモチーフのデザインが好きなんですよね。
HAROSHI GUZO(偶像)って神様みたいな存在だと勝手に思っているんですけど、例えばキリストは人々の感じる痛みを全て彼自身が受けることによって、神様に近い存在になったと言われていて。そこでよくよく考えたらスケートボードも同じなんじゃないかなって。
僕らスケーターの代わりにあらゆる痛みに耐えて、最後には朽ち果てるというか。だとしたらスケートボードの廃材はきっと僕らにとっての神様を作るには最適の材料になるんじゃないかと思ったんです。ちょっと気持ち悪い話になってしまうかもしれないんですけど(笑)。
〈HUF〉のファウンダーであり、プロスケーターとしても多くの功績を残したキース・ハフナゲルとHAROSHI氏の貴重なツーショット。今となっては〈HUF〉のお店のシンボルとなっているアートワークの多くをHAROSHI氏が手掛けている。
テンションとか雰囲気でごまかせてしまう作品ではなく、“ちゃんと作る人”になろうって思った。(HAROSHI)
小澤 HAROSHIくんの作品ってかなり重労働だと思うんだけど、その割には〈HUF〉のミドルフィンガーもそうだし、僕と太呂が「Sb」でお願いした地球儀の時も割と依頼主の要望とかに応えてくれるじゃないですか。そこが他の頑固なアーティストとは違うよなーと思ったんですが、その辺りに関してはどう思いますか?
HAROSHI その頃はコミッションもやっていたんですけど、今はもうやっていないんです。話が少し変わってしまうんですが、スケートカルチャーに携わるアーティストって、例えば著名なプロスケーターのように実績や名声があったほうが当然いいんですよね。っていうのは例えばマーク・ゴンザレスが描いてるアートって、スケートスタイルでも評価されていたゴンズだからこそ評価されているわけですよね。
はっきり言って、これをゴンズ以外の人間が描いていてもどうしようもないですよ(笑)。なので、ことスケートアートに関しては、“誰がやっているか”というのが大事なんです。だからこそ僕はプロスケーターでもないし、ネームバリューのあるスケーターでもなかったからこそ、アートを作ろうと思ったわけなんですよね。その時に、言い方があまり良くないですけど、テンションとか雰囲気でごまかせてしまう作品ではなく、“ちゃんと作る人”になろうって思ったんです。
それは僻みや批判ではなくて、僕自身も彼らのようなアーティストたちが好きだからこそ、尊敬の念も込めつつ、同じ土俵ではないところで戦うしかないなと思うんですよね。
竹村 これはスケートだけに限らずだけど、確かにスケートアートはそういったフィルターが特に強いかもしれないですね。
平野 HAROSHIはこれまでスケーターということもあって、スケートデッキにこだわり続けているイメージがあるけど、今後の作品もやっぱりその姿勢は変えないの?
HAROSHI 売れないから発表していないだけで、実はスケートデッキ以外に普通の木材だったり、全く異なる素材を使って作品も作っていましたよ。これまではまず僕自身の名刺となる作品を作ることに必死だったので、デッキの廃材を使ったスカルプチャを作り続けてきましたけど、今後はさらに自分の好きなものを追い求めて全く異なる作風の作品も世に送り出したいなって思っていますよ。
平野 いいですね。日本代表として頼もしいなぁ。HAROSHIくんの話にあった、ゴンズやニール・ブレンダーはスケートボーダー界のヒーローであるというフィルターがある。しかし自分にはそれがない。ならば違うやり方でやるんだという話、感慨深いですね。
スケーターってそうしたアートに限らずデッキの選び方から着こなし、スポット選びからトリックの種類に至るまで人とは異なるスタイルを求める種族だと思っていて。むしろそこにこそ価値があるんですよね。
そう考えるとやっぱりHAROSHIくんってスケートボーダーなんだなって再認識したと同時に、そのスタイルが認められた数少ない日本人アーティストなんですよね。
竹村 HAROSHIの作品ってそのままスケートカルチャーへの愛情だったり、熱も伝わってくるからね。
HAROSHI そこだけは誰にも負けない自信がありますね。
平野 魂の吹き込まれた作品。それだったら人々を魅了しますよね。でもこれから先、HAROSHIがスケートデッキを使わなくなった時というのもまた見てみたいですね。そしてまだまだHAROSHIくんには聞いてみたいお話が沢山あったんですけど、残念ながらお時間が来てしまったので、最後にひとつ僕から質問を。
平野 HAROSHIくんにとってのスケートボードの楽しみ方ってどんな形なんだろう?
HAROSHI アメリカのレジェンドスケーターたちを見てると、今だにみんなスケートに乗り続けていますよね。当然体力やスキルは落ちるわけなので、年齢にあったスタイルに変化させながら、その人にあったスケートを楽しんでいるように思えるんです。僕も同じように歳をとり、40代に突入して、改めてプッシュしてるだけでも楽しいなって思えるんですよね。
とにかくスケートが上手くなりたいって気持ちは若いうちは特に大事だと思うけど、気がつくとそれがきつくなっちゃう時がいつかくるんですよね。スケートボードの正解は沢山あるんだなって今改めて気付かされましたね。
竹村 確かに。日本でもアキ秋山さんはいまだに現役な訳だもんね。なんなら俺や太呂もそうだしね。
平野 そうですね。HAROSHIくん、今日は貴重なお話ありがとうございました。今回もスケートカルチャーを語る上で欠かせないテーマだったということもあって、なかなか濃い内容になりましたね。そして次回の講義テーマは、『スケートボードとビデオ』。ゲストはこの人しかいないんじゃないかなということで、「FESN」の森田貴宏君に登場してもらおうと思います。こちらも負けじと濃厚な講座になると思いますので、また来月14日にVACANTでお会いしましょう。
今回のゲストの一人であった竹村卓氏が持参してきた大量のスケートリンクZINEや写真集、さらには名だたるスケーターやアーティストから直接もらったという手紙や落書き、アートワークなど。そのいずれも長年スケートカルチャーを追いかけてきた氏のコミュニティがあってこその貴重な代物ばかり。
この日は講義イベント終了後に、急遽HAROSHI氏の作品や竹村卓氏が所持するスケーターたちの貴重なアートピースを聴講生の参加者たちが実際に手にとり、触れられる時間をご用意。さらに普段はなかなかお話の聞く機会もない登壇者たちと雑談する場面も見られた。