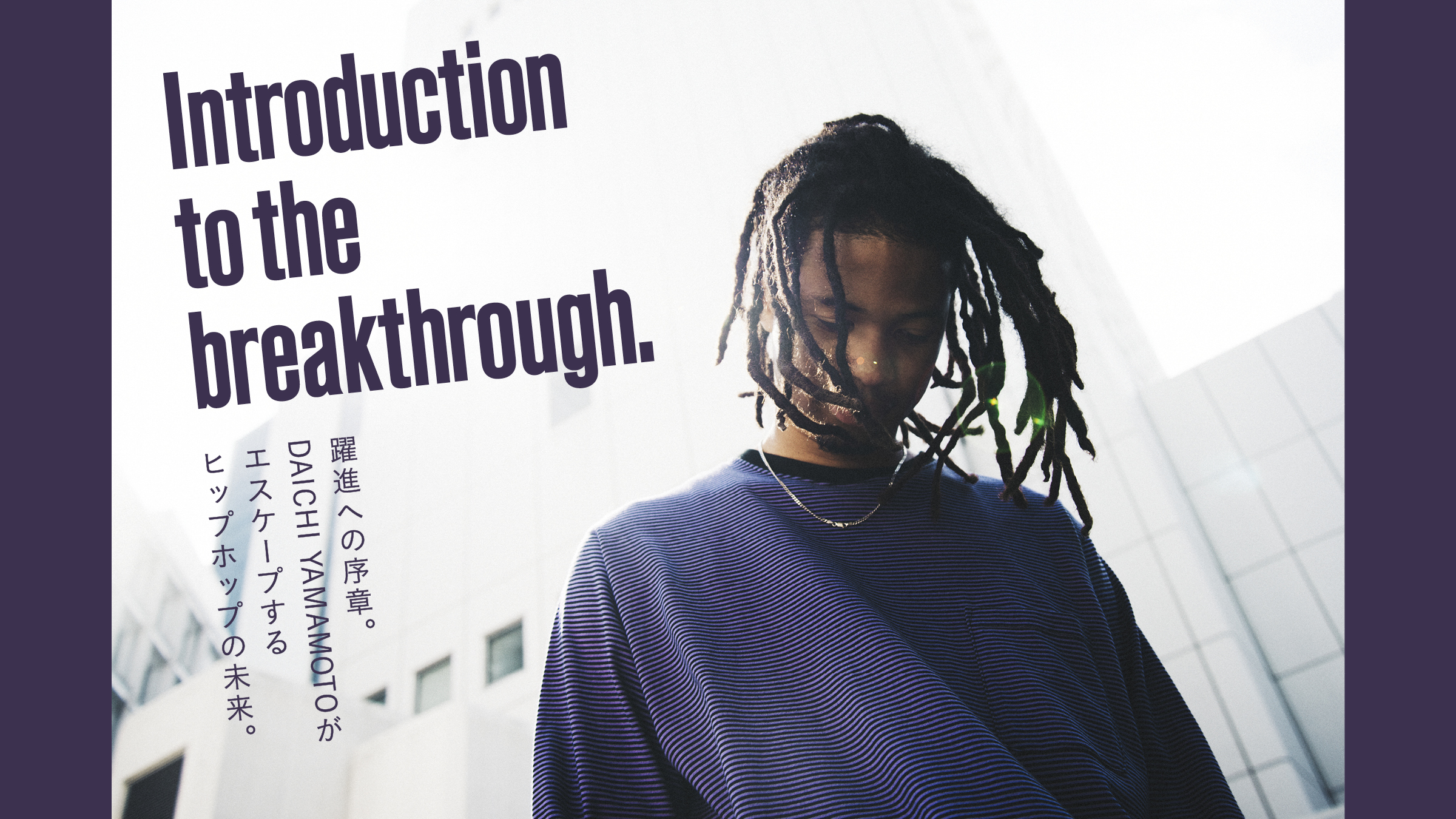その時に必要じゃないと思えるものは置き去りにしながら、変わらずその時に見える景色を音にしていくだけ。
ー また今回の作品ではこれまで親交のあるアーティストの客演に加え、意外性のあるフィーチャリングも目を引きました。特に4曲目の「Los Location」ではCREATIVE DRUG STOREのVaVaくんを迎えいますよね。
DAICHI:はい。実はVaVaくんとは面識がなかったんですけど、マサトさんに『意外と一緒にやったら合うんじゃない?』って紹介してもらい、いざやってみたら本当に良くて。今まで出会わなかったタイプというか。それまでは自分の知っている人たちとだけやっていたような部分もあるので新しい発見がありましたね。曲を作る前に一緒に銭湯に行ったりして親睦を深めながら、信頼関係を築いていく過程も新鮮でした。一種の化学変化ですね。
ー 同じように「Let It Be」では全くタイプの異なるフロウを持ったKid Fresinoとも共演しています。オートチューンや気鋭ビートメイカーのQUNIMUNEによる生楽器やシンセなど、アナログ&デジタルのトラックが見事に融和し、今っぽいミックス感も感じられました。
DAICHI:Kid Fresinoくんとも当初は一緒に曲を作る予定がなかったのですが、その時期にちょうどリリースがあったKid Fresinoくんの「ai qing」の世界観と自分がファーストアルバムで目指していた方向性がすごく合うような気がして、オファーしました。正直サビのフックは入稿ギリギリまで落とし所に悩んじゃって。負けず嫌いな性格もあって、客演する人のバースのクオリティが高いほど自分のハードルを上げちゃうんですよね。この曲に関して、まだもう少し自分のバースを極められたかなって思う部分もあるんですけど、おっしゃる通りQUNIMUNEさんの十八番でもある生楽器とシンセのトラックも抜群でしたし、効果的なオートチューンなどの要素も取り入れながら、ひとつのアルバムを通して存在感のある一曲になったと思います。

ー 本作ではDAICHIくん自身もビートメイキングを行なっていますが、ラッパーやシンガーとしてではない全くの別のクリエイションという意識で取り組んでいるんですか? また今回参加したビートメイカーから受けた影響などもあるのでしょうか?
DAICHI:そうですね。僕自身ビートメイカーを本業にしているわけではないので、そういった人たちと作り方は全く違って、影響はもちろん受けているんですけど、そこまで意識はしていないかもしれないです。どちらかというとFrank Oceanのような感覚に近いですかね。実験的な取り組みの延長というか、歌い手の視点の中でコントロールしながら作っています。まだまだ荒削りな部分もあると思いますけど、満足はしていますね。


ー ちなみにタイトルの「Andless」に込められた意味というのは?
DAICHI:これは造語なんですけど、 “続きのない”って意味を込めています。元々は「Undress」という言葉をベースにしていて、それは“脱いでいく“という感覚に近くて、今まで対外的なイメージを気にして着膨れした僕自身の偽りの厚みを、一曲ごとに表現していくことで研ぎ澄ますように減らしていくという意味もあるんです。つまりはネガティブな一切のものを振りほどいて、解き放たれていく感覚というか、丸裸の等身大の姿を見せたいっていう思いでつけたんです。
ー なるほど。その感覚は12曲目の「Escape」でも強く感じられますよね。今回の記事のタイトルでも掲示しているエスケープという言葉。アルバム内にもある楽曲タイトルから拝借したワードでもあるのですが、次世代の音楽を手がける存在に共通して感じている言葉でもありました。ネガティブな意味合いではなく、でもアップデートやチャレンジともまた違う解釈。“自由な表現を求めて既存のスタイルから脱出していく”感覚。それはDAICHIくんがこの先、見据える未来を示唆しているのかなと。そういった意味でも、DAICHIくんがこれからエスケープしていく先にはどんな景色が広がっているのか、聞かせてください。
DAICHI:制作をしている中で誰しもが逃げ出したくなる状況ってあると思うんです。もちろん僕もそうした感情に駆られることがあって。ただエスケープって受け取り方によってはネガティブな言葉でもあると思うんですけど、僕の中ではもっとポジティブな意味でもあって、辛い状況や現状を打破したい時、自分のマインドを今までとは違う場所に持っていくことで新しい視点が生まれたり、発想が生まれていくのかなって。多分僕は無意識のうちに次の世界、時代にエスケープしていきたいんですよね、きっと。その時に必要じゃないと思えるものは置き去りにしながら、変わらずその時に見える景色を音にしていくだけなのかと思っています。その思いが変わらない限り、これからもずっと音楽を作っていける気がします。