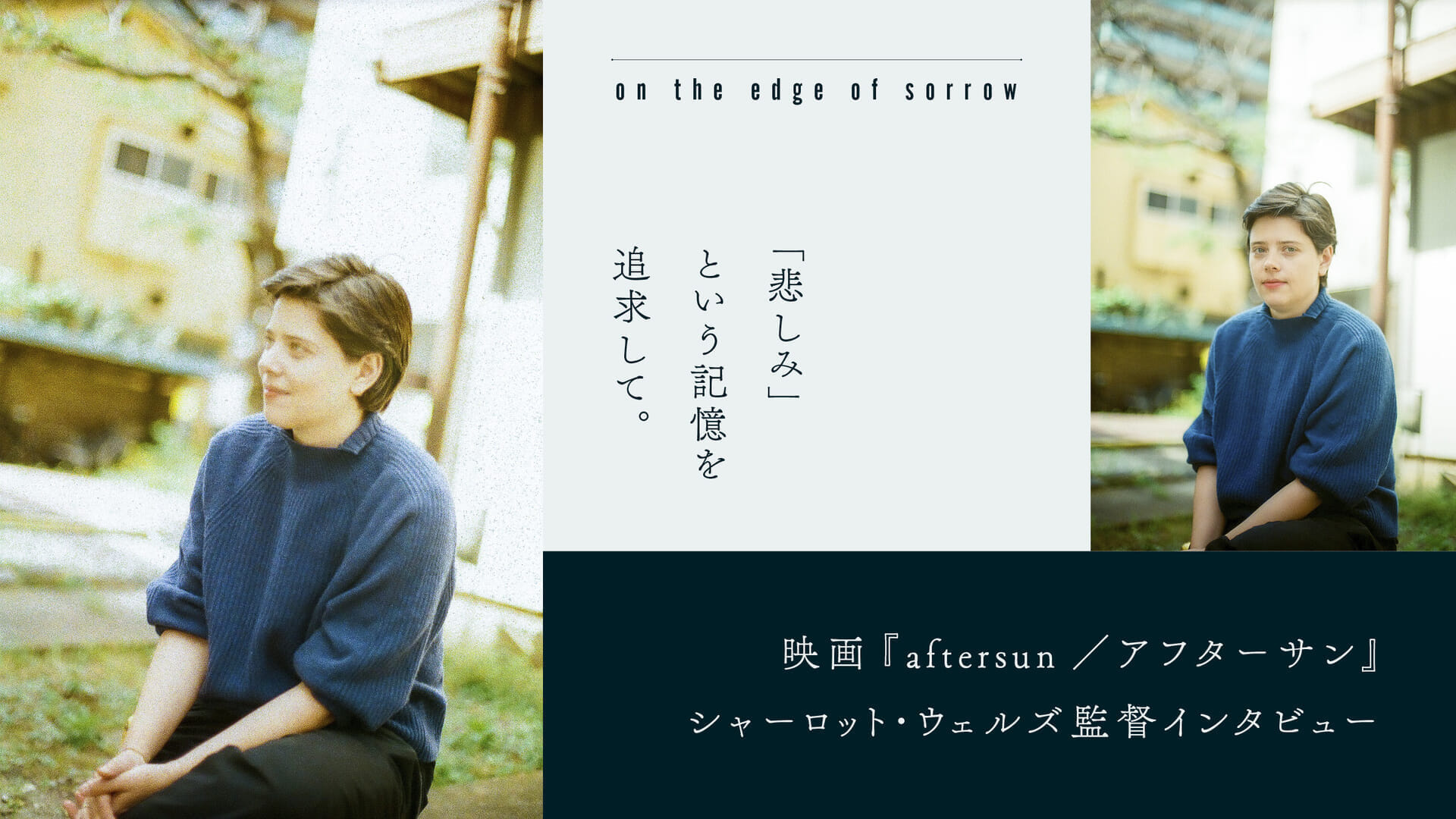親と子ども、それぞれの時間が重なり合うように。

─思春期の性的関心の高まりと揺らぎの渦中にあったソフィの20年後、パートナーが同性である描写がありました。劇中でも多様な恋愛のかたちが描かれていましたが、それらのシーンから、90年代という時代背景を踏まえてもカラムは性自認に悩んでいたのではないかと考えました。事実は個人の判断にゆだねるとして、セクシュアリティの揺らぎを描こうとする意識が監督にはあったのでしょうか?
ウェルズ: ソフィの思春期の性に対する興味については、描こうと思っていました。好奇心という意味で男の子とキスをしてみるけれど、あまり積極的にはなれない自分がいて、そうした揺れですよね。その後に、少年同士がキスをしているシーンをソフィは見ますが、その光景に自分自身の感情の変化があります。さまざまな解釈をしてもらえる余白を残した映画なのでいろいろな意見があって当然なのですが、伝えておきたいのは、セクシュアリティがカラム自身を抑圧しているという描き方はしたくなかった。ただひとつの苦悩に帰結するのではなく、もっと複雑なものではないかと思っています。
─悩みの根源はひとつではないと。
ウェルズ: はい。たしかに彼は抑制されている状態で精神的な苦悩を抱えていましたが、その原因をセクシュアリティに絞りたくなかった。そこを意識的に描かず、彼の精神状態に焦点を当てるようにしました。
─最後に、監督が理想とする親子関係についてお話をうかがいたいです。親が子に対して弱い部分を見せられない、というのはよくある話ですが、本作では「ひとりの人間として内なる父を知ることができたなら」と子が願う姿がありました。それは、内なる部分を見せ合うのがいい親子関係なのでしょうか?
ウェルズ: 編集を担当してくれたブレア(マックレンドン)がこんな詩を読んでいました。
They fuck you up, your mum and dad.
They may not mean to, but they do.
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you.
『This Be The Verse』Philip Larkin, 1971
(訳)意図的ではないのだけれど、親というのは子どもの心をかき乱す。そして、親自身の欠点が子どもにプラスされてしまう。
完璧な親、完璧な子育てというのは存在しないと思います。そして、子どもが親を完全に理解することは難しい。大人になるにつれて見えてくるものもあるけれど、それでも不透明です。なので、できるだけ親は子どもに正直に接するのが理想ではありますが、見せきれない部分があって当然です。子ども自身も成長し続けていることを認識して、時間をかけてお互いを知っていくしかないのかなと思います。どう思いますか?
─親と子どもはまったく別の人間であることを、わかっておきたいと常々思います。似たような世界を生きているつもりでも、考えや価値観はまったく違うものになる。欠点を加えていくような関係性ではなくて、互いの異なる視点を尊重しあえる関係でありたいですが、そう多くは望まないようにしよう、とも思います。

ウェルズ: この作品をなんと説明しようかと、何度も地下鉄の中で考えたんですね。そのときに、このふたりは離れ離れで暮らしていることもあり、圧倒的に共有できない時間がある。旅では一緒に過ごして、喜びや悲しみを共有しているのですが、今限りの “メランコリック” な部分があります。だからといって、現実に戻れば美しい記憶や楽しい気持ちが削ぎ落とされるわけではなく、それぞれの時間が合わさっているような、そんな映画なのかなと思っています。
─だからなのか、私はカラムからソフィ自身の世界を尊重する気持ちと、できるだけ幸せで健康でなりたい自分になってほしい、という親の気持ちと、両方の感情に引き裂かれながらもどちらも本音である感じを受け取ったのかもしれません。
ウェルズ: ありがとうございます。