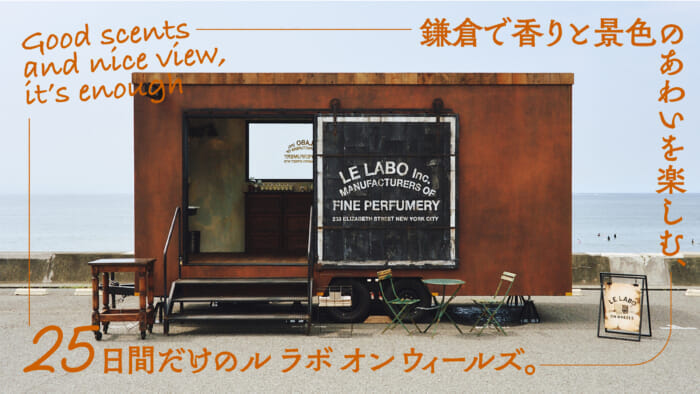香水と相通ずる町家の世界観。

実際に「OSMANTHUS 19」が販売されるのは、京都にある二店舗。その一つ、「ル ラボ 京都町家」は、酒造屋だったという町家をリノベーションして、この春に生まれました。




ベースとなる建物が建てられたのは明治時代。150年以上前に建造されたという厨子(つくし)二階の町家は、長い年数の末に生まれた独特の雰囲気があり、ほかのどの店舗とも異なります。暖簾をくぐり、フレッシュ ブレンディングを行なう旧ミセノマにあるラボを横目に、ミセニワからハシリニワへと進むと、陰影の効いた店内はまさにモダナイズされた京町家。
うなぎの寝床という言葉の語源となった京町家は、間口が狭く、奥行きのあるつくり。天井の火袋と呼ばれる伝統的な梁や炊事場などはそのままに、新しく設えた銅の水道管や木製の棚などは、この世界観を損なわないように配慮された素材を選んでいることが伺えます。というのも、さまざまな場所で使われる新旧の素材が違和感なく同居しているから。この建物自体が「OSMANTHUS 19」のコンセプトと共鳴しているのは、いわずもがなでしょう。




この「ル ラボ 京都町家」は、〈ル ラボ〉の他の店舗と異なる特別なストアデザインです。ヴィンテージの家具や盆栽、建物に備わっていたガラス扉から見える坪庭、木製の格子に囲われたラボも、世界でここだけ。海外ブランドでありながら、ここまで日本の美意識を精度高く感じ取れているとは…。
なかでも大事にしているのは日本が生んだ“侘び寂び”という美意識であり哲学。いまから100年ほど前に西洋へと渡ったその考え方は、レナード・コーレンの『Wabi-Sabi わびさびを読み解く』に影響を受けて「WABI SABI DESIGN BOOK」という本を出版するほど、〈ル ラボ〉にとっては大切な考え方のようです。
長く使われ古色がついた家具やディスプレイされた工具などは、ディテールまで注意深く観察しないと素通りしてしまいそうなほど上手に調和が取られ、〈ル ラボ〉らしい繊細さと奥ゆかしさを感じ取ることができます。


広く取られた窓からは光が差し込み、置かれているクラシック コレクションの香水も、いつもとは異なる趣に。シンプルなボトルデザインは、どんな空間ともマッチしてくれます。四季折々の眺めを楽しみながら、自分好みの香りを探すと、またいつもとは違った発見があるかもしれません。
もちろん香水のほかにも、シャワー ジェル、ボディ クリーム、ハンド クリーム、ハンド ソープ、リップ バームといった定番アイテムからトートバッグまで、ほぼすべての〈ル ラボ〉のクリエーションが揃っています。


ハシリニワの流しを過ぎてさらに奥へと進むと、店内から見えた京町家らしい奥庭と蔵を改装したカフェが見えてきます。陰影が効いている落ち着いた店内とコントラストを感じさせる明るい庭で、バリスタが淹れるおいしいコーヒーやクッキーを楽しみながら四季を感じたり、建築をつぶさに観たりするのも一興です。カフェはテイクアウト専門で、メニューはすべてヴィーガン仕様。



靴を脱いで2階へあがると、調香の間と工匠の間があります。古い木造建築のため上がれる人数が限られているというのもユニークで、ときおり1階の屋根の上を猫が横切っていくのが見えるそう。
調香の間は、調香師の仕事場をイメージしてつくられました。エッセンシャルオイルをはじめとしたさまざまな原料をビン越しに見ることができ、身の回りにあるものが香水の原料の一部ということを体感できます。厨子二階特有の天井の低さもワクワク感を演出してくれて、まるで隠れ家のようです。
また、工匠の間では、定期的に職人を招き、その技を実演しています。これも職人のクラフツマンシップに対する〈ル ラボ〉のリスペクトの表れでしょう。これまでに書道家や伝統的なうちわ職人などが登場し、作品ができあがるその過程を目の前で観ることやサービスを受けることができたそうです。店舗に飾ってある作品も、そのときに筆を揮ったもの。日本の美意識や丁寧な手仕事を体感できるこのスペシャルなサービスは、この店舗でしか体験できません。公式サイトで告知されるらしいので、気になる方はぜひチェックを。