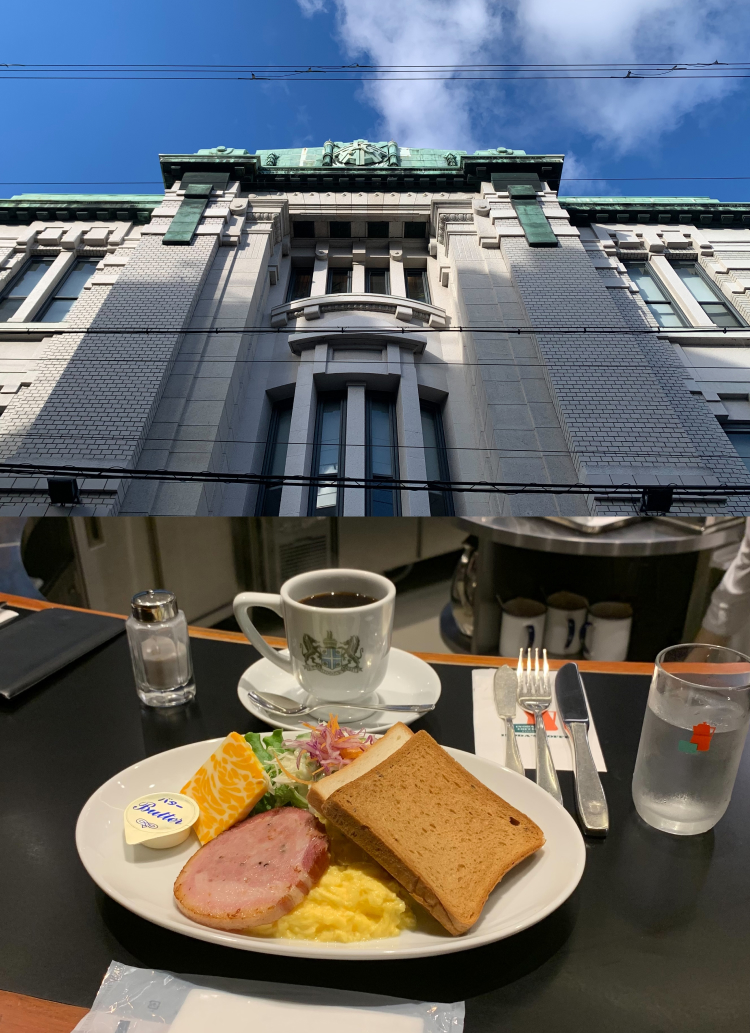広がる領域と、描く未来のカタチ。
吉本はファッションデザイナーだが、アーティストとしての顔を持つ。ここから東京・六本木の「21_21 DESIGN SIGHT」に舞台を移し、彼が企画協力者のひとりとして参加し、作家としても名を連ねる企画展「ゴミうんち展」を紹介します。
「ゴミうんち展」。非常にインパクトの強いタイトルですが、これは我々のゴミや排出物に対する固定観念を多角的な視点からアップデートしようとする試み。展覧会のディレクターを務めるのは、この館の館長でグラフィックデザイナーの佐藤卓と、文化人類学者の竹村眞一。その脇をバラエティ豊かなアーティストたちが固め、「pooploop(循環)」というキーワードのもと、近づきにくい題材をユニークかつポジティブに解釈しています。この展覧会は昨年9月からはじまり、幅広い世代、さらに訪日外国人まで、注目度が高く多くのひとが訪れるといいます。

この展覧会はサステナブルやアップサイクルに括られるテーマを違う角度で捉える。
そもそも吉本が参加したきっかけは、佐藤からのオファーでした。二人の出会いは2021年に「愛知県美術館」で行われた「スタジオジブリ」の展覧会に遡ります。当時、佐藤が企画監修し、その空間デザインを吉本が担いました。
そして「ゴミうんち展」では、吉本が企画チームのメンバーに加わり、展示構成や展示作家などをチームと共に考えました。
会場構成は大きく分けて2つ。まず来館者を驚かすのが「糞驚異の部屋」と題し、作品と資料を合わせて700種以上展示したスペース。細かな展示物をひとつひとつ数えると、その数は2,000を超えるといいます。

実際にゴミになるものや排出物、リサイクル資源、化石など多種多様なものが並ぶ。
そもそも “驚異の部屋” というのは、珍品を蒐集する貴族が自分のコレクションを見せる部屋のことを指します。展示様式として昔から存在するもので、博物館の原型になったといわれています。
「この展覧会のテーマは、循環をキーワードにあらゆるものに繋がっていきます。参加した作家の作品づくりのもとになった循環の概念など、企画する段階で自分たちが学んだもの、それをそのままここで見せたいと思いました。自分は『糞驚異の部屋』の発案者のひとりで、これを表現するのは覚悟のいることだったのですが、アートディレクターの岡崎智弘さんを中心につくりました」
ここには吉本の私物であるトルソーの型、サルノコシカケ、フェルトの端材、コルクの樹皮なども飾られています。



「糞驚異の部屋」に並ぶ吉本の私物たち。
そして、「糞驚異の部屋」の奥に広がるのが、この展覧会の核となる空間です。普通、ゴミや排出物として扱われるものをあえて再利用した作品や、循環や価値観に対する概念を再定義した作品など、そこには13組のアーティストが参加します。
このスペースに吉本は「気配」というシリーズの3作品を出展しました。目を引くのが木製の巨大な什器を中心に、苔に見立てたニットモジュールを配した「気配 – 覆い」です。

什器に共存するのは吉本の作品と、彫刻家・井原宏蕗の作品「cycling -go at-」。これはヤギの糞で出来ている。
「このシリーズでは自然物と人工物の境界線を探っています。その揺らぎを服づくりのテーマに据えることもありますが、『気配 – 覆い』は建物が徐々に侵食されて、分解されていくようなイメージのインスタレーション作品です。手編みしたニットモジュールを設営の時に編み足したり、色を混ぜたり、現場発生的につくっていきました。本展で空間構成を担当した『ドミノアーキテクツ』の大野友資さんが提示した地形のような什器に配しています。会場全体の他者の作品を読み取りながら作品をつくり上げる、環境を操作するような、庭をつくる感覚とも近いと思います」
毛足のあるこのニットは特殊なコットンの糸を用い、職人の手でいろいろな色や柄が編まれるといいます。

ニットモジュールには4つのサイズがあり、それらを組み合わせて構成する。

会場で作品を調整する吉本。
実はこのニットモジュール、巨大な什器を使った作品のみならず会場のさまざまなところに配され、会期中に増えたり減ったり、移動したりしているからおもしろい。
「一番目立つのは什器にあしらったものですが、どちらかというと、会場の隅にあるものが作品の本体だと思っています。実際に生えそうな場所を考えながら、ときどき会場に来て作業しています。会場全体に浸透していくようなイメージです」


「気配 – 覆い」は建物を侵蝕するかのように、さまざまなところに配される。
二つ目の作品は「気配 – 痕跡」。「気配 – 覆い」の脇、吉本が収集した古物を組み合わせてつくられた什器に掛かるジャケットです。これは先ほど紹介した「コレクション000」のもの。純天然染色を用い、ナチュラルなプロセスで染められているので、自然光に当たると色が変わり、ひとが着たり脱いだりしても擦れて表情が変わります。この作品はスタッフ用のユニフォームでもあり、会期中は彼らが着用します。

きれいに並ぶ姿はひとが整列しているかのよう。
「循環を自分のフィールドで捉えた時に服をリサイクル素材でつくるとか、そういうことも考えましたが、物質的な視点だけではなく、もっと違う循環があると思いました。そもそも服は新品の状態が最も価値が高くて、徐々に価値が下がると思われていますが、その考え自体を変える必要があるようにも感じています。色が変化するのは、最初の状態が最高とはいえなくて、その価値も変わるという考え方です。変化するのも価値の循環、これはそんな作品でもあります」

服のシームから出る糸。「気配 – 覆い」は建物だけでなく「気配 – 痕跡」をも侵蝕する。

生地に染料が入るとジャケットは自立するほどしっかりする。
実は1月18日(土)に行われる、この展覧会の関連プログラムを吉本が担当します。それはこの館の中庭に配した樹木の枯れ枝や落ち葉を使い、その場で彼が〈アマチ〉の服を染めるライブパフォーマンス「Records of Phenomena = 現象の記録」で、作品「気配 – 痕跡」と通じる内容です。来館者が持参する〈アマチ〉の服にも施すというから、体験したい方はぜひ参加を。


光のような、影のような模様はリアルなカモフラージュ柄だ。
そして、最後の作品はギャラリー奥の薄暗い部屋を使った「気配 – 存在」。ジャケットやパンツなど、服のかたちをしたものが工業用の分厚いフェルト生地でつくられています。それは柔らかい彫刻とも、硬い衣服ともいえるような、不思議な作品です。あるじ不在の姿はどこか抜け殻のようでもあります。
「循環を考えた時、分解されるプロセスを突き詰めていくと、いずれ自分自身も土に還るのだと思い出しました。本来、衣服はひとが着るものであり、誰かの気配をそこに感じますが、そのひとがいなくなった姿を作品にしました」

2024年秋冬のコレクションピースからパターンを取り、彫刻化している。

素材のフェルトは落ち綿を圧縮したもの。
以前から吉本は空間の最小単位が衣服で、逆にそれが大きくなると部屋や建物に発展するという考えを持ちます。
「衣服は着飾るとか、外に対しての記号的な意味を持つ側面もありますが、自分のなかでは最初の環境だと認識しています。ひとと外側を繋ぐための間にあるもの、それは建物も同じです」

「気配 – 存在」は全部で5作品。
インスタレーション、空間デザイン、そして服と空間の間にあるインテリア。いま吉本の視野はファッションを起点に少しずつ広がりはじめ、服よりもっと大きなものにも意識が向いています。
「この展覧会を含め、自分のなかで多方面に広がるものが、まだ個別に存在し、繋がり合っていません。これがひと繋ぎになると、それぞれを補完しあって、さらに深まっていくはず。この先、これらがすべて同時に見せられる空間というのは必要だと思っています。ブランドのよいところは社会性にあって、それがいろいろなものを取り込めるコミュニティというかハブになる。ファッションデザイナーを志したのもそれが理由です」
吉本にとっていまは中間地点。いずれ彼にも拠点を定める時期が来るはずで、そのために肌に合う土地を探していると言います。
「最終的にどの土地に自分がコミットするのか、ずっと考えていることでもあります。詩人のゲーリー・スナイダーは “場所の感覚” という言葉を使いながら、自分たちが人生のなかで他者と関係を築くように、どの土地と関係を結ぶのか重要だと説きます。それを彼は再定住とも呼びます。それは必然的に自分たちが開かれた空間を持ち、表現の場にするのとイコールだと思います」

ゲーリー・スナイダーの本は吉本のアトリエで。