That Way About Things
ハラダユウコ
Archive&Style Shop Press
1971年2月東京生まれ。アメリカ、ヨーロッパを中心に幅広いジャンルと年代からバイイングされたUSEDやデッドストックを扱う古着屋「アーカイブ&スタイル」のショッププレスとして、古物をこよなく愛する日々を送っています。
www.archiveandstyle.com
-

-

- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
-

-


Madras Check Items
2009.07.17
フイナムブログをご覧の皆様、こんにちは☆
今日は幾分、凌ぎやすいお天気ですね。
久しぶりの朝方の雨に、我が家のベランダ野菜たちも、ホッとしている感じでした。
今日は、この時期になると気になるので、
店頭にあるマドラスチェックアイテムを少しアップします。
そのついでに、
マドラスチェックの歴史を簡単に説明いたしますね☆
そもそも、マドラスチェックとは?
インドのマドラス地方で生まれた綿織物で、
グリーンや黄色、オレンジなどの鮮やかで多彩な
チェックの事を指します。
マドラス(チェンナイ)は南インドの東側にある、コロマンデル海岸沿いのベンガル湾に面する、
タミル・ナードゥ州の州都である港湾都市です。
古くから、南インドの商工業、文化の中心で,
かつてはイギリスの「東インド会社」の経営拠点でもありました。
1996年に現在のチェンナイと改名され、
現在でも、人口600万人のインドで第5番目に大きな都市として栄えています。
また、
「南アジアのデトロイト」や「インドの健康首都」など、
たくさんの異名がついている町でもあります。
マドラス・チェックの歴史は古く、
発祥は明確ではないものの、初めて歴史の表舞台に顕われたのは、
大航海時代より少し前の15世紀、1450年代です。
東ローマ帝国が滅亡して、
世界的な大航海時代が始まり、コロンヴスがアメリカ大陸を発見したのが、
たしか1492年ですよね?それより古くから文献などに登場しているそうです。
ちなみに、
私の大好きな日本史に照らし合わせると、室町時代ですね。
応仁の乱(1467)の頃と思うとマドラスチェックの歴史、古いですね~。
17世紀には
前出のイギリスの特許会社である「東インド会社」でも扱っていた貿易商品の一つでもあり、
同じ頃、17~18世紀にカリブ海を支配していた、
映画でも有名になったパイレーツ・カリビアン「カリブの海賊」たちも使用していたとの、
文献もあるそうです。
そうそう、大切な事を書き忘れていましたが、
本物のマドラスチェックは草木染によって染められていて、
草木染特有の「にじみ」の効果が特徴の織物の事を言います。
堅牢度が低いため、
洗濯でも柄がにじんでしまうのですが、本来は、
それを楽しむ織物でもあります。
発祥説は、仮説等々、いろいろあるのですが、
イギリス人が持ち込んだウール製のタータンチェックの文化が、
気候の暑いインドでは綿で作ることで変化し、
独自の柄や色で発展したのではないか?との見解が一番有力であるようです。
現在では、本来の草木染めではなく、
科学染料で染められたイミテーションがほとんどで、
多色、多彩で、多様な幅のチェック柄の綿織物を総称してマドラスチェックと指していると、
考えた方が妥当かもしれません。
マドラスチェックをモードとして、
最初に取り上げたのは、
先日もフイナムブログでご紹介させていただいた、
「ブルックス・ブラザーズ」です。
時は1920年代で、
日本では、大正新時代といわれた約90年も前の事ですが、
マドラスチェックの長い歴史を思うと意外に遅い感じがします。
ちなみに、私個人としては、
1950年代の映画「麗しのサブリナ」で、
オードリー・ヘップバーンがカシュクールの様に、
メンズのマドラスチェックのシャツを着ていたルックスが可愛くて印象に残っています。
アップさせていただいた商品以外も、
これからまだ入荷してきますので、
暑い夏にマドラスチェックで気分も明るく如何でしょうか?
ついでに、今朝のごまとむぎです。
むぎの肩にちょこんと置かれた、ごまの手がなんとも可愛くないですか?(笑)
ブログをご覧の皆様は、
明日から殆どの方が、久しぶりの3連休でしょうか?
今日は連休用にバイヤー堀江氏が新しい商品を、
後で倉庫から持ってきてくれるそうなので、
表参道までいらっしゃるご予定の方はアーカイブにも遊びに寄ってくださいませ~。
あ、ちなみにスペックスさんも、
塾長がアメリカから帰国して新アイテム揃っているらしいですよん☆
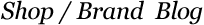









※コメントは承認されるまで公開されません。