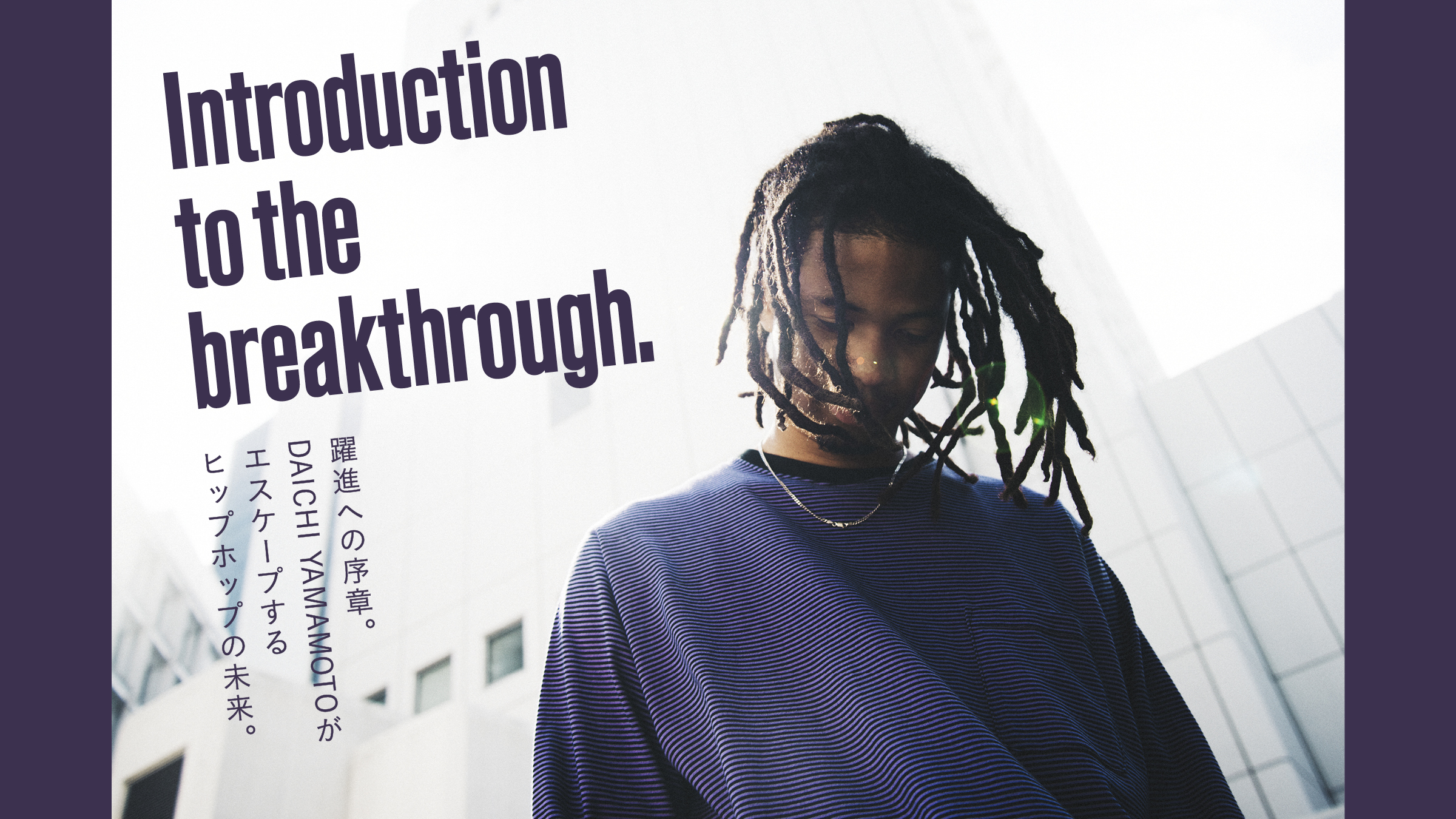自分の音楽に対するリアクションが欲しかった。
ー 大学では具体的にはどんなことを学びましたか?
DAICHI:初めは考え方の基礎を学びました。デザインやアートだけでなく表現の概念について学び、そこから自分は何をしたいかというのを探っていくような感じですね。そうした自由な学びを得られたからこそアートだけではなく、人によっては写真家になったり、映像ディレクターになったり、建築やファッションの道へ進む人もいたり。あるいは写真と建築を掛け合わせたりするような人もいました。ただ僕はというと、最初の二年間くらいはなかなかコレだ! っていうのものを決めきれずにいたんです。とはいえ焦る必要もないと思い、気分転換に学生時代から好きだった音楽を自分でも制作してみようと思ったんです。主にSoundCloudにまだ作品とも言えない完成度の音源、というか見よう見まねで作ったトラックやラップをただひたすらアップロードしていた感じです。あとは大学二年生の冬くらいから少しづつ音を使ったインタラクティブなインスタレーションの制作なんかも行うようになりました。
ー そこから少しづつプレイヤーとしての活動が始まっていくわけですね。ちなみにその頃にDAICHIくんが発表したSoundCloudでの音源が海を越え、ここ日本でも耳の肥えたリスナーや音楽関係者のもとに届き、密かな話題となりました。またSoundCloudを選んだのもデジタルネイティブなDAICHIくんの世代ならではだなとも思いましたが、その辺りはいかがですか?
DAICHI:はい、当時はイギリスでもSoundCloudが無名なアーティストが音源を発表するのに主流のサービスだったんですが、周りにヒップホップを好きな人がほとんどいなかったので、自分の音楽に対するリアクションが欲しかったっていうのが大きかったですね。それも友達ではなく、お世辞を言わない第三者の他人というのが僕にとっては大事だったんです。
ー 当時からビートメイクとラップは並行して行なっていたのですか?
DAICHI:そうですね。ラップの方がメインでしたけど、とにかく興味のあることはやってみようという気持ちでビートも独学で作っていました。そうした活動をしていくうちに、学校でも音楽とアートを結びつけるような取り組みを行うようになり、なんとなく自分のやりたいことが見えてきました。
ー その頃は、卒業後の進路に関するビジョンはあったのですか?
DAICHI:音楽系の制作プロダクションだったり、サウンドエンジニアの会社だったり、はたまた舞台芸術の会社に入ろうかな、なんて漠然と考えていました。アーティストとして活動したい気持ちもあったんですけど、何から始めたらいいかその時は分かりませんでした。その手掛かりを探すつもりで一度は就職を視野に入れていたんですけど、それもなかなか上手くいかなくて。それで就職活動と並行して、当時、自分の好きなアーティストだったjjjくんやOlive Oilさんなどのアーティストに直接コンタクトをとって音源を聴いてもらったりしていたんです。

ー 反応はどうでしたか?
DAICHI:まったく無名で異国の地にいる僕の音源を面白がってくれて、二人とも色々な人を紹介してくれました。音源をリリースしたいならレーベルの人を繋ぐよとか、似たような感性のアーティストを紹介するよ、とか。そうやって物事の歯車が動き始める感覚を肌で感じた時に、初めてもしかしたら音楽を生業にできるかもしれないって思いました。
ー それから2017年の秋に帰国し、京都に拠点を移すことになりますが、その時すでにJazzy Sportへの所属が決まっていたわけですが、そこにはどんな経緯やストーリーがあったのでしょうか?
DAICHI:何をきっかけに僕のことを知ってくれたのか定かではないんですが、就職活動に思いあぐねていた僕のもとに、いきなりJazzy SportでA&Rを担当しているマサトさんから連絡があったんです。『よかったら一度会えませんか?』って。それで僕がロンドンから帰国した当日に京都でマサトさんと会った時に、色々話して、帰り際に『いつかアルバムを一緒に出そう』って言ってくれたんです。もしかしたらjjjくんとか同時期に製作を進めていたOlive OilさんやKOJOEさんから話を聞いていたのかもしれないですけど、あの時は嬉しかったですね。
ー 日本での実績がほとんどない状況でJAZZY SPORTからオファーがあるのはすごいことですよね。それから正式にアーティストとしての活動がスタートしていった感じですか?
DAICHI:そうですね。まずはアルバムの制作に向けてリードシングルを作ったり、親交のあったAaron ChoulaiやThe Nostalgia Factoryとの楽曲を制作したりすることから始まりました。それまでは全部一人でやっていたことや遠隔でしかやり取りができなかった部分など、製作する上での環境の変化は大きかったですね。そしてなによりマサトさんが担当している5lackさんやKOJOEさんの音楽に対する姿勢を間近に観れたのは貴重な経験だったなと思います。みんなとにかくストイックで、音楽に対して真摯的なんですよね。