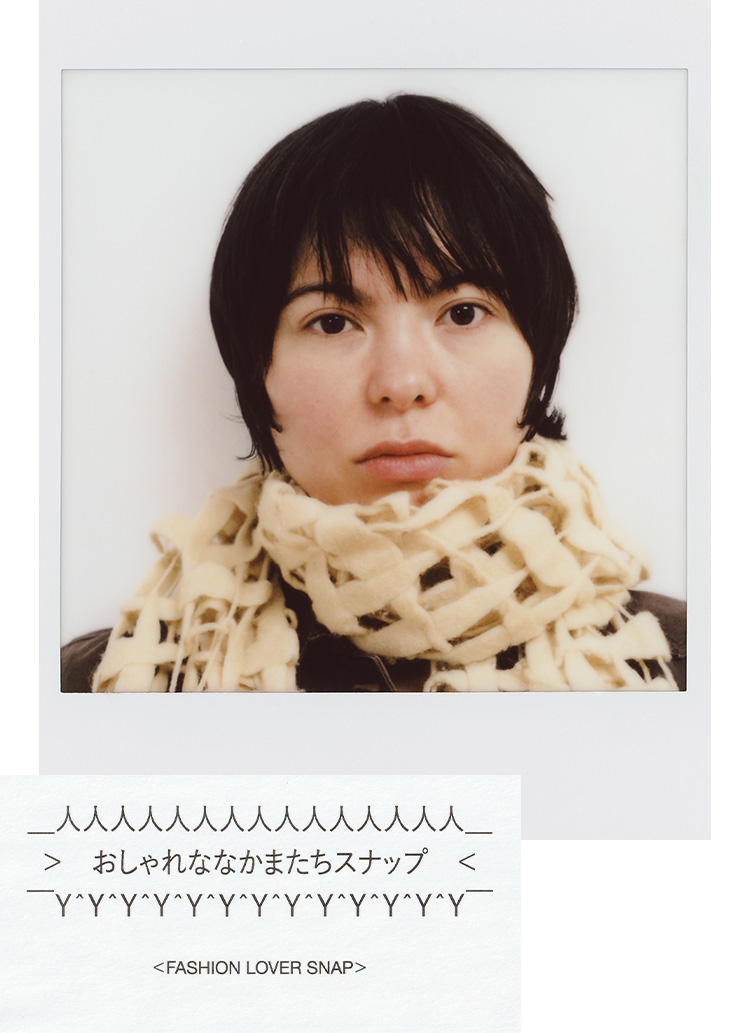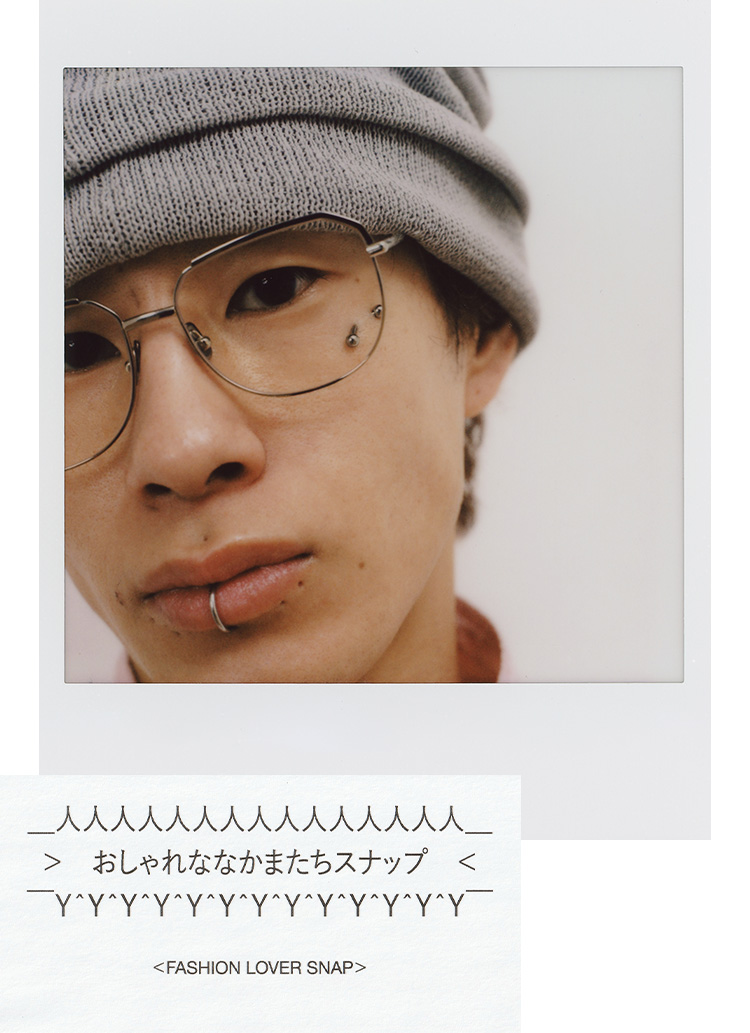文化を受け継ぐ、雑誌づくり。
ー 具体的には、どういうつくり方をしていますか?
井出:アートディレクターの仁木順平さんと僕とが中心となって、信頼しているエディター、ライターの方に協力していただきながら、今はすごく小規模にやっています。海外を拠点とするフリーランスのスタッフ、外国人のスタッフにも参加していただいています。
第2号では民藝運動の中心人物だった染色家・芹沢銈介の弟子である山内武志さんという浜松の型染めの作家さんなども紹介していますが、これは1年以上前から、取材や撮影をしていました。そういうふうに、じっくりと時間をかけ、何度も足を運んで記事にしているものもあります。

ー 分厚い紙を糸で縫った、仁木順平さんのデザインのディレクションも面白いですね。
井出:〈ビズビム〉のものづくりの特長でもある“糸から作る”というところから、ブランドのプロダクトで使っている天然染色の糸をヒントに、豪華本ではなくパラパラと気軽にめくって楽しめるような、雑誌らしい体裁ができないかと、特殊製本を専門に手掛ける〈篠原紙工〉に相談に行きました。普通はこれだけの厚さがあると一般的な製本の機械に通せないので、「中ミシン綴じ製本」は難しいんですが、これはアパレルの工場で使うような工業用ミシンを使って職人さんが1冊1冊、手で縫ってくれているんです。
だから、製本に時間も手間もかかって、校了してから本ができるまでもすごく長い。第1号は2,000部でしたが、第2号は4,000部刷っているので、まだ全部本ができていなくて、今も縫ってくださっている最中だと思います。でも、そういった職人の方のご協力があって、第1号はコチニール、第2号はクルミで染めた〈ビズビム〉オリジナルの糸を使う製本が実現できました。自分たちがいいと思うものを、そうしたさりげないところでも伝えられたらと思います。

ー B4サイズの大判にしたのは?
井出:今はスマホやPCで記事を読む時代ですが、小さな画面で写真を見ても正直、あまり心に響いてこないなあと感じることが多くて。大きな誌面のレイアウトで、迫力のある写真やイラストなどのビジュアル表現を楽しむ、ちょっと贅沢な気分になってもらえたら良いなと考えました。
あと世代のせいもあるかもしれませんが、僕はネットで文章を読んでいると、気になる言葉があるとそれを検索してしまったりして、気が散って、長い文章を集中して読むことが難しいんですよね。でも紙上でなら、読書に集中して、その世界に没入できるような気がします。
SNSに象徴されるような、「パッと見」「パッと聞き」のような、合理性を重視した短期的な情報のコミュニケーションが急激に増えているその一方で、それだけでは満足できない部分というのもあるのではないかと思います。ものごとを深く知ることや、メインストリームと異なる新しい視点に出会うことなどもそうかもしれません。
そうしたことを表現するには、紙の媒体の方が適していると感じています。単なるノスタルジーや復古ではなく、現代だからこそ、紙でしか味わえない雑誌の必要性や意義があると思って、雑誌を作っています。