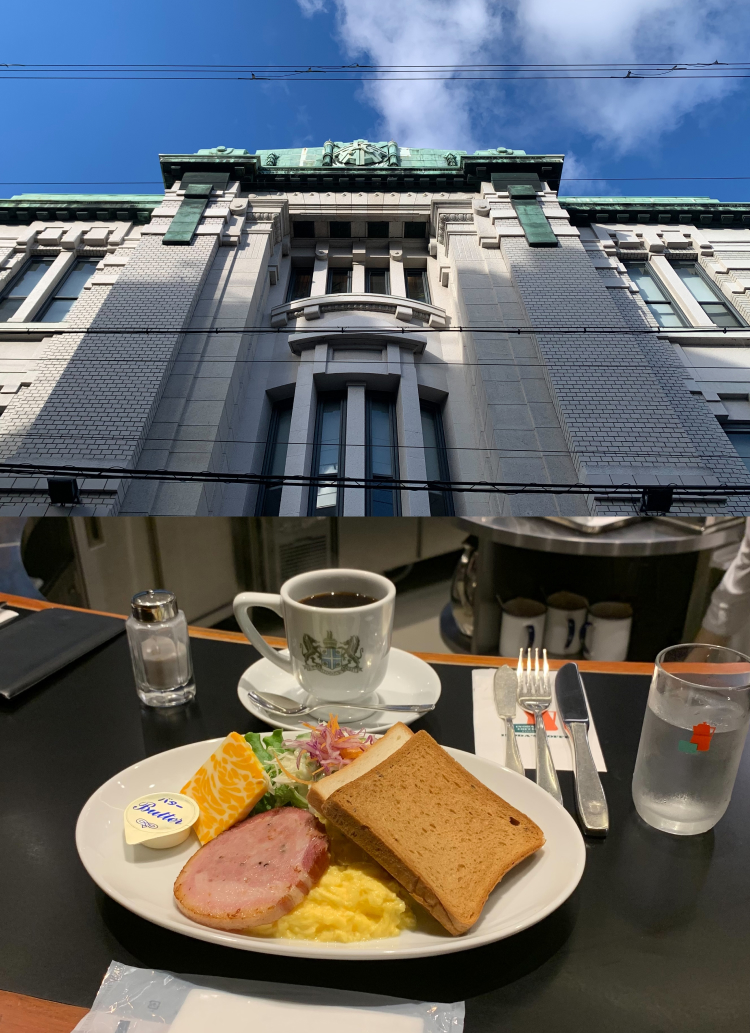濱口監督が心を奪われたショット。
濱口:監督の経験から始まっているということですが、一点だけ確認させてください。その家は高いところ——この映画のように坂の上にあったのでしょうか?
ポン:いいえ、そうではないんです。映画的、視覚的に設計するときに、“垂直的”に表現したいと思ったんですね。まるで、黒澤明監督の『天国と地獄』(1963)のように。『天国と地獄』の英語タイトルはまさにHigh and Lowですね。最初からそのような配置・構えにしたいと思いながら、2013年にアイデアを構想して以降、ずっと頭の中で考え続けていました。最終的な『パラサイト』のストラクチャーが組み立てられたのは、2017年の秋ごろから冬にかけての4カ月間、ひとりでキーボードを叩きながらシナリオ作業をしていたときでしたね。


ー 『パラサイト』は半地下の家族と坂の上の裕福な家族という、対照的な位置関係が描かれている映画ですね。
濱口:僕はもともと、ポン・ジュノ監督の映画の中では“高低差”というものがよく描かれると——垂直的な関係に強くこだわる監督でいらっしゃるという印象を抱いていたんです。その主題が『パラサイト』で完全に結晶化した、と感じます。
ポン:なぜ自分がそこまでこだわるのかは自分ではわからないですね。この映画では半地下の家を描いていますが、中学生のとき友だちに誘われて、暗い部屋に置かれた卓球台で遊んだことがあります。その記憶は強烈に残っていますね。照明が少し当たっていて、卓球のタンタンタン……という音だけが響いている。そうした場所で卓球をしている光景というのは、少しおかしな感じがします。
濱口:ええ、その光景を映画化したいぐらいです。
ポン:妙な臭いもこもっていたし、中の上ぐらいの暮らしをしている人たちが捨てた家具などを、警備員や掃除のおばさんが拾ってきて、そこで休憩をとっていた。湿った空間に高級家具が置かれ、そこで人々が横になっている……とても奇妙でもありましたし、階級そのものを表しているような感じもしました。

濱口:やはりそうした感覚が『パラサイト』に結実したのだ、ということが改めてハッキリとわかりました。垂直的な関係については、心から感動したショットがあります。坂の上の豪邸から雨の中、半地下の家族が自分たちの家へ向かって、住宅街の階段をくだっていく。それに合わせて、下降のクレーンショットを撮っていらっしゃいますね。
僕はこれほどまでに、カメラワークという「形式」と「主題」が完全に一致した瞬間を見たことがないような気がしていて、本当に素晴らしいショットだと思いました。そうした空間全体をつくるだけでも大変なことだと思うのですが、あのショットはどうやって構想し、実現に至ったのでしょうか。
ポン:ありがとうございます。そのショットだけではなく、雨が降っていく中で移動していくあのシークエンスというのはとても重要で、映画はあそこからロードムービーとなっていくんですね。裕福な家の街から貧しい街並みへの移動、あるいはパク(IT会社)社長の家から自分の半地下の家までのロードムービー。台詞はほとんどないのですが、果てしなく思われるようなこのふたつの家の距離を観客に体験してもらうための重要なシーンでした。
降りていく階段の一つひとつのロケーションは、実は全部違います。こちらの街中でワンカット撮って、今度はソウルの真逆に移動してワンカット撮って……というように、点々と散らばった場所をつないでいるものなんです。そんなふうに、とてもこだわってロケーションを選んでいきました。おっしゃっていただいたカットはソウルの非常に古い住宅街にあります。あの場所を見つけたときは、とても嬉しかったですね。
階段によって、垂直的な空間というものが描かれているわけですけれども、息子が一度、足を止めますよね。その足の隙間から、雨水が滝や洪水のごとく、上から下へと流れていく。まるで裕福な家から、貧しい家へと流れていくように。反対方向に流れていくということはありません。それは何か哀しくもあり、凄まじいことでもあると、撮りながら感じていました。
『寝ても覚めても』でも、防波堤の上にカメラが上がっていくと、海が広がっているというシーンがありましたね。あれは本当に、圧倒的な水の存在感というものを感じました。
濱口:嬉しいです、ありがとうございます。

ー 『寝ても覚めても』の後半に出てくるシーンですね。
ポン:島に住んでいる人々、悲劇的な災害を経験した人々——こうした日本の方々が持つ集団的な無意識を強打するようなシーンだったのではないかというふうに、僕は自分勝手にも思ってしまいましたが……あのシーンの曇った天気というものは、濱口監督が待ち望んでいたものだったのでしょうか。
濱口:我々の制作体制はそんなに余裕があるものではなくて、この日に撮るとなったら撮らなければならない環境でつくっています。本当は当初、脚本を書いているときは、このシーンは晴れていてほしい気がしていました。主人公の朝子、彼女の心情を考えると、晴れ渡っていてもいいんじゃないかと思っていたのですが、当日は曇っていました。
ただ実際に撮ってみて、「ああ、こういうことなのかもしれないな」と思ったんです。彼女をとりまく出来事は何も解決していないのだから、彼女が見るものはこういうものでなくてはいけない——この光景ぐらい激しいものが、今後も彼女を待っている、そういうことなのかもしれないな、と教えられるような経験でした。
ポン:僕は結果的に撮られたものしかわからないですが、あの場面を観たときに、天気も非常にいいと感じましたし、女性のクローズアップも素晴らしいと思いました。海以上に、人物の顔からすごいものが伝わってきたんです。あのシーンを撮ることができるということは、濱口監督の性格がすごく執拗にこだわる、しつこいタイプだからだと思うのですが(笑)。
濱口:そうですか、どうなんでしょう……(笑)。