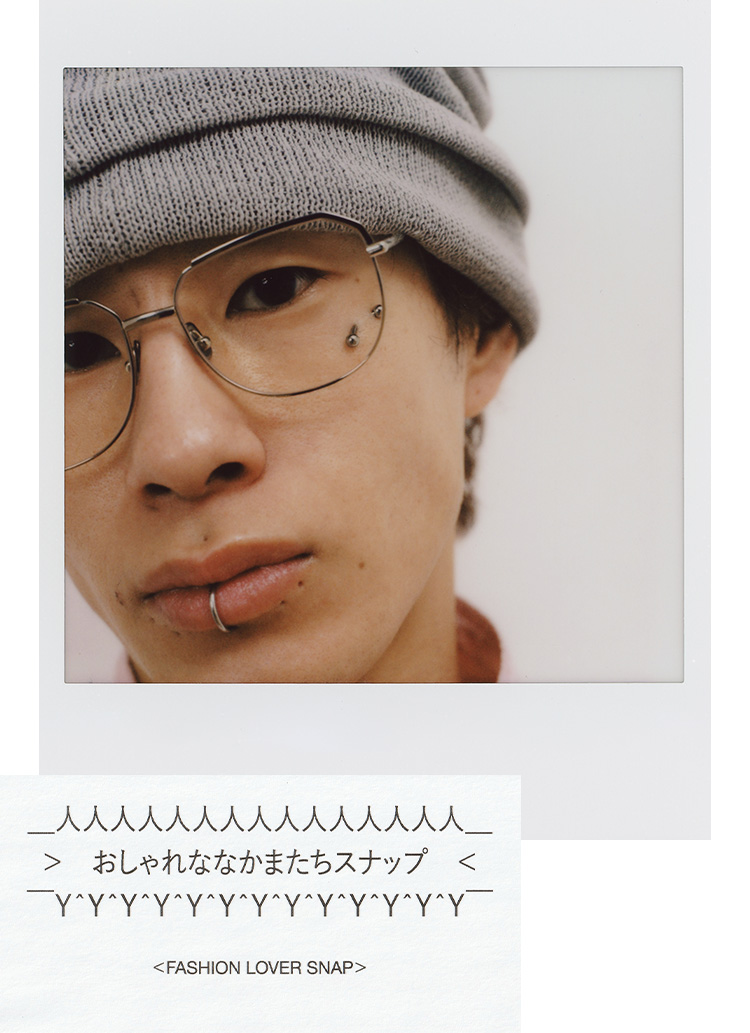パンクとは羞恥心を抜きにして、いきなり表舞台に立つということ。
ー 今回は無観客での開催で、ライブ配信という形で披露されました。
末安:無観客は初めてだったんですけど、やってることはお客さんがいてもいなくても変わらないんです。裏で着せつけをずっとしてたから。だから本番の映像も見てないし、正直わからないというのがいまの感想ですね。



ー 最後のクライマックスも含めて、とても素晴らしい演出でした。ロンドンのパンクからインスピレーションを受けたコレクションと、切腹ピストルズの和のコントラストもいい意味での違和感がありました。
KIDILL 2020AW COLLECTION
末安:精神がパンクで繋がっていれば絶対に合うと思ったんです。和だろうが洋だろうがそこはもう関係ないなって。
ー おふたりが抱くパンクの精神はどういったものなのでしょうか?
末安:ぼくは音楽ではなく服なんですが、自分の目指していることを曲げずにやりきることを心がけてます。まぁ好きなものをデザインしているので曲げる必要もなければ、流行にとらわれることもないんですが。自分の価値観を信じて、それをやりきるのが自分のパンクかな。ベニオくんはどう?
飯田:俺は喋ると長くなりますよ。
一同:笑

飯田:ただまぁ、俺は服じゃないので。もちろんパンクで人生変わったんだけど。じゃあいまなんでこんな格好して和楽器演奏しているかっていうと、いろいろあるんですけど。羞恥心抜きにやっちゃうってことがパンクなのかなぁと。
ー それはどういうことですか?
飯田:昨日まで全然関係ないことをしてたやつが羞恥心を抜きにしていきなり表舞台に立って、なんかやっちゃうとか。それがパンクの面白さだと思ってて。とくに音楽ってそういう素人のパワーがすごく発揮されやすい。誰かに教わったとか、勉強したとか、そういうのでもなく、演者を見る側だった子たちがいきなり始めちゃう。なんの作法もないまま、「それやっちゃマズいでしょ」って言われても関係ない。そうした表現には稚拙なものがあれば、一方ではすっごい面白いものも襲ってくるんです。それがパンクだと思ってて。

飯田:和楽器って江戸時代くらいまでは好きなように演奏してよかったんです。それが明治維新からちゃんとした文化として世界に発信しようという動きが活発になって、格式化されてしまった。だからいま和太鼓って聞くと、アスリートみたいな体つきの人がやってるイメージありますよね。和太鼓の会に入って、ちゃんと習わないとできないみたいな。でも、俺たちはそれをすっ飛ばしてやっちゃった。あんまり上手く演奏すると格式的になるから、どれだけ適当にやるかっていうのが本当の心情だったりします。結局、やりたいことを続けるってことは、周りへの羞恥心とかもなく、好きなことを突き詰めることなのかなと。
ー 初期衝動をどれだけキープできるか、ということですね。
飯田:そうですね。人目を気にせずに、やりたいからやるっていう。邪魔を蹴散らす。
末安:ぼくもその価値観には賛成だな。イギリスで服をつくりはじめたときは専門学校なんて行ってないし、縫い方もわからないけど始めたんですよ。
飯田:勝手に始めたんでしょ? だからそういうことだよね。
末安:フリーマーケットで買ってきた100円のセーターをハサミで切ってみたり、それを燃やしたり、ペイントしたりしてて。そのとき思いつくことをすべてやるみたいな。それを実際に売るってことは、素人が殴り込みにいくような感じですよね。だからベニオくんの言ってることはすごくわかる。でも、ぼくはいますごく上手になっちゃってるんですよ、パリにまで行ってるし(笑)。でも忘れちゃいけないものってある。それだけは頑なに守りながらやっていますね。