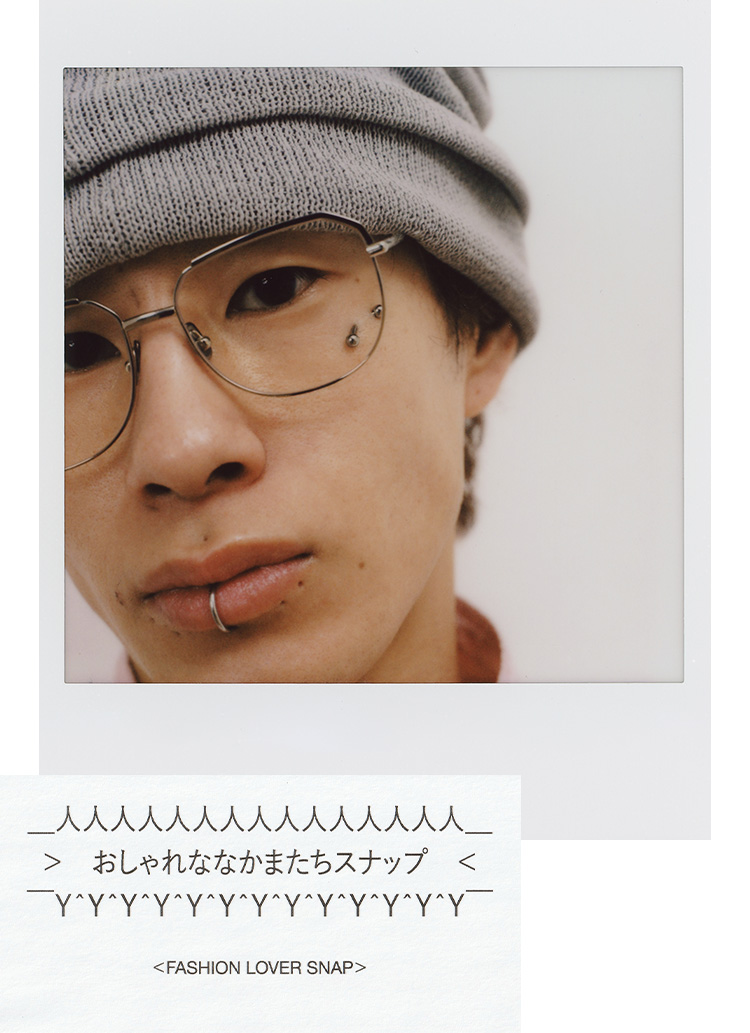土着的なものを守ろうとするのが反体制的なこと。
ー そうしたマインドを持ったブランドがパリでショーをやるのが痛快ですね。
末安:がんばります。今回のショーもリハーサルの段階で鳥肌が立ちました。ライブハウスで見るのとはまた違った雰囲気があって。
飯田:ジェイミー・リードまで揃えててさ。そりゃあ気合も入るでしょう。ヒロくんらしさやパンクの要素がきちんと混ざってて、すごい進化してると思ったよ。


飯田:パンクって言ってるんだったら、それこそピストルズとか70年代の音楽をかけとけばいいじゃないですか。それでも絶対成立するし、コントロールもラクなはず。でもそれを選ばずに、いくら俺たちが切腹ピストルズだからって、下駄や草履履いてるんですよ? なのに、「それがいい、一緒にやろう」って言ってくれるってところに、ヒロくんの人となりが表れてますよね。
末安:いくらパンクといえど、懐古的なことをやってもしょうがないと思うんだよね。自分の世代の新しいパンクをつくっていかないといけない。そうなると周りの協力も必要で、ジェイミー・リードはぼくのヒーローのひとりだからずっとやってみたかったし、ベニオくんも一緒。あとは、ニットブランドの〈ルルムウ(縷縷夢兎)〉の佳苗ちゃんも同じ意志を持ってる仲間。パリのシューズブランドの〈ボス(both)〉も同じ意識を持ってる仲間です。20AWでは、この2ブランドとコラボレーションを行なってます。
ー 今回のショーは末安さんがいま仰った新しい価値観が生まれていたように思います。切腹ピストルズにしても、決してメインストリームの存在じゃないですよね。つまりは、パンクという共通言語を大事にしているのがよく見えたというか。
飯田:そこがヒロくんの面白いところですよね。
末安:ぼくは濃く、鋭くやるっていうことを決めていて。パリコレもそうだし、今回のショーもそうです。薄めたくないんですよ。濃ければ濃いほどいいっていう思想になっているので、そういう人たちとやりたいって常日頃から思ってるんですよ。

ー そういう意味では、飯田さんは普段から野良着を着て生活してますよね。それってすごく濃いことだと思うんです。そうした人たちの演奏と〈キディル〉の服の共演というのは、なにか共通したものを感じます。
飯田:おもしろい話があるんですよ。マルコム・マクラーレンか、ジェイミー・リードが言ったのか忘れちゃったんですけど、進化の中にはいい進化があれば、「あれ? そっちに進化するの?」みたいな必要のない進化もある、と。それで今回、ヒロくんは〈エドウィン〉と一緒に取り組みをしてるんでしょ? なんか環境的なことで。
末安:使わなくなったインディゴの排水の体制を整えて、きちんと環境に負荷をかけない方法で生産をしてるね。
飯田:いままではそうした部分をテクノロジーで隠そうとしてたでしょう。けど、進化をするには土着的な要素がすごく大事なんだけど、その過程で新しいものがその上に乗っかろうとしてくるんだよね。その土着的なものを守ろうとするのが反体制だっていうのをマルコム・マクラーレンとかあの辺の人たちが言っていたのを覚えている。
ー なるほど。
飯田:マルコム・マクラーレンはテディボーイズを復活させるとか、着るなら本物を着るべきだってテディボーイズたちのシャツをつくったりとか、その余った生地でアナーキーシャツが生まれたりとか、とにかく伝統を守りながら新しいものをつくるっていう発言をしたことがあるんです。
俺たちが着ている野良着も超土着的なものなわけです。一方でタータンチェックやボンテージパンツって、もともとは民族衣裳としてのルーツがある。そういうことを考えると、たしかにマルコム・マクラーレンとかヴィヴィアン・ウェストウッドとか、彼らのやってた〈ワールズエンド〉もそうだけど、単なるSF的な進化じゃなくて土着的な進化を感じますよね。

飯田:土着的なことって自然とか環境とか、土地にも関わってきます。ヒロくんが〈エドウィン〉と一緒にやってることも、まさに土着的なことなんだよね。
末安:ジェイミー・リードとコラボするときに、「俺はいま環境破壊とか森林伐採とか、そういうことに興味がある。それに対してお前はなにができるんだ?」って言われたんだよね。それですごい考えて、調べて、結果的に〈エドウィン〉との取り組みに行き着いて。「自分たちはインディゴを海に流さない方法でやる」っていうことを話したら、すごいよろこんでくれて「じゃあ一緒にやろう」って言ってくれたんだよね。そこから意気投合できた。
飯田:それ最高です。
末安:ベニオくんの話を聞いて、点と点が線で繋がった感覚があるね。
飯田:パンクの思想を持った人たちのなかでそういう思想があるのかもしれないよね。