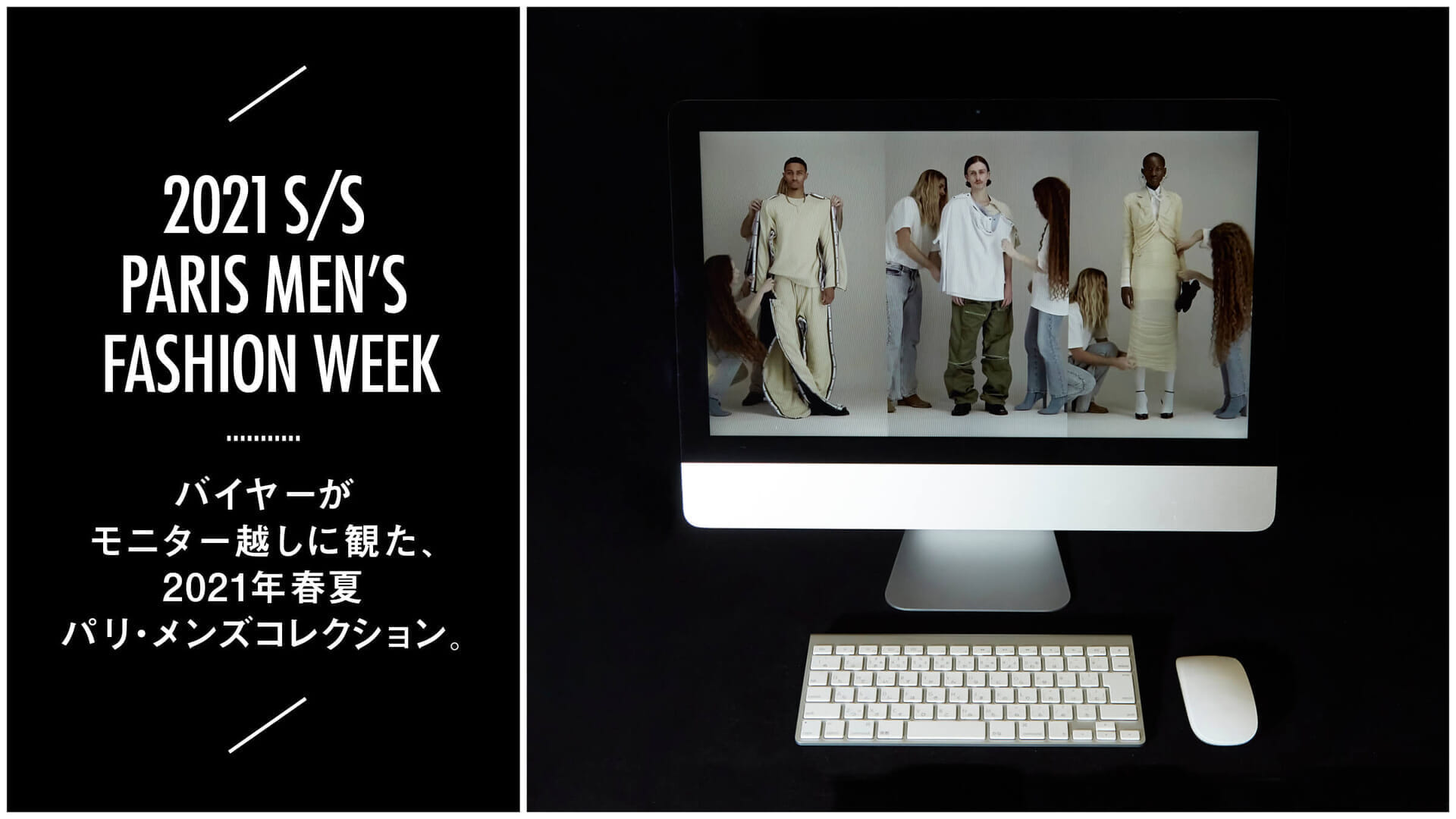BUYER 02 表現の先に、シーズンの服が見えてくることが重要。
PROFILE

「インターナショナルギャラリー ビームス」メンズディレクター。1971年生まれ。大学時代からアルバイトとして「ビームス 銀座」に勤務し、卒業後入社。「インターナショナルギャラリー ビームス」で2006年からメンズ部門のバイヤーを担当し、14年から現職。
www.beams.co.jp/international_gallery_beams
ー パリ・メンズの映像作品のなかで、印象深いブランドを教えてください。
〈ワイ・プロジェクト〉の映像は、内容や構成において非常に斬新でしたね。私たちバイヤーは、ショーなどを通してブランドのムードや雰囲気を感じつつ、服のディテールや素材などをしっかりと目に留めなくてはいけないという役割を持っています。その上で、ものを仕入れていくというのが仕事。モデルが立て続けに着替えていく、ある種の “デモンストレーション” の方法をとった〈ワイ・プロジェクト〉の表現は、受け手側がトランスフォームする服をディテールのレベルまでしっかりと理解できるという点で、一方通行なプレゼンになっていないのが良かったです。
どんどんスタイリングが変わっていき、複雑な服を「どのように着ることができるか」を分かりやすく示す方法をとった〈ワイ・プロジェクト〉。
〈コモン スウェーデン〉は、純粋に、普段ショーを観ている感覚を思い起こさせてくれました。席に座った我々が、どういう目線で服を見ているのかを汲み取っていて、それがカメラワークに現れていましたね。シンプルかつストレートに、服を見て欲しいという意図が感じられました。3つ目は、クリス・ヴァン・アッシュの〈ベルルッティ〉です。アーティストのブライアン・ロシュフォールとコラボレーションして服をつくっていく過程が垣間見えました。ランウェーショーだけでは伝わらない “裏側” をドキュメンタリー的に捉えていて、まさにデジタルだからこそ表現できるプレゼンテーションだったと思います。また、パリではありませんが、〈プラダ〉の作品も非常に興味深かったです。
稲穂に囲まれたランウェーをモデルがウォーキングする〈コモン スウェーデン〉。モデルの正面、サイド、背面に加え、袖や首元といったディテールにフォーカスするなど、細かくカット割りされている。
〈ベルルッティ〉は、クリス・ヴァン・アッシュとコラボレーターであるブライアン・ロシュフォールのインタビューで構成。それぞれのアトリエが映るドキュメンタリー風の映像だった。
〈プラダ〉は、タイプの異なる5人のクリエイターがそれぞれ違う表現方法で多面的に見せた。「今回のコレクションは、90年代後半のムードがあり個人的に懐かしさも感じていたのですが、特に写真家のマルティーヌ・シムズ(チャプター4)が、90年代を彷彿とさせる少々粗々しいデジタルとアナログのミックス的な表現方法を選び、服そのものと非常にうまく結び付けているのが素晴らしかったですね」と服部さん。
ー デジタルファッションウィーク全体に対する見解があれば聞かせて下さい。
服よりもムードを重視する傾向が強く、ショーやコレクションの要素をしっかりと満たしているブランドは残念ながら非常に少なかったと思います。バイヤーやディレクターの立場からいうと、展示会やショールームを含めたファッションウィークの主旨を考えても、当然、服をしっかりと見せなくては互いに商売にならない。さまざまな表現方法があること自体は良いのですが、その先に、シーズンの服が見えてくることの重要性に改めて気付きました。
ー サンプルを直接見ることのできない状況ですが。
一番の難点は実際に着ることができないので、バランスや着心地、素材の雰囲気、ウエイトといった部分を正確に把握できないことですね。一方で、実際にショールームでサンプルを見ることのできるものはオーダーが増えると思います。
ー 具体的にはどのようなブランドでしょうか?
たとえば、ドメスティックブランド。このような情勢ですから、個人の消費自体は萎んでいく傾向にあります。国内ブランドの単価が高くないもの、納期の問題を掴みきれない海外ブランドとは違って、その辺りを把握することができるメリットは大きいですね。
ー ディレクションにも関わってくるかと思いますが、エンドユーザーが服を選ぶ傾向に変化を感じていることはありますか?
もともと「インターナショナルギャラリー ビームス」のディビジョンでは、TPOに合わせた服の買い方をする人が非常に多いんです。自分の周囲にある社会で、自身をどう表現したいかを考え、その目的や基準に沿った服への需要が常にありました。今後、そうした側面はより強くなっていくのではないかと思っています。たとえば、オンライン上のコミュニケーションが主流になると、いわゆるビジネスの場が移っていく。我々のような職業はまだしも、金融やコンサルといったTシャツ一枚でクライアントと話をすることのできないビジネスマンを中心に、オンラインの “場” に合わせたファッションとコミュニティができ、そこで必要とされるものが選ばれていくのではないでしょうか。
ー 現在形で起こっている、生活や行動の変化と密接なのですね。
かなり強く捉えていますね。PCを使いながら動きにくいジャケットは絶対に着ませんよね。当然、画面に映る姿は上半身だけなので、ボトムスはオンオフ兼用できるものが求められていくかもしれない。在宅ワークが一週間の半分を占めるようになれば、ドレスシューズを履く機会そのものが減り、そうした靴が駄目になるスピードも遅くなりますから、そんなに揃える必要はない。そうしたこととは別軸で、自己表現をしたい方々のなかには実際に着てみて購入される方々も変わらずいらっしゃる。アイテム単位での需要の高まりを踏まえつつ、ターゲットを絞りながらのセグメントが顕著になっていくと考えています。