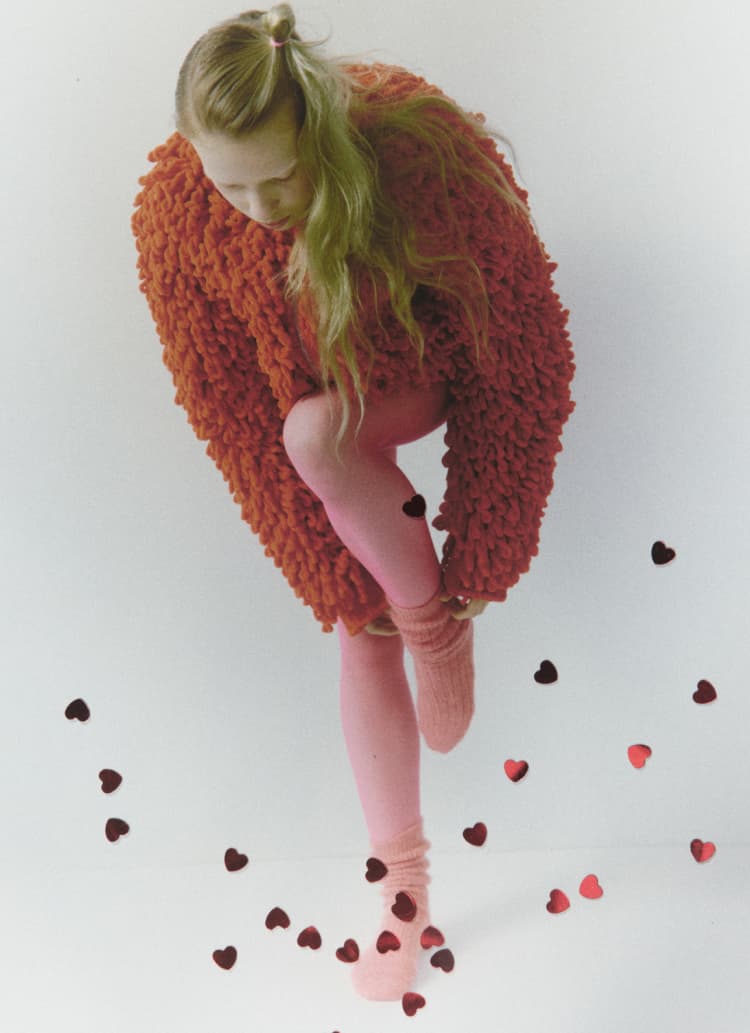名品と呼ばれる革靴は、接着剤をあまり使っていない。
ー 〈レッド・ウィング〉はもともとお好きだったんですか?
太田:高校生のときに古着屋でワークブーツを買ってから履いています。履いていても、修理していても思うんですが、〈レッド・ウィング〉のブーツはすごく丈夫だし、修理という行為に対してすごくエフォートレスなんですよ。
ー それはつまり、修理を繰り返しながら長く履くことを前提につくられているということですか?

太田:そう思えるほどに修理がしやすいです。そのひとつの要因として挙げられるのが、接着剤の使用が少ないということ。ぼくが思うに、それはいい靴の条件でもあります。名品と呼ばれる革靴やブーツのほとんどは、接着剤をあまり使っていないんです。
ー 縫製でパーツ同士をくっつけていると。
太田:そうです。だから糸を解けばパーツが取れます。接着剤は剥がすときに上手に剥がさないと、無駄な力がかかってパーツが破損してしまう可能性があるんです。でも〈レッド・ウィング〉の場合は一部の工程を除いて、そのほとんどが縫製でつくられています。だからすごく修理がしやすい。変な話、ある程度の技術しかない職人でもきれいに仕上げられるんです。細かな話をすると、縫製のピッチも程よいんですよ。
ー ピッチというのは、間隔のことですか?

太田:そうですね。間隔が細かすぎてもよくないし、逆に開きすぎてもよくない。どちらも糸やレザーが切れやすくなってしまいます。〈レッド・ウィング〉のブーツは、箇所によって適正な縫製がされているんです。
たとえばカカトの部分は比較的細かな縫製がされています。ここはよく擦れる部分なので、糸がほつれやすいんです。でも、間隔が開きすぎると糸の露出する面積が多くなってしまうので、より摩擦が多くなってしまう。だから他の部分よりは細かめなんです。
ー どうして細かすぎるのはよくないんですか?
太田:修理の際はもともとあったミシン穴を目で追って、そこに合わせて手でミシンを操作しながら縫い直していきます。これが細かすぎると本当に慎重にやらないといけなくて、万が一ズレてしまうと、新たなミシン穴が空いてしまい、生地がもろくなってしまうんです。
ー 生地の引き裂きが起きやすくなるわけですね。
太田:そうです。だから細かすぎると処理が大変で、熟練の技術が必要になります。だけど〈レッド・ウィング〉は、細かな部分でも間隔がちょうどよくて、ミシン穴を追いやすい。だから技術のある修理工なら誰でも直せてしまうんです。それってすごいことだと思うんですよ。クオリティがきちんと担保できるということですから。
ー 縫製に使用するミシンは特殊なものなんですか?


太田:靴修理にはこの「HAPPOミシン」を使用するのが一般的です。これはその名の通り、四方八方に縫えるのが特徴。針がついたアタッチメント部分が360度回転するので、通常のミシンだと縫いにくい部分でもこれなら縫いやすいんですよ。
ー 先ほど話されていた、縫製間隔の開いている部分というのは、ヴァンプとシャフトの結合部分のことですか?

太田:そうですね。比較的間隔が空いていて、表面積が広め。だけど、トリプルステッチになっていて強めに補強されています。それにラテックスというワックスのような溶剤を染み込ませた糸を使っていて、より頑丈に縫製がされているんです。だからここがほつれた靴っていうのは、ぼくの修理人生を振り返ってもほとんどありませんでした。