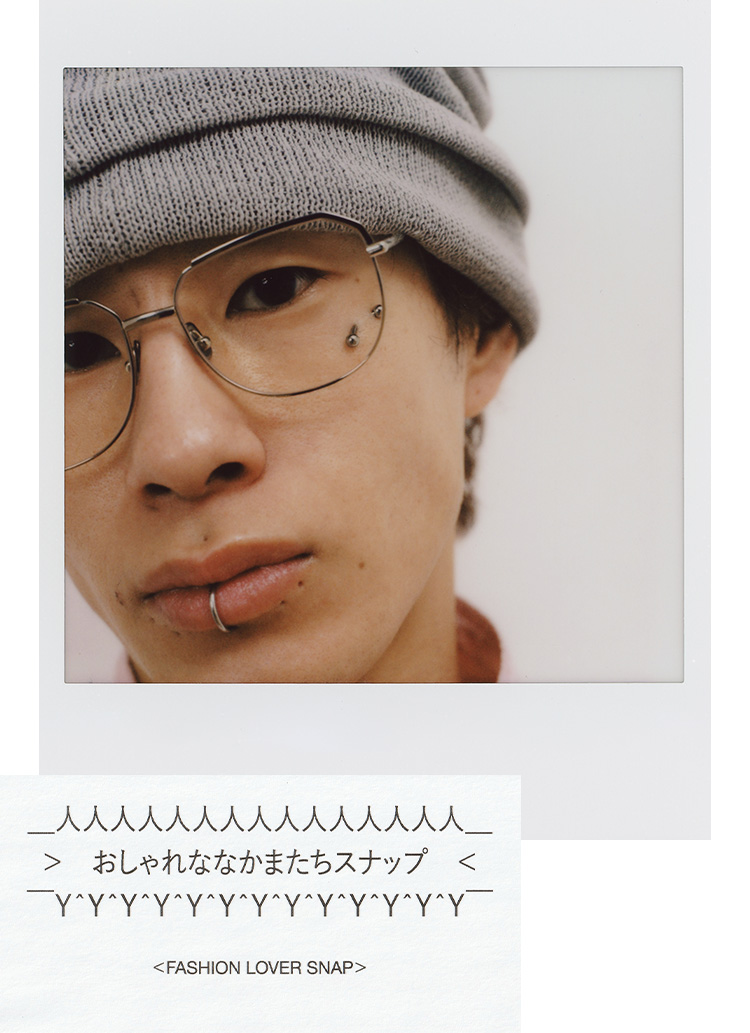サ活 2022の振り返りとサウナの未来を考える。
ー これまで数多くのサウナを訪れたと思いますが、今年のサ活で印象的だったエピソードはありますか?

ちょっと前にドイツ、フィンランド、ラトビア、オーストリアなど6ヵ国40サウナを回ったんですが、なかでも衝撃的だったのが、オランダで行われたアウフグースの世界大会。会場にサウナが20箇所ほどあって、音楽フェスみたいに「この時間はこのサウナでこの演劇があります」っていうタイムスケジュールがあるんです。そのひとつのアウフグースがとにかくスゴくて。年齢も国籍もバラバラの参加者が40人ほど集まったんですけど、そのセッションが45分間とめちゃくちゃ長かった。これ、いつ終わるんだろう? みたいな(笑)。
そこで特徴的だったのは、サウナ室のドアを開けて、温度を一旦下げること。ある程度下がったら、ドアを閉めて、ロウリュをして、温度を段階的に上げていく。上がり過ぎたらもう一度ドアを開けて温度を下げて…、といった具合に、DJがテンポをアップダウンさせる感じでストーリーをつくっていくんですよね。そうして体や精神をコントロールし、最終的にサウナを出たところで小花を渡されて、40人が2列になって湖まで歩き、全員で手を繋いで湖に潜るというスピリチュアルな儀式で終わります。そうすると、そこに一緒にいたひとたちを、人種や国籍も超えた家族のような存在に感じられるんです。
ー 聞いているだけでもピースな気分になりますね。
もちろんソロで入るのもいいと思うんですけど、何かを超えて同じ体験を分かち合うというか、そういう精神面に訴えかけるサウナは日本には少ないなと。日本でメジャーな、交感神経をドーンと上げて、それを水風呂でガーンと下げる行為は、例えるならショック療法みたいなもの。でも、世界にはいろんなサウナの楽しみ方があります。それを国内の建築家やデザイナーたちが経験して、日本に持ち帰ってくれば、また面白いサウナが生まれるはず。ぼくと親方は、コロナ前に行けたから先にインプットができたんですけど。
ー サウナはこれから、ますます多様化する可能性があるというわけですね。そして、“ととのう”だけがすべてではないと。

“ととのう”というのは、あくまでメソッドでありゴール。そこを目安にみんながサウナを楽しむようになったのが、ここ3〜4年のことです。サウナはこれから、いろいろなライフスタイルに浸透していって、生活のなかでもっと身近な存在になっていくでしょう。歯磨きするのと変わらない感覚。サウナ付きの賃貸も増えていくと思いますし、当たり前のように日常に落とし込まれていき、いつかはフィンランドみたいになってもおかしくないんです。
ー 明るいサウナの未来ですね。
一方で、そこじゃないと体験できないような、いわゆるオンリーワンのサウナも需要が高まっていくと思います。例えば、知床や屋久島といった秘境にあるサウナや、無人島の満天の星空の下で外気浴ができるサウナだったり。そういう非日常と、先ほど言った日常の二極化になるんじゃないですかね。
ー なるほど。一方で、サウナシーンの現状に感じる課題はありますか?
女性や子供が入れる施設がまだまだ少ないことですね。うちの子は7歳なんですけど、2歳からサウナに入っていて、水風呂に浸かっていると「やっぱりサウナはいいよね。この前ドッジボールで負けたこととか全部忘れられるもん」なんて言うんです(笑)。でも、子供が良さをわかるということは、そのコンテンツに何かしらの魅力があるということ。子供はそういうものに敏感ですし。2歳の頃からサウナに入るような子もどんどん増えていく気がします。そういうひとたちが世界を見つつ、日本のサウナを研究していったら、スゴイことになるんじゃないかなと。
ー サウナの英才教育ですね(笑)。
もっと壮大なことを言うと、いつかは、子供たちのなりたい職業に、プロサウナーが挙げられるようにしたい。それも、Youtuberを越えて。そういう点では、サウナがカッコいいとか、イケけてるとか、モテるとか、成功して儲かるとか、そういう次元に持っていかないとダメ。そうじゃないと、希望を持たせられないので。そのためにもぼくは、サウナの仕事が素晴らしい仕事だと思ってもらえるように動いていきたいんですよね。