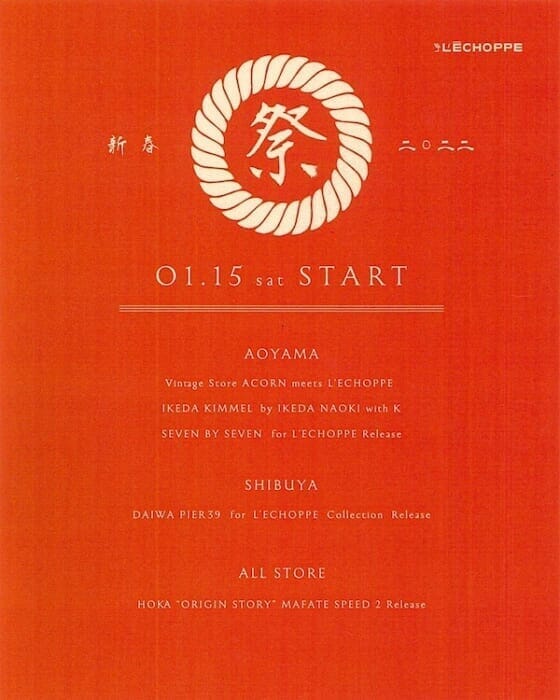PROFILE
1978年生まれ、新潟県出身。高校を卒業し、19歳で渡米。その後数年を過ごした西海岸で古着の面白さに夢中に。2013年にサンフランシスコの愛称を冠したショップ「7×7」を渋谷でスタートし、そこでつくったオリジナルプロダクトが、現在の〈セブン バイ セブン〉のルーツになっている。
伝えるって難しいんですよ。
―まずは初めてのランウェイ、お疲れ様でした。終えてみて、手応えはどうですか?
川上:ありがとうございます。やってよかったなと思ってます。いまできること、ひらめいたことを淡々とやって、それを見せられればいいのかなと思いながらやりました。先輩方からも「思ってたよりもすごい上品だった」とか、褒めてもらえましたね(笑)。
―このタイミングでショー形式の発表にいたったのは何かきっかけがあったんですか?
―ブランドとして刺激を加えたい、みたいな感覚があったんでしょうか?
川上:そうですね。あとはブランドの見え方が固まってきてる感じがしていたので、ランウェイを通して間近で観てもらえたら、もっとちゃんと伝わるのかなとか、いろいろと考えた結果です。


―“固まってきた見え方”というのは具体的にはどんなものですか?
川上:「〈セブン バイ セブン〉=リメイクデニムだ」とか、そういうことですね。本当に伝わってないんですよ。デニムやブルーのイメージが強くて、自分たちが変えていってることとかを伝えるというのは難しいんだなと。展示会を見てくれていても、やっぱり。
―部外者が言及しにくいことですけど、それもブランドのひとつの現実なんだろうなと感じます。
川上:でもまぁ、ショーをやるんだったらウチっぽくやんなきゃ意味ないなっていうのはずっと考えてました。別に他に合わせる必要もないし、ショーだから何かすごいことをやってやろうとか、そういうワケでもないよなと。〈セブン バイ セブン〉を初めて見てくれる人も多いだろうから、昔からやってることももう一回見せるとか、ブランドのアイデンティティをしっかり見せるっていうところにフォーカスして。
―“ウチっぽいショー”についても聞かせてください。
川上:なんだろう。お客さんにちゃんと服が見えるようにしたかった、とかかな。
―そう言えば、ランウェイとフロントロウがかなり近かったですよね。
川上:はい。それはもう最初から狙ってて。やっぱり生地感とか、ウチがやってることをちょっとでもわかってもらいたかったし、どストレートにやりたかったというか。ベタベタでいいかなとも思ってました。演出はもちろんしてるんですけど、それをしすぎないように。今回は演出家の金子繁孝さんに協力していただいたんですけど、自分の意図をすぐに汲み取ってくださって、シンプルに強くしてもらえたなと思ってます。
―楽天ファッション・ウィークではあの時期にいくつもショーが行われましたけど、それが結果的に〈セブン バイ セブン〉のランウェイを印象的にしたんじゃないでしょうか?
川上:他のブランドさんがいろんな表現をやると思うので、それとの差別化でもないけどやっぱりブランドらしさをストレートに見せればいいんじゃないかなとは思ってました。みんな同じような所に向かってたら、おもしろくないじゃないですか。今回のランウェイも基本的に偶然の部分が大きくて。これまでの縁とか、このタイミングで出会う人とかがだんだん繋がってきて、それがおもしろいと思ってます。
―ここまで聞いていて、川上さんはもちろん今回の一番の当事者のはずですけど、ちょっと客観視してるようにも思えますね。
川上:いざショーが始まっちゃったら、超他人事でしたね(笑)。「よし、行ってこーい!」みたいな。俯瞰しているというか不思議な感覚で、緊張も何もなかったです。スタイリングもあれだけの体数を組んでますけど、最初から見えてるものはもう見えてて、あとは締まりをどうするかっていう感じでした。