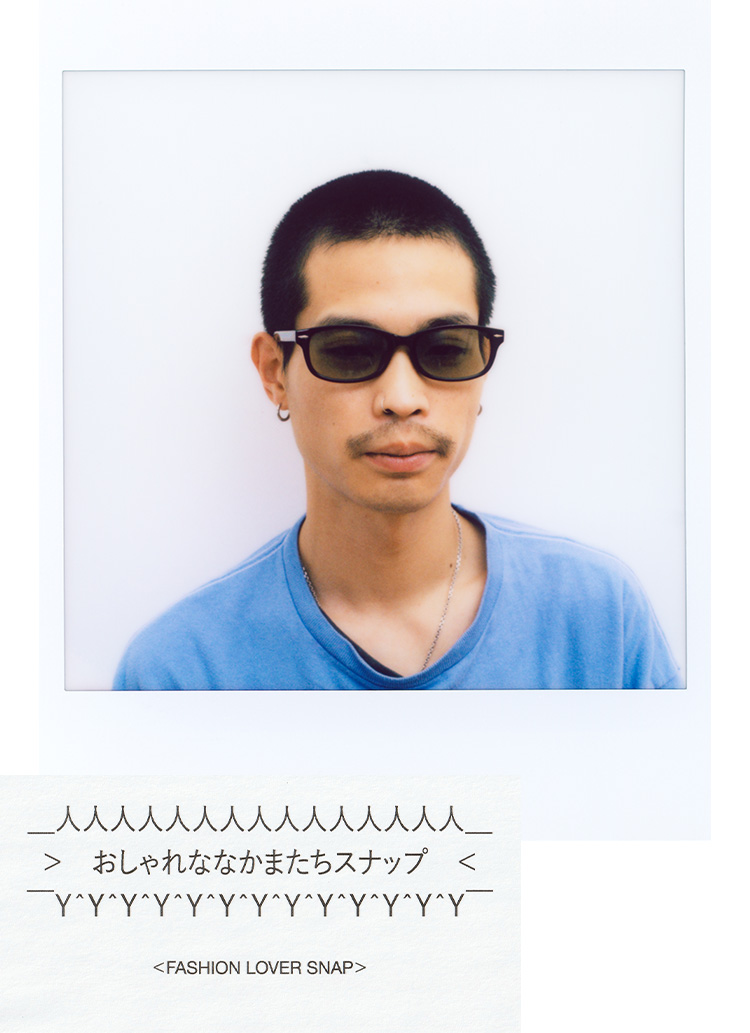1300年前から存在する
奄美の伝統工芸、大島紬泥染め。


東京から飛行機で約2時間の距離にある奄美大島。島内にはマングローブの原生林があるなど、豊かな自然の景色が見どころ。
暖かく穏やかな気候、力強く生い茂る草木、そして美しい海に囲まれる鹿児島県の最南端、奄美大島。その豊かな自然と南国特有のスロウな空気が心身をリラックスさせ、足取りを軽快にしてくれます。

「肥後染色」の裏には山があり、近くに川が流れるなど、泥染めをするのに最適な場所に工房を構えている。
空港付近にはのどかな景色が広がり、高い建物がないせいか、空に浮かぶ雲に手が届きそうな錯覚を起こさせます。奄美大島に到着したあと、その足で向かったのは、島の北部に位置する龍郷町。この町にある「肥後染色」という泥染めの工房が目的地です。

大島紬は絹糸の状態から泥染めを行う。写真の通り、何十回も染め工程を繰り返した上で美しい黒色が出る。
今回〈ワーク ノット ワーク〉がスポットを当てた泥染めはこの島に伝わる伝統工芸で、世界三大織物のひとつとして知られる大島紬の美しい茶褐色も、この泥染めの色なのです。発祥がいつ頃なのか、詳しいところはわかっていないそうですが、大島紬はすくなくとも1300年前から存在していたのだとか。それから現在に至るまで、世代が受け継がれ、伝統を継承してきたわけです。

国家資格である伝統工芸士の資格も保有している親方。多くを語らず、黙々と作業を行う職人気質な人物。
「ここがはじまったのは昭和48年から。うちの親父が10年近くやってて、あとは私たち兄弟で受け継いだんです」
そう語るのはこの工房の親方である肥後英機さん。現在「肥後染色」は、英機さんと弟の純一さん、そして娘婿である山元隆広さんの3名で運営されています。工房では大島紬の染色に加え、さまざまなアパレルメーカーからの受注の仕事、そして観光客を招いた泥染め体験が実施されています。

英機さんの弟である純一さんも工房に立つ。みんなからは「純アニ」の相性で親しまれていた。気さくで明るい性格の持ち主。

こちらが大島紬に使われる絹糸。基準に満たない色に染まった場合は、すべての工程が無に帰してしまうため、丁寧な仕事が要求される。
「奄美で大島紬の生産が盛んだったときは、島の中にも工房が80軒近くはあったんじゃないかな。だけど、だんだんそれだけでは食べていけんくなって、いまじゃ本格的に泥染めをしているのはうちともう数件だけ。それでも今回の取り組みのように、アパレルブランドと手を取り合ってやっていかな難しいんですよ」
語るのは簡単なことかもしれませんが、大島紬のためだけに使用してきた歴史ある伝統技術を別の衣類に応用するというのは、きっと大きな決断だったのではないかと思います。とはいえ、そうした軌道修正があったからこそ、身近に泥染め楽しめるようになったともいえます。

取材に同行してくれた〈ワーク ノット ワーク〉の吉田さん。
MDとしてブランドの舵取りを行う。今回は泥染めの体験もしていた。
〈ワーク ノット ワーク〉が泥染めの商品をつくることになったのは今回がはじめて。「単純にその色に惹かれたんです」と教えてくれたのは、ブランドのMDである吉田さんでした。
「とあるメーカーさんからこの『肥後染色』さんを紹介してもらって、先シーズンに藍染めの商品をつくったんです。そしたら『じつは泥染めもできるんですよ』ということで、サンプルをあげてもらったらすごい仕上がりがよくて。それでブランドのディレクターと話しながら、泥染めの商品をつくることを決めました」