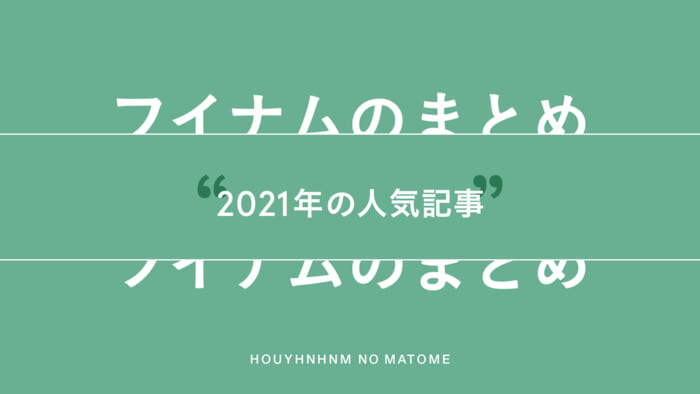PROFILE

1977年生まれ。2001年 N.Yより〈ネクサスセブン〉を始動。2020年11月にリニューアルオープンした「渋谷PARCO」にて新店をオープン。去る1月には『NEXUSVII.×GREGORY EXLUSIVELY FOR URBAN RESEARCH』が大きな話題となった。
PROFILE

1977年生まれ。2011年よりフリーバイヤーとしての活動を開始。古着屋のみならず数々のセレクトショップやブランドからも絶大な信頼を集める日本屈指のヴィンテージバイヤー。奥渋谷には自身のショップ「ミスタークリーン」も展開中。
PROFILE

1977年生まれ。L.A.発のデニムブランド〈ヤヌーク(YANUK)〉のアドバイザーとしても知られ、近年のGジャンブームの集大成とも言える『Levi’s VINTAGE DENIM JACKETS Type l/Type ll/Typel lll』の監修人でもある。
PROFILE

1976年生まれ。これまで編集・ライターとしてメンズファッション誌に携わり、多くの古着関連の記事を扱ってきた有識者。現在はアパレルメーカー「ワールド」にて、EC関連や社内報、イベント企画などを担当。ヴィンテージバンダナのコレクターとしても知られる。
ヴィンテージラバーも納得のデニム生地をアッパーに採用した、スペシャルなジャックパーセルが完成!

今回の別注ベースに選ばれた「ジャックパーセル」は、アメリカのバドミントンプレイヤー、ジョン・エドワード・ジャック・パーセルのシグネチャーモデルとして1935年に登場し、“青ヒゲ”の愛称でも知られるロングセラーモデル。当初は〈A.G.スポルディング&ブロス〉社が開発製造に携わり、その後OEMを請け負っていた〈B.F.グッドリッチ〉社へと版権が移り、1972年に同社を傘下に収めた〈コンバース〉社に全権が譲渡されました。さらに〈ネクサスセブン〉の今野さんが指揮を振るい、国内の有識者たちによって開発された話題の国産デニム〈ビヨンデックス(BEYONDEXX)〉をフィーチャーと、やはり一筋縄にはいきません。世紀をまたぐロングセラーモデル「ジャックパーセル」を、なぜ4賢者はベースモデルにセレクトし、どんなこだわりを持って本企画に望んだのか? 今回もまた深堀りさせていただきます。

ー 前回はいわゆる“珍バース”からのセレクトでしたが、第2弾は王道モデルというのが何より驚きでした。
今野:じつは1年半ほど前から水面下で動いていたのですが、当初はモデルの選定よりもまず生地選びからはじめました。以前から(藤原)裕くんとは「デニムベースでやってみたい」と話していて。
藤原:はい。今日はクリくん(栗原)に持ってきてもらいましたが、80年代にリリースされた「オールスター」のデニム仕様を以前からずっと探していて。マイサイズがなかなか出てこなかったのもあり、デニムでやってみたいと。

栗原さん私物のデニム製「オールスター」。オレンジのステッチやレザーのシューレースなど特筆すべきディテールが満載。80年代製。

こちらも同じく栗原さん私物の「オールスター HI」。ホワイトデニムをアッパーに採用した珍しい一足。アメリカ製。
今野:モデルの選定はやっぱりクリくんの存在が大きかったですね。世界でも有数の「ジャックパーセル」コレクターですし。
栗原:前回の別注では色々と無理を聞いてもらえましたが、逆にどのモデルでもできるとなったら、やっぱりぼく的には「ジャックパーセル」かなと。

〈B.F.グッドリッジ〉時代の大変貴重な60年代製ジャックパーセル。アッパーとソールのつなぎ目のサイドテープがネイビーに配色されているのが特徴。
阿部:クリくんは、なんでそんなに「ジャックパーセル」が好きなの?
栗原:20歳くらいの時、周りの先輩や友人は〈コンバース〉では「オールスター」を履いている人が多くて。一方でぼくは天の邪鬼な性格もあって「ジャックパーセル」を集めはじめたのがきっかけです。それにその頃はアイビーっぽいスタイルが好きで、それにはまるところもありまして。
阿部:そうだったね(笑)
藤原:くわえて世界的にも「ジャックパーセル」への再評価が高まっているという点も大きかったと思いますね。
栗原:そうだね。


ー アッパーに〈ビヨンデックス〉を採用した経緯をお聞かせください。
栗原:これまでもいろんなブランドからデニム素材のスニーカーがリリースされていましたが、それらに使用されたデニムは少なくともぼくらのような古着好きが履きたいと思うようなものではなかったと思うんです。
阿部:確かにそれはあるね。かといって当時の〈コンバース〉のデニム製スニーカーの仕様をそのまま復刻するのなら、ボクらが別注をかける意味がないワケで。だからこその〈ビヨンデックス〉だったと。

今野:そもそも〈ビヨンデックス〉の開発にはぼくのほかに裕くん、さらに裕くんにお声がけいただいた識者の方々が関わっていて。生地の開発には都合5〜6年ほど費やしていると思います。
阿部:当初から大戦モデルに使われた生地を再現しようとスタートしたプロジェクトなの?
今野:はい。相当数のダブルエックスデニムを見てきましたが、やっぱり大戦中のモノは明らかに迫力が違うんですよね。他のダブルエックス生地とは明確に異なる力強さがあるというか。
阿部:実際、織りが違うとか、オンスが高いとか、糸が違うとか、わかる範囲の差異ってあるの?
今野:国内の各社が大戦モデルの再現にトライしていますが、あくまで個人的な見識だと、完璧と思うものはなく単にオンスを高めたり、縦畝が強めに出るよう工夫しているものが多い中、実際の大戦生地ではそういった仕様になってないんですね。
阿部:そうなんだ?

第二次世界大戦当時のデニム生地の色落ち部分をよく見みると、所々に点状に色落ちした跡が見える。
今野:はい。本来は“点落ち”や“短落ち”と呼ばれる部分的に点状や短い縦落ちするデニム地が使われていて。
栗原:わかりやすく線状の色落ちにはならないってことですね。
今野:そう、もちろん縦落ちはするんだけどね。だから糸の素材となる綿花や形状からじつは開発していて。それにデニム生地自体もいわゆる加工用に使用するモノとは変えて、今回はデニムスニーカー特有の変なシワ跡が先に際立ちすぎない様にじっくり育てていただいて魅力的な色落ちをゆっくり楽しめるよう調整しながら開発しました。
阿部:オンスとかも違うの?
今野:ですね。そこは細かくは言わず(笑)