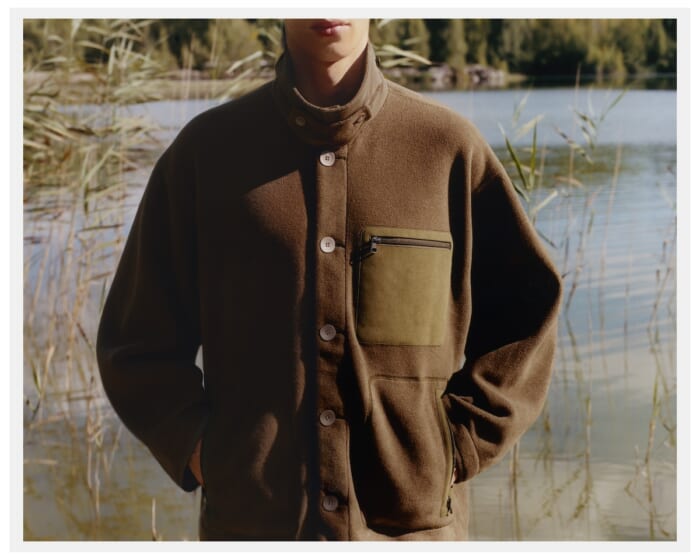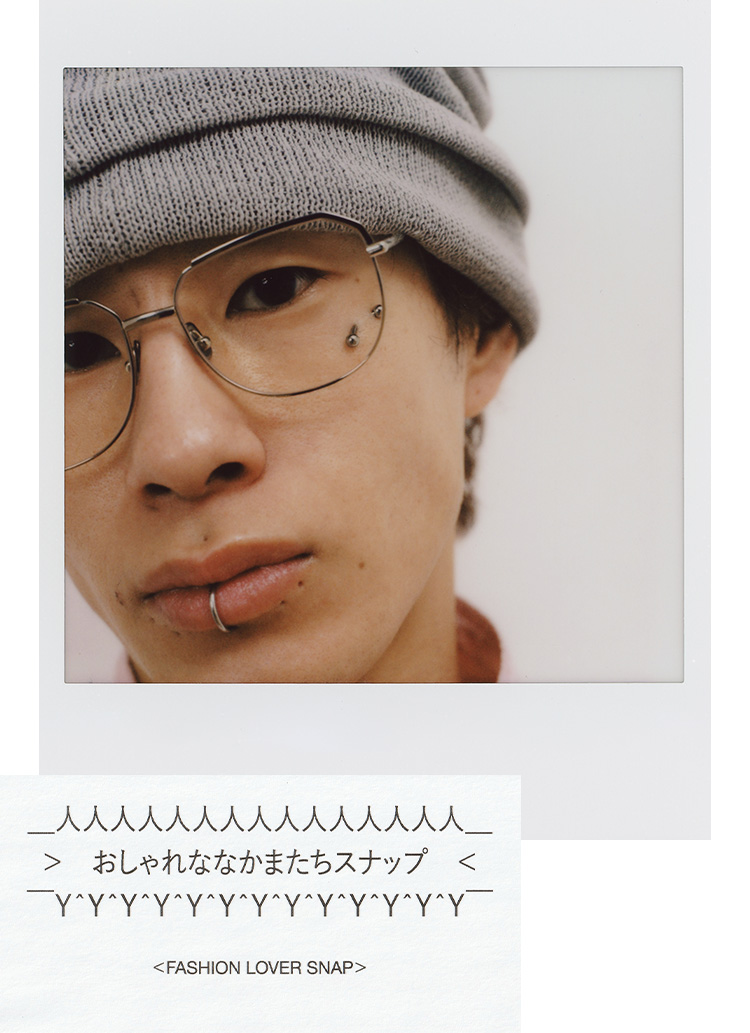日本のアウトドアファッションを牽引する存在といえば「ゴールドウイン(Goldwin)」です。〈ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)〉や〈ヘリーハンセン(HELLY HANSEN)〉など、多数のブランドを抱えるこの企業が、創業の地である富山でコト事業をはじめるとか。新たにつくる施設「Play Earth Park Naturing Forest」にキャンプや農体験、スポーツアクティビティなど、自然から学ぶさまざまな企画を用意します。今年4月、このプレスカンファレンスが行われ、「ゴールドウイン」の渡辺貴生社長を中心とするプロジェクトメンバーがそれぞれの想いを語りました。
Edit_Tsuji, Ryo Muramatsu
山林と、そして水、自然を大切にする心が宿る町。
「ゴールドウイン」渡辺貴生社長
「ひとと自然の可能性を広げるには、私たち人間が持つテクノロジーである想像力を使い、ひとと自然を共によりよくするためのイノベーションを想像して、実行することが有用です」
プレスカンファレンスは渡辺社長のスピーチからはじまりました。モニターにはクロード・モネの「ポプラ並木のあるアルジャントゥイユの野原」が映し出され、この作品のように「ひとと自然が共にある美しい時間、風景をつくっていきたい」「100年以上の時間を超えて、人々の好奇心を刺激できる場所をデザインしたいと考え、スタートしました」とプロジェクトの構想を説明します。
富山県南砺市長、田中幹夫さん
続いて登壇したのは富山県南砺市長の田中幹夫さん。南砺市に広がる自然の豊かさ、そこで育まれる人々の生活や文化について、力を込めて語る姿が印象的でした。
「南砺市は670平方キロメートルありますが、上流は白山から水が流れ、それが一旦、桜ヶ池というところに溜まります。そこからまた砺波平野に流れ、400平方メートルくらいの田畑をその水で耕す。そんな場所が開業予定地の桜ヶ池という場所です」
プレスカンファレンスの会場には桜ヶ池の間伐材でつくった演出が。
南砺市は山からの水が平野を潤し、自然とひとの営みが交差する場所。市域の8割が山林で、市長自ら「山林と、そして水、自然を大切にする心が宿る町」だと話します。
「高野ランドスケーププランニング」村田修一さん
そして、開発地に選ばれた桜ヶ池について「北側は砺波平野が広がり、反対を向くと自然の山並みが見える場所に位置し、人々の営みと自然の接点がある場所になる」と話すのは、施設全体をプロデュースする「高野ランドスケーププランニング」の村田修一さんです。
開業予定地は「大きな水面と、起伏がある山と森、そして田んぼ、畑があります」と言うように、さまざまな自然環境が入り混じる場所です。尾根や谷がある複雑な地形だからこそ、光や風の当たり方も場所によってまるで違う「そんな多様性が、この原郷のような土地の魅力」だと話します。
「Play Earth Park Naturing Forest」の全体イメージ。
印象的だったのは「四方どこを向いても美しい景色が広がる」と語っていたこと。それを活かして「この場所をめぐるだけでも地球と遊んでいる、そんな感覚が生まれるランドスケープを目指していきます」と言って村田さんは話を締めました。
イギリス人ガーデンデザイナーのダン・ピアソンさん
ガーデンデザイナーとして名を馳せるダン・ピアソンさんは、ガーデンの設計を担当。
「ガーデンは、ひとと自然がつながる特別な空間であり、生き物や季節の流れ、自分たちの存在を感じさせてくれる場所」と語ります。
今回の計画では「自然が入り込める場所へと土地を変え、訪れる人々も自然の一部と感じられるようにしたい」とし、日本文化に根づく季節の移ろい「七十二候」にも触れ、「5日ごとに訪れる自然の小さな変化を感じ取れる場所を随所に設けます」と説明。自然が持つダイナミズムと、ひとの手による細やかな設計を重ね、新たな風景をつくることを約束しました。
五感を使って自然を満喫し、新たな気づきを得る場所。
ここで気になるのは「Play Earth Park Naturing Forest」にできる建物やその機能です。約40ヘクタールの敷地には、キャンプ場や地形を活かした遊び場、自然観察の塔、森の中のコテージ、池に囲まれたヴィラ、地元住民とのつながりを生むアクティビティセンターを設けるといいます。さらに農、食、宿泊、アクティビティが連動し、訪れる人々の想像力と好奇心を刺激する、記憶に残る体験を提供するというから、かつてない取り組みです。プレスカンファレンスには、それらを担う設計者たちも集まりました。
南砺市の散居村からインスピレーションを得たというヴィラは、夕日や星空、雨など、時間ごとの美しい自然の表情を眺め、花々や虫、鳥の声に耳を傾ける時間が楽しめる空間です。
これを担当したのは、小田原にある「江之浦測候所」を手がけたことでも知られる「新素材研究所」の榊田倫之さん。「ヴィラ」は「自分がどの場所に存在しているかということを、建築がひとつの装置になって体験できるように考えました」と言うように、太陽の動きも感じられるように方角まで意識して設計されます。
榊田さんは「自分の存在を意識しながら、同時に感じることのできる建築をつくっていきたい」と語ります。
施設の中心にくる、螺旋階段を備えた展望台には、各方角に自然観察できるスペースを設けます。この最上階では砺波平野を一望でき、地下階では土中の根や虫の様子をガラス越しに観察できるようになるとか。そして、周りの森につくられるコテージに滞在しながら自然と触れ合えます。
これらの設計を手がけたのは、「大阪・関西万博」の「バーレーンパビリオン」も担当したリナ・ゴットメさん。「一本の木のようでもあり、木材のリズムが生命のサイクルを想起させます」と言う展望台と、「木の実に棲むことをテーマに、自然の造形美を体験できる空間」のコテージが訪れるひとたちの憩いの場になります。
「子どもの野性の解放」をテーマにしたのが、パークエリアの遊び場です。洞窟へ迷い込んだり、岩山を登ったり、子どもたちが地形と会話をするように、自然と遊びが生まれるようにデザインされます。
ここを担ったのは、東日本大震災の復興プロジェクト「石巻の東屋」を手掛けた萬代基介さんです。「いわゆる遊び場の施設のようにはしたくない」という考えのもと、「雨や落ち葉が建物内に入り込むことも遊びにつながるようにしたい」と言い、自然と連続した体験を生むつくりを目指すと意気込みを語りました。
イギリスの建築集団「Assemble」が担当したのは、キャンプサイトです。ここでは富山に根付く農業や工芸、自然との関わり方を学ぶ、新しいキャンプ体験を提供します。
ここはかつて水田だった地形を利用。いくつか設けるキャンプサイトごとに違う植物を育て、農業や工芸の知識も得られるようになるとか。地域の木材や粘土、籾殻、釉薬などを使った建築により、自然と地域文化が融合するようなキャンプ体験ができるというから気になります。
「Assemble」のメンバーのひとり、マリア・リソゴルスカヤさんはこのように説明します。「自然の中での建築は、ただ存在するのではなく、動き、移動し、料理するといった行為全体を含みます。植物を育て、それを使って何かをつくるようなワークショップにもつながる場を考えました」
続いて紹介するのは、パークとガーデンをつなぐプラザ棟です。ここは施設の玄関口になり、自然の中で遊ぶためのウェアやギア、南砺の食文化を扱うショップを併設します。
担当した川島範久さんは、自然との共存を重視して「既存の樹木を傷つけないように配置しました。光や風、雨を受け入れるつくりになっています」と教えてくれました。
最小限の素材で最大限の効果を引き出す構造のプラザ棟の建物は、世界で最も厳しいとされる持続可能な建築の認証プログラム「リビング・ビルディング・チャレンジ」の日本初の取得を目指しているのも注目すべきポイントです。
「本瀬齋田建築設計事務所」齋田武亨さんと本瀬あゆみさん
アウトドア遊びの拠点となる、アクティビティセンターは桜ヶ池の水辺に建てられる予定です。アウトドアショップやカフェベーカリーが隣接し、池につながるデッキからアクティビティを楽しめます。さらには地域の人々が日常的に池に訪れ、遊びや体験をとおして地域の自然への理解が深められる機会もつくるといいます。
この場所は富山を拠点に活動する「本瀬齋田建築設計事務所」の本瀬あゆみさんと齋田武亨さんが担当。「ネイチャリングのエリートである南砺市民の場所としても機能すると素敵だと思います」と締め括り、地域とのつながりを大切にしている姿勢を印象づけました。
たくさんのプランが計画されている「Play Earth Park Naturing Forest」はいよいよ今年5月から造成工事がスタートし、今秋には建築工事もはじまる予定です。これだけいろいろな話を聞くと、2027年初夏の開業がより楽しみになってきます。
自然との共生を目指す「ゴールドウイン」の新たなコト事業は、ぼくらにどんな遊びと学びを与えてくれるのか。その動向をフイナムでは追いかけていきたいと思っています。