Boolog A Go-Go!
石光 史明
VISUAL CONNEXION C.E.O
NY発のヴィジュアル誌、VISIONAIRE<ヴィジョネアー>の日本総代理店を営んでいますが、最近はもっぱら映画鑑賞家として「つぶやいて」います。昨年は自腹観賞232本! 今年も観まくるぞぉ~♪
visualconnexion.com
-

- ART [25]
- BBB9700 [6]
- Dying to eat [30]
- Gadget [36]
- Misc. [206]
- Movie '10 01-03 [35]
- Movie '10 04-06 [59]
- Movie '10 07-09 [62]
- Movie '10 10-12 [61]
- Movie '10 Misc. [6]
- Movie '11 01-03 [68]
- Movie '11 04-06 [54]
- Movie '11 07-09 [34]
- Movie '11 Misc. [11]
- あなたはVISIONAIREを知っていますか? [37]
- 取扱説明書 [1]
- 都内映画割引情報 [2]
- Movie '11 10-12 [34]
- Movie '12 01-03 [26]
- Movie '12 04-05 [28]
- Movie '12 07-09 [8]
- Movie '12 10-12 [3]
- Movie '13 01-03 [1]
- Movie '13 10-12 [1]
- Special [2]
- VIS [1]
-

- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
-

-


At last? ... or the last...?
2010.06.01
小さい頃、ことあるごとに「この原作はたった一行しかないんだよ」と父親が言っていたのをずっと信じていた作品があります。
実は正直なところあまり興味がなかったというのも相まって、今日の今日までその事を疑いもせず、ましてや何人かの人にはそう伝えてしまっていた事をこの場を借りて訂正したいと思います(笑)。
そこでこのブログを書くにあたってWikiなどを調べてみると、実際には文庫本でいうと10ページほどある掌編小説らしいのですが、1962年の第一作が公開されて以来、38年に渡って広い世代に愛されてきた事には変わりなく、紆余曲折あるようですがその理由が原作の長さに由来するとは思えません。
まったく知らないであろう人のために一応書いておくと、原作者の子母澤寛(しもざわ かん)は1892年に北海道に生まれた菊池寛賞も受賞した小説家で、今日紹介する作品は「ふところ手帖」という彼の随筆の中に書かれているもの。
ただ実際にこの随筆の中では主人公についてあまり多くを書いていないようで、原作では長ドスだったものが仕込み杖になったりと、その風貌やキャラクター設定は、合計26本で主演を演じ続けてきた俳優、勝新太郎によるものだそうですが、あなたはこの作品を単なるリメイクだと思いますか?
「座頭市 THE LAST」
とにかく、とにかくZEEBRAが良い。
通常、友人・知人の映画は観ないか、観てもその部分だけは感想を省くようにしていますが、これだけは何と思われようが言わない訳にはいかないほど、良い。
言えば言う程嘘っぽく聞こえるかもしれませんが、その佇まいやら台詞まわしといい、普通に良いのだから仕方ない。
もし今からあの港町を訪れたら、間違いなく彼はそこにいるであろうと信じて疑わない程、リアルというよりも、とっても自然体だったし、キチンと評価されるべきだと思います。
天は二物を与えないと言うが、例外もあるという良い例。
マジで良かったよ、ヒデ(笑)。
そして、反町隆史もこれまた良い。
個人的には「GTO」以来初めて「ハマった!」と声をあげたくなるくらい。
新たな新境地か...
★★★★★
132分という長さを全く感じない作品。
そしてとてもストーリーとディティールに対するこだわりが伝わって来る作品。
朱色のちりめんに、雪、桜、泥、刀の重さなどなど...
それこそ挙げ出したらきりがないほど、その思いが伝わってくる瞬間があります。
「最後の座頭市」と銘打っている本作。
細かい事を言うのであれば、2017年が原作者である子母澤寛の没後50年にあたるため、法律的には著作権が切れてしまうのでそれ以降は誰でも自由に映像化する事が可能になる訳ですが、果たしてフォロワーは現れるのか? それとも本当にこの作品がラストにふさわしいのか?
実際に劇場に行って、その目で確かめてみてはいかがでしょう?
あ、その前に親父が生きてるうちに間違いを正さないと...と思ったら、どうやら一行と言うのはあながち嘘ではなく、子母澤寛がこの作品を書くにあたって千葉県・房総地方のの任侠について取材した際に「飯岡助五郎一家に盲目のばくち打ちがいて、目が見えないのに賽子の丁半をよく言い当てた」という昔話からヒントを得たと後年語ったそうです。
まさに僕が子供の頃に親父から聞いた話と一緒です。
さすが往年の文学少年、あなどれませんね(笑)。
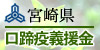


※コメントは承認されるまで公開されません。