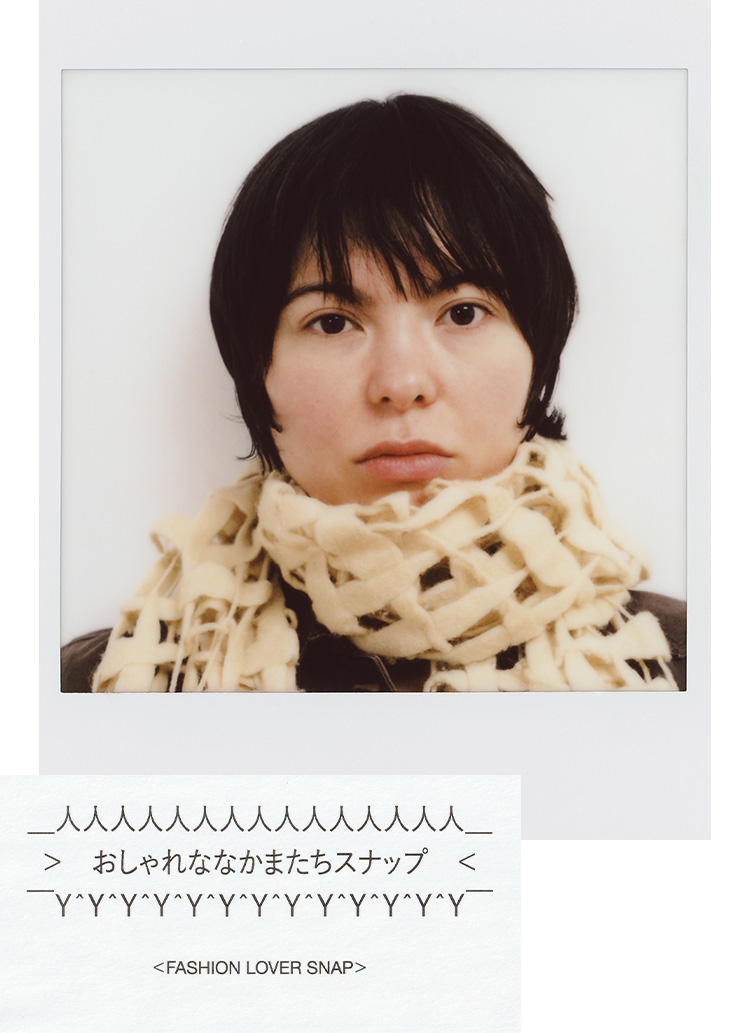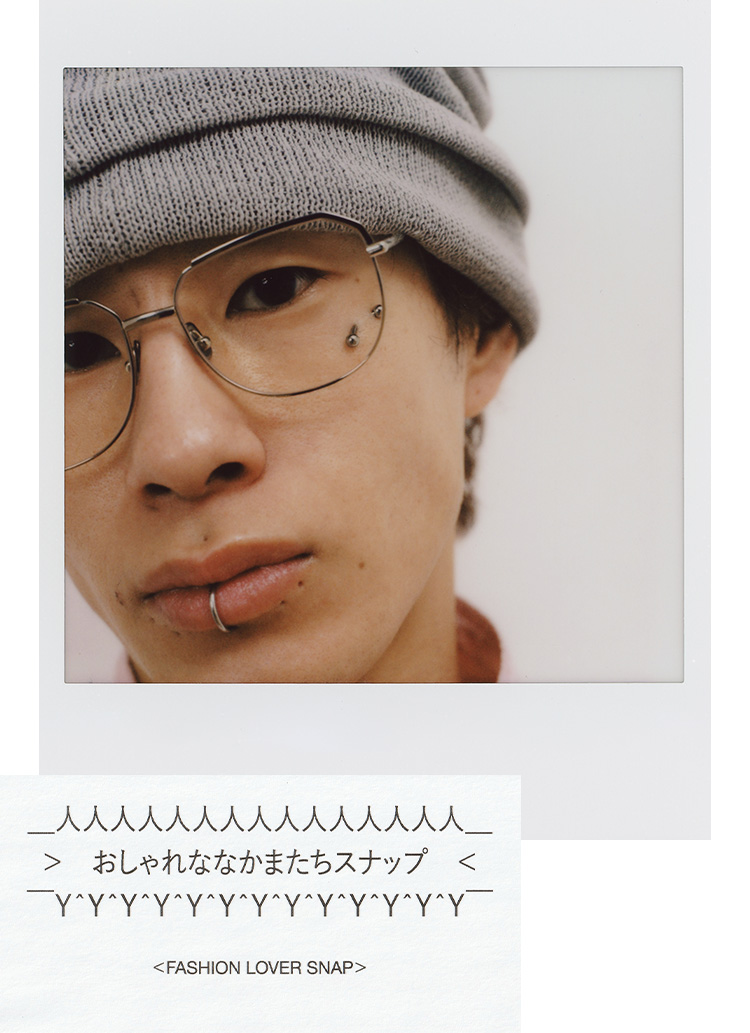型屋さんの驚くべき技術とアイデアで象られる日常のデザイン。


サンプルをもとに原型をつくる型職人。ちょっとのミスが命取りになるので、木の棒で支えながら慎重に削る。

つくっている瓶の原型は〈ブラックアイパッチ〉からリリースされる波佐見焼の作品。
馬場さんがその制作をディレクションしている。
馬場さんが最初に案内してくれたのは型屋さんでした。焼き物を大量生産するための型をつくる場所。実際につくる焼き物の形を象った「原型」づくりから作業開始です。「原型は、言うなれば型の型。これをもとに『使用型』という実際に生地を流し込む型をつくるんです」と馬場さん。

左が原型で右が焼きあがった完成品。生地を焼くことで水分が飛び、そのぶん縮む。
そのことを頭に入れて原型をつくる。
作業場で慎重な面持ちで原型をつくっていたのは、この道37年のベテラン職人である岩永喜久美さんです。「生地は焼き上げることで14%ほど縮んでしまいます。なので、それを見越して実際よりも大きなサイズで原型をつくらないといけないんです」と馬場さん。その言葉の通り、ときどき途中で削るのをやめてサイズをミリ単位で計測する岩永さんの姿が印象的でした。


サンプルとして使われているのはアメリカのビールの瓶。
よく見るとラベルが貼られているボディの部分は若干痩せていたりと、単純な直線の造形ではないことがわかる。
「この瓶のようにサンプルがあるときはその形を忠実に再現すればいい」と岩永さんは語ります。とはいえ、一見シンプルな瓶でもよく見るとカーブが描かれたりしていて、その微妙な差も見落とさずに再現するのが職人の技。“忠実”という言葉は経験があってこそ実現できるものなのです。

過去につくられた原型の数々。溝のあるお皿もひとつひとつ手で彫られている。
下に積んであるのが使用型。原型に石膏を流し込んでつくる。
一方で「形をイチからつくるときは大変」と続けて話す岩永さん。企画者の意図を汲み取りながら頭の中でイメージを練り上げて型をつくるときこそ職人の腕のみせどころ。馬場さん曰く「喜久美さんは複雑な立体の造形が上手。いつもぼくの無理を聞いてくれるんです。ぼくらは平面でしか図面を描けなくて、それを立体にするとなると職人さんたちのアイデアや引き出しが必要になる。実際にここへ来て、作業を見ながらイメージの擦り合わせをすることが多いですね」とのこと。それに対して岩永さんは、「たとえばお皿でも真っ平らにするんじゃなくて、溝を彫って影がでるようにしたりとか、それをいかに美しく魅せるかなど、そんなことを考えながらやってますね」と教えてくれました。普段何気なく使っている食器も、形や飾りのひとつひとつに職人たちのアイデアが注ぎ込まれていると思うと愛着が湧いてきます。

作業場に併設された倉庫には床から天井までびっしりと使用型が保管してあった。
37年の歴史がここに蓄積されていると思うと圧巻。手前にあるのは岩永さんの趣味であるバイク。

自分の父親世代の職人にも臆さず対等に話す馬場さん。
岩永さんへのリスペクトと、いい焼き物をつくりたいという熱意があってこそできること。
最後に出来上がった原型をもとに使用型をつくって型屋さんの作業は終了。次は生地屋さんへと向かいます。