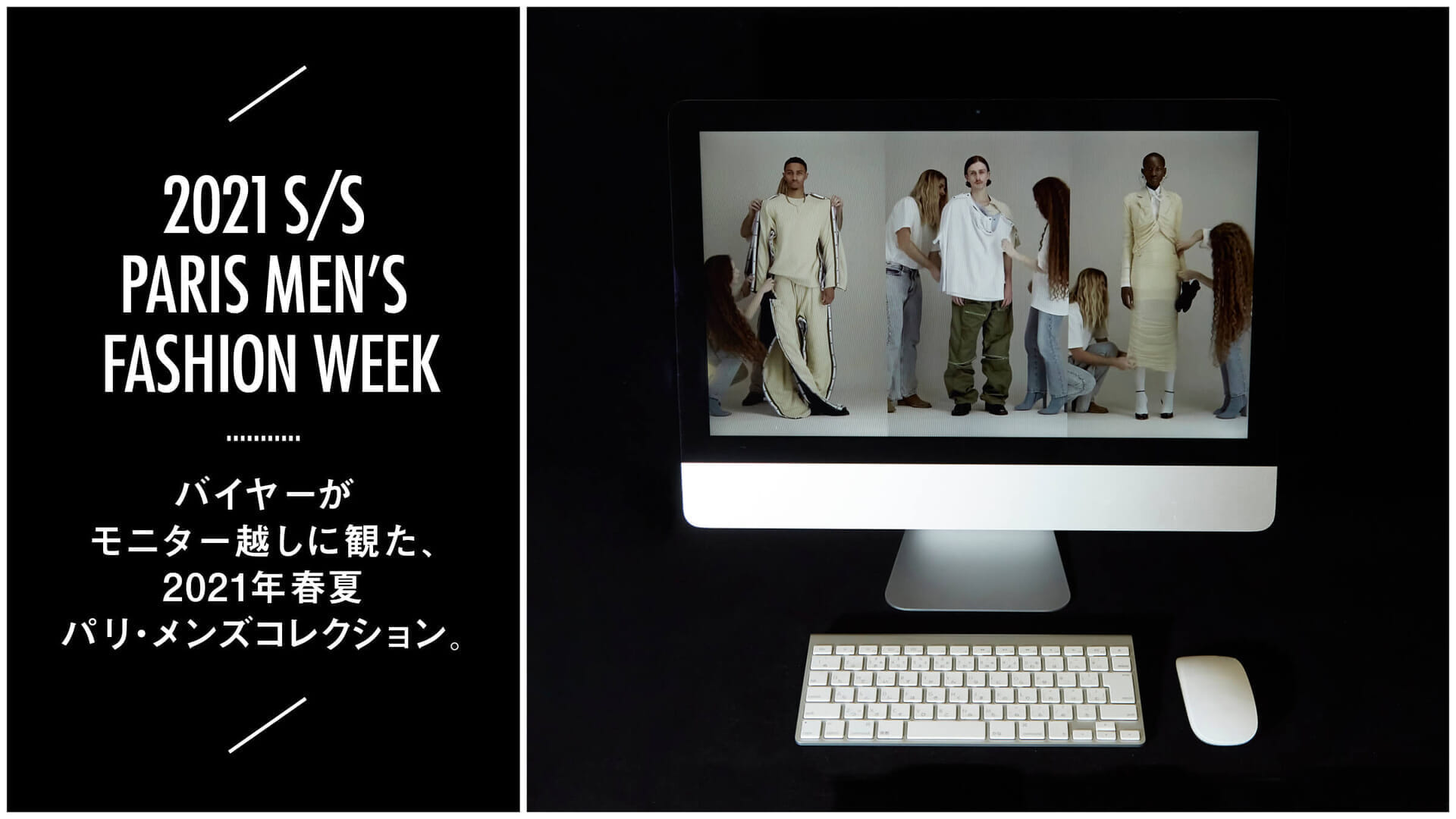BUYER 05 肌で感じてはじめて分かる “驚き” がファッションの楽しさのひとつ。
PROFILE

「アディッション アデライデ」マネージング・ディレクター。高校卒業後に渡英し、ロンドン芸術大学を卒業。2009年、両親が立ち上げた「ザ・ウォール」に入社。「アディッション アデライデ」で販売員、店長、バイヤーを経て、マネージング・ディレクター兼バイヤーに就任。
adelaide-addition.com
ー 今季のパリ・メンズで発表された映像で、印象に残ったブランドを教えてください。
一番は〈ワイ・プロジェクト〉ですね。かなり早い段階から、デジタルで発表する準備を進めていると耳にしていました。商品のタグにモデルが着用した写真を載せているほど着方が難しいデザインですが、ひとつの動画のなかでスタイリングを明快に表現していて。バイヤーのこともしっかりと考えられていたので、もしこれを観ていなかったら買ってないピースがあったかもしれません。映像を観た後、オンラインプラットフォームの「ジョア」で気になった品番を用意しつつ、セールススタッフと「ズーム」を通じて細かく話をしていきました。
ー 〈ワイ・プロジェクト〉は新しいラインも始動しますね。
いわゆるシグネチャーとなっている形に、サスティナブルな生地を載せかえたライン「エバーグリーン」をスタートさせます。斬新なデザインでファッション性に特化している彼らもマインドが動いているんだなと。コレクションをつくっている時のヨーロッパでは、日が経つごとにコロナの影響が深刻化する状況だったので、サンプルがつくれない状況も想定していままでのアーカイブの活用を考えはじめたブランドも多かった印象です。〈ラフ シモンズ〉も限られたショップでアーカイブの服を販売しますね。
2021年春夏コレクションのなかで発表された「エバーグリーン」。17年春夏シーズンから20年秋冬シーズンに掛けて販売されたアイコニックなアーカイブアイテムを再解釈し、オーガニック素材とリサイクル素材を使ってリリースするというもの。ルック写真の1枚目で使われたのはジーンズ、2枚目はデニム地のブーツ、3枚目はシャツ、4枚目はジーンズ、5枚目はコートとパンツ。
ー 先行きの見えない状況だからこそ、興味深い動きですね。
そうですね。大変な情勢のなか、今回のデジタルのショールームを通して見たコレクションでサスティナビリティへの意識が浮き彫りになっていたブランドも多々ありました。実は、お客様側から「過剰包装をやめてほしい」といった話をよく耳にしていたので、サスティナビリティを真剣に考えているブランドに対してはバジェットを増やしていきたいとちょうど思っていたんです。ブランドは製造や製作過程だけでなく、消費者の手に届くまでの流れを汲んでビジネスをやっていかなきゃいけない。私たちも、お客様にそうしたデザイナーの考えを伝えていく役割を担っていますから。
ー 長谷川さんの視点から、オンラインでの見せ方で特筆すべきブランドはありましたか?
これまでのコレクションのテーマやいままでのストーリー性もきちんと分かるようにウェブサイトを一新した〈マリーン セル〉ですね。彼女は、「アポカリプス(黙示録)」や「ラディエーション(放射能)」などをテーマに、このままいくと地球が汚染されてマスクしないと生きていけない世界になることを暗示し続けてきました。つまり、改めてブランドを理解してもらおうという動きをしていたんです。彼女たちは、服の機能性をすごく重視しつつサスティナブルの意識も高くて、独自のストーリーからデザインを展開しています。一方で、オンライン上でルックの写真が360度回転する見せ方を2、3年前からすでに取り入れていて、仮に展示会に行かなくても買い付けがしやすいシステムを採用していました。

現在、注目を集めるデザイナーのひとり、マリーン・セル。2017年、若手デザイナーの登竜門である「LVMHプライズ」でグランプリを獲得したことで話題に。現在はロンドンでコレクションを発表している。写真はブランドのHPから。
ー もしかして、そうしたオンライン上での見せ方を見据えていたことも、“暗示” がベースになっているのでしょうか?
すごく不思議なんですけど、そうですね。専門のチームがあるんですが、コロナ禍を予測していたのかとさえ考えると、スピリチュアルな感じさえしますよね(笑)。あと、バイヤーだけがアクセスできたのですが、〈ボッテガ・ヴェネタ〉のデジタルショールームは素晴らしかった。パスワードを入れてサイトを開くと、その空間を写したパノラマのなかに、素材の落ち感や光沢も良く分かる服がラックに掛かっている姿、靴やバッグが置かれたかっこいい什器もあって、まるでショールームを訪れた気分になりました。〈バレンシアガ〉など、世界観が反映された展示会に行くと毎回感動しますし、そうした場所で買い付けることはバイヤーにとってとても大切なことだと思っています。
ショーをスキップせず、オープンエアな場所で行われた〈ジャックムス〉の夢のようなショーは、ライブ映像のカメラワーク、音楽、演出のどれをとってもクリエイティブで、いっときでもコロナを忘れさせるほど、私は心が癒されました。
約100名と限られた観客を招いてランウェーショーを開催した〈ジャックムス〉。フランス・ヴェクサン地方にある小麦畑に200mのランウェーをつくり、ソーシャルディスタンスが確保されていた。「デザイナーが育ってきた南仏の環境を想起させるリゾートウェアなんですが、“着たい” と思わせるブランディングとしてショーに重きを置いていました。デザイナーのサイモンをはじめ、クリエイティブなアイデアを持っている人たちが集まっている。旅行できない私たちに夢を見せてくれました」と長谷川さん。
ー 今後、ファッションウィークのデジタル化は加速していくと思いますか?
何ごとも五感で感じることは大事だと思っているので、映像や画像、オンラインミーティングだけというのは限界があると思っています。普段の打ち合わせは良いですが、バイイングとなると金額も桁が違いますから。そもそも、実際に手に取って見たり、肌で感じてはじめて分かる “驚き” がファッションの楽しさのひとつだと思いますし、そういう目を持っているお客様に提案もできなくなってしまいます。また、ショールームでの会話は、国境を越えた景気や経済の話題だったりと、コレクションのことだけではありません。時差の関係で、今回のファッションウィーク中の10日間、私は夕方から夜までほとんどがアポイントで拘束されていましたが、次のアポがあると早く切り上げなきゃいけない。あっちもバタバタしているし、雑談をする余裕もなく、話ができる環境じゃないのも私にとっては残念なポイントでしたね。