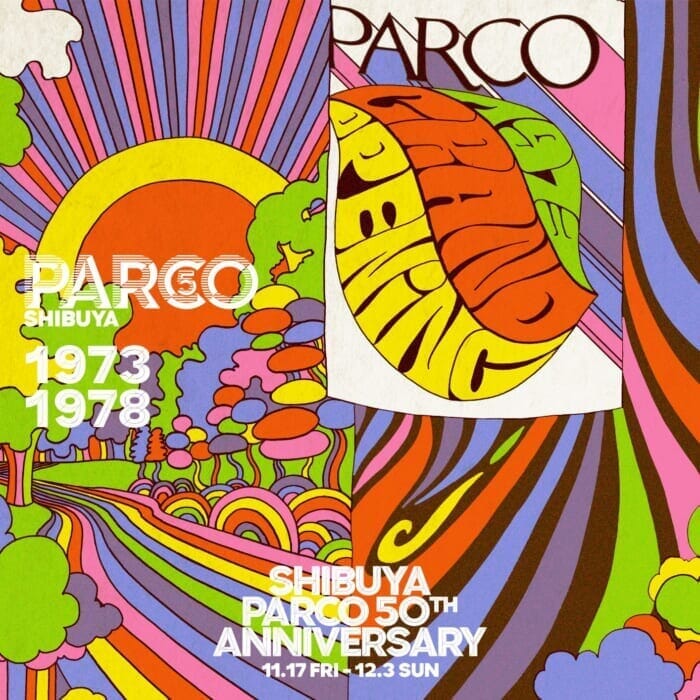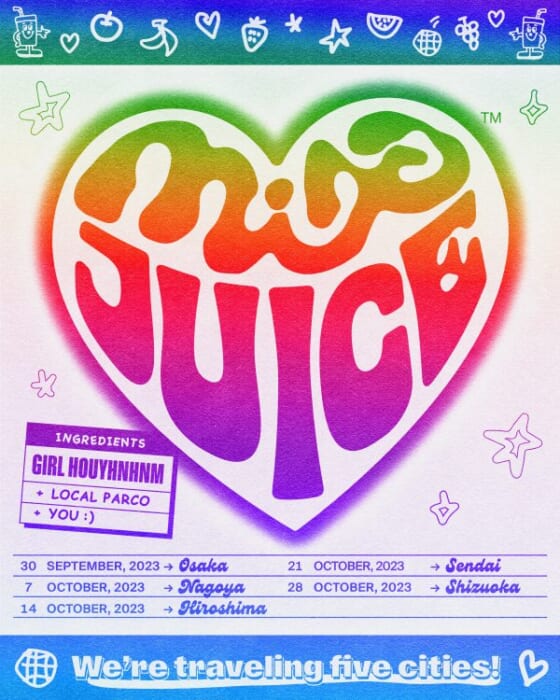PROFILE
エッセイスト・漫画家。1978年生まれ。多摩美術大学美術学部二部芸術学科卒業。高校生のときに描いた漫画『女子高生ゴリコ』(1997年)でデビュー。ウェブや雑誌等でエッセイや小説を発表し、著書に『マイ・リトル・世田谷』『ガールフレンド』などがある。『アフター6ジャンクション』(TBSラジオ)のレギュラー出演でも活躍中。父は写真家の島尾伸三さん、母は写真家の潮田登久子さん、祖父は小説家の島尾敏雄さんという文化色の濃い家庭で育つ。自身は、2015年に第一子を出産。
アートと自然に触れ合える。
ー しまおさんは、パルコによく来られるんですか?
息子がマリオ好きで、任天堂ショップに来ますね。学生時代に、よく来ていたパルコとはまた違いますが、今のパルコもすごく好きですよ。
ー 今回パルコでは、「SHIBUYA PARCO ART WEEK 2021」と題して、アート作品がいろいろな場所に点在していて、周遊するようにして作品を見ることができます。
美術館とは違って、ファッションビルの活気のなかにあるのがいいですよね。服を見に来るついでに見ることができる。美術館に行く習慣のないひともアートと自然に触れ合えるしね。
ー なるほど。では順にまわっていきましょう〜!
【SPOT1】 Jean Jullien Exhibition「PAPER PEOPLE」
思ってたのと違う。そしてファンに。
ー すでにイラストレーターとして人気のJean Jullienというこのフランス人アーティストのこと、ご存知でしたか?
Instagramはフォローしているんですが、そこまでしっかりとは作品を追いかけたことがなくて、*サヴィニャック風のレトロな作風のポスター展なのかなと思ってました。でも実際は、全然違いますね。静物画のようで、躍動感のある筆のタッチが伝わってきました。モチーフ選びもセンス抜群だし、カラフルでファンになりました。
*レイモン・サヴィニャック- フランスのポスター画家。商品の宣伝に人や動物のモチーフを組み合わせ、明快な造形と色彩を用いるなど、当時としては斬新な手法で業界を牽引した。

ー ここにある作品は故郷ブルターニュの海や趣味のサーフィン、さまざまな生き物、子供のおもちゃなど、アーティスト本人の身の回りの美しい世界を捉えたものばかりです。
オンオフの違いがないということを、彼の作品から感じます。生活に密着して、日常を切り取っていることにも共感しますし、生活の細部を見ているんでしょうね。あとは、海やサーフィンの絵は、日常のさらに先にある普遍的なものを描こうとしてるのかなとも感じました。
ー アーティストの細かな視点に気づくには、作品を直に観るのがいちばんいいですからね。しまおさんのエッセイも、生活をつぶさに見ている感じが伝わってきます。表現物が日常の延長線上にあるというか…。
私は、日常と作品に差がない方がやりやすいんです。たとえば、街を歩いていて、すれ違うひとの気になるポイントが着想になったりとかもしますよ。

【SPOT2】 Jean Jullien Exhibition「POCKET PARENTS」

NANZUKA 2G(2F)
NANZUKAが手がけるアートスペース。MEDICOM TOY、小木“Poggy”基史とデイトナ・インターナショナル、NANZUKAによる新形態のスタジオ「2G」内に位置。アートトイやコンセプトショップなどスタジオ内のコンテンツとも連動する展示を行うなど、定期的に様々なアーティストの作品を紹介している。
03-5422-3877(NANZUKA)
公式サイト
絵画では描けないことをコミックに?
ー つづいて、先ほどとは別のテナントにある、同じくJean Jullienの展示です。壁に貼ってあるコミックが目を見張りますね。こちらは、ViviとNinoという夫婦、その息子Albert、夫婦が出会ったTiboという人物を中心に展開されるフィクションだそうです。自身の家族をすこしなぞらえているような登場人物なんですかね。
Jean Jullienさん自身、家族が生活の軸にあるからこそできた物語ですね。コミックは先ほど見た絵画では表現しきれないことを描いているのかなと思いました。海外作家のコミックはあまり詳しくなくて*ダニエル・クロウズくらいしか知らないのですが…。日本に彼らのファンが多いのは、飛び抜けたセンスと冷静な観察眼に惹かれているのかもしれないですね。
*ダニエル・クロウズ- アメリカ合衆国の漫画家、イラストレーター、脚本家。日常と非日常を行き来する独特の世界観や、憎めないキャラクター、小気味いいセリフまわしが特徴。スカーレット・ヨハンソンら出演の映画『ゴーストワールド』(2001年)では脚本を務めるなど、その活躍は幅広い。

ー 先ほどの展示もそうですが、Jean Jullienのこの作品もすべてこのコロナ禍の一年半の間に生まれたものだそうです。
それはすごい。筆がノッているんでしょうね。友達で現代アーティストのこたおちゃんもすごい人気ですが、いまのアーティストは多作な方が多い印象です。更新頻度を求められるSNS時代っていうことも関係あるのかな…?
ー 多作なうえ表現方法もさまざまで、今回のアートウィークではそんなJean Jullienの作家性を漏れなく体感できますね。ちなみに、しまおさんが写真を撮られているそちらの立体作品、お値段は3セットで100万円ちょっとだそうです。
びっくり!
ー 日本でつくられたソリッド(無垢)のブロンズ製で、1点ずつすべてハンドメイドなんだそうです。それも、世界で25セットしか存在しないとか…価格に見合うクオリティですね。
【SPOT3】 #ホテルカワシマ

ほぼ日曜日(8F)
「ほぼ日曜日」は、糸井重里が主宰する 「ほぼ日刊イトイ新聞」のリアルスペース。 日々ウェブからコンテンツをお届けする 「ほぼ日」が、このリアルなスペースではさまざまな催しを実施。展覧会、イベント、 ライブ、トークショーなどなど、「生」の 出会いを提供する。
03-5422-3466
公式インスタグラム
ホテルってちょっと不気味じゃないですか?
ー ここはお笑い芸人の麒麟・川島明さんによる、 “ホテル” をテーマにした展示です。なかでは4つの部屋に分かれて、それぞれでホテルにちなんだ設備を体験しながら、そのユニークな展示を楽しめるというものです。今日は支配人の川島さんが会場にいらっしゃるということで、しまおさんといっしょに話を伺いましょう。
しまお:客室風の部屋では、「#眼科でしかみられない景色」が好きでした。ハッシュタグを多用されていて、ハッシュタグへのこだわりを感じました。
川島:もともと自分がやっている「ハッシュタグ大喜利」がいろいろと発展していって、今回の展示になったんですね。ハッシュタグって、ちょっと独特で気に入っているんです。というのも一般的にハッシュタグを使えば、タイトルにもできれば、ツッコミもできる。額縁がつくようなイメージなんですよね。ハッシュタグなしで大喜利のツッコミのような言葉だとちょっとしんどい気がするんですが、使うと温度が一度下がってちょうどよくなるんですよ。
しまお:温かい言葉と冷めた言葉のシャワーを浴びる、浴室の部屋もさすがのアイデアでした。映画『シャイニング』の浴室っぽいなと。
川島:そうですね、気持ち悪さを出したかったんです。ホテルってちょっと不気味じゃないですか? 昨日までひとが寝ていたところに、クリーニング、ベッドメイキングしましたよって書いてあるだけで、みんな安心してよう寝られるなって。


ー ホラー映画とかお好きですか?
川島:ホラーはめっちゃ好きです…いや好きでした。以前、そういう作品をたくさん借りて観まくったんですが、お笑いと変わらないと。緊張と緩和。エピソードトークと怪談も似ていますしね。
しまお:お笑い芸人の方といえば、バラエティ番組『アメトーーク!』でも取り上げられた、いまはなき六本木のホテルアイビスを思い出しちゃいます。
川島:今回の展示は、ほぼ全ての人が一度は泊まったことがあってイメージできるホテルというものがすでに前振りになっているんです。だから客室はビジネスホテル風になっていたり。その前振りを使って、2Dではなく3Dとして体験できる展示を楽しんでもらえたらと思ってます。

朝の情報番組『ラヴィット』の収録終わりの取材にも関わらず、真摯に対応してくれた支配人・川島明さん。展覧会では、そんな彼の脳内がたっぷり見られます。
【SPOT4】 Kensaku Kakimoto Exhibition 時をかける
ただやるだけでも楽しい。
ー 映像作家・写真家として広告や美術界で活躍する柿本ケンサクさんの展示です。奥の映像は、AIに音楽を聴かせて、その音楽からインスピレーションを受けたAIが、柿本さんの写真にイメージのフィルターをかけるというものです。
そんなことができるですね、すごおもしろい技術。さっきの川島さんとコラボすると、相乗効果がありそうですね(笑)。

ー あとは、別のコーナーではスコープをのぞきながらペダルを踏むと、その瞬間見ている画が感熱紙にプリントアウトされて出てきます。
何枚でも持って帰れるの? すごく太っ腹。昔、こういうのゲームボーイであったの知ってますか? 「ポケモンプリンタ」ってやつ。懐かしい。こういうのは、お客さんはもちろん作品が欲しいというのもあると思うけど、ただやるだけでも楽しいんですよね。
作品には、そのひとの日常が根底にある。
ー さて、今回いっしょに見て回りましたが、しまおさんはあまり解説などは参照せずに、パッパッと作品を見ていくスタイルなんですね。
せっかちなんです。電子機器も、説明書は見ないでまず動かす! アートを鑑賞するときは解説を見ることもありますが、さっと回ることの方が多いですね。一旦見て、気になる作品の解説をあらためて読んだり。逆にお伺いすると、そういう解説はよく見ますか?
ー そうですね。現代アートに多いと思いますが、コンセプトを踏まえないと掴めないものは、見ないと「?」で終わることが多いので。
そういう意味では、どっちかといえば現代のものはあまり見ないかもしれません。でも、作品自体はちゃんと説明して欲しいし、わかりやすい方がいい。自分も学生時代に映像学科で作品を見せる機会が何度かあったんですが、若い学生は感じてくださいという感じで、フィーリング先行になって説明不足に陥りがちですよね。使っている画材の種類がちゃんと書いてあるとかそういう方が親切ですし、スタンダードな解説があった方が、逆にノイズなく見れたりしますから。先ほどの柿本さんの作品では、AIなどの技術の解説を聞くと、作品自体への理解も深まりました。

ー 今日ご覧になって、他に気になったアーティストはいますか?
Jean Jullienですね。この1年半で、あれだけの量の作品を描いたって、すごく多作な方で、タッチも素敵でしたし、日常を描いているところにすごく共感しました。
ー しまおさんも日常を描くエッセイをよく書かれていますが、なぜ日常なんでしょうか?
作品には、そのひとの日常が根底にあると思いますし、上っ面の刺激ばかりだと深みがないと思うんです。作品に、どこか自分を写すものがある方が見るひとにとってもおもしろいんじゃないのかなと。
影響があったのは、鑑賞した作品そのものよりも…

しまおさんが注文したのは「ホットココア 500円(税込)」。はまの屋パーラーでは、さくっと食べれるサンドゥイッチサンドウィッチやクリームソーダなどもご用意しているそう。鑑賞や買い物おわりにちょうどいい。
ー ちょっと昔の話をお伺いできればと。かつてオリーブ少女だったしまおさん。1990年代当時のオリーブ少女にとって、アートは一般教養必修科目だったんでしょうか?
たしかに休日に美術館、展覧会巡りというのがオリーブ少女のイメージのひとつでした。原美術館とかね。金沢21世紀美術館や直島はオリーブよりもすこし時代があとですが、休刊後の迷えるオリーブ少女たちがこぞって訪ねていた印象があります。ちなみにわたしが初めてひとりで行った展示は、高校時代。渋谷パルコのすぐ近くにあった宇宙百貨の並びのビルの2階にあったART WAD’Sギャラリーの「蛭子能収展」でした。
ー なんだかしまおさんらしくていいですね(笑)。当時のアート鑑賞がいまの自分を形成していると思いますか?
どうかなあ。作品そのものよりも、見に行った場所や時代、その時のエピソードをひっくるめて影響があったかなとは思いますね。蛭子さんの展示はまさに、ですし。文章書くときのネタにはなってるかな。
ー あらためて、振り返って思い出深い作品はありますか?
94年にフジテレビの深夜放送で「コンフィグ・システム」っていう番組があったんです。あがた森魚、飴屋法水、内田春菊、ケラリーノ サンドロヴィッチ、田口トモロヲ、ピエール瀧…などなどとにかく錚々たる出演者のショートフィルムが流れていました。主に監督していたのはイワモトケンチだったかな。あれはいま思えば自分に大きく影響を与えたアートかもしれませんね。全ての出演者を知っていたわけじゃなく、怪しい大人たちが出ている気持ち悪い映像が深夜に流れてきたっていう。そのなかで会田誠の『巨大フジ隊員対キングギドラ』も使われていたのも印象的で。
ー では、ご自身とアートとの関係について。昔と今とではどんなところが変わったと思いますか?
アートって昔は “敵わない” ものっていうイメージでした。発想の裏切りとか、単純に絵が上手い! とか。何がよくて、何がイマイチかって言語化しにくいけど、人々を圧倒するという意味で私には無理でしょって感じでしたね。先ほどの「コンフィグ・システム」などは、その時は気づかなかったけど、あとから考えるとアートだったなっていうものもあって。つくり込まれたとんねるずのコントとかタモリの存在とか。そういう、日常に潜んだアートからジャブを受けていた感じはします。
でも、歳を重ねると日々の暮らしや仕事にもアートを感じる瞬間はたくさんあることに気づきました。つまり、アートの定義が緩くなってきてるんでしょうね。値段がつくかつかないかの違いはあれど。とはいえ、すぐ「これもアートだよね〜」とか言うのはちょっと恥ずかしい(笑)。子どもの泥遊びとか、散らかった部屋とか見てあえて言う感じってありますよね? ただ汚いだけなのに(笑)。

ー わかる気がします(笑)。作為や打算がないとアート枠に入れがちですよね。さて、それこそオリーブ少女くらいの世代くらいになると思うのですが、いまの思春期の子たちは自分の世代に比べて、アートに対する意識が変わったと思いますか?
やっぱり今の子たちの方が身近になっているんじゃないかなあ。自己表現の場が、昔とは比べものにならないくらいたくさんありますもんね。わたしの時代は「壁新聞」とかですもん。しかも家の中でやってました。見るのはもちろん家族だけ(笑)。
値段のつくすごいアートもたくさんあって、それはSNSであっという間に広がっていく。可能性も速度も全然違うなあと羨ましく思いますね、壁新聞女子としては(笑)。

はまの屋パーラー
創業55年を迎える老舗の喫茶店。 名物の玉子サンドゥイッチをはじめ、 クリームソーダやホットケーキなど、どこか懐かしい喫茶メニューを提供している。 コーヒーは、自社農園で収穫されるハワイのコナを使用した「はまの屋ブレンド」を抽出。
03-5422-3015
公式インスタグラム