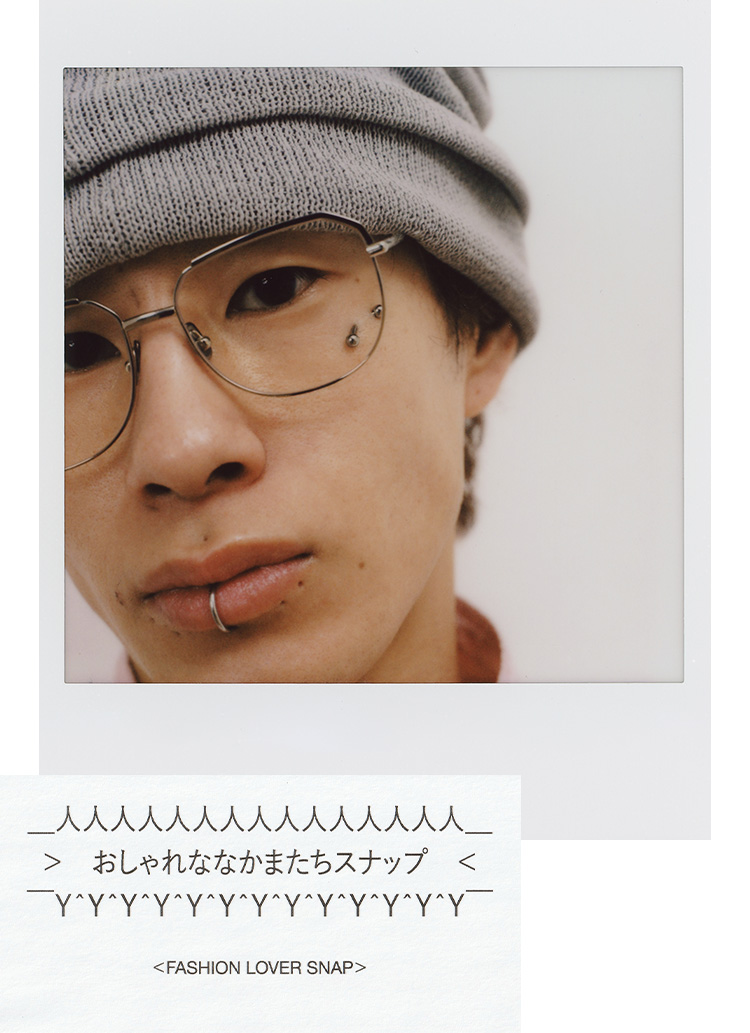観客は謎の存在でしかない。

ー 今日は曽我部さんと大下さん、それぞれ世代が異なるカラックスファンが、今回の新作『アネット』をどのように観たのかという話を伺っていきたいと思います。まず、それぞれカラックスでいちばん好きな作品はどの作品ですか?
曽我部:『汚れた血』は思春期のトラウマのような作品なので、ちょっと他の作品と同列には語れないんですよね。大人になってから観た作品では『ホーリー・モーターズ』がいちばん好きかもしれない。
大下:自分も『ホーリー・モーターズ』がいちばん好きな作品なんです。劇のような構成をもった作品を観たのも自分にとってあの作品が初めてということもあって、ものすごく衝撃だったんですよね。「演じる」ということについて、これまで考えたことがなかったことを考えさせられた作品というか。
ー 大下さんは、役者を仕事にするようになってからカラックス作品に出会ったんですか?
大下:最初は高校生のときに観た『ポンヌフの恋人』で、他の作品は全部役者になってからですね。今回『アネット』を観て、『ホーリー・モーターズ』がいちばん近い作品だと思いましたね。
曽我部:近い。近いけど、自分は『ホーリー・モーターズ』の方が好みかもしれない。『アネット』は自分にとってカラックス度がちょっと足りないというか。カラックスがミュージシャンだとすると、『アネット』はちょっとカバーアルバムのように感じたんだよね。
大下:ぼくは『アネット』、かなり好きでした。
曽我部:俺は、ちょっとどうやって観ていいのかわからなかった。だから、今日は『アネット』の魅力を教えてください(笑)。
大下:脳を直接刺激してくる感じですかね。次の展開とかを予想して観てると、物語の展開も、映像も、音楽も、全部その予想を超えてくるというか。すべてが速いというか。
曽我部:あー、なるほど。
大下:『アネット』はものすごく新しいことをしている映画だと思うんです。ひとつの作品のなかで視点が4段階くらい変わっていくというか。これは『ホーリー・モーターズ』を観たときにも感じたんですけど、その視点がメタフィクション的に自分のなかに入っていく感じがすごく気持ちよくて。
曽我部:何か刺激物を摂取したみたいな感じ?
大下:そうです。あと、この物語に込められている皮肉にも、けっこう共感を覚えるところがあって。「見るひと」と「見られるひと」というのがこの作品のテーマのひとつだと思うんですね。演者と観客の関係が作品の経過とともに変わっていくじゃないですか。
曽我部:「観客」の存在というのは、『ホーリー・モーターズ』でも象徴的に描かれてましたよね。
大下:はい。それが今回、より過激になっているというか。アダム・ドライバー演じるスタンドアップ・コメディアンがこれはあなたたち”観客”の問題だって、いきなりぶん投げてくる感じというか。
曽我部:自分があの主人公のシーンでちょっと思い出したのは、トム・クルーズが『マグノリア』(ポール・トーマス・アンダーソン)で演じていた自己啓発セミナーの主宰者役。途中まで客の心をコントロールできていたのが、自我を出しすぎたことで、途中から客がしらけていくところとか。
大下:ああ、たしかに。
曽我部:お客さんが明らかにある一定のタイプの客、つまりトランプの支持者を思わせるような、非リベラルのアメリカの白人ばかりだというのもきっと何かのメッセージなんだろうね。

ー 舞台の上にいる人間、つまり作り手と、その観客との関係ということでいうなら、曽我部さんがかつてカラックスに直接質問したことともつながりますよね。自分もあの現場にいたんですけど。
曽我部:あ、あのとき、いらしゃったんですね(笑)。
大下:いつの話ですか?
ー 『ホーリー・モーターズ』の公開前に、カラックス本人が登壇する試写会が渋谷のユーロスペースであったんですよ。
曽我部:あのとき、最前列で観てたんですけど、もう絶対にこの機会を逃したら一生カラックスと話すことなんてできないだろうと思って挙手して質問したんですよ。で、「はい、いちばん前の真ん中の男性の方」って司会の方に指されて。
ー 「あ、曽我部さんだ」って思って見てました(笑)。
大下:どんな質問をしたんですか?
曽我部:『ホーリー・モーターズ』は、何がかかってるかは映されていないスクリーンに向かって監督が犬を連れて歩いているシーンではじまるでしょ? で、そこで観客はみんな寝てるんですよ。あのシーンを観て、カラックスにとって観客というのはとても遠くて、理解し難いものなんだろうなって思ったんですよ。だから、「あなたにとって観客とはどういう存在なんですか?」って訊いたんですよ。
大下:で、カラックスはなんて答えたんですか?
曽我部:「映画をつくるときに観客のことはまったく意識していない。観客というものがなんなのか、どういう存在なのか、自分にとってはまったくわからない。謎の存在でしかない。ただ自分にわかっているのは、彼らがある一定数の一団で、やがて死に行く運命にあるということだけだ」って。
大下:おおおお(笑)。
ー あの質問は、あの日いちばんの質問でした(笑)。
曽我部:『ポーラX』までは、カラックスって作品のなかに完全に没入していて、観客の存在は完全に作品の外にあるものだったでしょ? でも、『ホーリー・モーターズ』ではああいうかたちで観客が作品のなかでも描かれるようになった。だから、その理由が知りたかったんですよね。

ー その延長上に、今回の『アネット』における、あの観客の存在があるとも言えますよね。
曽我部:でも、今回はよりわかりやすく世界vs自分になってて。そのあいだには自分と血縁関係にある子供の存在も出てきて。さらには#MeToo運動のような描写もあったりして。
大下:そのあたり、わかりやすく描かれていましたよね。
曽我部:そう。だから、ちょっと社会性が出てきたのかなって。でも、それは俺がカラックスの作品に求めるものではないんだよね(笑)。
ー 曽我部さんがカラックスにした質問、「観客とはどういう存在なんですか?」を自分自身に向けたらどう答えますか?
曽我部:「お客様は神様です」って言葉がありますけど、自分はそれですね。
ー へー。そう言い切れるのはすごいですね。
曽我部:だって、実際にそうですから。お客さんがいるから、自分が音楽をやれてる。
ー カラックスと曽我部さんとの比較で言うなら、超寡作家と超多作家というのも好対照ですよね。
曽我部:でも、それって実はどこかでつながっていて。自分にとっていちばんの客、いちばんのファンって、自分なんですよ。ものを作るときは、常にそのいちばんの客である自分との対話のなかでやっていて。もし自分がファンだったら、このひとのどんな活動を見たいかなって考えながらやってる。
大下:なるほど。
曽我部:その結果が、カラックスの場合は10年に1本みたいな今のペースなんだと思うんですよね。