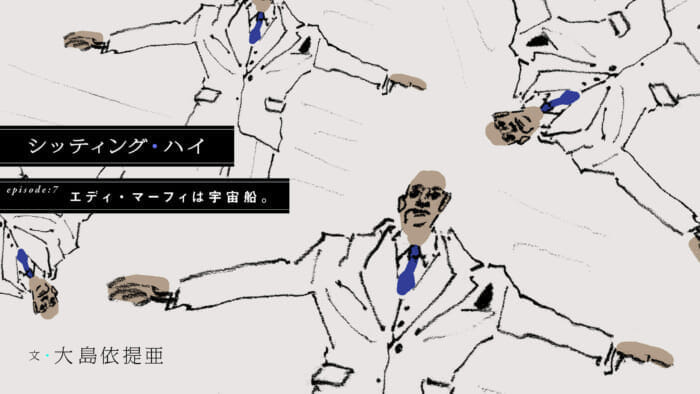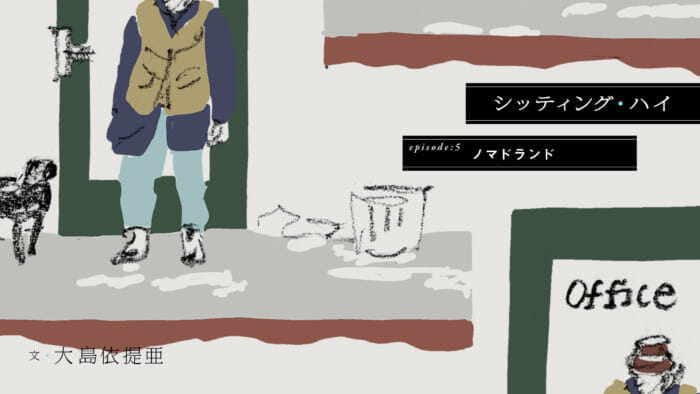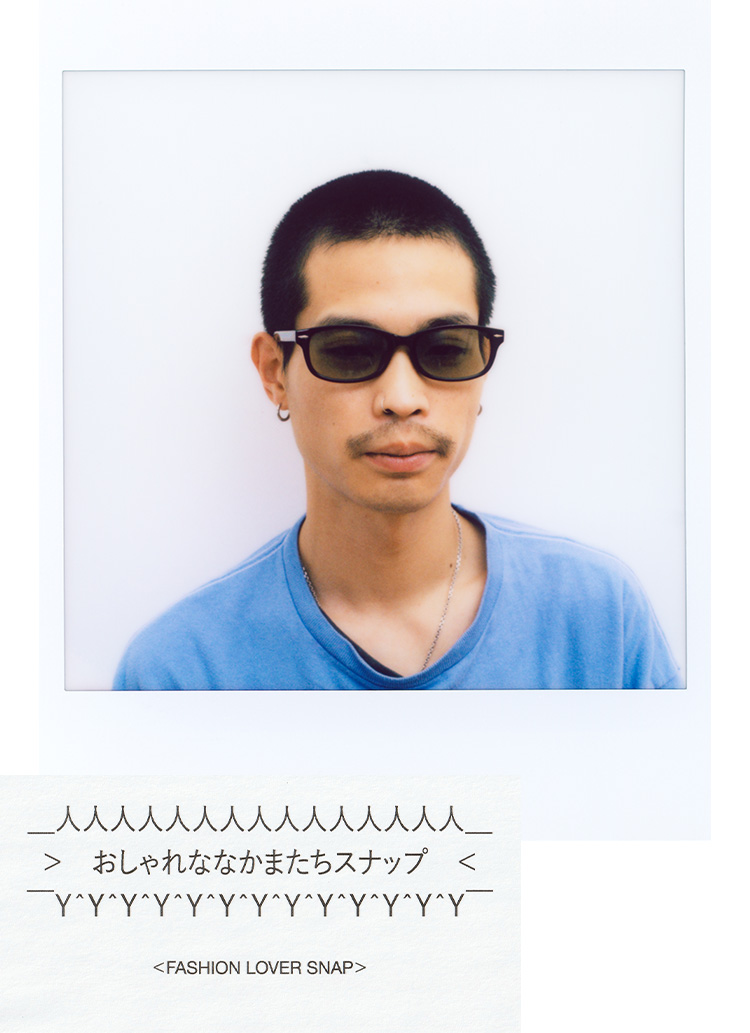PROFILE
栃木県出身、東京造形大学卒業。映画まわりのグラフィックを中心に、展覧会広報物や書籍などのデザインを生業としている。主な仕事に、映画は『パターソン』『ミッドサマー』『枯れ葉』、展覧会は「谷川俊太郎展」「ムーミン展」、書籍は『鳥たち/吉本ばなな』『小箱/小川洋子』がある。
Instagram:@ideaoshima
X:@oshimaidea
カウリスマキ作品のロケ地巡り。

ー大島さんは、今回カウリスマキの映画館のあるフィンランドのカルッキラという街を訪れたとか。この映画のビジュアルデザインのためだったんですか?
いえいえ。だとしたら相当贅沢なお仕事になります(笑)。フィンランドにまつわる別の案件で、現地に視察に行くことになったんです。ちょうどその頃、この映画の配給の方から「キノ・ライカ」のドキュメンタリー映画なんですがと依頼を受けまして。この映画を観ると、どうしても現地に行きたいと思っちゃいますね。
ーたしかに観ると、現地を訪れたくなる不思議な魅力がありますね。
ということで、フィンランドに行く機会はある。しかし、3泊5日で視察内容も決まっているので、無理かなと思っていたんですが、最終日に朝から動いて、現地でコーディネートもやってるデザイナーの遠藤悦郎さんという方のお力も借りつつ、夕方の飛行機の便までなんとか行ってくることができました。
ーメインは、ヘルシンキだったんですね。
そうです。すごく楽しかったですよ。たとえばこれは『ナイト・オン・ザ・プラネット』のヘルシンキ編の酔っ払いたちが出てくる冒頭のシーンの場所です。

ここは『ナイト・オン・ザ・プラネット』を撮った場所ですよという看板も出てました。映画を観ると、タクシーも呼べないくらい、どうにもならないような田舎かと思いきや、普通の街中ということにびっくりしました(笑)。
ーカウリスマキのロケ地ツアーみたいですね(笑)。
そうそう。それでカルッキラはヘルシンキから車で1時間ぐらいなんですが、もうそろそろ映画館に着きますよという時に回した動画がこれです。
工場に入っていくみたいですよね。こんなところに本当に映画館があるんですかと。現地は寒い田舎町という感じです。僕の経験に照らし合わせると、例えばアラスカのアンカレジに似ていて、『ツインピークス』の雰囲気もちょっとありました。
ー映画でも描かれていましたが、映画館はもともと鋳造所だったんですよね。
そうです。でもどうやって変えたの? というくらい完全に映画館に変わっていて、うまく工夫してつくったなと。劇中でも描かれていましたが、手弁当でやっていたからさぞかしディープな映画館だろうと思っていたら、想像以上に洗練されていました(笑)。




写真右/左は「キノ・ライカ」共同オーナーのミカ・ラッティさん、右は大島さん、後ろにいるのは後述の篠原敏武さん。

たとえば、音響が素晴らしかったです。レトロな感じなのかなと思っていたら、最新のスピーカーが何個もずらっと。アメリカの大作もの、ブロックバスター系の映画とかも上映するんですよね。僕が訪れた時は、『グラディエーターII』とかやってましたね。時間がない僕のために、カウリスマキの短編3本を特別に上映してくれて観ましたが、スクリーンもすごくきれいでした。ここで『グラディエーターII』も観てみたいなと思いました(笑)。「一度は行ってみたい世界の映画館20選」があったとしたら、確実に入るであろう、いい映画館でした。
ー映画からはそんな雰囲気をつゆほども感じませんでしたね。
すごく洒落ているんですよ。バーやカフェスペースがあって、その奥に会議室のような空間があって、住人の皆さんが集まって、一緒にスポーツ観戦や食事会をしたりするコミュニティスペースとしても機能しているそうです。ここに飾ってあるのが、カウリスマキの奥さんの絵なんだとか。奥さんもカウリスマキのお父さんもペインターだと聞きました。
ー人口9,000人の街にこんな映画館があるのはいいですね。
羨ましいですよね。劇中だとカウリスマキ本人がDIYで工事に参加していましたが、あまりにも自然に溶け込んでいるから、本人だとわからないくらい(笑)。でも、お金はしっかりとかけたんだろうと感じました。地元に住みつづけている映画監督というと、お金がないのかなと思うけど、コンサートを開いたりとビジネスセンスもしっかりしていると聞きました。

ー映画『キノ・ライカ 小さな町の映画館』はどうでしたか?
劇中の歌が素晴らしかったじゃないですか。これまでにカウリスマキの映画でも曲が使われている、篠原さんという日本人の方が友人の家に招待してくれて、何人かでセッションする様子を見せてくれたんです。
ー今回の劇中にも出演されていた、篠原敏武さんですね。
まさしく理想の老後という感じで、カッコ良すぎて痺れました。
ー映画を観ると、カルッキラという街には、アーティストなどおもしろそうなひとが多い印象です。
短い滞在では、そこまではわからなかったけど、映画を観るとそうですよね。先ほど言った、アンカレジに行った目的は、90年代の『たどりつけばアラスカ』というアメリカのドラマシリーズがあって、大好きだったから。いわば『ツインピークス』のミステリー要素がない、変な人ばかりが出てくるコメディドラマ。
たとえば、ラジオDJがイングマール・ベルイマンのコアファンとか、知的でこだわりのあるひとたちがいっぱい出てくるんです。それを思い出しました。僕の視野が狭いだけなんですけど、地方でひっそりと暮らしている方々の中にも、知的かつ個性的な営みがあるんだなと。あんなのはドラマの中でしかないと思っていたけど、実際にあるんだな、素敵だなと短い滞在期間でも感じました。




ー劇中ではカルッキラの住民がたくさん出てきます。
出てくるひとも説明がほとんどないから、謎だらけですよね。このひと誰? って(笑)。でも、説明的ではないその緩さがいいなと。カウリスマキ本人がドキュメンタリーを撮ったらこんな感じかな、というのをこの映画から感じました。映画や映画館とは何か? ということをダイレクトに問いかけていて、なかなか深い映画だなと。本来映画とは? と問われるときには、時間軸の話が出てくるケースが多いと思うんですが、映画館の話なので、当然地理的な視点から問われるというところがこの映画の特徴だなと。すごくいい映画でしたね。

ー劇中で、ミュージシャンのヘッラ・ウルッポが、カウリスマキと会った時に、「いつか会うと思っていて、それが今日だと知ってた」というような話をしたと思い出を語るシーンがあるじゃないですか。セリフじゃなくて、あんなことを日常で言えるのかとびっくりしましたね。
本当にそうで、なんだか誤解しちゃいますよね。フィンランド人は、カウリスマキの映画の登場人物のような感じなのかなって(笑)。

ーあと、カウリスマキ本人がDIYしているという話では、朝7時から夕方17時まで働いているというのも驚きでした。
それこそカウリスマキ本人が作った映画館だと言っていいですよね。自分で手も動かして、お金も出しているんだから。監督自ら動くんだから、そりゃみんなも頑張りますよ。だから実際はわからないですけど、映画作りのスタンスを垣間見る感じもありました。それにしても、本当にテキパキ働いていたなと。お年がお年で不摂生な方だから心配しちゃうけど、嬉しくなりましたね。こんなに働けるのかって。
ー不摂生な方なんですね。
若い頃からやんちゃだし、お酒がお好きで。昔のカンヌのインタビュー映像を観ても、焼酎がそばに置いてあったりとか。他にもいっぱいそういう映像がありますよ。筑紫哲也さんとのインタビュー動画とか本当にすごいので、ぜひどこかで探して観てください。とはいえ、最近はそこまででもないと聞いて、安心しました。
ー観てみます! 映画で他に印象的だったシーンはありますか?
最後の方でジム・ジャームッシュに映画評論家の方がインタビューしているシーンがありましたが、非常に知的で素晴らしい内容で感心しました。