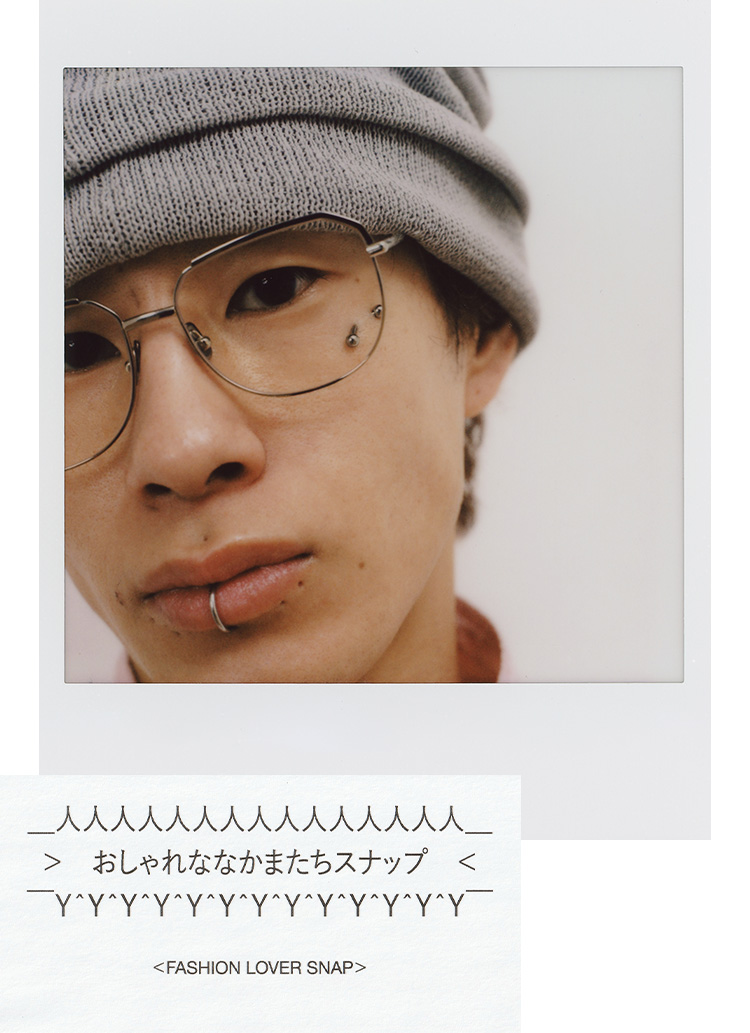効率やコストを優先するのであれば、プリントしたポスターやデジタルサイネージに軍配が上がるのが正直なところ。しかし、数字では表せない魅力があると彼らは語ります。そのことを教えてくれたのはクライアントだったそう。
倉嶋:ポスターやデジタルであれば、作業が数日かかったり、天候に左右されることはないと思います。だけど、あえて時代に逆行して、手描きにこだわることにぼくらの意義があるのかなって思ってるんです。以前、クライアントに伝えられて嬉しかったことがあって。

倉嶋:そのときは、「オフィスの廊下にスローガンを描いてほしい」という依頼だったんです。その会社では、これまでスローガンを全社会議で発表したり、ポスターで掲示したりしていたんですが、誰も覚えてないってことが当たり前。だけど、それをレタリングアートとして表現することで、社員さんたちがスローガンを写メしたり、SNSでシェアするようになったりして、自然とスローガンを覚えるようになったそうなんです。しかも、そのオフィスに来たときに、お客さんとの話のきっかけになることも多くなったようで。ぼくらも最後のひと筆を社長さんに描いてもらったり、社員さんと一緒に描いたりすることがあって、それがひとつの体験になるんですよね。アートだけど、僕たちが描いて終わりではなく、参加してもらうことで自分ごと化できるというか。そうすることで無機質なように感じていたスローガンに、ストーリーが生まれるんだと思います。


下地を塗り終えた後は、今回のビジュアルの下書きを転写。あらゆる角度から確認し、ミリ単位で調整していく

情報だけでなく、手仕事ならではの熱量と時間を費やすことで、“風味や面白さ”が加わると彼らは口を揃えます。その言葉通り、壁面に近づくと、筆を走らせた軌跡や乾き固まったペンキの跡が見受けられ、手描きでしか出せない“味”が感じられます。
倉嶋:“味”って言ってもらえるとうれしいですね。ぼくらがやってることって、クラフトビールやクラフトジンとかと同じ文脈だと思うんですよね。昔ながらの手法を取り入れることで、深みが増すというか。そういうのが伝わればいいなと思いながら、描いています。

下書きが済むと、いよいよ筆入れ。慎重であり、大胆でもある筆運び。ペンキの乾き具合を見ながら、完成へと近づけていく