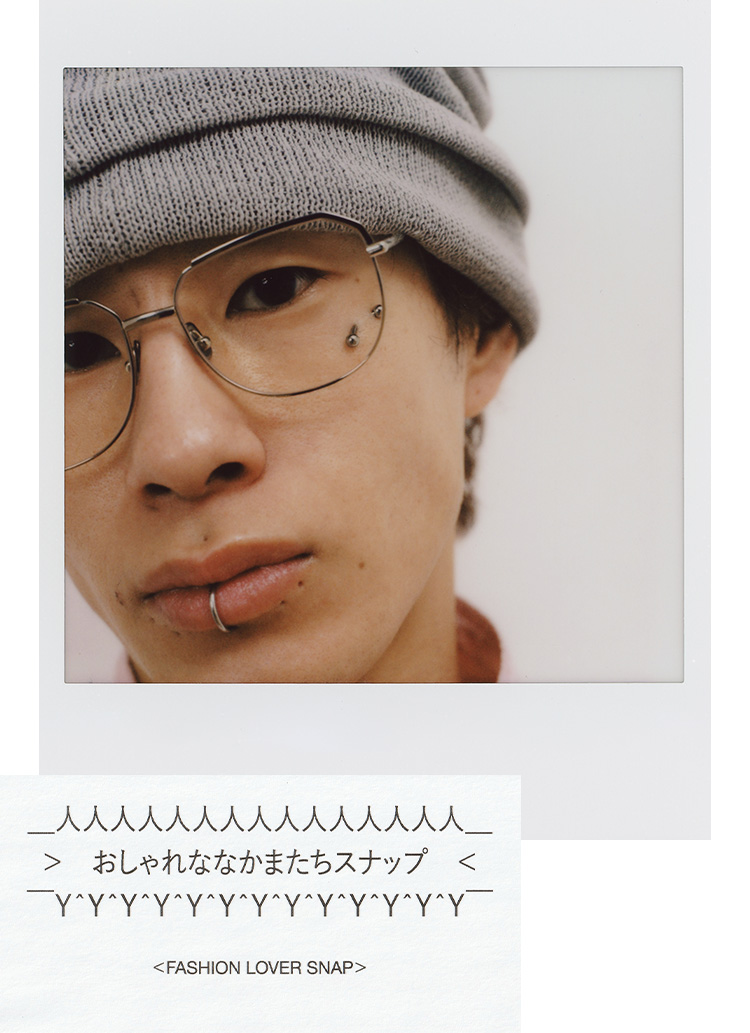クリエイティブは混ぜることで生まれる。
原宿のオフィスにお邪魔すると、いろいろな場所で英語が飛び交っていて、さまざまな国籍をバックグラウンドに持つひとが集まっていることが感覚的にわかります。現在は、およそ20カ国の国籍のひとで構成されているそう。
「クリエイティブというものは、バックグラウンドや文化の異なる人が集まったときに生まれるものだと信じています」と話すのは、この会社のピープル&カルチャーマネージャーを担当するケリーさん。
「私たちがコアとして大切にしていることは、自由に考えること、常に好奇心を持つということの二つ」と続けます。


クリエイティブにもっとも必要なもの、つまりつくるひとにとって喉から手が出るほど欲しいものは、閃き。そして閃きは、新しい気づきや視点にもたらされます。読書などでインプットすることもそうだし、旅もそう。海外旅行をすると、異文化に触れることでさまざまな固定観念が外れていく感覚は、誰しもが持っているのではないでしょうか。「ウルトラスーパーニュー」が大切にする、自由に考えること、固定概念にとらわれずに発想するには、その枠を壊してくれる異文化や他者に触れなくてはなりません。
それを能動的に、積極的に引き起こそうとした結果が、この会社の多様性に繋がっているというわけです。もちろん会社として、採用して終わりと安穏としているわけではありません。クリエイティブなチームづくりの“レシピ”もちゃんとあるのです。

オフィスで採用しているフリーデスクもそうだし、クリエイティブランチと呼ぶものもそう。広告の宿命として、すごくいいものをつくっても、その方向性を正しいとみるかどうかはまた別の話。結果として不採用だったとしても、そこで終わらせずに、会社内のスタッフに見てもらい、制作過程を説明したり、批評を受けたりする。そうやって会社内で共有することで、レガシーとして残していき、つくり手本人も会社全体もスキルアップしていきます。ときには、スタッフが共有すべきだと考えるサービスやスキル、アートなどを自由に発表できる場を設けることも。そうすることで、ちゃんと議論が生まれていくのです。
たとえば、マジックジャーと呼ばれる別部署の人たちが交流するランチミーティングも。普段は交流のない経理担当やCEOと一緒にご飯にいくということが、毎月起こっています。国籍も役職も年齢も異なる人たちが、お互いの趣味嗜好や文化を知ることで、お互いを理解できるようになっていく。そして、お互いの文化に触れて、理解して、それがクリエイティブに繋がっていきます。そのクリエイティブに引きつけられ、全世界から多数のインターンが集まり、絶えず新鮮な風を吹き込み、企業文化を活性化させていく。そんな、気持ちのいい循環が起きているのです。

海外にも支社があって、その場所はシンガポール、台湾、スリランカ。海外支社のスタッフが東京オフィスに滞在したり、その逆も然り。大きなプロジェクトでは海外スタッフも含めてチーム編成が組まれることも。クリエイティブな人材において、国境は限りなく消えつつあるのでしょう。
さまざまなバックグラウンドを持つひとたちが混ざることによって、新しい見方や発想が出てくることを信じ、定式化しているのがこの会社の大きな個性になっているのです。