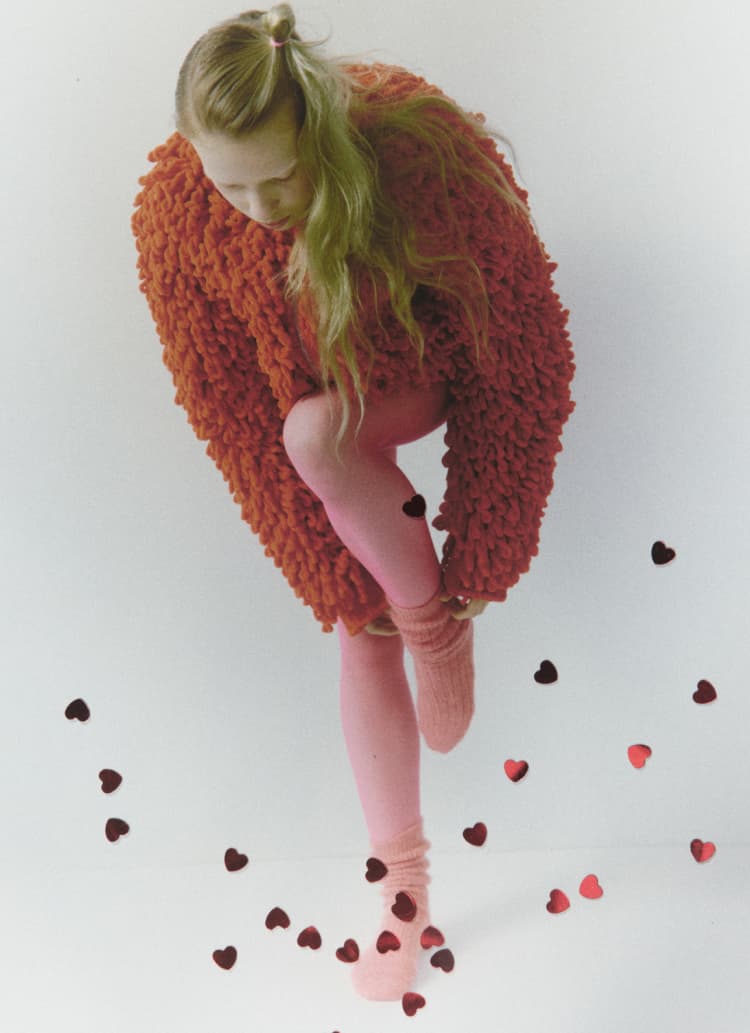これからの時代に大切なのは、余白。

鳥羽:難しい食材じゃなきゃできない料理も差別化できていいんですけど、みんなが家で簡単にできて美味しいっていうのはすごい重要。建築の場合はどうなんですか? 家としてはかっこいいけど、実際は住みづらいという家は結構あると思うんですけど、その辺りはどう考えてるんですか?
長坂:案件によるのかもしれないけど、ぼくは住んでいる人が自分で手を入れたくなるような感覚の建物がいいなと。
鳥羽:それはめちゃくちゃわかるな。レシピは余白が大事なんで、全部この通りにやってくださいというのだと、しんどいじゃないですか。
長坂:そうですね。建築家の巨匠だと、壁に張り紙を張っちゃいけないとかあるんですけど、そういうのがぼくはまったくないんですよね。ある時から、変えてもらっても全然OKとなったんですよ。
鳥羽:それは何がきっかけだったんですか?

長坂:「Sayama Flat」っていう、うち(スキーマ建築設計)の代表作で、初めて自由に手を入れていいっていう賃貸だったんです。それで住む人たちに手を入れてもらったのを見たら、すごくいいなと。それまでは洗濯物や、違うなと思う家具が置いてあるだけで嫌だった。最初の10年ぐらいはそうだったけど、「Sayama Flat」の時になんか吹っ切れたんですよ。
鳥羽:それって逆に幅が広がったって感じですね。
長坂:そうそう、いろんなものが受け入れられるようになったし。それまではデザインされたものしか嫌だったのが、意外と悪くないなっていうか。あそこもいいねとか、あっちもいいんじゃないっていう感じで見れるようになった。
鳥羽:それはぼくも一緒ですね。あるタイミングでコンビニとかをやるようになったのもそう。自分の世界観の押し付けになっちゃうと広がらないっていうか、やっぱり使う人が優先じゃないとダメなんだなっていうのはすごく思いましたね。
長坂:そうそう、面白くない。
鳥羽:その“余白”の話はこれからの時代では、すごく重要だとぼくは思っていて。余白があることで、いろんな人がシェアしたり、広がるような、余白からの拡張があるんだなと。レシピにしても、建物にしても、余白が展開していくようなものだといいですよね。
長坂:前までは住み手が考えるっていう余地がまったくないし、住み手に見せないようにつくってたし。いまは仕組みとかを理解して、 自分たちでも手を入れられるようになってるような気がします。

鳥羽:それも多分時代や環境によって変わってくると思っていて、提案の仕方も含めてそういう風にレシピも進化していかなきゃいけない。時代とともに生活も変わるし、住んでいる人や食べる人も変わっていく中で、ぼくらつくる側もチューニング能力みたいなものは必要ですよね。
長坂:まあ、感じているんだろうね。自分で考えているつもりでいるけど、実は感じている。
鳥羽:そうですね。ベクトルが相手に向いていれば、自然と感じとって、アウトプットも変わってくるのが普通ですよね。 話が変わりますが、もしぼくが田舎とかでレストランをやるとなったら、どんな空間がいいと思いますか?
長坂:ぱっと思いついたのは、やっぱり単純に外で食べているイメージ。いまの話を聞いただけのイメージですけどね。
鳥羽:それ、いいっすね。
長坂:室内って印象がないですね。
鳥羽:もうレストランってよくも悪くも、高止まりになってしまってきていて、いい素材を使って特別な場所でやるのはよくあるコンテンツで、もう飽和してきちゃってる。だから、逆にぼくはみんなでシェアできる日常的な食べ物を、外の空間でレストランクオリティで出すことには可能性を感じます。
たとえば、おにぎりとかをシェアして食べることで一体感を産んで、その価値をみんなで共有するような新しいレストランの形もいいなと。その空間と食べ物と会話を共有して、何かをつくり上げていく体験は、まさに衣食住の中の一つである食体験にふさわしい。それこそ常さんと尾道で、でかい鍋で土地の物を使ってビリヤニをつくるとかいいですよね。