小径逍遥、再び。
青野賢一
ビームス クリエイティブディレクター / ビームス レコーズ ディレクター
「ビームス創造研究所」所属。選曲・DJ業、執筆業。音楽、ファッション、文学、映画、アートを繋ぐ。
www.beams.co.jp
shop.beams.co.jp/shop/records/
blog.beams.co.jp/beams_records/
No.31 食事のしかた
2011.11.02
文芸誌『IN THE CITY』のコラムの資料として、
食事にまつわる書籍を幾つか読んだ。
日頃、何気なく摂っている食事ではあるが、
これが調べてみるとなかなか面白い。
日本の食事のしかたは、一度に色々な料理が出てくる。
これを「平面展開型」と呼ぶのだそうだ。
日本の他には、朝鮮半島などに見られる。
一方、フランス料理のコースなどは「時系列型」という。
時系列型というのは、元来ロシア式サービスだそうで、
フランスの宮廷料理にこのサービス方法が採用されたことで、
ヨーロッパに広まっていった。
『IN THE CITY』で書いたことを、
発表前にここで披露しても仕方ないので、
実際にどのようなかたちでコラムに使っているかは、
是非次号にて確認いただければと思うのだが、
それとは違う角度で気付いたことを記しておきたい。
かつて、人の趣味趣向は比較的容易にジャンル分け可能だったと思う。
ファッションでもカルチャーでも、それはある程度当てはまった。
トレンドとの接し方も、ピラミッド型などと言われ、
ピラミッドの上の方に居るのがトレンドセッター、
下の方にいくにつれて、マスと呼ばれる層となり、
当然、下の方にボリュームがある。
しかし、今はどうだろう。
今や、人の趣味趣向はひとつの言葉だけでは
まったく不十分であり、系統立てることすら容易ではない。
よく言われていることだが、人が色々な「タグ付け」をされた状態だ。
そのタグはかなり細かくて、例えば映画なら、国はもちろん、
年代、出演者、あるいは監督名など、多種多様。
この多種多様なタグが個々人に付いて(付けられて)いる。
だから、同じジャンルの中でも、あるタグでソートした集団と、
別のタグでソートした集団は、随分と異なる性格を帯びているだろう。
この、一見散り散りでフラットな状態が現在だ。
人は散り散りの断片から、自分の好みにあったものを選ぶ。
それは、もう早い遅いで語れるものではない。
同じタグを背負った人同士は、SNSなどを通じて
互いに認識し合うことも可能になったのだ。
冒頭に述べた、食事のしかたの分類を知った時、
現在の日本のマーケットと相似形にあるように思った。
これまでは、早い遅いといった時系列型のマーケットだったものが、
個々の趣味に基づいた、平面展開型となった。
そう考えると、ある種の先祖返りというか、
元々、色々な事柄について、日本に根付いていた様式が
再び立ち現れてきただけなのかもしれない。
食事のしかたから、色々と見えてくるものがあり、
気付かされることも多いのだが、
よくよく考えてみれば、生命維持の根源的な行為である
「食べる」ということには、情報が詰まっているに違いない。
卑近な例だと「食べ方を見れば育ちが分かる」のようなことも
食事の作法を通じて、その人物の過去を見抜くわけだから。
食にまつわるあれこれに、
当分興味は尽きそうもない。
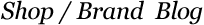






※コメントは承認されるまで公開されません。