小径逍遥、再び。
青野賢一
ビームス クリエイティブディレクター / ビームス レコーズ ディレクター
「ビームス創造研究所」所属。選曲・DJ業、執筆業。音楽、ファッション、文学、映画、アートを繋ぐ。
www.beams.co.jp
shop.beams.co.jp/shop/records/
blog.beams.co.jp/beams_records/
No.34 見世物から考える
2012.03.16
江戸時代、安政2年10月2日に「安政大地震」が起こった。
いわゆる直下型地震で、江戸は相当な被害を被った。
その二ヶ月後、新しい年の幕開けに、
歌舞伎よりも早く再開したのが、浅草の生人形見世物興行だった。
最近読み終えた『江戸の見世物』(川添裕・著/岩波新書)は、
江戸時代の見世物の種類や、その活況ぶり、社会に与えた影響などを
一次資料にあたり、丁寧に読み解いたものである。
見世物というと、蛇女、かに男などという、
丸尾末広『少女椿』のような世界を想像する向きも多いだろうが、
江戸時代の見世物の本流は、籠細工、変わり細工、生人形、
異国の動物、軽業などであり、各々が現代までかたちを変えながらも
その火を絶やしていない。
どの見世物も、寺院の「御開帳」に合わせて開催されることが多く
(つまり門前で開催される)、参拝と不可分のものであり、
見世物の内容もまた、ご利益を期待される(させる)ものだ。
例えば籠細工は、竹で巨大な像を編み上げたものだが、
何を拵えたかといえば、『三国志』の関羽、あるいは釈迦涅槃像であって、
それらは言うまでもなく「ありがたい」ものであった。
また、変わり細工の有名どころでは、
魚の干物で作った三尊仏(「とんだ霊宝」と呼ばれた)
などというものまである。
ついでに言えば、異素材の採用は、伊藤若冲『野菜涅槃図』
などにも見られ、
それらは、尊い教えを卑近なもので表現することで、
庶民にも親しみやすいものに翻訳する、
という作用も多分にあっただろう。
こうしたユーモアが、見世物を大盛況に導く
ひとつの要因であったことは、想像に難くない。
冒頭に引いた、生人形の見世物は、
細工物よりもやや時代を下った頃に登場する。
生人形とは、文字通り生きたような人形であって、
当時の決して豊富とはいえない資材で人肌を再現したものだ。
これにも当然熟練した技術が必要で、
そういう意味では、細工物の系譜と言えよう。
生人形も、誰しもが知る伝承物語を下敷きにしたものが多く、
そのテーマは日本神話にまで及んでいる。
信仰の見世物化は、籠細工の頃から脈々と続くものなのだ。
さて、再び冒頭の話に目を移すと、
安政大地震の二ヶ月後に再開された浅草の生人形見世物興行は、
爆発的に流行したそうである。
何よりもまず娯楽であり、そしてまたありがたさ、
目新しさもあった、この生人形見世物は、
当時の江戸っ子たちから大歓迎を受けたに違いない。
落ち込んだ気持ちが少し元気になったり、
題材となっている古い伝承物語から改めて何かを学び取ったり、
見世物小屋で出会った仲間や友人たちと
無事(や被害の度合い)を確認しあったりと、この時の見世物興行は、
コミュニティとしての機能も果たしていたのではないだろうか。
震災から一年となるタイミングで、
偶然手にしたこの本から、色々と考えることも多かった。
シリアスな話題がたくさんの世の中でも、
少しのユーモアはあっていい。
そこから伝わることだって、あると思うのである。
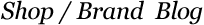






※コメントは承認されるまで公開されません。