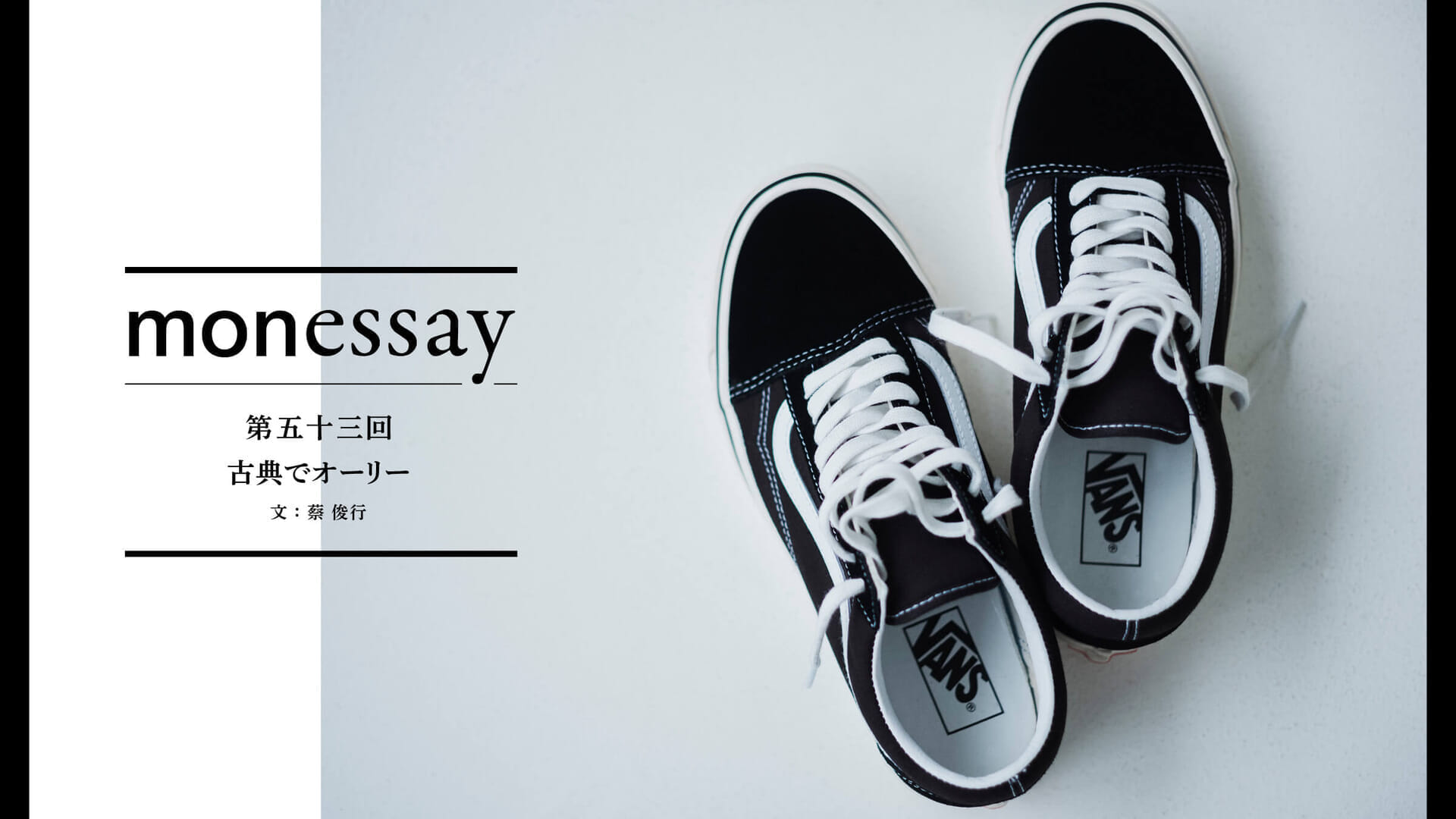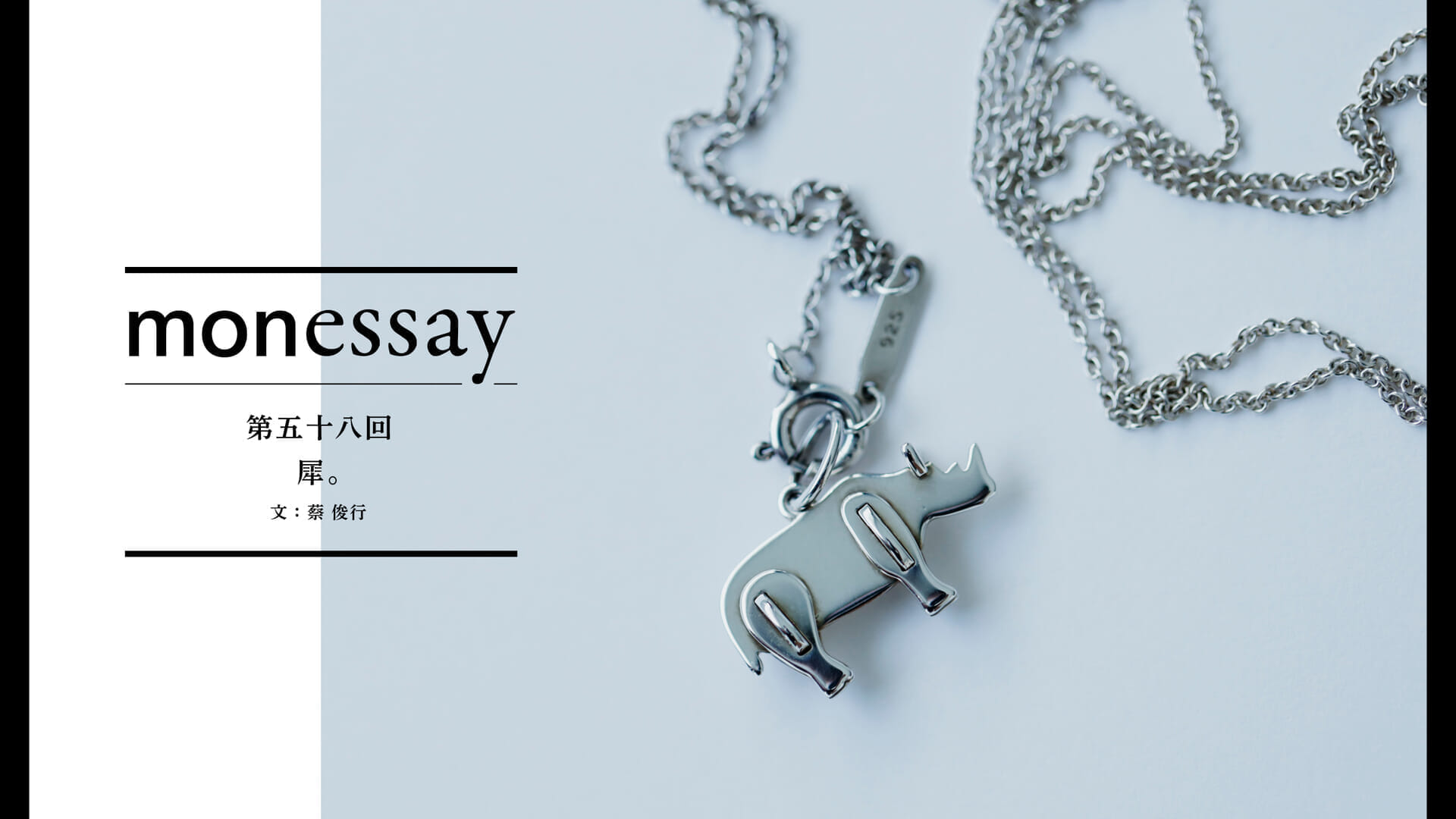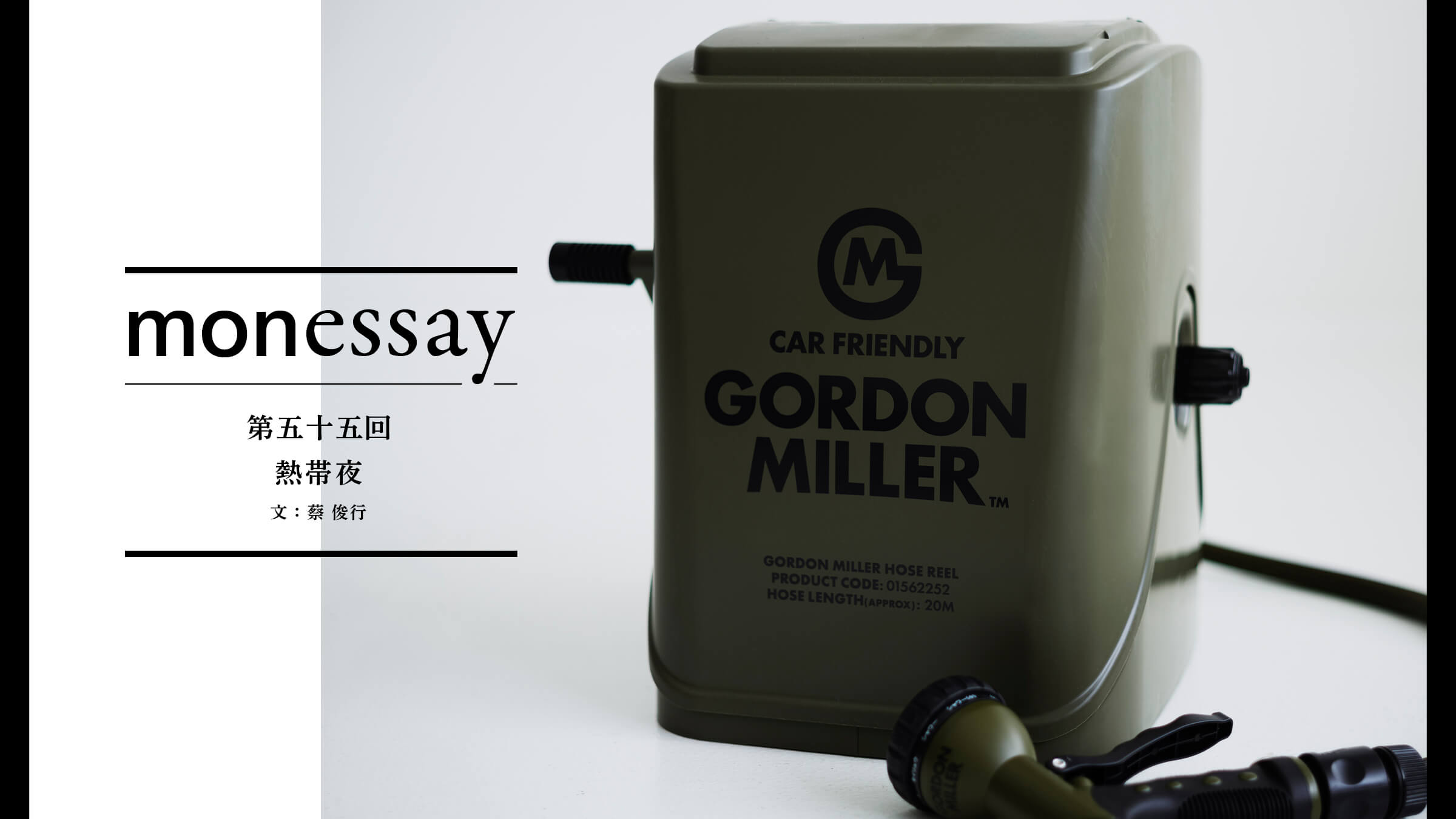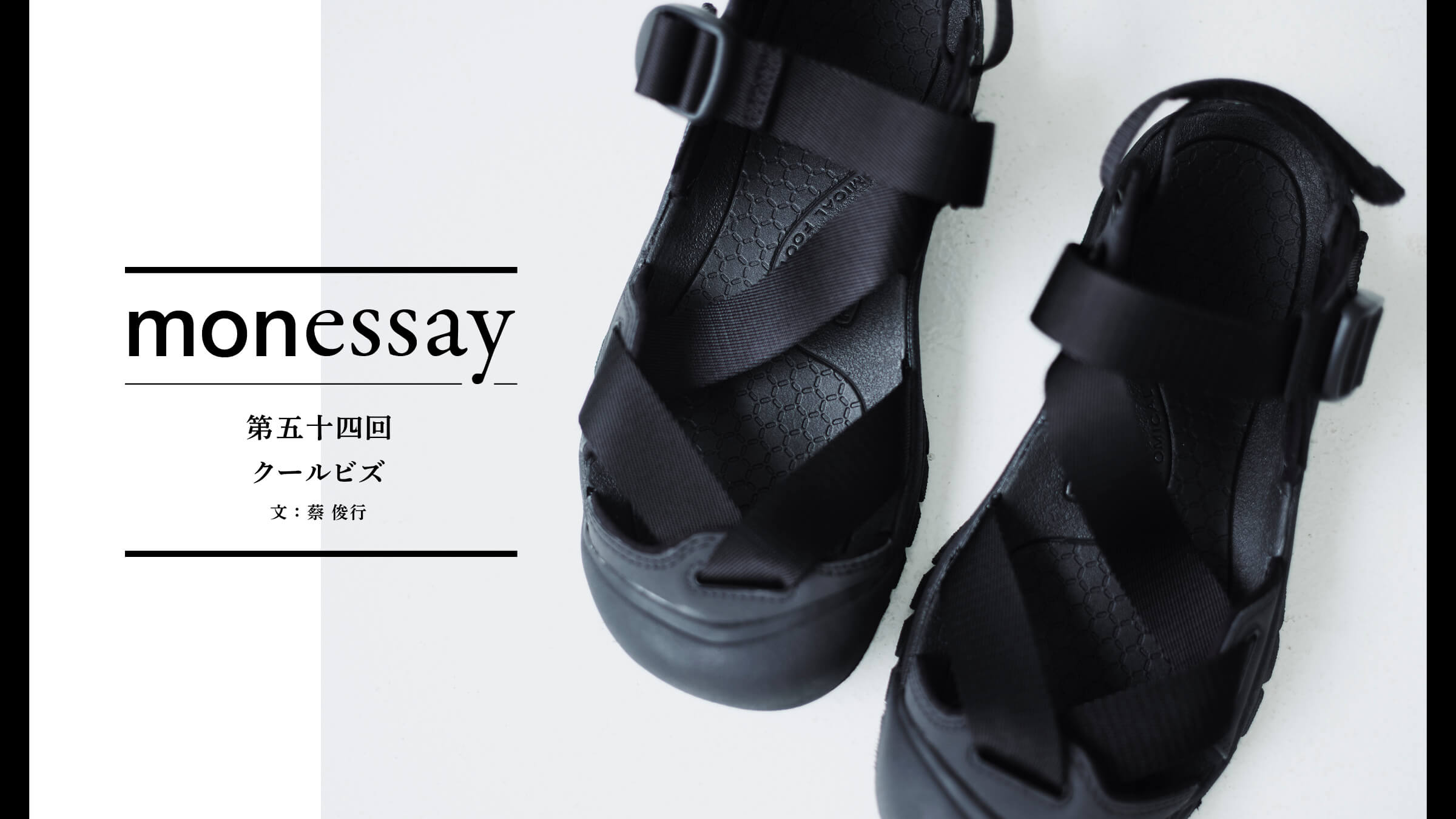第五十三回古典でオーリー
コロナ謹慎中に古典文学をいくつかおさらいした。『モンテ・クリスト伯』と『レ・ミゼラブル』。あまり関連性はないけれど、共通項をあげるなら仏文学ということになるか。なんとなく読み返してみようということで、書棚から引っ張り出して読んだ。いやあ長いね。
さらにモダンクラシックともいえる作品もいくつか。『ライ麦畑でつかまえて』、『悪童日記』三部作、そして『ハックルベリーフィンの冒険』など。これらはブックカバーチャレンジというSNS上の不幸の手紙みたいな企画に乗って、自分でポストした作品。
やはり古典というのは、何十年にもわたって読み継がれているので、テーマが普遍的でどの時代に読んでも古臭くならない。次はドフトエフスキー、もう一回行ってみるか。『カラマーゾフの兄弟』なんて大審問官のところを飛ばして読んでるので、次はここをきちんと読もうと思う。果たして読みこなせる読解力と忍耐力と集中力はついただろうか。文頭の仏文2作も今回かなり飛ばしてストーリーを追っただけに、少し心配だ。
このような古典小説のような超長編が、これから書かれることは考えにくい。これらの作品が生まれた時代と現代では背景が違いすぎる。この情報過多で消費スピードの速い時代にこのような大作は生まれづらいだろうし、書かれたといってもウケなさそうだ。
日本ではライトノベルのようなものが近年、若い人たちの間で流行しているようだが、そのなかで何十年も読み継がれていくような作品は稀だろう。むしろマンガの方が可能性があるかもしれない。
よく週刊誌などで識者に読むべき古典を紹介してもらう企画があるが、そのうちの10分の1も読んでない。こういう滅多にない家籠りがチャンスなのに、このたびはそんな未読作に取りかかれなかった。すでに自粛が解けて半分ほど日常が戻ったが、コロナ第二波が襲ってきたときのために、次に読むものをリストアップしておこう(ちなみに古典をあたるのは図書館がいいです。必ずあるし、人気ないからいつでも借りられる。時節柄よく拭いてきれいにしてから読みましょう)。
書籍に限らず、音楽も新旧譜ひっくるめておもしろいジャンルである。クラシック音楽はもちろん、クラシックロックやジャズなどは、今日でも最新ヒットチャートと同時に誰もが楽しんでいる。大量のアーカイブがあるジャンルで新しいものを創るのは難しいと思われるが、それでも新しいものが生まれるのだから、作家の創造力の凄さに改めて感服するしかない。
毎日生まれてくる作品と長い歴史のある文化遺産。それらすべてを読み聴きするのは困難である。だからこそいつでも新しい作品との出会いというバッファがあるのだ。そう考えると、自粛生活でやることなくてパチンコ行かなくて済むのではないか。
暇つぶしができる能力を教養と呼ぶ、と言ったのは作家の中島らも。なるほどなあと思う。
ところで長年、ファッションやってる身としてはおよそ古典とも呼ばれてもいいロングセラーなアイテムは、大体通り過ぎてきている。しかし唯一、縁がなかったのが〈ヴァンズ〉のスニーカー。
それがいまや毎日履いてるもんだからわからないもんだ。めざせ、オーリー。

VANS OLD SKOOL 36 DX -BILLY’S EXCLUSIVE ¥9,500+TAX
1966年当時にカリフォルニア州アナハイムにあるファクトリーで製造されていたクラシックモデルにフォーカスした、「アナハイム・ファクトリー・コレクション」。当時から使用されているモデル名・スタイルナンバーを用いて、重厚感溢れる10オンスキャンバスやスエードを取り入れるなど、実際に当時ショップに並んでいたラインナップを忠実に再現。
PROFILE
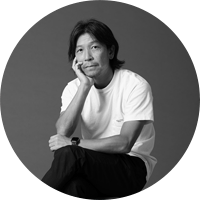
フリー編集者を経て、スタイリストらのマネージメントを行う傍ら、編集/制作を行うプロダクション会社を立ち上げる。2006年、株式会社ライノに社名変更。
BILLY‘S渋谷
電話:03-5466-2432
www.billys-tokyo.net