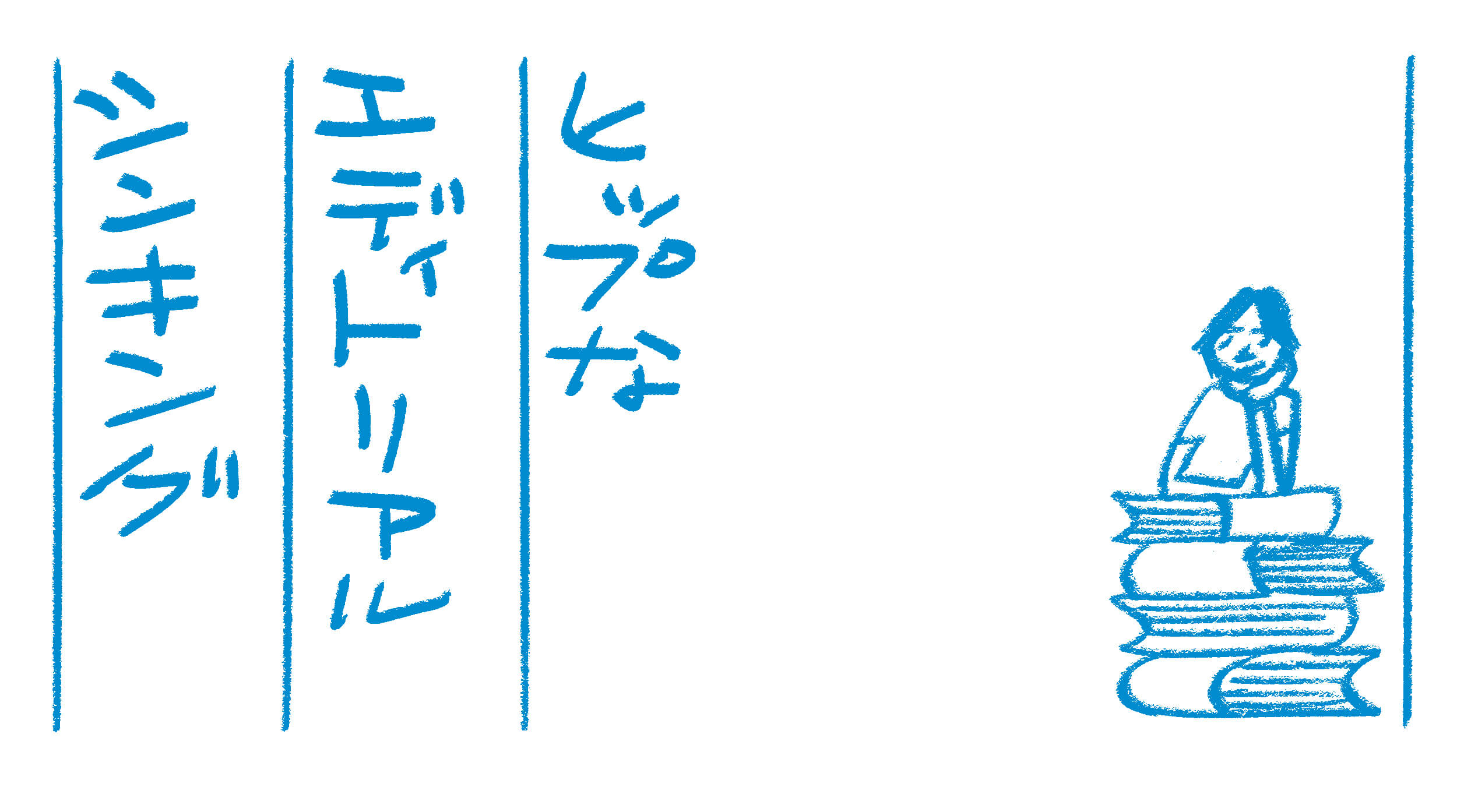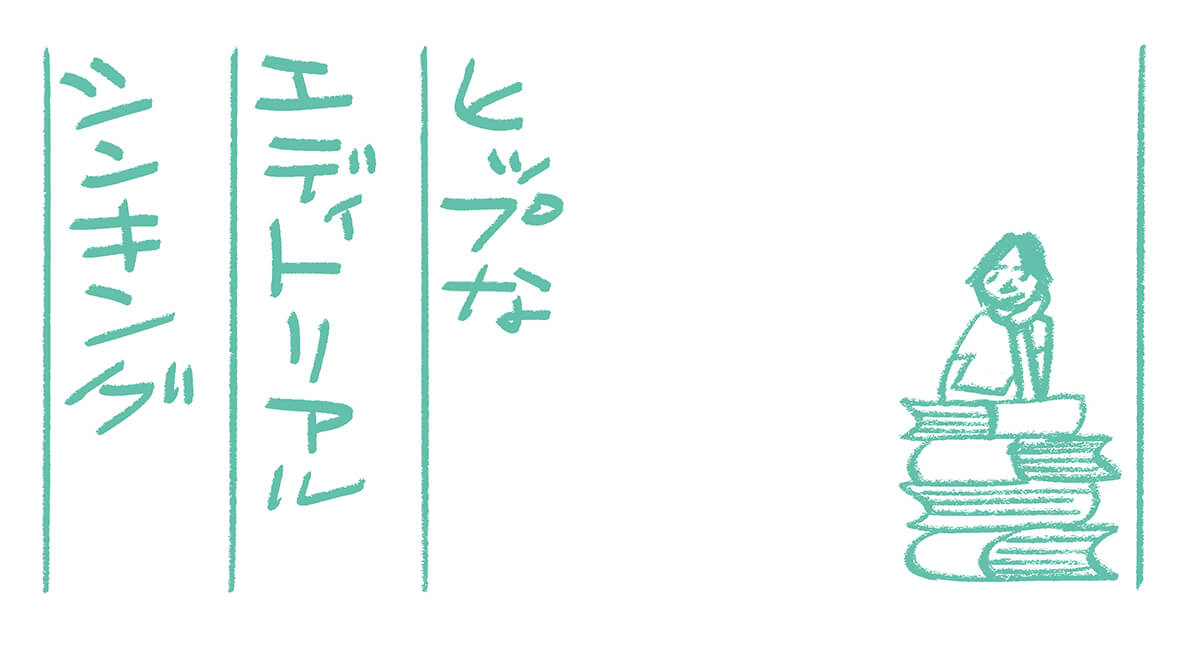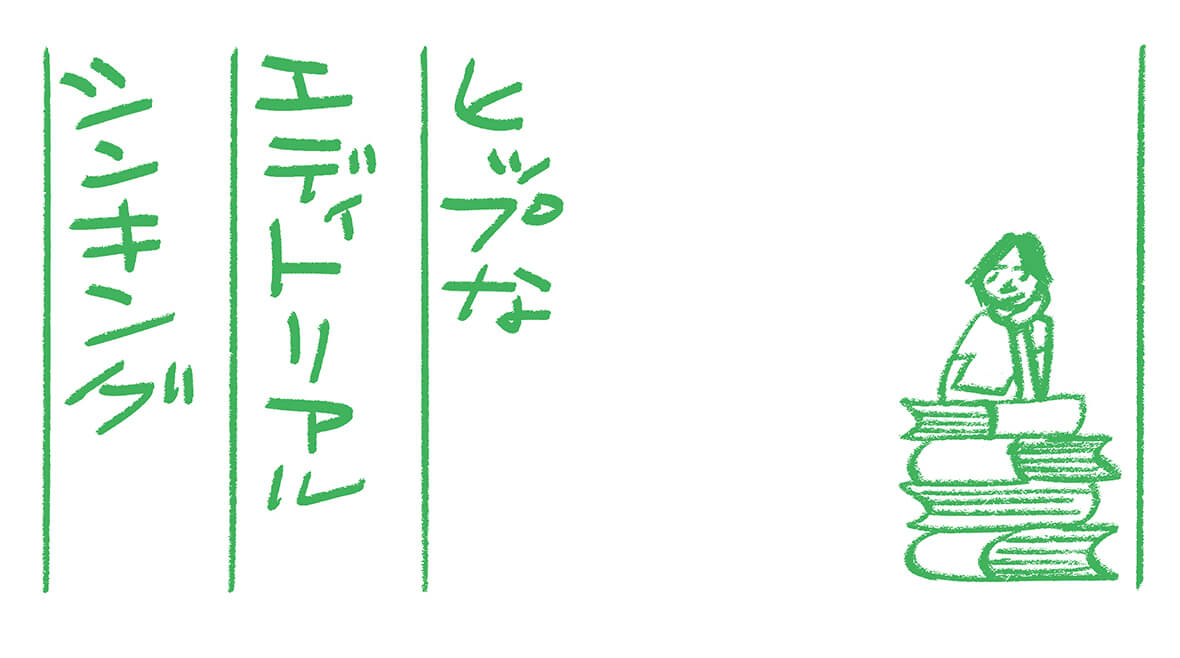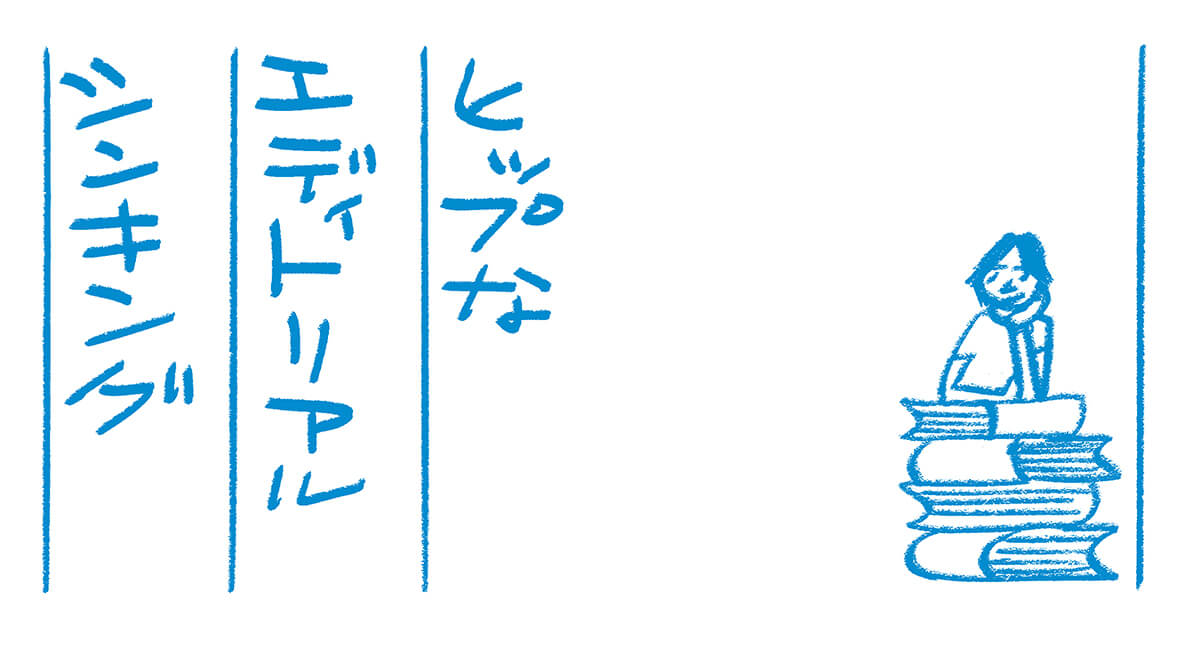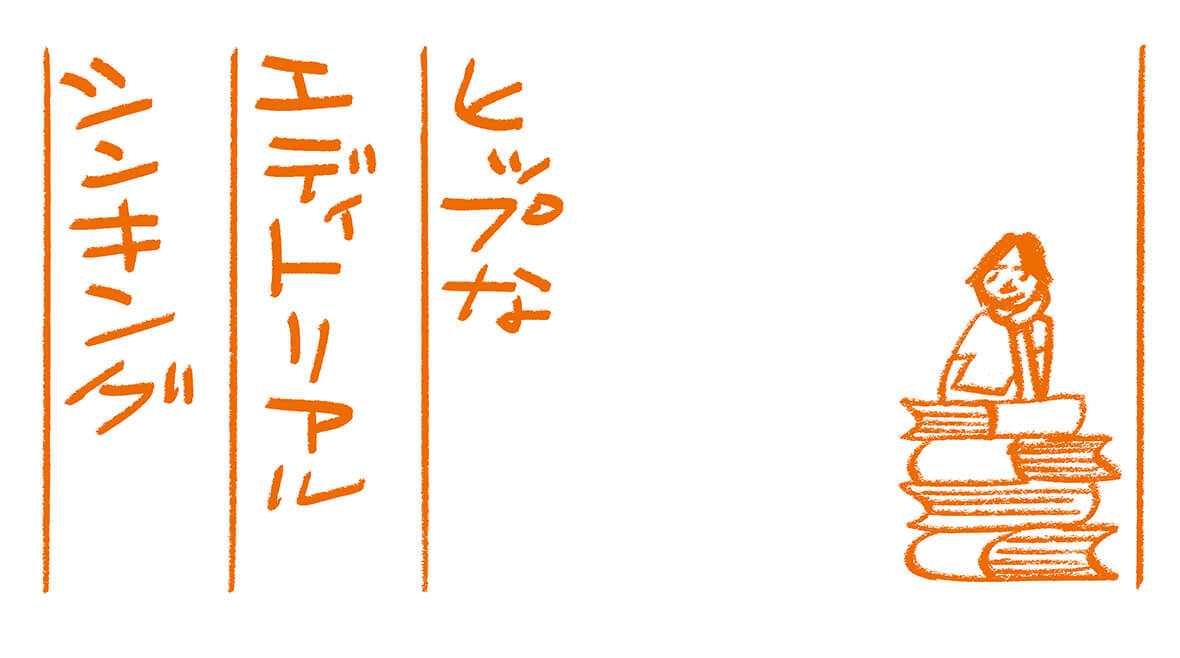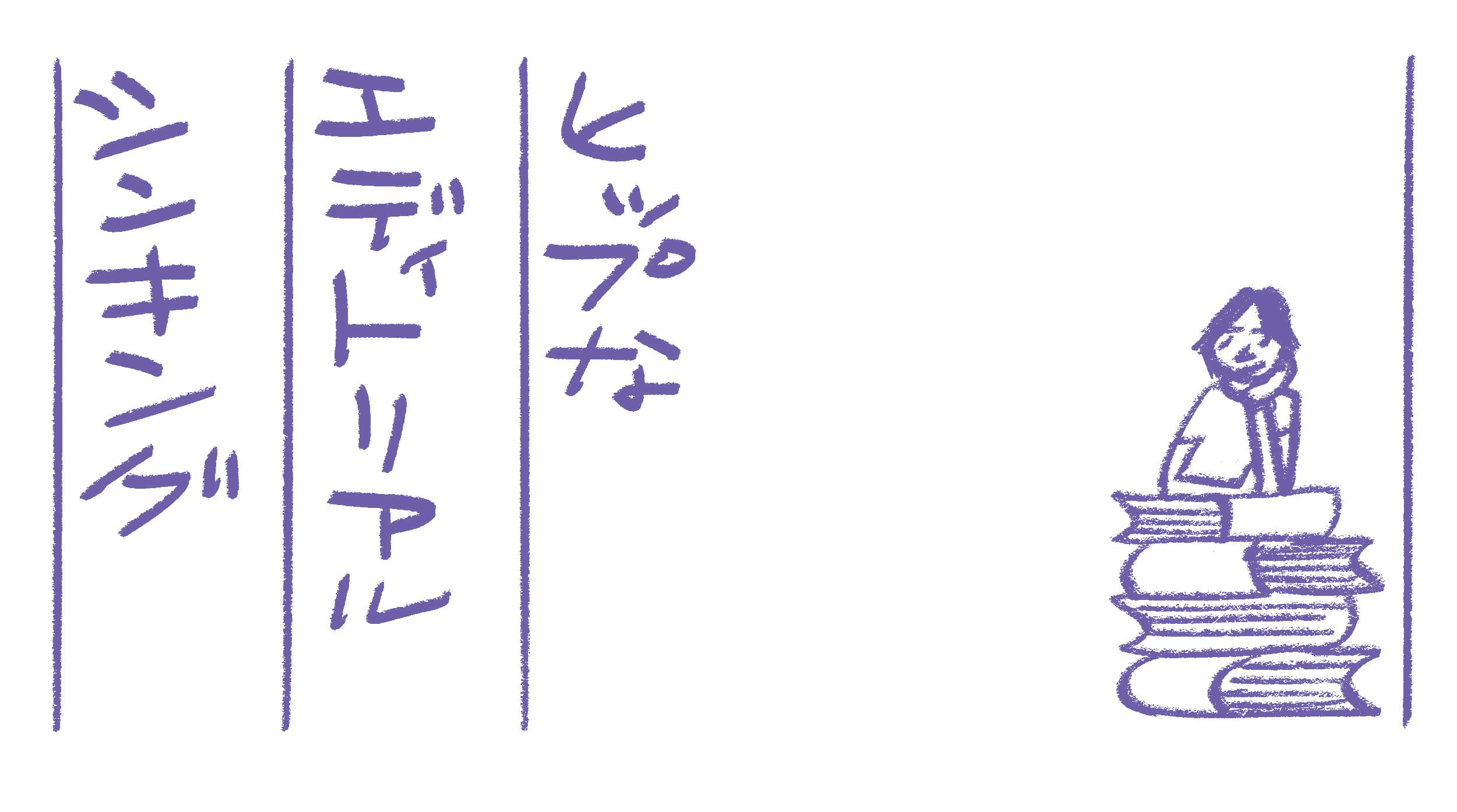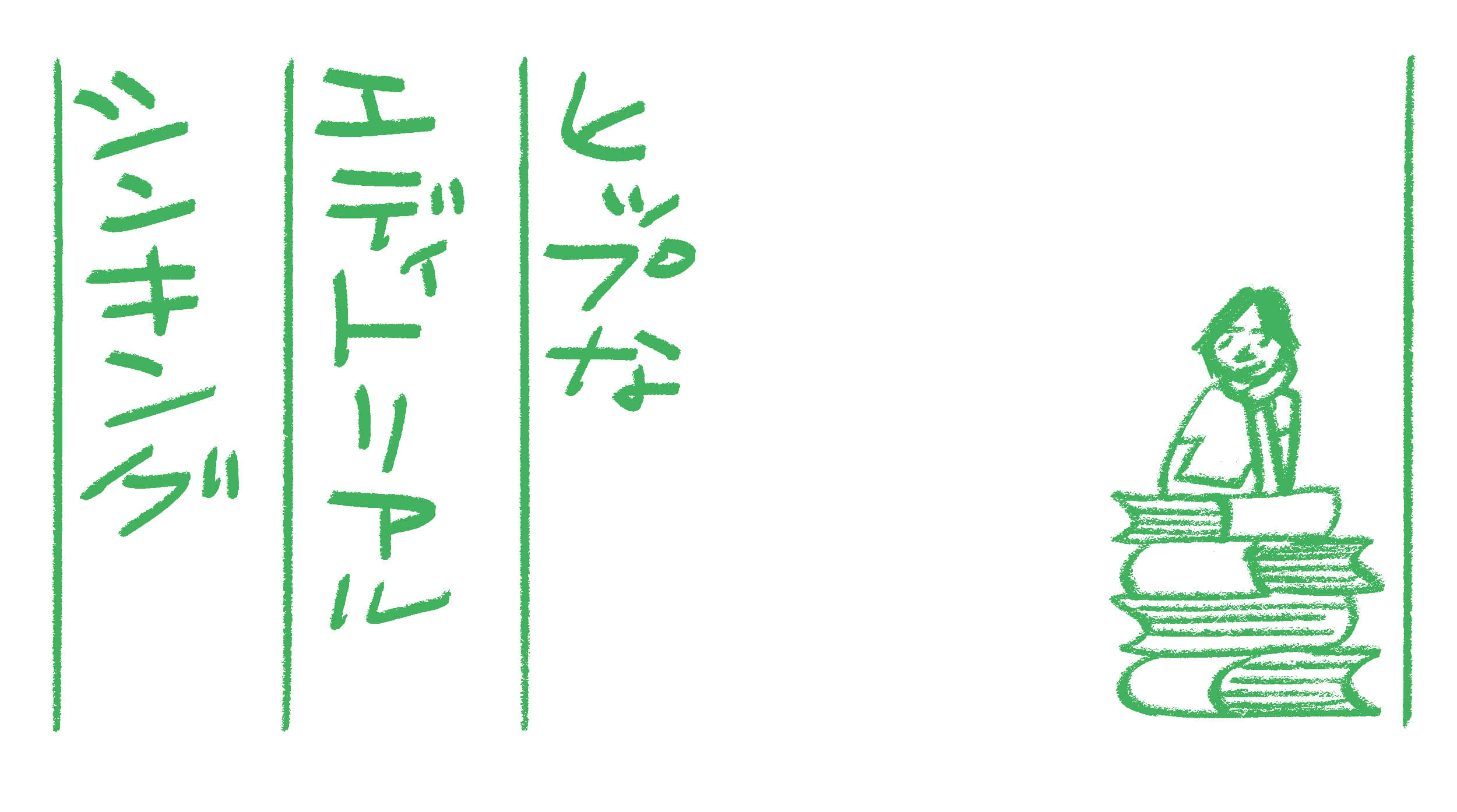第2回誰もが編集思考を使っている
「食」への関心がこのところやたらと高くなってきている。いわゆるクリエイターと呼ばれる職業の人たちのこのところの話題は「食」である。北海道の寿司屋に食べに行ったとか、サン・セバスチャンに行ってきたなんて情報を交換しあっている。確かに誰もが食事するので、共通の話題としては悪くない。「ホッジ予想」のような代数幾何学の難問を持ち出しても、たぶん熱を帯びないだろう。
SNSの発達などもあり、あらゆる人たちが食に対して関心を寄せている。そしてそれがエスカレートして一部のお店は予約が困難になってしまった。1年半待ちの焼肉屋とか2年待ちのお寿司屋とか、まるでアイドルのコンサートのような人気ぶりである。
たまにそうしたお店にも連れて行ってもらうこともある。確かに美味しい。これなら予約が難しいのもわかる。しかしまれに一部のお店ではクエッションマークが頭に浮かぶこともある。情報を食べてるという言い方をする人もいるが、確かにそうかもしれない。
こういう状況が面白くない人のなかには、何ヶ月後に何が食べたいかそんなのわからないからこんなのは、バカバカしいという人もいる。でもそれを言うとすべての計画が台無しだ。半年後にハワイに行きたい気持ちになってるかなんて、エクスペディアを見ているときにはわからない。ディズニーランドや演劇もそう。今日はエド・シーランの気分じゃないなんて、直前にチケットを破り捨てたりしない。
食べることもエンターテインメントなのだ。
とはいえ自分自身もあまり先の予約はしない主義。良くても一ヶ月先まで。そんな予約困難店の予約を持っていて、直前に行けなくなってキャンセルするのもお店に悪いし、ましてや知人に権利を譲り合うというのも道義的にやりたくない。お店は食べるものもそうだけど、そこにいる人とのコミュニケーションを重視するからだ。
自分で選ぶお店は、いくつかのお馴染みばかり。気に入ったら足繁く通うのでお店の人たちとも親しくなり、さらに居心地が良くなってさらに通うという循環だ。
食事しながら飲むのはワインが多い。とはいえ、和食のときには日本酒を選ぶし、居酒屋では焼酎なども飲む。原則、その料理に合うお酒を選択している。
一時はワインについての知識を詰め込もうとしたけど、あまりにも生産国やブドウ品種、生産者が多すぎて諦めた。むしろこちらの稚拙な知識をもって選ぶより、ソムリエに頼んだ方が間違いないし、こちらが知らない未知の世界を案内してくれるから、より楽しい。
近年マリアージュで料理に合わせてグラスワインをサーブしてくれるお店が増えた。魚には白、肉には赤、フォワグラにはソーテルヌなんてオールドスクールな考え方を吹き飛ばして、ナナメ上の提案をしてくれるソムリエもいる。

ある意味ソムリエは、お皿に合うワインをコーディネートしてくれる編集者でありスタイリストだ。膨大なデータから最適種を選び、未知の世界のドアを開けてくれる。
料理人にも同じことが言える。料理を作り盛り付けて、どんな風に供するかも編集である。盛り付けで食欲を刺激することもできるし、それこそ皿の形や色も無限にある。
スタイリストの仕事
ファッションのスタイリングという仕事も、編集に含まれる。
その仕事とは、服や装飾品を集めてコーディネートすることだ。つまり「スタイルを編集」する。
自分のスタイルをベースにトレンドや仕事の目的を意識しながら、古着屋さんからラグジュアリーブランドまであらゆるお店やメーカーのプレスルームをまわり、服を集める。そしてただ組み合わせるだけではなく、シャツはパンツに入れるのか出すのか、サイズは小さめに着るのか大きめか、ボタンは開けるのか締めるのかまでディテールを大切にしてスタイリングを作り上げる。
昨今、IT系のスタートアップがスマホなどでサイズ計測して、その人に合う服をECで買いやすくするなんてニュースもあったが、スタイリストからするとポイントはそこじゃないと言いたいだろう。あれはスタイリングではなく、フィッティングだ。
いまはスタイリストの活躍範囲は多岐にわたり、仕事によってはクリエイティブディレクター的な役割を果たすこともある。そこもまた編集に通ずるところである。
スタイリストの果たす役目は大きい。
デザイナーのクリエイションもとても大切だ。毎シーズン、新しいコレクションをまるで身を削るようにして発表している。自分の羽を抜いて機を織るという昔ばなしを思い出すくらい、神経をすり減らしている者も少なくない。
工業メーカーが開発費をかけ、大きなチーム内で研究者やエンジニアとともに開発し、市場に出す製品に劣らない膨大な利益を、ひとりのデザイナーが生むこともある。
しかし彼らの仕事は編集ではなくクリエイションである。なかには編集者的視点を持っているデザイナーもいるかもしれないが、産業に例えると第一次創作だ。スタイリングや編集は第二次創作といえるかもしれない。
そこにはそれぞれの役割がある。優劣の問題ではない。どちらもとても大きな影響をファッション界や世界に与える役である。
スタイリストがいなければ、ジャケットの下にジージャンを重ねるとか、古着とデザイナーズブランドの組み合わせなんて考えられなかったかもしれない。ときにはルールを守り、ときには型破りなコーディネートの提案もする。そういう蓄積のなかからまた新しい世代のスタイリストやデザイナーが生まれてくる。
しかし最近では、一部のブランドがスタイリストのクリエーションを妨げることも少なくない。雑誌などで発表される場合は、同一ブランドであらかじめ決められたルックでしか対応しないというところもある。
スタイリストや編集のクリエイションで、さらにブランドの価値を高められる可能性を自ら放棄しているのだ。これは本当に残念でならない。
組織というのは大きくなると硬直し、役所みたいになっていくものである。クリエイションとは真逆な方向に。
DJも編集である
音楽、つまり楽曲も第一次創作といえる。
つい数年前、銀座でウォークマンの発売40周年の特別展示があった。歴代ウォークマンが並んでいる景色は迫力だ。
ウォークマンの登場で音楽の楽しみ方は変わった。オーディオセットにLPレコードをかけて聞くというリスニングスタイルから、テープを自主編集し、自分の聞きたい曲を聞きたい順番に並べてよりアクティブに楽しむというスタイルになった。
ミュージシャン側はそれまでレコーディングはアルバム偏重だった。曲順を決め、その順番に聴いてもらうのがそれまでのスタイルだ。しかしウォークマンの登場でミュージシャン側が求めるような聞き方をしてくれなくなった。もっと自由に音楽を聞きたいというスタイルが確立したのだ。
ぼくらも若い頃、レコードやCDからテープを編集したミックステープを友人たちに貸し借りしていたものだ。マーベル映画『ガーディアン・オフ・ギャラクシー』で主人公が母親のミックステープを初代ウォークマンで再生しているのを見て、懐かしくて嬉しくなった。
これはプライベートなDJ的な楽しみ方である。DJはディスクジョッキー、つまりレコードを操る人である。ラジオDJ、クラブのDJやらいろいろあるが、膨大な音楽コンテンツのなかから、曲を選択しその場にふさわしい曲をかける人だ。
ラウンジ、バー、クラブ、コンサート会場などいろんな場があるが、音楽を編集し「場」をつくる仕事。DJには曲をつなげるテクニックも必要だが、いちばん重要なのはどんな曲をどのタイミングでかけるかという選択と編集のセンスである。
そういう意味で、DJは場のスタイリストと言える。
こういう風に話を広げていくと、バーなどの照明をクリエイトする人も同じ役割をしているし、店舗の内装プロデューサーも同じだ。
どんな仕事も、集めて編むという編集的なセンスが要求される。つまり編集的な考え方ができるかどうか。
編集思考はこんな風にあらゆるジャンルにおいて誰もが意識しようとしないに関わらず、使っている能力のひとつなのだ。
PROFILE

フリー編集者を経て、編集と制作などを扱うプロダクション、株式会社ライノを設立。2004年フイナムを立ち上げる。