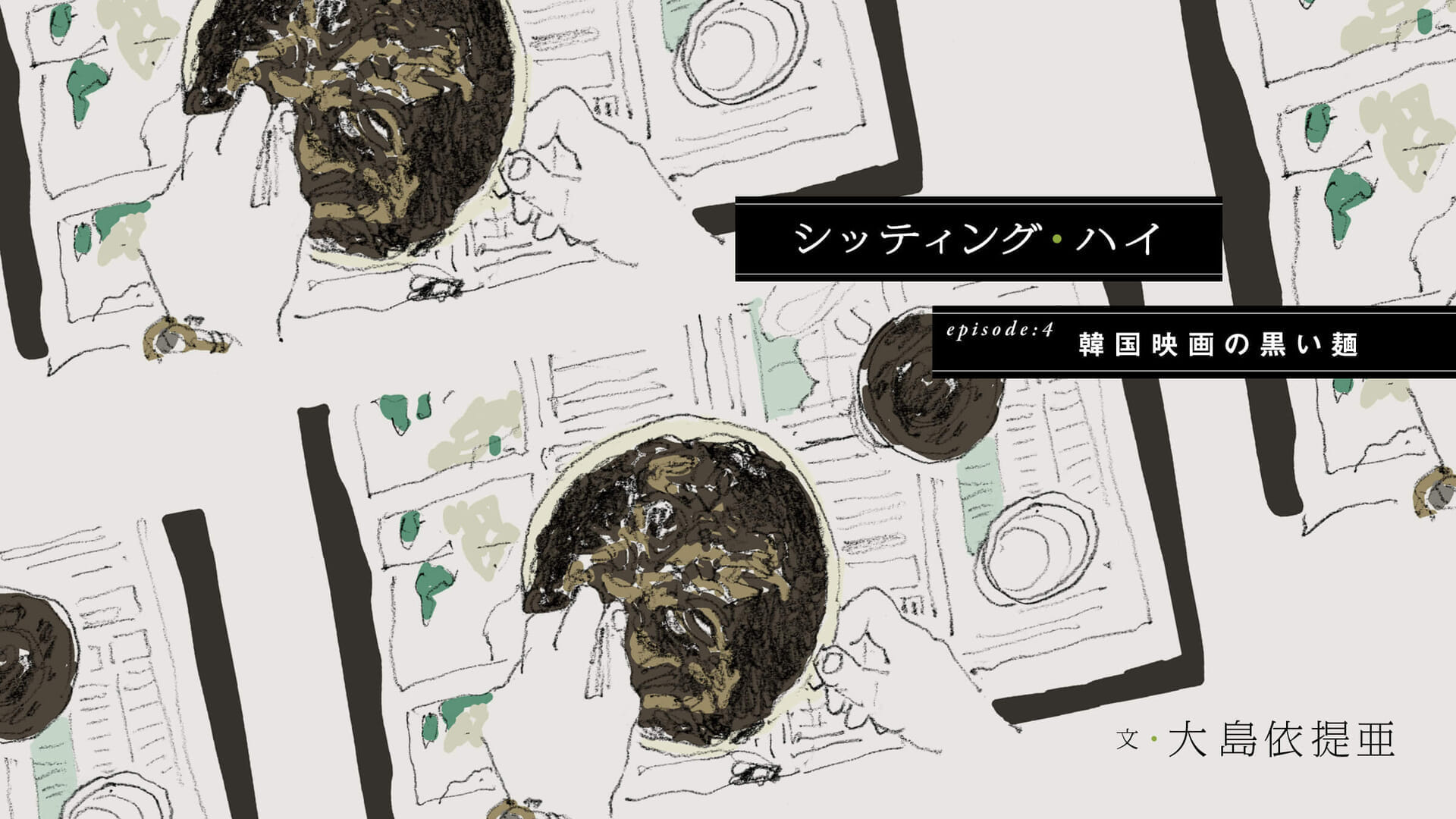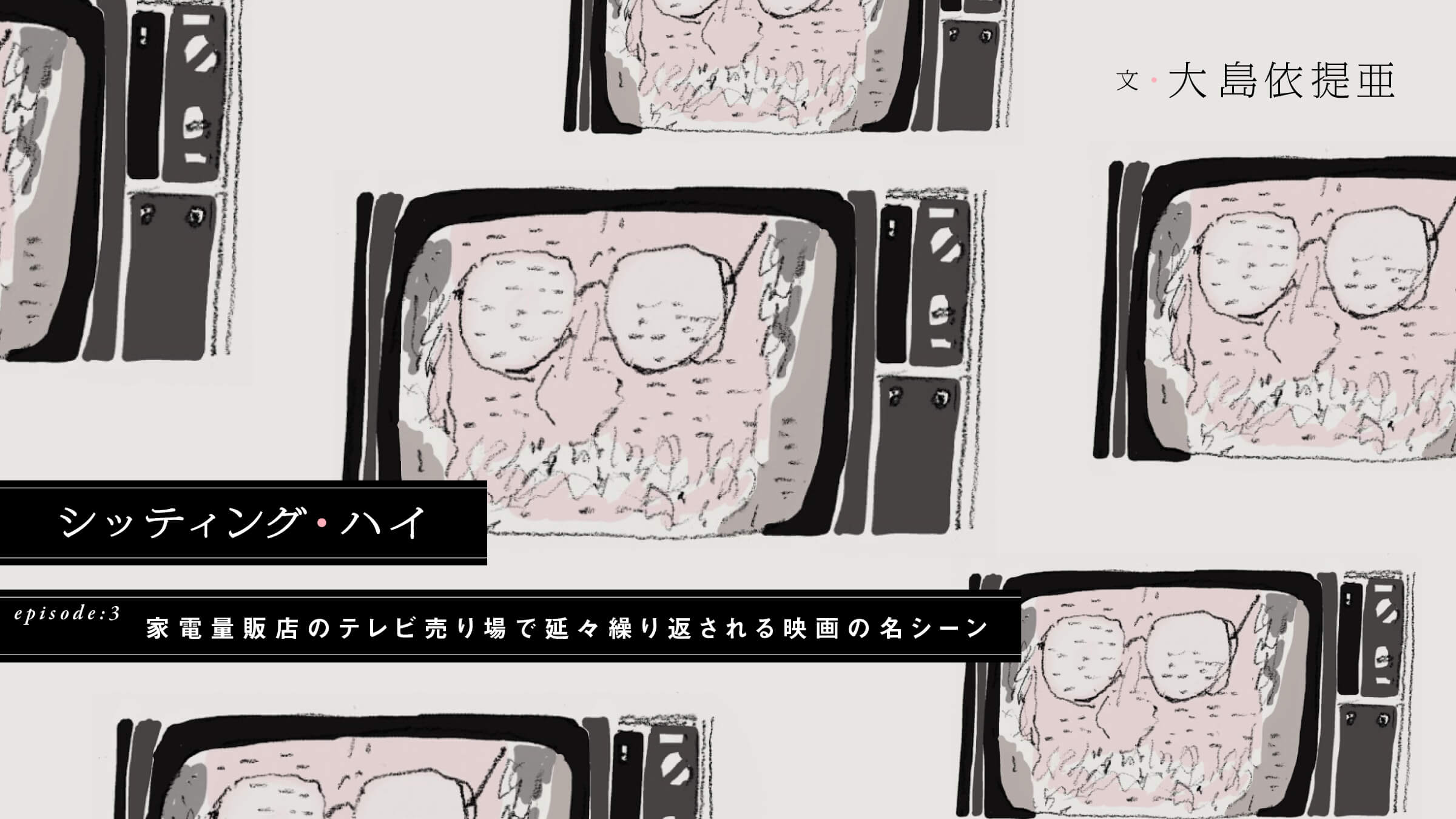episode.8 そろそろ『君たちはどう生きるか』の話をしていいですか。
戦略というより意思である。
宮崎駿の引退宣言撤回から待つこと6年。いよいよ日の目を見た今作。公開後の作品の感想合戦、批評合戦が盛んなのはもちろんですが、ひときわ注目を集めたのは作品情報をシャットアウトしたその宣伝手法。仕掛けたのは、長きにわたって宮崎駿と伴走してきた、プロデューサー鈴木敏夫さんでした。
「今回の宣伝手法は、鈴木さんの見事な戦略…、もう戦略というか、意思ですよね。その意思をしっかりと感じて、今作は宮崎駿の集大成というよりは、鈴木敏夫の集大成的なものになったんじゃないかなと。なぜかといえば、この広告をまったく打たないという展開は、SNSやYouTubeとかのいまの環境によほど精通していないと、このドンピシャな戦略は立てられないでしょう? (SNSアカウントを持っていないと言われている)鈴木敏夫さんは、ほんとうはSNSの裏アカを持っているんじゃないのかなって思うくらい(笑)」

大島さん自身もこの手法に倣って、意識的に、そして慎重にSNSなどの感想やレビューを排して、今作の初鑑賞に臨んだそうです。
「話題作はもちろんのこと、ましてや宮崎監督作品となれば、玄人素人問わず、考察や感想がひしめくわけじゃないですか。そういう餌食にまみれてしまう。とくにこの1、2年のSNSではそういう風潮が顕著で、映画をはじめとした文化が、感想や考察によって、作品の質を問わずに、ただただ消費されて、流されていってしまうという感じが個人的にするんです。その危機感をどこまで鈴木さんが意識していたのかはわからないけど、作品を見てみると、なるほどそういった批評を拒絶するような時代性を感じました」
大島さんの好きなジブリ作品。
さて、では今作の批評へと至る前に、ここでは大島さんがジブリの “熱狂的な信者ではない” ことをまずは明らかにしておきたい。
「リアルタイムでジブリ作品を鑑賞したのは、(1986年公開の)ラピュタが最初かな。なんだこれ! おもしろい!! となって、それからさかのぼってナウシカやカリオストロの城とかを観て、夢中になりました。でも、好きな方の気分を害すつもりはないんですが、トトロあたりからあれ? と。ストレートなストーリーが絵本みたいで、僕にはちょっと食い足りなさを感じて。色彩設計がガラリと変わってしまった魔女の宅急便も、紅の豚ももののけ姫もちょっと合わなかった。で、しばらく離れていたら、千と千尋を見たらすごくクレイジーになっている! と」
では、よく巷でも議題となる、ジブリ作品のなかでのベスト作品は?
「宮崎監督作品でいえば、『ハウルの動く城』。高畑監督作品では、『ホーホケキョ となりの山田くん』です」
そう、大島さんの好みはちょっと変わっている。
アニメーションの方法論の外にいる。

この取材までに、今作を二度鑑賞したという、巷の考察やレビューに触れることをできるだけ避けて、作品に対する理解を独自で深めてきた大島さん。では、実際のところどうだったんでしょうか?
「宮崎監督の映画は、脚本なしで順撮りするアニメーションですよね。これはつまり、効率性とか、アニメーションの方法論とはちがうなにか…リズムや呼吸でつくっているんだろうなと。だって映像のリズムという点では、今作は決して心地のいいリズムじゃなくて、変拍子というか、どんどんズレていっちゃう感覚はあるんですよ。あまり気持ちよくないというか、ちょっとおかしなリズムで進行していく感じ。でも、あれがすごくおもしろい。
実写とアニメーションのちがいとして、実写映画は実在する役者が動く一方で、アニメーションは簡略して効率的に描くことができる。たとえば、アニメーションではひとが部屋に入ってきて座るという一連の流れをカットを割るだけじゃなくて、部分部分はささっと早回しにしてテンポよくできちゃう。でもそこすら間の悪さみたいのをあえて導入していたような気がしました。
例えば、これはネタバレじゃないと思うけど、主人公が母親の部屋にお見舞いに行くシーンがあって、廊下から部屋に入って手前に歩いて横に曲がって、奥の方にある母親のベットまで歩くという一連のシーンがやたらと長いんですよ。物語としてそんな必要でもないから、普通はもっと省略するはずでしょう? こういう時間軸は、いままでの宮崎作品からすると珍しい表現だと思います。だから、物語に乗れない以上に長いと感じるひとも結構出てくるのは、まあ仕方ないのかなと」
アニメーションの緩急。
宮崎作品といえば、独特なフェティッシュ性が作中で顕れるのは有名な話。偏執的とまでいわれるそのこだわり、描きこみはその作家性へとつながっている。しかし、ここにも変化があると大島さんは語る。
「アニメーションの描き込みにもやたらと凝っているところと、力を抜くところの緩急のバランスが顕著でした。たとえば冒頭の主人公が病院に行かなきゃと階段を駆け上がるシーンとか、人の重さが人力車に伝わるシーンとか、いい意味で気持ち悪いくらい描き込まれている(笑)。でも、アオサギが歩くシーンは昔だったらもっと滑らかに歩いていたであろう描写がさらっとしていたり、引きの絵では、すごく抜けた感じもあった。

これは『宮崎さんも歳をとって全部をコントロールできなくなったんだな』というひともいそうだと思いましたが、僕はちょっと違う捉え方をしてまして。というのは、宮崎監督も現代のCGアニメーション作品は絶対にご覧になっているはず…それこそ『SLAM DUNK』とか。CGアニメの特徴は、緻密な絵を完全に一律でまったく同じように描けるんです。あれは確かに見ていてキレイなんだけど、緩急がないというか、なんか絵自体に飽きちゃうんですよ。なんというか、瞬間の驚きみたいなものが非常に希薄だなと。
だからこそ、今作では緻密な部分と抜けた部分を混在させることによって、独特のテンポを生み出しているんじゃないのかな。だって、抜いたシーンがあるからこそ、緻密に描かれた部分に気付いて、驚きが生まれるわけですよね? それを今回は特に過度に強調してるように見えました。
僕はイラストの学校で教えているんですが、その授業でよく引き合いに出す話があるんです。いまはやっぱりCGで描く子が多いんですが、CGだと近くのひとも後ろのひとも、際限なく細かく描けてしまうんですよ。でも、手書きだと後ろは単純に小さいから省略して描かざるを得ない。で、CGをジブリに初導入した『もののけ姫』の制作ドキュメンタリーで見たんですが、アニメーターが前後のキャラをすべて細かく描いちゃって、それだと遠近感が出なくなっちゃうから、後ろは省略して描くことで手前を強調するんだと宮崎監督が説明していて、本当にその通りだと、学校で教えていて感じます」
「物語=映画」ではないことに気づいているか。
さて、この映画の物語の筋のわからなさ…いや、正確にいえば各シーン、各キャラクター、各イベントが何を象徴しているかは、鑑賞後の答えあわせ、批評に拍車をかけているのは間違いない。ここでその答えあわせはしない。そこだけに論点を合わせてしまうのは、この映画の魅力を受け止め損なってしまう。
「僕がハウルを好きということにも繋がるんですが、昔からジブリを好きなひとで、2000年代以降の作品などにモヤモヤしているひとは、物語を非常に効率よく読み取りたいひとなんじゃないのかなと。宮崎監督は、とっくの昔に物語性とかそういうものにも興味をなくしていると思うんです。以前、金曜ロードショーで千と千尋を放映していたときに、冒頭を観たあとに用事で席を外して一時間後くらいに戻ってきたら、赤ちゃんはネズミになっちゃっていたりと、登場人物が全員何かに変わっていた。ハウルにしても、若い女の子がおばあちゃんになったりとか。要するに、同じ人物だけど、どんどんメタモルフォーゼしていくというパターンが通底していて、一貫したキャラクターを1つの物語として見るというところを放棄しちゃっている。
その時点くらいからストレートな物語をきちっと描くことに対して興味がなくて、絵が動いて、変化していくというアニメーションの仕組み、いわばアニメーションの起源に立ち返っているんじゃないかなという気がしています。常に変化するという部分に、忠実でありたいというか。でもそれは実は初期作品からあって、物語としてもとてもおもしろいんだけど、例えば階段をかけ登るシーンのような、これは楽しい! となるようなディテールのおもしろさが長編映画まで拡大化したのが今作だと思うんです。だから、宮崎監督がすごく純粋になってきていると感じました」
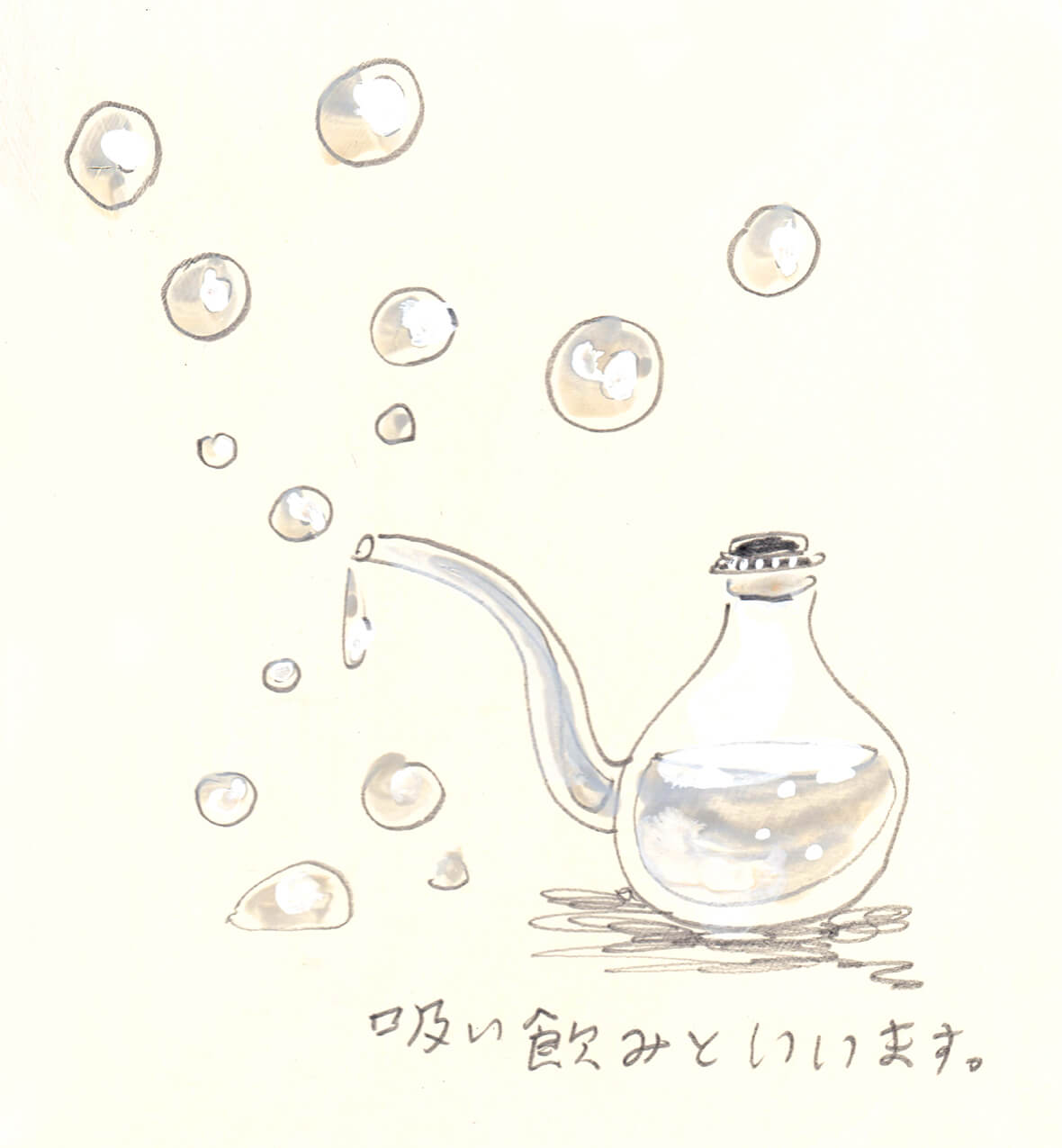
それは老いてますます盛んなり、といえるのかもしれない。そして、単純明快なストーリーラインにまとめなかったと同時に、観客を置いてけぼりにするような自分よがりな作品にもなっていないというのが大島さんの見立てだ。
「今作をアート性の高い作品というひともいるかもしれないけど、真逆で、あくまでもエンターテインメント性のある大衆向けの映画としてつくるというスタンスは変わってないなと。物語性が希薄で、わけがわからないから黒澤明の『夢』みたいというひともいると聞くけど、全然そんなポエティックな作品ではない。理解できる・できないは置いといて、なんとなく物語らしいラインに乗っ取っているところがあって、大衆向けの映画を撮るという気概を感じました。ちゃんとエンターテインメントとしてこういう作品をつくって、アートと言ってしまえば成立させることもできるでしょうけど、そうせずに担保したままああいう作品を撮ってしまうことのすごさ…」
気付いていますか? 今作『君たちはどう生きるか』は、宮崎駿監督の最後の作品とは公式に銘打っていません。大島さんをして「あと5作くらい撮れるんじゃないかな(笑)」という、祈りにも似たその希望が実現することを願っています。
PROFILE

栃木県出身、東京造形大学卒業。映画まわりのグラフィックを中心に、展覧会広報物や書籍などのデザインを生業としている。主な仕事に、映画は『パターソン』『ミッドサマー』『旅のおわり、世界のはじまり』、展覧会は「谷川俊太郎展」「ムーミン展」、書籍は「鳥たち/吉本ばなな」「小箱/小川洋子」がある。