小径逍遥、再び。
青野賢一
ビームス クリエイティブディレクター / ビームス レコーズ ディレクター
「ビームス創造研究所」所属。選曲・DJ業、執筆業。音楽、ファッション、文学、映画、アートを繋ぐ。
www.beams.co.jp
shop.beams.co.jp/shop/records/
blog.beams.co.jp/beams_records/
No.22 演劇におけるマニエリスム
2011.02.16
日本大通り駅からほど近いところにオープンした、神奈川芸術劇場(KAAT)。
オープンしたばかりのこのKAATに、
チェルフィッチュの公演『ゾウガメのソニックライフ』を観に行った。
チェルフィッチュの公演を観るのは、これで二回目だ。
前回は『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』を
ラフォーレミュージアム原宿で観たのだが、
「身体」と「言葉」の折り合いのつかなさ、
日常で使われる現代の「話し言葉」の奇妙さがないまぜになり、
まるでリアリティを劇場化してしまったかのような
奇妙な興奮を覚えたものだった。
それから暫く、観ることが出来なかったので、
今回の『ゾウガメのソニックライフ』は
随分と楽しみで、予約した日にちが待ち遠しいほどであった。
本作のオフィシャルサイトにある紹介文を引くと、
「満ち足りた生を送りたいものです。それには結局日常が大切です。
物語の主人公(男女のカップルです)が、そう考えているのです。」
とある。
繰り返される日常はつまらない。
だからせめて旅行にでも行きたい。
こう主張する女と、
日常に楽しみを見つけて
日々楽しく暮らすのがいいんだ、
と言う男。
女は日常に楽しみを見つけて云々と言われることに
とてもプレッシャーを感じている。
舞台の上で演じる役者は5人。
女が2人、男が3人。
舞台装置は、ラグビーのゴールポストのようなもの、
その奥にダイニングテーブルと椅子2脚。
ゴールポストの前方には可動式のベンチ的なもの。
舞台向かって左手にはパイプ椅子と
ヴィデオカメラが置かれ、
ヴィデオカメラの映像は中央奥のスクリーンに投影される。
複数の人間がひとりを演じるように、
5人が代わるがわる台詞を言い、
そこにそれとは距離を置いた動作が加わる。
チェルフィッチュの主宰者である岡田利規の言葉を借りれば
ある人物の会話を「引き受けて」別の人物がまた会話を進めることで
重層的なレイヤーを生じることとなるのが、本作の特徴でもある。
作品のストーリーをここで細かく述べるのは
野暮な気がするが、会話、舞台装置、動き、
そして劇中劇のような入れ子構造の話が絡み合って、
太古の「地層」のようなイメージが
90分という演劇の中に感じられるものであった。
観終わった後、日常との折り合いのつかなさと、
しかしその折り合いのつかない人々の気持ちの上にしか、
「今」という時間が存在しないことを思いながら帰路についたのだった。
暫くの後、本作の断片を反芻しながら、
これまで自分が興味を持ってきたこととの
関係性を探ってみた。
ルネサンス後期に登場したマニエリスムは、
表現的には、長く引き伸された手足や構図、
綺想的な寓意などを特徴とする美術様式であり、
それまでの調和が取れた表現とは
趣を異にするものであった。
それは常に、古典様式と対立する概念でもある。
グスタフ・ルネ・ホッケ『迷宮としての世界』によれば、
人間には「原−身振り」というものがある。
これは意識せずとも、滲み出てしまう、
ある種の「性向」とも言えるのかもしれないが、
チェルフィッチュの演劇から、
この「原−身振り」という言葉が思い浮かんだ。
マニエリストたちの原−身振りとはすなわち、
技巧、不安定、分裂、歪曲、自由、無秩序などであり、
これはそのまま舞台上で繰り広げられる
あの独特の動きや台詞、役者の存在に符合するように思われたのだ。
高山宏氏はマニエリスムとピクチャレスクが
時代を超えて呼応していたと
『高山宏の読んで生き、書いて死ぬ』で論じたが、
チェルフィッチュの演劇も、なるほど、
そういうところが感じられるのではないか。
18世紀英国に現れた「ピクチャレスク」という概念は、
文字通り「絵のような」というような意味だが、
まさに「絵になる」風景を美として求め、
英国式庭園が誕生する。
「絵になる」ということは、
ある特定の枠組みがあって、
その中で「絵になる」のであり、
自然のままの状態とは言いがたい。
どちらかというと人工的な、それでいて自然な、
不一致の一致と呼ぶべき状態を美とする。
このことは、広重や芳年とも重なると
高山氏は述べているのだが、
絵画に見られる、本当なら不自然なパースペクティヴや、
画面内でのモティーフの強調などを考えるにつけ、
今回、KAATで観たチェルフィッチュの舞台装置を
思わずにはいられない。
ヴィデオカメラで大写しにされた顔。
ゴールポストのような枠。
これはそのまま、浮世絵のあの構図を想起させる。
演劇をこういう視点で観るのは
はっきりいって野暮で邪道かもしれないけれど、
感じたことを整理して書き連ねてみた。
最後に、この『ゾウガメのソニックライフ』の
特設ウェブサイトで、主宰の岡田利規が、
特別インタビュー中、この作品のことを
「ロバート・ラウシェンバーグの『コンバイン』をまずイメージした」
と話しているのは、非常に興味深い。
http://zougame.chelfitsch.net/
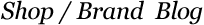






※コメントは承認されるまで公開されません。