小径逍遥、再び。
青野賢一
ビームス クリエイティブディレクター / ビームス レコーズ ディレクター
「ビームス創造研究所」所属。選曲・DJ業、執筆業。音楽、ファッション、文学、映画、アートを繋ぐ。
www.beams.co.jp
shop.beams.co.jp/shop/records/
blog.beams.co.jp/beams_records/
No.26 ドラキュラだ
2011.07.14
暑い季節の風物詩といえば、怖い話だ。
70年代以降は、ホラー映画の世界では
主に「スプラッター」と言われるものが増えたけれど
(もちろんそうではないものもいろいろあった)、
個人的には、じっとりウェットなムードのあるものがいい。
そうなると必然的に日本かヨーロッパのもの、となる。
中でもクラシカルなものが肌に合うようである。
おどろおどろしさや不気味さとともに、
どこか物悲しさ、儚さを感じさせるのも好きな理由のひとつだ。
そこで、ドラキュラである。
小説の中のドラキュラは、
ご存知ブラム・ストーカー作『吸血鬼ドラキュラ』を
まず思い浮かべるだろう。
19世紀末、アイルランド出身の作家によって書かれた本作は、
すぐさま劇化され、そして後に映画化されて、
吸血鬼ものの定番となった。
ドイツ表現主義映画の代表作『ノスフェラトゥ』(1922年)も、
版権の問題で「ドラキュラ」の名前を使えなかっただけで、
原作はブラム・ストーカーのそれである。
もっと遡ると、ブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』以前、
すなわち19世紀前半にはジョン・ポリドリ作『吸血鬼』があった。
このポリドリの『吸血鬼』、実は誕生のきっかけは
シェリー夫人『フランケンシュタイン博士の怪物』と同じだった、という
非常に面白いエピソードが残されているので、
興味のある方は調べてみるといいだろう。
先の1922年公開ムルナウ監督作品『ノスフェラトゥ』は、
一般的には知名度のあまり高くないものといえる。
なぜなら、吸血鬼のヴィジュアルイメージは、
圧倒的に『魔人ドラキュラ』(1931年)の
ベラ・ルゴシが演じたドラキュラ伯爵、
もしくは1958年、ハマー・フィルム・プロダクション(英)
により製作された『吸血鬼ドラキュラ』の
クリストファー・リーに負うところが大きいからだ。
米、英のこうした作品は、興行的にも成功し、
その後のいわゆる「ホラー」というジャンルの確立を準備した。
ドイツ表現主義の、どちらかというと芸術気質なものから、
大衆の娯楽作品という性格のものへと移行する契機となったのだ。
ルゴシ、リーの演じるドラキュラは、クラス感がある。
「伯爵」の名に相応しい風格は、着ているものや髪型などからも
感じられるだろう。
一方、ムルナウ版のノスフェラトゥは
禿頭に尖った耳、ネズミのような前歯、
長く伸びて鉤状になった爪という、
それは不気味なヴィジュアルである(このイメージは、
ストーカーの思い描いていたそれに忠実なものでもある)。
『魔人ドラキュラ』以降の吸血鬼ものは、
大衆娯楽としての耐性をつけるべく、
善と悪の対立構造を中心に据え、
いかに悪(この場合はドラキュラ)を退治するかを、
恐怖を煽りながら綴っていく。
一方、『ノスフェラトゥ』はペストという疫病を運んでくる
象徴として描かれており、「目に見えない恐怖」を可視化したものである。
もちろん、対立構造は存在するが、
吸血鬼を滅ぼすのは勧善懲悪のヒーローではなく、
ミーナというひとりの女性(ここはストーカーの原作と異なる)。
彼女が血を吸わせながら朝を迎えることで、吸血鬼は灰と化す
(とともに女性は息絶える)。そうして街から疫病は去った。
純粋に娯楽映画として楽しむなら、
後年の米、英のドラキュラものなのだろうが、
時代や風習などを考えながら観るには
『ノスフェラトゥ』だろうと個人的には思う。
何より、このすっきりしない感じ
(エンディングはとてもあっさりしている)に、
えも言われぬ不気味さが残る。
夏の夜中、暑さで眠れない時には
灯りを消してこんな映画を観るのも悪くない。
しかし、そのまま朝を迎えることのないようにせねば。
灰にはならずとも、溶けるおそれがある。
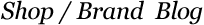






※コメントは承認されるまで公開されません。